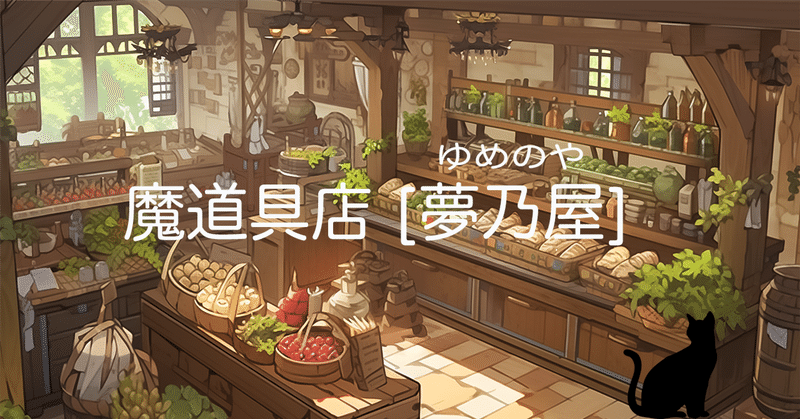
【連載小説】No,9 忘れじの花
魔道具店の主になって一週間。
奇妙な客の訪れにも少しずつ慣れてきたように思う。
「い、いらっしゃいませ」
例えば人の形はしているけれど影だけだったり、上半身はごく普通の人間なのに下半身が四つ足だったり。この世界ではありえない姿を目にすると、思わず息を吞んでしまうこともあるけれど、できるだけ態度には出さず笑顔で接客するよう心がけている。頬のあたりが多少引き攣ってるのは気のせい、気のせい。
それに、どうしても現実感が希薄になるので、毎日どこかのアトラクションで働いているような気分になる。
とは言っても、やはり扉を開けて入ってきたお客様が人の姿をしていると、ほっと安堵するのも事実だ。店主である琴音と同じ世界で暮らしている術師はもちろん、よその世界からの来訪者であっても、旅の魔法使いや勇者パーティーの一行などは注文の品が比較的分かりやすい上に、ビジュアルインパクトが少なめで心理的負担がないので、大変ありがたい。
今日も開店早々、二組ほどそうしたお客様の来店があった。
「ちょっとケビン、あんたなんで新しい剣買おうとしてんの。そんなお金ないわよ」
買い物の最中、仲間の一人が壁に飾ってある剣に手を伸ばしたことにいち早く気づいた魔法使いの少女が、眉を吊り上げて怒り出した。
「いや、だって俺の剣、結構使い込んでて刃こぼれしてるからさぁ」
剣士の青年は少女の剣幕に押されながらも、手にした剣を戻そうとはしない。
「だったら研ぎに出しなさいよ! なにも新しいの買うことないでしょ」
「でもこれ、すげーカッコよくない?」
「知らん! ポーションだって安くないのよ。余分なお金なんてないわよ!」
「えぇ、ちょっとぐらいいいじゃん」
(恋人かな。いや、この甘えた感じ、どっちも若いけど夫婦だったりして)
二人のこうした小さな諍いはきっといつものことなのだろう。他の仲間二人は各々気になる商品を眺めていて、間を取り持つ気はなさそうだ。
もちろん店主である琴音もお客様の買い物に口を出すことはないので、何事も起こりませんようにと祈りながら横目で静観していたのだが。
「すみませーん、これっていくらですか?」
「ちょっと! 待ちなさいったら!」
よほど気に入ったのか、青年が剣を大事そうに抱えたままいそいそと値段を訊きに来たので、魔法少女の怒りがさらにヒートアップしてしまったようだ。
「アンタあたしの言うこと聞いてたの!?」
「いっつも我慢してんだから、たまにはいいだろ!」
「よくないわよ!」
彼女の叫びに重なって、カーンとゴングの鳴り響く音が聞こえた気がした。
本格的バトル勃発。でも、カウンターの前では止めて欲しい。
「だいたいね、もしポーションが足りなかったら死にかけるのはアンタなのよ」
「ならねーよ。最近レベル上がってるから大丈夫だって」
「そんなこと言って、ついこの間、魔物に捕まって溶かされかけたのどこの誰でしたっけ?」
「はあぁっ!? あれはおまえが……」
投げ合うセリフの応酬がどんどん熱を帯びてくる。
(これ、やばいな。どうしよう)
内心焦り出した店主に、仲間の僧侶が「騒いじゃってすみませんねぇ」と小声で詫びてきた。
「あの二人、いっつもああなんですよ。でも、どうせすぐ仲直りしますから」
そんな僧侶の両腕には抱えきれないほどの惚れ薬の瓶が。
(こいつ棚にあった在庫全部持ってきたな)
惚れ薬といっても依存性、常習性のない媚薬程度の代物だが、そんなに立て続けに使ったらおそらく別の天国に直行だろう。
「ちょっと、そこの腐れ坊主!」
そうはさせじと、すかさず罵声が飛んでくる。
(口喧嘩の最中でも気づくとは、なかなか目ざといじゃないの魔法少女)
「僧侶です」
「アンタまでこっそり何を買おうとしてんの!?」
「いやぁ、ダンジョンを攻略する前にちょっと英気を養おうと思って」
「色街じゃなくて、魔界の洞窟で精気吸われてこい」
「ひどい」
(賑やかなパーティーだなぁ)
あと一人の仲間はどうしたと視線を巡らせれば、小柄な戦士が店の端に座り込んで念入りに防具を検分している。
(…………ダンジョンなんか入って大丈夫かな、この人たち)
それから三十分近くケンカしながら、ああでもないこうでもないと商品を物色し、結局彼らは数種類のポーションと護符付きのショートソードを一本購入していった。
「ありがとうございました」
ダンジョン攻略、上手くいきますようにと祈りながら背中を見送る。
すると入り代わりに、また別の冒険者パーティー五名が入店してきた。
銀の甲冑を身につけ腰に大剣を下げた屈強そうな剣士。
己の背丈よりも大きな斧を背負った戦士。
長い杖を手にしたあご鬚の老魔法使い。
聖職者然とした温和そうな面持ちの僧侶。
あとの一人は軽装だから泥棒(シーフ)だろうか。
こちらの冒険者たちは絵に描いたような出で立ちで、如何にもファンタジー物に出てきそうな一団だ。先程のパーティーメンバーよりも年嵩だからか、全員が落ち着いた雰囲気で、買い物中も無駄なおしゃべりを交わさない。概ねアイコンタクトで通じるようだ。
(この人たちは、なんか強そう)
数分後、
「これをお願いします」
彼らがカウンターに置いたのは数種のポーションと資源探知の方位磁石だった。
(お、これは)
この店では接客以外にやることがあまりないので、暇なときはなるべくカタログを眺めるようにしている。おかげで最近、見た目や効果が印象的な品はだいぶ頭に入ってきた。この方位磁石もその一つだ。
探知の精度は中程度と書いてあったから大まかなんだろうけど、三つの針で水と炎、そして一定の金属類がある方角をそれぞれ指し示してくれるらしい。確か詳細説明の欄にはダンジョン内での宝探しや、魔族討伐のための森林や山岳地帯行軍に役立ちますと記載されていたはずだ。
ということは、つまり。
(魔族討伐に向かう勇者一行なのかなぁ)
ちょっとワクワクしてしまう。
会計を済ませたあと、出口へと向かう途中で戦士が「本当にそれだけで大丈夫なのか」と仲間に問いかけた。
「問題ないさ。今回は様子見だからな」
さらりと答えた剣士のセリフに、老魔法使いの言葉が続く。
「発見されたばかりのダンジョンは仔細が分からぬでな。無理は禁物。深部の探求は無謀な若者らに任せておけばよい」
そうして彼らは入ってきたときと同様、静かに店を出ていった。
開いた扉の向こう側には、中世欧州風の家々が建ち並ぶ町の景色がチラリと見えた。彼らが目指すのは先のパーティーと同じダンジョンだろうか。
二組のパーティーのようすが脳裏に甦ってきて、少し気分が沈んでしまった。
「なんか、ちょっと……がっかり、かな」
思わずそんなセリフが口からこぼれ落ちてしまうほどに。
「何がだい?」
お気に入りのクッションの上でくつろいでいた看板猫のクロが、わずかに頭をもたげて訊いてきた。
「んー…………想像と違ったから、だと思う。勝手に期待して、勝手に裏切られたような気分になっちゃった。あの人たちが悪いわけじゃないのにね」
反省しつつ、正直に吐露する。
すると、ああ、なんだそんなことかとクロが苦笑した。
「琴音が抱いているイメージとは少し違うかもしれないけど、冒険者たちが魔物や魔族を探して戦うのは、大半が自分のためだからね」
ズバリと核心を突く一言だ。
「つながっている世界の中には人の国が魔族に滅ぼされそうになっている地域もあるから、そういうエリアの戦士たちは国防第一だけど。そのほかの星の数ほどいる戦士たちの大半は名を上げたいとか、一攫千金とか、夢とロマンを追い求めて旅に出た連中だから冒険者と名乗ってる」
「まぁ、そうだよね」
「最初のうちこそ目的のために無茶もするけど、長年キャリアを積んだ冒険者たちほど職業的な立場でリスクを回避するのは当然だと思うよ。その方が生き残れるから」
「シビアな話だなぁ」
「漁師が潮の流れが速い海や、岩礁の多い浅瀬に船を出して漁をするのと似たようなものかもね。他人からは無謀に見えても、知識と経験を活かして必ず帰れると自負しているからこそ船を出す。そのおかげでボクたちが美味しい魚を食べられるのと同じように、彼らの動機が多少利己的だったとしても、巡り巡って結局は人々の腹を満たしたり、災いから町を救ったりしているんだ」
「え!? 魔物って食べられるの?」
「世界によって異なるね。文化の違いもあるし、存在する魔物の種類にも差があるから」
「なるほど」
欧米では昔、生魚を食さなかったというし、キャビアは食べるのにイクラは全部捨てられていたと聞いたことがあるから食文化の違いは影響大かもしれない。だとすると、食べる地域では魔物退治よりも狩りの要素が強くなるのではないだろうか。
獲物を狩って生業とするなら、冒険者というより狩人とかトレジャーハンターと呼ぶ方がふさわしい気もするけれど。それでもやっぱり未知なるものに立ち向かうのは恐ろしいから、冒険者という呼び名で自分たちを奮い立たせているのかもしれない。
「…………ちなみに、先に来た四人組のパーティーは」
「船の底に穴が開いても運が良ければ生きて帰れる」
「……運も実力のうちって言うしね」
「そうそう」
(まぁ、わりと運は良さそうだったから大丈夫……かな?)
彼らが無事に戻ってこられるように、改めて祈っておこう。
「さて、それじゃあ少し休憩しようか。今日は杏のジャム入り紅茶にしよう。ジンジャークッキーもあるよ」
「お、いいね」
わたしとクロは次のお客様が来店するまで、しばし甘い香りのお茶で喉を潤した。
午後八時を過ぎると、店に入ってくる客はほとんどいない。
結果として緊張感がなくなるので、カウンターの奥でだれている店主の腹の虫がグーキューと盛大に鳴くことになる。
「お腹すいた……」
途中でちょこちょことお菓子をつまんで休憩を取ってはいるけど、開店する正午前に昼食を済ませたあと、閉店する夜九時過ぎまで食事を取れないのは結構つらい。
「しかも夜遅い時間にご飯いっぱい食べると胃がもたれるし、肌荒れしやすいんだよねぇ……会社員時代も残業で同じような時間帯に食べてたけど」
最近なんだかんだおやつもしっかり食べてるから、これが続くと体重増加は避けられない。危機的状況だと嘆くわたしを、まぁまぁとクロが宥めてくれる。
「あまり匂いのしない物なら、持ってきて食べてもいいと思うよ。サンドイッチとか。前の店主もここでよく食べてたし」
「え、そうなの!?」
早く言ってよって思ったけど、そういえば最初にクロに言われた気がするわ。二階にいてもお客さんが来れば分かるから、お客さんがいないときは上に行って食べてもいいよって。ところがですね、ちょうどお腹がすいてくる夕方から夜七時過ぎぐらいの間が、一番来客が多いんですよ。で、なかなか二階に上がるタイミングが見つからなくて結局こうなっちゃう。八時を過ぎると、どうせあと一時間だしって思っちゃって。
「昼をボリューム多めにすればサンドイッチでもいいかもだけど、どうせなら温かいものが食べたいしなぁ」
よし。このままお客さんが来なかったら、今日は早めに二階に上がって食べちゃうか。
そう決意してカタログをしまった直後だった。
軽やかに鳴るドアベルの音。
(あちゃ……)
続いて、店内に入ってくる人の靴音。
(ま、そういうもんだよね~)
「いらっしゃいませ」
頑張って口角を上げ、笑顔で振り返る。
(わたしの晩ご飯、あと一時間待ってて)
催促するお腹の虫に鳴き止んでくれとお願いしながら、店内に入ってきたお客さんのようすを視線で追った。
(あれ? あの人って……)
その人は昼に一度来店した冒険者パーティーの一員だった。開店と同時に入ってきた賑やかな冒険者たちの中でただ一人、最後まで何もしゃべらなかった小柄な戦士だ。
(買い忘れた物でもあったのかな?)
はて、と首を傾げながら見つめていると、こちらを向いた戦士と目が合った。
「すみませんが、これを」
呼ばれたので、慌ててカウンターを出て商品棚の前に移動する。
「えーと……こちらの花瓶ですか?」
「ああ」
戦士が指差していたのは陶器でできた一輪挿しだった。
同じような品が数種類並んでいるが、その中でも一番質素で飾り気がなく、色味も地味な商品だ。表面に魔石が埋め込んであるわけではないので、一見するとごく普通の安い花瓶に見える。実際お値段も魔道具にしてはかなり安価だ。
「これは魔力を込めれば、どんな花でも咲かせることができるのだろうか?」
「あ、いえ……」
わたしはカタログを見てどんな品物なのか把握するしかないんだけど、魔力がある異世界の方々は商品を見ただけでだいたいの使い道が分かるらしい。ただし詳しい説明や注意事項を伝えるのは店を預かっているわたしの仕事だ。
「見たことのない花は無理です。でも花瓶の底に埋められている魔石に、イメージした花を咲かせる魔法の刻印が施されていますので、色や形を知っている花なら咲かせることができるはずです」
「それはどのくらい咲いているものなんだ?」
「期間ですか? そうですねぇ……注がれる魔力量によって多少差があるようですが、最長でおおよそ一ヶ月だったと思います」
「…………そうか」
戦士は目を伏せ、何か考え込むような仕草をしたが、すぐに面を上げてこちらを見た。
「これを故郷の村に届けてもらうことは可能だろうか?」
「えっ!?」
持ち帰りじゃなくて配送希望?
これは初めてのパターンだぞ。
「ちょ、ちょっとお待ちください」
わたしは慌ててカウンターに戻ると、前の店主が残してくれた虎の巻のノートを捲りまくった。それによると、どうやら地域配送も可能らしい。この店、なかなか行き届いてる。でもやっぱり送料は高い。しかも地域によってめちゃくちゃ差がある。まぁ魔物の多さとか、どんな治世が敷かれているエリアかで差があるのは当然だろうけど。
彼が希望している商品のお値段との差がなかなかエグい。
「えっと、できますが…………おそらく商品よりも送料の方がかなり高くなってしまいますが、よろしいでしょうか?」
「ああ、構わない」
「でしたら、こちらで送り状を書いていただけますか」
わたしはキャビネットから伝票を取り出し、ペンを添えてお客様に差し出した。
すごいよねぇ、ちゃんと送り状まである。異世界専用の送り状。
思い当たる配達業者は、あのツナギの人たちしかいないけど。
戦士は渡された用紙に出身地である村の住所を記入すると、花瓶と送料の代金を合わせて支払った。たぶん彼が昼間しげしげと眺めていた頑丈そうな新品の鎧が一式買えそうな値段だ。
「ありがとうございました。では、こちらの品は配送の手配に回しますので」
「いや、待ってくれ」
「はい?」
「今から花を咲かせるから。それを届けて欲しい」
なるほど。花瓶をではなく、花を届けたいのか。
でも、その状態で配送可能なのかな?
「えっと……」
わたしは視線をキョロキョロ動かし、クロを探した。
カウンターの近くにいる彼に気づいて目で尋ねると、頷きが返ってきたので思わずホッと息をつく。
「はい、畏まりました。どうぞ」
わたしが促すと、戦士は両手でつかんだ花瓶をじっと見つめながら、器に魔力を注ぎ始めた。
(まさに、念を込めるって感じ)
何かを思い出しているのだろうか。
その横顔はとても真剣で、でもやさしい想いに溢れているようだ。
(きっと大切な人に届けたいものなんだろうな)
魔力が込められた花瓶からは、見る間にするすると茎が伸びていく。
あっという間に蕾ができて――――やがて開いたその花は、清流の雫を汲み取ったかのような、あるいは澄んだ青空をそのまま映し取ったような美しい青い花だった。可愛らしい五枚の花弁が星の形のようにも見える。
「…………きれいな花ですね」
「そうだろう?」
戦士がにっこりと微笑んだ。
やさしい笑顔だった。
「故郷の山に咲く花でな。年に一度、ほんの短い間にしか咲かないんだ。今年こそ村に帰って、あいつに見せてやろうと思ってたんだが……」
「恋人か、ご家族ですか?」
「幼馴染みだ。病で寝たきりになっている。五年前、俺の村は魔物の瘴気にやられて不治の病にかかる者が大勢出た。魔物自体はみんなで何とか倒したんだが、町から医者を呼んでも病は治せなくてな。どうにか手段はないものかと探すうちに、ダンジョンではどんな病も治す秘宝が見つかると聞いて仲間たちと旅に出たんだ」
「ご一緒にいた方たちですね」
「ああ、全員同じ村の連中だ。魔法使いのセシリアは母親を、剣士のケビンは妹を助けようとしている。僧侶のクリフは……あいつは魔物のせいで家族全員を亡くした。いつもふざけた態度だが、友人のために命がけの旅を続けてるのさ。秘宝はなかなか見つからないがな」
あのときは到底そんなシリアスな事情を背負っているようには見えなかったけど、何らかの事情を抱えた人がいつも深刻な表情をしているわけではないのだから、それも当たり前だ。笑っているから元気というわけではないし、友人とふざけているから能天気というわけでもない。
そもそも人間とは多面的で、常にたくさんの感情を持ち、さまざまな面を(ときには本人さえ知らずにいるようなものまで)持ち合わせているものなのだから。
「次のダンジョンで見つかるといいですね、秘宝」
「そうだな……」
最深部までたどり着くのも難しいかもしれないけれど。
「きっとこのお花、贈られた方も喜びますよ」
「覚えているといいんだが」
戦士の笑みが少し悲しげに歪んだ。
「思い出のお花なのでしょう?」
「ああ………………村が豊かで美しかった頃のな」
彼の目が遠くを。
過去を見つめている。
懐かしさと愛しさと、やるせなさが混ざった瞳で。
「では、よろしく頼む」
やがて戦士は静かに店を出ていった。
明日、彼は仲間と共に再びダンジョンに挑むのだろう。熟練の経験者たちが様子見しかしない危険な場所に、それぞれの大切な人を守るため、一縷の望みをかけて。
どうか間に合ってくれ、と祈りながら。
わたしは花瓶をそっと箱に入れ、表に送り状を貼りつけた。
送り主である戦士の名はヴィンスというらしい。
宛先はナッシュ王国トレントノ領リトルリバー村のマリア様。
品名の箇所には――――忘れじの花、と記されていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

