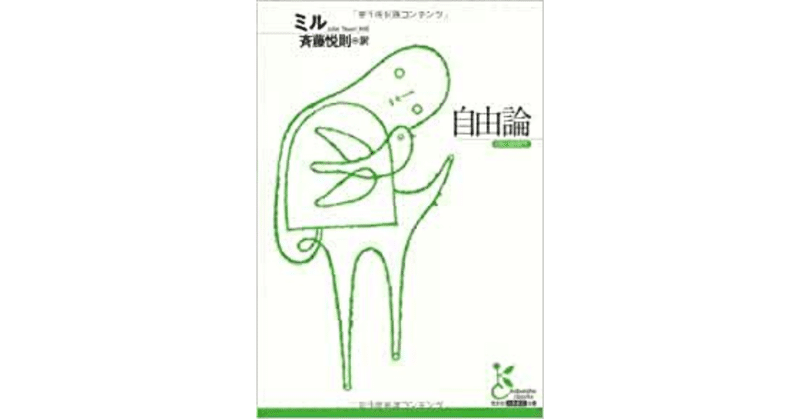
ネット世論の危険性、自由であることの意義
『自由論』ジョン・スチュアート ミル , (翻訳)斉藤 悦則 (光文社古典新訳文庫)
本当の「自由」とはなにか、考えたことはありますか? 個人の自由への干渉はどこまでゆるされるのか。反対意見はなぜ尊重されなければならないのか。なぜ「変わった人間」になるのが望ましいのか。市民社会における個人の自由について根源的に考察し、その重要さを説いたイギリス経験論の白眉。哲学を普通の言葉で語った新訳決定版! 現代人が必ず読むべき、今もっともラディカルな書。
権力の制限
1、自分たちの政治的自由と権利を支配者は侵犯することは出来ない。それに対しての反抗も反乱も正当化される。
2、憲法にもとづくチェックが設けられた。これは国民から支配者へのものだが、多くの国ではそうならなかった。
社会(多数派)による抑圧は政治的圧迫よりも遥かに怖ろしいものになる。それは人を奴隷化する。人はそれから逃れる手立てを失ってしまうからだ。
それは習慣化することによって、人があたかも同意しているように見えるが、習慣は普遍的存在するものではなく、感情よりも道理が大事であり、人の道理にもとづかないものであるならば変えることはできる。例えば男尊女卑や人種問題。
そんな中で唯一、宗教的な信仰の問題は、より高い立場で原理が問われ、そうした道徳感情は間違いを犯しやすい。
まじめ一徹の狂信者が抱く神学的な憎悪は、道徳感情のもっとも際立ったものとなる。
支配者はしばしば間違いを犯すものだ。それは原理や原則が示されないからだ。本書の目的はその原理を明らかにすること。
その原理とは、人間が個人としてであれ集団としてであれ、ほかの人間の行動の自由に干渉するのが正当化されるのは、自衛のためである場合に限られるということである。文明社会では、相手の意に反する力の行使が正当化されるのは、ほかのひとびとに危害が及ぶのを防ぐためである場合に限られる。
質的功利主義
効用こそがあらゆる倫理的な問題の最終的な基準なのである。ただし、それは成長し続ける存在である人間の恒久の利益にもとづいた、もっとも広い意味での効用でなければならない
ベンサムの「最大多数の最大幸福」の功利主義を引き継ぎながら典型的な自由主義者であるミルは、個人の自由を尊重するゆえに全体の功利主義と相容れないところがあるが、その共通項を見出して行こうとする。
人は自分の意見を好み、行動のルールとして人に押し付けたがるものだ。支配者は、それを利用して権力基盤を強化していく。権力は今弱まるどころか、逆に強まっている。そうなると服従する人ばかりになり自由を求める人は抑圧される。
そこで「暴君殺し」の問題はどの時代においても未解決のまま残された道徳問題の一つである。しかし、一民間人が悪政の支配者を打ち倒す行為は、いずれの国においても崇高な行為とされてきたのも事実である。これは殺人の範疇ではなく、内乱の範疇に属する。
個々の人にとって世間(世界)とは、社会の全体ではなくてその人が接触する一部分にしかすぎない。一旦世間というものを絶対的に信頼してしまうと、ほかの時代や、他の国、ほかの宗教や党派に自分たちと違う意見があると知っても受け入れられない。しかし、世界は拡充するのであれば異なった人も受け入れなければ絶えず争いを生むことになり両者にとって発展的ではない。
そして自分の意見に反駁・反証する自由を認めることこそ、自分の意見が相手に受け入れられることへの指針として絶対的な条件なのである。全知全能でない人間は、これ以外に、自分が正しいと言える合理的な保証を得ることができない。
人間は自分の誤りを自分で改めることができる。それは経験と議論によってである。議論がないところでは誤りを改善することは出来ない。
善良で誰よりも学識があるものでも独裁者であれば間違えることもあるのだ。ローマ皇帝マルクス・アウレリウスも誰よりも立派な哲学を持っていたが、キリスト教を採用できなければ弾圧することを当然とした。彼はキリストの教義が信じられずにそれを排除することにしたのだ。そうしてキリスト教の迫害を認めてしまった。
知的に秩序の平和を目指す限りこうした過ちは起きるのであり、知識人が活発な探究心を持たずに自分の信念を曲げてしまう者が多くなればそれだけ権力者に都合よく、ものごとを考えない人が増えていく。それは権力者の奴隷化であり、そういう社会ではありきたりな俗論を唱える者か日和見主義者しか生み出さない。自分の思考の関心や範囲を狭め、小さな日常の話題しか好まなくなるのだ。
異端者の発言は徹底した議論を呼び起こす。異端者が沈黙すれば支配者が公正な政治を行わずに利権や特権だけの社会になり、その社会は没落していく。正統者は何が正統かもわからなくなるのだ。
ルソーの逆説的な主張
18世紀当時、ほとんどの人が文明なるものを賛美した。ルソーの説は主流の意見に欠けていた心理が大量に含まれていた。簡単(自然)な生活のすばらしさ。人工的な社会の束縛と偽善は、人を無気力にし堕落させる。
公共に対する義務という考え方
この考えがヨーロッパに広まったのは、ギリシアやローマから受け継いだもので、キリスト教の考えではない。純粋な人間教育は、宗教教育とは別である。神による服従が唯一の価値であると認める道徳基準からは生じ得ないものである。キリスト教の真理の言葉は(イエス)キリストの言葉以外ないが、キリスト教会がキリストの言葉をもとに構築した道徳体系はキリストの言葉を脇に追いやってしまった。こうした誤った偏狭な理論は、異なった意見の排除に向かう。至高の意志(神)に服従することが、至高の善という概念に到達することも共感することもない。それは低劣で卑屈な奴隷のような人を育てる。現にいま、それは進行している(ミルのいた時代の言葉なのだ。そして、その言葉は再び蘇らさねばならない)。
ここまでのまとめ
1、発表を封じられた意見は、もしかすると正しい意見かもしれない。そのことを否定するのは、人間は絶対に間違わないと仮定することだ(歴史的に人間は間違える)。
2、発表を封じられた意見は、間違った意見であっても、一部分の真理を含んでいるかもしれない。また含んでいるものである。そうした対立する意見のぶつかり合う場合のみ、真理の残りの部分が得られる。
3、世間で一般的に受け入れられている意見が真理であっても、議論されない状態が続くとその意見は偏見となって、合理的な根拠もなく理解もされず、実感もなく硬直化していく。
4、自由な議論がされないと、その真理もぼやけてしまう危険があり、権力者によって拡大解釈される。それは人の成長を妨げ、理性や個人的体験からの確信を得られなくなる。
表現の自由にも限界がある。ふつう、議論の場で不当とされるのは、口汚い非難、嘲笑、人身攻撃と言ったものである。そういう武器の使用を禁じれば対立し合う意見も納得する合意が得られる。だが実際にそういう武器を禁じられるのは反対意見に対してだけなのだ。そうした武器を弱者に対し用いると弊害が大きくなるばかりなのである。制限されるべきは支配的な意見の方なのだ。何故なら、弱者の意見を封じることは暴力(実力行使)しかなくなるから。
幸福な要素としての個性
自分の自由な意見を持つことも表明することも、人間には絶対必要なものである。自由が禁止されると、人間の知性にとって有害であり道徳にも害が及ぶ。人間が自分の意見にもとづいて行動する自由は必要なのである。
つまりそれは自分の意見を自分の生活において実行することは、自分の責任でなされるかぎり、周囲の誰にも妨害されず、自由に行える。そういう自由は必要なものである。
自分の責任でなされる限りという条件は外せない。
人間は間違いをおかすものであること。
人間が不完全な存在であるかぎり、さまざまな意見があることは有益である。同様に、さまざまの生活スタイルが試みられることも有益である。他人の害にならないかぎり、さまざまの性格の人間が最大限に自己表現できるとよい。誰もが、さまざまの生活すたいるのうち、自分に合いそうなスタイルをじっさいに試してみて、その価値を確かめることができるとよい。
自発性こそ尊重されるべき考え方である。ただ大多数の人は現状のあるがままの生活に満足(我慢)している。それは、現在の状態は彼らが作ったものであるから当然だとする意見は、この状態に不満を抱く人を理解出来ない。自発性は彼らの理想ではないからだ。
「すべての人がたえず努力すべき目標、また、他人に影響を与えたいと思っている人ならば特に保持すべき目標は、能力と成長における個性である」。そのためには「自由であることと、境遇が多用であること」の二つの必要条件である。(略)それが、「独創性」となる。
伝統や慣習は、かれらの経験が何を教えたかを示してくれる証拠であるが、それは他の人々の経験が狭すぎて間違って解釈されてきたのかもしれない。かれらの解釈は彼らには適切であるが他のものには不適切かもしれない。その習慣が良いものであっても、ただの慣習だから従うのでは、自分の内部での育成も成長もない。洞察力、判断力、識別力、学習力、さらに道徳感情を含む人間の諸能力は、選択を行うことで鍛えられる。慣習は、選択を行わない。最善なものを見分ける能力や望む能力が育たないで、形骸化していく。
そもそも人間とは、機械のようなものではない。機械は、ひとつのモデルに従って組み立てられ、あらかじめ定められた作業を行うだけだ。人間はむしろ樹木のようなものである。自らを内部の力によって成長させていく。
ある人の欲望や衝動が、強く多様であることは、その人のほうが人間性の素材をたくさんもっていること。その人は多くの悪をなしうるが、しかしまた、確実に善もなしうる。それは個人の性格を育てる。欲望と衝動がない人は、何の性格ももたない。機械や奴隷と同じである。
人を管理、統制する社会は、そういう欲望と衝動を束縛しなければならない。そのバランスなのだ。今日では社会の方が個性をかなり制限している。
現代人が自分に問いかけるのは、自分が何をしたいのか?である。
個性とは人間として成長することである。個性を育ててこそ、十分に発達した人間が生まれる。
現在、個性は群衆に埋没している。いまでは世論が世界を支配すると言っても誰も驚かない。
世論と呼ばれれるのがどういうひとびとの意見なのかは、かならずしもどの国でも同じとはかぎらない。
世論の専制は、変わった人を非難するものだ。だから、まさしく、この専制を打ち破るために、われわれはなるべく変わった人になるのが望ましい。現在、あえて変わった人になろうとする者が極めて少ないことこそ、この時代のもっとも危うい点なのである。
画一化の傾向は現在も進行中である。現代の政治の変化全体がこの傾向を促進している。教育・交通手段・商工業の発展は画一化をもたらした。その生活スタイルから逸脱する人は、不信心、不道徳、醜悪で人間にそむくものとさえかんがえられるにいたる。
個人にたいする社会の権限の限界
ミルは社会契約説を否定する。しかし社会の保護を受けている人は、その恩恵に報いなければならい。社会の中で他者に対する一定の原則があると考える。それは1つには、互いの利益を侵害しないこと。2つ目は、社会とその構成員を危害や攻撃から守るため、それを公平に全員で分担すること。
1は、相手に損害を与えない限り個人は完全に自由である。その結果の責任は自分が被る。これは自分を大事にする美徳は社会の美徳の次に大事なものである。その二つを育てるのが教育である。
他人の権利を侵害することは、社会的な処罰や制裁を受ける。
2の社会の権限は、個人の生活の自由を侵犯してはならないし、現に我々の社会は自由の侵犯はますます激しく行われている気配なのだ(ミルが生きていた19世紀の時点でそうだったのだが、この指摘は最近の日本でも特に感じられる)。それは世論が支えている。いくらでも禁止できる無制限の権利があると思わされている。例えば禁酒ということがある国や州の場合い法律によって禁じているからと言って、それは実際上に飲む人が多くいれば禁酒法は解除される。それは禁酒する側の社会的権利を主張する意見は、自由に商売したり酒を飲んだりする権利を弾圧するのならばさらに危険なものである。この原則は、自由に対する侵害を正当化する一歩になりうるのだ。そうした宗教や道徳上のものは、原則が変化する場合があるのだ。そうなるとより自由な国の方へ人々は向かうだろう。
けれどもミルは悪法が存在する国に他の国が干渉すべきではないという(国の思想も自由だとするのだが)。それはその国の文明であるならば遵守される必要がある。ここでの個人との自由の問題は、国家とバッティングすると思うのだがミルは明確な答えを出していない。というかこの本が個人の自由論なので、国家論ではないということなのだろう。ミルのベンヤミンから受け継いだ功利主義的な思想があり、その思想の元からの展開しているのだと思う。
原理の適用
教育は国家が管理すべきではない。そうしたミルの思想で教育が重点に置かれるのは、それこそ教育は個人の自由を尊重して、国家から切り離されて行われるべきなのだ。国家は自由な人権よりも隷属的な服従者を育てようとする。
それは官僚の支配する社会にも言えることで、官僚的な人間に育てば育つほど国民の奴隷化が進んでいく。官僚は自らの組織とその規律の奴隷になる。中国や日本の官僚制度とキリスト教国の聖職者は教団の奴隷となることで信者を支配していく。官僚組織を監視する外部の優秀な者がいる機関が必要である。そうしない国はたちどころに政治は滞り、進歩のない社会になっていく。政府が大きくなると、ひとびとの自由と進歩にとって怖ろしい弊害が起きる。しかし社会の全体の幸福にとって政府は必要不可欠なものである。社会全体の活動のうち政府が扱う部分が大きくなりすぎないような統治機構は難しい複雑な問題でもある。
効率を損なわない範囲での、権力の最大限の分散。
情報の最大限の集中と、中央からの最大限の発信。
民主主義の弊害、危険性は、議会の多数派が「人民の意見=真理」と見なすことである。抵抗する少数派の自由を不正義として抑圧する問題が近年出てきている。日本はその国の一つだろう。それはアメリカの民主主義の影響もあるのかもしれない。トクヴィル『アメリカのデモクラシー』でも「多数派の専制」に陥る危険性を指摘している。ミルも「多数派の専制」問題をクローズアップして、『自由論』が書かれた。
父権的干渉主義(パターナリズム)は、公共の利益を標榜する多数派の論理と結びつくと反対意見が言いづらくなる。同調圧力は、人々を隷属化し考えさせないようにする。
ミルの「私的領域」に属する「自由」
1、内面における良心の自由
2、人生設計における目的追求の自由
3、個人の団結の自由
これらは公的領域から切り離して、個人の自由としなければならない。そのための「思想と言論の自由」の重要性。ミルは多様性の思想が意見として議論され、切磋琢磨する社会「思想の自由市場」論を最初に理論化した。ネット社会では人々の政治参加も容易になった反面「世論の専制」の危険性も高まった。情報を操作する国家があることに注意しなければならない。サンスティーン『インターネットは民主主義の敵か』。同質の者ばかり集まり閉鎖的な社会になりやすくなるという「サイバーカスケード(エコーチェンバー現象)」は極端な思想に走りやすくなっていく。トランプ現象とか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
