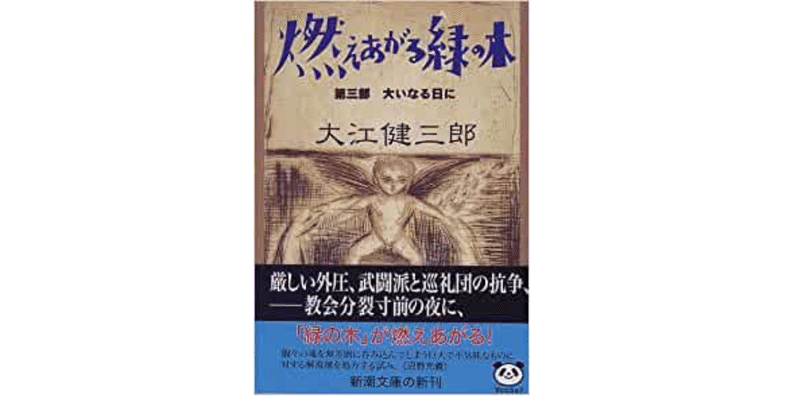
歴史の受苦から”Rejoice”へ
『燃えあがる緑の木〈第3部〉大いなる日に 』大江健三郎(新潮文庫)
教会を離れた私が性の遍歴から帰還すると、襲撃を受け障害者となったギー兄さんは、遥かに大きな存在となっていた。しかし、戦闘力を増す農場派と巡礼団の対立が深まり、巨大化と外的緊張の中で分裂の危機を迎える教会のメンバーに、ギー兄さんは最後の告白を行った。そしてその夜「緑の木」が燃えあがる! 「神」に極限まで近づき、なお新たな道を求めるライフワーク、完結編。
第三部はサッチャンのギー兄さんの教会から離れたところから始まる。それは遍歴ということなのだが、性の遍歴なのである。それは両性具有として新たな生まれ変わりとして、ギー兄さんではもの足りなかったのかもしれない。それとエロスとタナトスということを目論んでいたかもしれない。エロスはサッチャンの遍歴であり、タナトスはギー兄さんの魂の救済である。
後半になってヴェイユが出てきたのがよくわからなかったのだが組織論に組みせずあくまでも個の救済がテーマだと思った。
文学である楽しさを描いている点で村上春樹と共通したものを感じるのは、河合隼雄の「中空構造」というか同じところをぐるぐる回っている気がするのだがそれは中心のなさじゃないのか?中心があるものは権力にならざる得ない。それがオウム真理教とかのカルト宗教の恐ろしさである。それは全体主義的なシステムになっていく。個人はそのシステムから逃れたところに文学という魂の救済を求めるのではないのか。それは喜び(快樂)をもたらすものでもある。
地下鉄サリン事件以後に村上春樹は『1Q84』を書いた。それは大江健三郎『燃あがる緑の木』を踏まえたようにサッチャンは青豆になったように感じた。しかし青豆もいき詰まる。それが解決される物語でもなかったのは解決できない社会的現実は個々の救いしかないのではないのか。
大江健三郎の『燃あがる緑の木』はオウム事件の前に書かれたのだ。そして刊行したのが地下鉄サリン事件の月だという。大江健三郎自身が岩波新書の『日本の「私」からの手紙』の中でそれまでのカルト宗教は内なる自決であったものが外に闘争を求めていくあり方が作家の想像力を現実が超えていたと書いているのだが麻原彰晃が権力を求めたのに対してギー兄さんは分散化を願ったのだ。それは大江健三郎の「魂の救済」は宗教ではなくて文学だから、世界を救いたいというのではなく、せいぜいのところ個人の救済なんだと思う。
K伯父さん(大江健三郎)は無神論で文学に救いを求めているからイェーツやダンテの引用も文学として引用している。それは個々の読みという解釈が大きく関わって行きながら外へ開かれていく通路を導き出しているのではないか。世界は闇夜なのである。そして生きている者だけではなく死者たちの声にも耳を傾けることも必要だと。
聖書の福音書も一元的な読みではなく多様な解釈としての個々の読みである(むしろ一つの聖書ではなく多くの書物の福音から魂の救済はなされるのではないか)。それが受苦となって身体的に刻印される。ギー兄さんが教祖になれなかったのも個人としての受苦でしかなかったから。その受苦を両性具有のサッチャンは背負きれなかった。ただギー兄さんの喪失はサッチャンの受苦として受け入れられたから次なるステップがあったのだ(サッチャンは語り手としてこの受苦を引き受けた、そして、それを”Rejoice”に変えていく方法も。)
原発を停止させるというこは、この頃はまだ危険だとは思われてなかったのだな。新たな禍に見舞われたことで現実から学ぶことは多いがそれで身動きできないこの地上に繋がれた身体性を魂へと開放していく読書だとは思う。今のところ出来るのはそのぐらいだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
