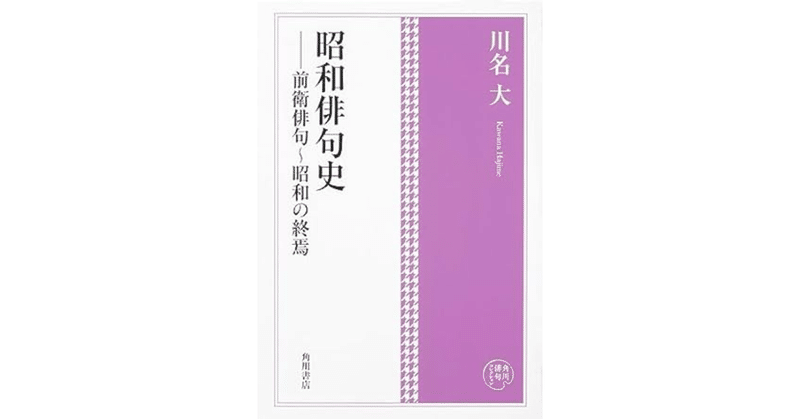
『昭和俳句史』俳句のカルチャー化は何をもたらしたのか?
『角川俳句コレクション 昭和俳句句史 前衛俳句~昭和の終焉』川名大
昭和の俳句は鮮烈だった。俳句史研究の第一人者が膨大な文献資料から分析・考察した、俳句表現に現れた新風の記録。昭和俳句史、決定版!
目次
1 前衛俳句の勃興―昭和三十年代前半
2 入れ子型の俳壇の断層―昭和三十年代後半
3 昭和世代の台頭―昭和四十年代前半
4 二項対立の時代、俳壇・総合誌・読み・物と言葉―昭和四十年代後半
5 眼高手低の時代、戦後世代の台頭―昭和五十年代前半
6 俳句の大衆化と戦後世代の新風―昭和五十年代後半~昭和の終焉
昭和の俳句史を句作から批評まで網羅した本。昭和の前衛俳句が中心だが、やがて現代俳句協会の分裂で、現代俳句協会の『俳句研究』と俳人協会の『角川 俳句』に分裂するのだがその時代はジャーナリズムの台頭で大衆化されてゆく。それと共に前衛俳句は尻つぼみになっていく。『俳句研究』は高柳重信というオーソリティの元で専門的になっていくがそれは俳句の分化を促していったのだと思う。今は角川俳句一強の時代で実質虚子が提唱した伝統俳句の勢力なのだというのは、この本が角川から出ているというのも頷ける。昭和俳句史の流れがよくわかる本だ。批評と共に多くの作品が掲載されているので、俳句史(前衛俳句寄りだが)を知りたい人には必読書と言えるかもしれない。
1 前衛俳句の勃興(昭和三十年代前半)
戦後金子兜太が前衛俳句運動の一環として「社会性俳句」を唱えたがそれに伴い中村草田男の議論があった。それは季語の扱い方の問題で、時代が変われば季語も変化していくものであり、いつまでも季語に寄りかかってばかり居るのは権威主義的だという金子の主張に対して、季語は古来からの日本の伝統であり日本人の精神そのものだというのが中村草田男の反論であったのだが、俳句が連歌や俳諧として座の文芸であったときには、俳句の挨拶として季語を読み込んでいたというのは納得がいく。その後に俳句がそうした座の文芸から離れて独自に詠まれるようになると季語と個人の季節感は合わなくなる。そこで新しいことを読もうとすると日本的季語から離れていくのではないか?
しかし、ここでの議論は「社会性俳句」がイデオロギーとして例えばマルクス主義の下部構造として詠まれてしまう。狭義の社会変革としての運動の一部ではないのかという批判に対して、金子兜太は個人で社会を読めばそれが社会性俳句となるのであって、それは狭義の社会変革の組織(例えば共産党とかの下部組織)の運動ではないとしたのであった。
しかし実際にそうした原爆の俳句が詠まれたりしたこともあり、戦後世代から新しい運動として文学運動「ユニコーン」の活動があった。
当時の高柳重信と金子兜太とは違う主張を持った俳句文学運動だったが(リーダーの安井浩司はこの二人を倒さなければならないと明言していた)、実際にはそれぞれ個人の違いが大きくまとまりのある運動にはならなかったようではある。
その後に大岡信が「季語論」で金子兜太との議論がなされていく。これも表現論で難しいのだが、新季語としてなりかわるものとして、渡邉白泉が「戦争」や「労働」を上げたけど、それは季語としてよりも事件として、例えば戦争体験は一つの事件として自然の循環の中には収まらないものであると捉えたいのだ。そうした個人がそれまでの権威的季語に寄り掛かるとスーパーではネギは一年中売られているのに冬のものだけだみたいな齟齬が生じてくる。また明確な季語がなくとも季節感は演出できる句として、
擦過の一人記憶も雨の品川駅 鈴木六林男
では「品川駅」が季語の代わりとして別離の象徴として詩語として成り立っている。例えばそこに中野重治の詩『雨の寮 品川駅』を連想させるものだ。その別離のシーンは、現在では進学する息子と親の別れ、先日のNHK俳句で詠まれていた、季語に成り代わる言葉だと思う。
2、入れ子型の俳壇の断層(昭和三十年代後半)
このへんは社会性俳句とか戦後俳句とかいろいろ入り乱れて混乱するのだが、その混乱の元になった飴山實だった。飴山實が登場したのは前衛俳句の理念に賛同して(金子兜太の造型俳句の影響を受けていた)、旧世代を批評していくのだが、前衛俳句が社会性俳句として社会主義的イデオロギー化していく党派性(共産党系)から金子兜太らを批判していくのだが、それは前衛俳句の表現形態と社会性俳句の生活形態の分岐を目指してのものだが、今ひとつ社会性俳句の概念がはっきりせずに前衛俳句から伝統俳句側へ転身していくのだった。
飴山實が提起したのは「作者の心音が聞こえる俳句」というなんともあやふやな精神論じみて境涯俳句との区別も曖昧化していく。それは中村草田男と金子兜太との議論から後退したものだったが、理論と俳句はまた別のことで、飴山實の俳句を比較すると後者の方がよくなっているという。
島を働く姿(なり)で錆びつく一人づつ
飴山實自身がそうしたイデオローグに染まっていたといたと言えるのかもしれない。
小鳥死に枯野よく透く籠のこる
そうしてそうしたイデオローグを取り去れば伝統俳句と変わらないものになっていた。つまり自己批判して転向した俳人と言えるのかもしれない。川名大はそうした飴山實の転身を有言実行ということで称賛しているのだが、それがいままでの中村草田男のいうような精神論と変わらないような気がしてくる。飴山實の弟子が長谷川櫂というのも納得できる。形式と内容の統一という精神論は新古典主義の保守化のような気がしてくる。表現が難しくなっていくのだ。
うつくしきあぎととあへり能登時雨
「あぎと」が普通は理解出来ない。
川名大の解説では「あぎと(顎)」を女性に見立て、しっとり能登の時雨模様に浮かび上がらせているとか。「能登時雨」という音韻も声調が美しいという。そういう感性の問題になってくるので、難解化してくるのだと思うのだ。どこまで難解用語を使ったら勝ちみたいな能力性はAIにでも任しておけばいいのである。その句が共感を得るかどうかだと思うのだが、あ行の音韻がいいかなぐらいだった。意味は近づけないのだから。
そうした流れは飯田龍太・森澄雄という旧世代の遺産を引き継いだ俳人によって強化される。飯田龍太は飯田蛇笏の息子であり、森澄雄は加藤楸邨の弟子系であり、人間探求派を継承していく。その二人を批評で取り上げたのが山本健吉であり伝統俳句化していく俳壇の潮流だったのだ。
戦後派俳人が「龍太・澄雄」という看板が立ってしまうとその他は亜流であって主流にはなれない。目配せをすれば、三橋敏雄や永田耕衣、阿部完市や河原枇杷男もいるのだが、山本健吉は角川の俳人協会のプロパガンダとして、前衛俳句や社会性俳句を祀り去ったと言える。ここに「戦後俳句」概念(理念)の終焉と第四世代の保守化となっていくのであろうか?
3、昭和世代の台頭(昭和四十年代前半)
入沢康夫『詩の構造についての覚え書』で作者、語り手、作中主体(語り手の「私」)は別なのだという詩の構造を述べたのだが、日本の短歌や俳句ではそれらが統一主体とみなされていた。
その意識の違いが境涯俳句の「俳句は私小説」だという一派と「俳句はフィクションである」という新興俳句系の分かれ目だった。そのことで寺山修司は和歌の本歌取りという方法でフィクション性の「私俳句」を創作したのだが理解を得られなかった。そして俳句の閉鎖性に辟易して、表現の場として短歌に進むのだった。
作者と発話者が区別がない俳句
いくたびも雪の深さを尋ねけり 正岡子規
俗に言う私小説的な俳句で解釈としては作者の伝記を知っていたほうが深く読める。
桐一葉日当たりながら落ちにけり 高浜虚子
この句は語り手で虚子(わたし)が黒子となり三人称(神の視点)で語っているのである。ただそこにも注意深く読むと一人称の語りが透けて見えるという。この句の場合「落ちにけり」という詠嘆が虚子の内面が透けて見える。この方法は境涯俳句や客観写生に多いという。
作者と登場人物が明らかに違うと分かる俳句。
大戦起こるこの日のために獄をたまわる 橋本夢道
作者の橋本夢道と獄に入れられた人物は別人。
わすれちゃえ赤紙神風草むす屍 池田澄子
作者は池田澄子だが私は逆説を述べている。現代人の忘れっぽさを皮肉った句。
南国に死して御恩のみなみかぜ 攝津幸彦
これも死人がかたるわけがないので作者と死人は別人である。戦争への社会詠は実際に体験者でなくとも戦争俳句は詠めるのだ。そのことで戦火想望俳句で衝撃的に登場したのが三橋敏雄である。
手を上げて此世の友は来りけり 三橋敏雄
あの世からこの世に友はくるはずはないという歌で、友は英霊となった親友を想う浮かべるのだろう。
切株は じいんじいんと ひびくなり 富澤赤黄男
「じいんじいん」というオノマトペは「切株」と共にメタファーである。「寺院寺院」とも読めるかも。
三番目は明らかに作者と登場人物が別だとわかるもの。二番目と同じようなのだが、二番目は作者と登場人物が重なるように書かれている。三番目は作者と語り手がはっきり別人のように書かれている。しかし、俳句や短歌ではこの例は極めて珍しいという。
蛇を知らぬ天才とゐて風の中 鈴木六林男
これは意味が良くわからん。鈴木六林男はかなり前衛的なのか?
藤田湘子は作者と登場人物の区別は有効だとしながらも発話者と作者も同一人物にしているので、それが俳句の限界のように捉えられている。一人称を三人称的神の視点で考えれば、一人称の我も作者とは別人でフィクション上のことである。その思考はモダニズムの小説を読んでいれば当たり前の理論であり、作者と一人称の私は別人で虚構のために作者が用意した登場人物であるのだ。それは作中主体を作者と同じように受け取ってしまう日本の短詩の遅れだろうか?短歌では実験的な塚本とか寺山が出てきたので、例えば穂村弘の作中主体を穂村のフィクションと考える事ができる(同じだという人もいるだろうが)。鈴木六林男の俳句なら天才=鈴木六林男ではないのだ。これは言語学の理論みたいだが、俳句の批評が内輪だけなのでそうした理論に疎いような気がする。
夏目漱石『こころ』で考えればわかりやすい。漱石と先生の関係は作者と語り手なのだが『こころ』という小説の中では手紙の部分が先生の一人称であり、それを漱石自身だと重ねられないということなのだ。何故なら手紙以外は三人称的な私(一人称)で神の視点で描かれている。漱石が問題にしたのは明治の精神だが、それが漱石そのものの思考だと考えるのはもうひとりの登場人物である「私」の視点があり、それが先生への批評として機能しているのである。この「こころ」を漱石の心だと受け取ってしまうのが、単純な心しか問題にしていないので、先生のこころ、私のこころ、漱石のこころと入り組んだ『こころ』という作品なのだ。
4、二項対立の時代(昭和40年代後半)
現代俳句協会と俳人協会の分裂以降、2つのジャーナリズム雑誌によって俳壇が二分されるのであった。『俳句研究』=現代俳句協会、『角川 俳句』=俳人協会。その中で俳人協会の排除ぶりが凄まじいということだった。1968年は全共闘世代のカウンターカルチャーの時代。俳句界もその流れはあるようだったが、寺山修司の批判などもあり保守化していく。
社会性俳句は暗礁に乗り上げ、個人は自然讃歌や精神性回帰という時代になっていく。龍太・澄雄はその象徴だった。そんな中で高柳重信が編集長時代の『俳句研究』で50句競作が出ることになる。それは俳句が短詩一句よりも50句まとめた作品とすることで芸術的表現となるということか?現在のプロ作家との分かれ目がここにあるのかもしれない。50句という連作が作れる力があることのような気がする。
戦後生で活躍した俳人としては攝津幸彦や坪内稔典。シュールレアリズムの影響を受けた阿部完市がいる。
『俳句研究』の方で批評も活発になるが「わかる」「わからない」俳句とか「言葉」と「もの」の違いとか難解になってわからなくなっていく。現代詩との絡みだと思うが、俳句がサンボリスム(象徴詩)を通過してないという指摘。つまり象徴は言葉の概念であり、自然のものを詠んでいるというのではないという。それは宮沢賢治の心象スケッチというような、心象風景の言葉の問題を現実の自然の世界と取り違えてしまうという方法論的なことなのか。フーコー『言葉ともの』あたりの思想なのかもしれない。
5 眼高手低の時代、戦後世代の台頭―昭和五十年代前半
戦後活躍していた世代は戦争を体験していたり激動の時代だから、そこから新しいものを作り出すことに懸命になっていた。金子兜太の前衛俳句運動にしてもそれに異を唱えた中村草田男の伝統俳句にしても議論は活発だったわけで、そうした動きや外部からの批判もありながら高柳重信が『俳句研究』の編集などしたりして、虚子の伝統俳句を批評するという流れはあったのだが、全体的に低迷していく。それは二極化が顕著になり、それが現代俳句協会の『俳句研究』と俳人協会の角川が出す『俳句』の対立構造である。そして大部分は有季定型の伝統俳句になるわけだが、それは初心者が学ぶのに学びやすかったからである。短詩という形の中で制限が設けられ、それは文学というよりも座の文芸としてゲーム化していくのだった。それはジャーナリズムに移行していくに従い大衆化していく定めだったのかもしれない。
その中で戦後生まれの俳人たちは旧世代の批評をしていくのだが、それは戦後の議論の焼き直しにしか過ぎなかった。そんな中でますます個人的な句が多くなる。むしろ旧世代の俳人たちが自身の作風を熟成させていくことで注目されていくので、戦後生まれの新世代は、より難解な句や自己中の句にならざるえない。例えば『俳句研究』では高柳重信が俳句新人賞として「50句競作」というハードルを設けるが、それが難解俳句や一般的にはわかりにくい俳句になっていく。
そういう中でも細部を見ていくと俳句手法についての議論がなされるのだが、それらは専門的な議論になって一般人にはわかりにくくなっていく。
例えばこの時代を皮肉った加藤郁乎の句。
小火(ぼや)と云ふいはば現代俳句かな 加藤郁乎
春しぐれ十人とゐぬ詩人かな
そんな中で高柳重信の「五十句競作」から登場した澤好摩の同人誌「未定」や坪内稔典らの「現代俳句」という同人的な活動はあったのだが、一般的には角川俳句の時代だった。その中でかつての前衛俳句運動に関わっていた三橋敏雄が『真神』で注目を浴びるのはそれが伝統回帰の俳諧的手法だったからで、そのことは坪内稔典らの批判を浴びることになった。
ふるさとや多汗の乳母の名はお福 三橋敏雄
手を上げて此世の友は来りけり
戦後生まれ世代の難解俳句や曖昧俳句に対して「読み」の方法論から高柳重信の厳密な俳句方法論(言語的な)が出てくる。それは象徴俳句として、意味のない取り合わせや独り善がりの「朦朧俳句(曖昧な俳句)」が多く産出されるのに釘を刺した。それは金子兜太と飯田龍太の座談会での感性の問題として対立することになる。例えば、
石一つ水紋堕落夏の果 今井静
高柳は「堕落」という言葉はここでは相応しくないといい、石を水面に投げて水紋が出来るのは当たり前であるという。「堕落」が前衛っぽさを醸し出しているだけで、ただごと俳句だと断罪する。それに対して金子兜太は「堕落」を新しい表現として評価するのだ。
野仏が刺さり断末の梅の山 谷佳紀
これも「断末」という言葉は正確ではなく「断末魔」を省略しただけの句で高柳は「断末」だけでは意味はなさないという。「断末魔」は「末魔」を断つという意味だから、この省略は無意味だという。それに対して金子兜太は「断末」という感性は理解出来るという。
こういう議論になると個々の感性の違いであり(高柳や龍太は言語が共同体のものなら正しく使うべきだという意見)、読み手側の解釈によって大きく評価が変わってしまう。その先例として、
満開の森の陰部の鯉呼吸 八木三日女
の句はエロス的女体の読みを誘うが本人は池での写生句だといい、作者と読み手の解釈の違いがある。また別の例では、金子兜太「山上白馬五句」の読みで「白馬」を象徴と取るか実際の固有名で取るかによって解釈の違いがでてくる。たぶんにこれらの議論は作者の深層心理は作者以上に読み手によって判断されるものなのだ。そこから誤読が生まれむしろそれは閉じられた世界ではなく開かれた運動となるのだと思う。そこは言葉の厳密さだけでは推し量れないものがあると思う。何よりも言葉は生もので、権力によって定義されるべきではないからだ。
そのことと関連してか「軽み」論争が起きる。それは表現として「軽み」の俳句を提唱した山本健吉への反論として、俳句の「重い」「軽い」を判断するのも読み手にかかってくるのだし、芭蕉の晩年の句(仏教的な世界観なのか)は「軽い」「重い」で判断出来ないとする。この辺も読み手の問題であり、それは読みは訓練によって感覚が押し開かれるというのがある。
6 俳句の大衆化と戦後世代の新風―昭和五十年代後半~昭和の終焉
俳句が結社からカルチャー教室化していくに従って、定年退職の者たちや主婦らの活動拠点になり大衆運動化していく。そのことは俳句が受け入れられると共に停滞化を引き起こす問題にもなる。何よりも俳句がビジネスとして、俳人のサラリーマン化が進み、角川一強の時代となっていくのだ。高柳重信が亡くなると『俳句研究』も角川に吸収されていく。そのことに危機感を持った若手俳人が『俳句空間』を創刊するがそれほど反響を得られなかった。
角川一強時代は、まさに虚子時代の到来であり、俳句が個人主義の時代へとなっていく。それは社会や俳句変革運動には関わりたくない者たちによって、ビジネスとしての俳句でありカルチャー化がもたらしたものは停滞でしかあり得ない。そこに角川の主張する伝統俳句がすべてになって新しい俳句が生まれにくい状態になっている。俳句としての智識を伝えるカルチャー化は定年退職者や主婦層の活躍の場になるが、批評の停滞、伝統俳句の一元化という状態になって、俳句の没個性が言われるようになる。
そんな中で少数の俳人が批評活動を続けているような状態であり、そうしたものは表には出てこないで地下活動のような様相になっていく。指導者は伝統俳句の者で占められ彼らが先生としてサラリーマン化していく文化(カルチャー)活動でしかなく、芸術と呼ぶことがもはや出来ない状態なのだと思う。それはゲームのように俳句を愉しみ、高得点の者の承認欲求を満足させる場でしかないのだ。そんな状態で新しい刺激的は俳句は生まれてこない。現に過去の偉大な俳人の作品を崇めるだけになってしまっている。
俳句のバラエティー化は「俳句甲子園」「プレバト」を生んだのだが、そこから革新的な俳人は生まれているのだろうか?疑問である。
この本が角川から出ているのもそうした事情なのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
