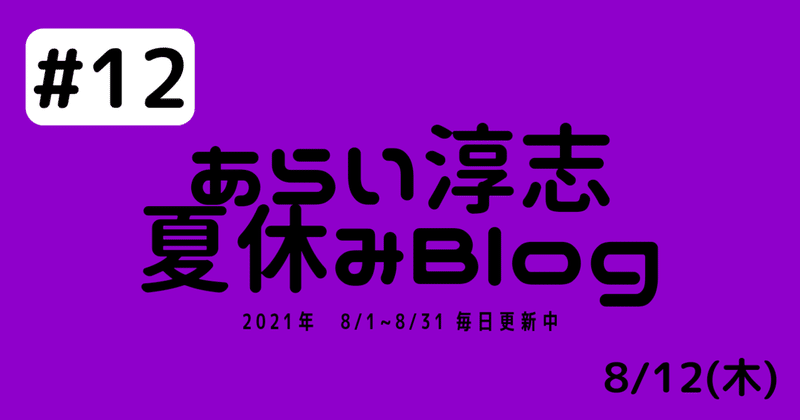
#12「見えない妥協の問題点①」8/12
金沢市で政治の活動をしています『あらい淳志』です。
昨日はブログを書けませんでした。
気づいたときには、すでに眠ってしまっていました。申し訳ありませんでした。
前回から、日本の『国会』を題材に、記事を書いています。
今日は、「実際に、日本の国会はどう動いてきたのか」を見ていきます。
見えないところで妥協する
日本の国会は、表面を見ていると茶番に見えます。
ですが、実は、裏で、色々な駆け引きをしているのです。
国民には見えないところで、それをやっています。だから、国民からは、政治が何をやっているかが分からない。
同時に、裏でこっそり利害の調整をするから、大胆な改革ができなくなる。
『見えないところで、妥協をする。』
ある意味では、それを「政治の技術」と呼ぶのかもしれません。
でも、その技術は、国民には見えません。
だから、技術が悪用されても、分からない。
大多数の国民と政治との距離が遠く、ときに一部の利権と政治が急接近をしてしまう原因も、ここにあります。
これが、政治不信の一つの原因だと、私は思っています。
日本の国会は、変換型>アリーナ型
前回の宿題の答え合わせをします。
日本の国会は、『変換型』か『アリーナ型』か。
先に、私なりの答えを、発表してしまいます。
答えは、両者の中間です。ハイブリッドになっています。
ただし、どちらかと言えば、『変換型』の方が強く出ているのが、日本の特徴だと私は思います。
ちなみに、時代によって、変換型とアリーナ型の出方は異なります。
昭和の時代は、より『変換型』が強かったです。
平成に入り、日本は『アリーナ型』を目指して改革を進めました。
かつてに比べれば、『アリーナ型』が強まっています。
それでも、改革は終わってはいません。
『変換型』が色濃く残り、日本独自の形で『アリーナ型』と融合しているような状況です。
今日はまず、昭和の国会を、見ていきます。
昭和の政治:55年体制
私は、最初に、「裏で駆け引きをするのが、日本の国会だ」と言いました。
これはすなわち、『変換型』だ、と言うこととほぼ同義です。
昭和の時代の国会は、皆さんご存知の通り、55年体制といって、自民党が1党優位体制を築いていました。
もう一方には、社会党がありましたが、政権を取れるほどの勢力は持っていませんでした。
基本的には、多数派である自民党の提出する法案がほぼ、国会で可決成立をするわけです。従って、国会における、与党の影響力の大きさには、議論の余地はありません。
それでは、多数派である自民党の思うとおりに、全ての物事がうまく運んだか? 答えは、NOです。
自民党内にも、色々な考え方をした議員がいたからです。
さまざまな議員がいて、党内で常に競争がありました。近しい議員で仲間を組むと、いわゆる「派閥」になります。
(派閥ができるのは、選挙制度との関わりがあるわけですが、それはまた別の機会に紹介します。)
国民の多様な意見は、この派閥を通じて、自民党内での調整を経ながら、政策へと転換されていったのでした。
党内の利害調整
法案の中身は、自民党内で一通り決めてしまいます。
党内決定までの間は、各議員が自分の意見を存分に主張し、自分の意見をなるべく取り入れてもらえるよう、働きかけるわけです。
色々な議員の利害関係を調整し、一つの法案にまとめ上げる。まさに「民意」から「法案」への「変換」作業に他なりません。
そして、自民党内で決まったものは、党の決定として国会審議にかけられ、基本的には多数派だから、そのまま可決をされていく。
すでに結果は決まっているから、国会での審議は、それほど重要ではありません。利害調整は、党内手続きでほぼ、済んでしまっているわけです。
利益誘導政治
自民党内の手続きとはいえ、それなりに国民の多様な意見を反映しながら政策を決めていたわけで、「このやり方が全て悪い」ということでは決してありません。
当時は、それなりに、多くの皆さんが納得していた部分もあったのではないでしょうか。だからこそ、自民党は政権を維持し続けました。
党内で政策を決める際に、自分の意見を通していくには、それなりの知識や人脈が要ります。だからこそ、当時の自民党の議員は、自分の専門分野を作りました。それが「族議員」です。
彼らは、日本にある各業界の利益を代表するわけです。ある意味では、それも民意の一つの形です。
さまざまな族議員が各業界の利益を代表し、それぞれがそれなりに納得できる内容で政策を作ってきたからこそ、自民党政権は長続きしたのかもしれません。
カネのかかる政治
ただし、このやり方には、大きな弱点がありました。
業界と族議員の関係が、あまりにも接近してしまうのです。
それが『癒着』につながりました。
業界から族議員に賄賂を渡し、利益供与を図ってもらう。
族議員や派閥の仲間を当選させるために、選挙資金をばらまく「金権政治」がはびこる。
政治にとてつもない「カネ」がかかるようになったのです。
その結果、昭和の中頃から終わりにかけて、大きな汚職事件が頻発します。
「カネのある一部の人たちばかりが得をする政治はダメだ」となったわけですね。
決められない政治
同時に、党内で丁寧に議論をして、それぞれの議員の意見を律儀に取り入れていては、政策そのものがつぎはぎだらけになってしまいます。
無駄な政策や、大胆な改革が必要な政策があっても、党内に反対勢力がいると、そうした改革ができなくなってしまうのです。
大切なことを変えられない、決められない政治は、日本の改革力を削ぎました。
全体最適を考えたときに、個別の利益を守ることよりも、大胆な改革が必要な場合がある。
それなら、国のリーダーが責任を持って、大胆な改革を取れる仕組みにした方がいい。
そうして、昭和の終わりから平成にかけて、こうした『変換型』の日本の政治を変えようという、改革のうねりが巻き起こっていくわけです。
まとめ
今日は、昭和の国会で、政策決定の際に大きな影響力を発揮した、自民党内の調整の仕組みを紹介しました。ここで民意を変換する作業が行われたわけですね。
その特徴は、「見えないところで妥協する」ということでした。
明日は、野党側の民意がいかに政策に反映をされたかも、見ていきます。
与党内の調整ほど政策への影響力はありませんが、それでも野党には野党なりの影響力がありました。その特徴を紹介します。
同じように、ここでも「見えないところで妥協をする」という日本の政治の仕組みが見られるのでしょうか。
詳しくはまた明日。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
