
初めて書いたやつ!(に照らされて)
初めて小説を書いたのは小学五年生のときだった。
クラスに作曲ができる生徒がいて、凄いな、と憧れ、僕にも何か作れないかな、と思って書いてみたのが小説であった。
タイトルは『最後の八分』、原稿用紙で二十枚くらいだったかと思う。
「太陽の光、ってのはね、『八分』も掛かって地球に届くのだよ」
というようなことを授業で聞いて、それをヒントにSFふうの話を書いた。
ノートに書き付けたそれ、今はもう手元に残っていない。
でも記憶の中にはある。
小学五年生の僕にかえったつもりで、以下にあらすじを書いてみる。
主人公はノーベルト。アメリカ人の科学者。
頻発する地震と、太陽の黒点周期の関連性に気が付き彼は、太陽の、小さくはない爆発を予見する。
発表された事実に世界は大混乱。泥棒やいじめがたくさん発生し、ひどいありさまに。
ノーベルトは世界会議に出席、各国に人工衛星の建造をお願いする。
一年後に続々と打ち上がったのは、たくさんの植物に光合成をしてもらい、そのことで酸素を生み出し得る『バイオライフシステム』を搭載した人工衛星たち!
続いて衛星たちは、広々とした宇宙空間で壮大なるドッキングを果たし、大宇宙ステーション『セカンドアース』が誕生する!

そしていよいよ避難開始!
のはずだったのだが……。
国ごとに地球を脱出する、その順番で世界は揉めた。一番目にはなりたくない、と国々は言った。安全性が確かめられていないから。ビリにはなりたくない、とも国々は言った。逃げ遅れてしまうかもしれないから。
戦争が起こりそうになるのを、なんとか食い止めたノーベルト。
結局はくじ引きで順番が決まった。

ノーベルトたち北アメリカの住人は一番最後の順番だった。
世界が固唾をのんで見守る中、一番手の南アフリカチームは宇宙に出発、そして……。

無事に宇宙ステーションへの移住を完了した! 計画は成功したのだ!
その後世界は順調に避難を重ね、ついには北アメリカの番になり、そのまた最後の最後でノーベルトたちが住むエリアの番になった。
ところが脱出ロケットの最終号機に乗り込む段になって、大変なことがわかった。
ノーベルトの一人息子であるマイケルが居ないのであった!
いつもの川や公園を捜して回るノーベルトとその妻、つまりマイケルのお父さんとお母さん。
やがて消えゆく山や川、森や動物たちや、蝶や花……。
息子の姿はどこにもなかった。
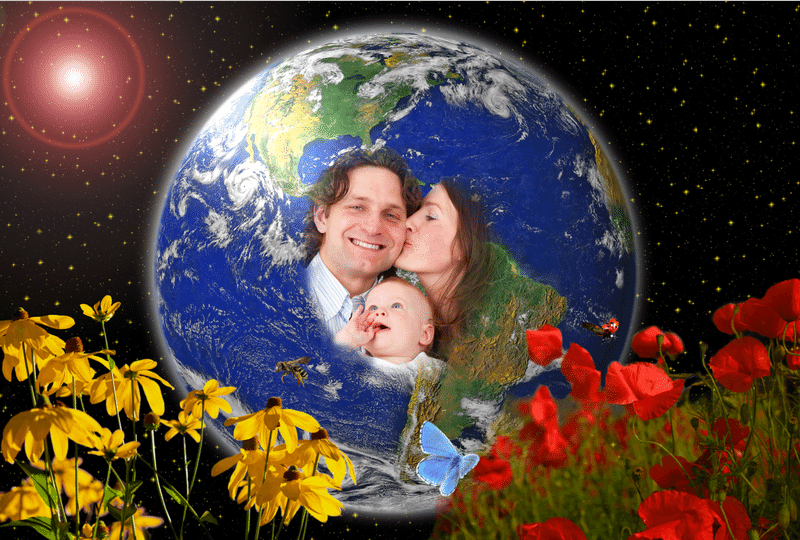
そのとき、太陽が爆発した。月と同じくらいの容積が吹っ飛んだのであった。
精度の高いコンピューターが、光よりも速くそのことを知らせ、けたたましく警報が鳴り響いた。
地球最後の避難民たちはパニックに陥った。
「安心してください、まだ八分あります!」
とノーベルトは叫ぶ。
しかし群衆は慌てている。
自分勝手を叫ぶ男、大地に伏して神に祈りを捧げる老婆、マイケルの身を案じて泣いてくれる若い娘……。
腕時計が時を刻む。
ノーベルトは葛藤する。
走馬灯のように浮かぶのは、マイケルが生まれた日のこと、三歳の誕生日の愛らしい笑顔……。
目の前に、避難民たちの不安そうな顔、顔、顔。その中の、ノーベルトを見上げる三歳くらいの男の子の表情に射抜かれてノーベルトは決断する。
「マイケルは……、置いてゆく!」
ロケットが飛び立つ。
小さくなる地球。
と、スーツケースからガタコトと音がした。
ノーベルトが開けてみる……。
と、なんと中からマイケルが!
幼いマイケルはかくれんぼをしたまま眠ってしまっていたのだ。
抱き合う親子。
ほっとして、窓の外の地球を家族は見詰める。
「最後の八分か……」
とノーベルトは呟き、同胞と息子を秤に掛けた数分について思いを巡らし、消えゆく人類のふるさとに心を震わせ、いったん目を閉じ、それから開くと、未来を、すなわち『セカンドアース大宇宙ステーション』の勇姿を見やって、マイケルの肩を引き寄せるのであった。
だなんてそんな話。
光のスピードに照らして爆風等の到達速度をどう捉えていいのか未だによくわからないし、精度の高いコンピューターなるものが、どうして「光よりも速く」爆発を察知し得たのか(あるいは事前に生じる予兆から未来の爆発を先取りして伝えたのであろうか?)不明だし、地球に影響を与えるほどの太陽爆発がなぜ宇宙ステーションには影響を与えないのか、そのへんの設定の雑さにも呆れてしまうのだが、ともあれさすがは小学生、『光合成で酸素を作る』だの、『混乱とはすなわち泥棒やいじめである』だの、『行方不明の息子という問題を「かくれんぼしてましたっ!」という脱力的なオチにより解決しちゃう』だの、発想が実に半径一メートル的で、ゆえに微笑ましかったりするので、この話、ホントにホントずいぶんと嫌いじゃなかったりする。
『公』と『私』とを対比させて描いているあたりにも、「十年程度の人生経験がもたらしうる洞察の深さをなめちゃいけないなー」と気付かされ、「コドモ、甘くみるべからず!」と背筋を伸ばしたい気持ちになったりもする。
でもって、さてさてこの話、実は印刷されて冊子になっていたりする。僕の手元にはないけれど。
四つ下の弟が、小学生だったとき、グループ制作で本を合作する際に〈なんと盗作しやがった〉のである(笑)!
弟が提出した『最後の八分』に、グループの女子が愛らしい挿し絵を付けてくれ、そしてそれらは美しいブルーの表紙をまとった本として、クラスの人数分きっちり印刷されたようなのである。

「上手に書けてたから、それで拝借したくなっちゃったんでしょうね」
と母が、いつになく丸い言葉遣いでとりなした。許してやってね、という意味だ。
僕の勉強机の引き出しから、弟がどんな気持ちでノートを引っ張り出したのか、尋ねなかったし、未だに想像もできない。
ともあれ、腹を立てたりはしなかった。
表現されたものが伝播してゆくことは好ましいことだし、ありがたいことである。
小学五年生だった僕の書いたものが、小学五年生である弟とその仲間たちにより出版されたのである。よきかな、としか思えなかった。
そんなわけで僕の処女作は、なんとちゃんと少なくはない人(子供たち!)に読んでいただけちゃったわけなのである。

あれからン十年、学生時代にもう一作書いて、 それが文筆の道を歩むきっかけとなったのだが、でも編集者になってからは人様の表現を拝読するのに忙しく、だから自分の創作活動をしてこなかったのだけど、退職し、堰をきったように小説やら、それに似た何やらを書き散らかすようになって月日が経った。
筆は速い。短いものなら一日で、長いものでも一週間以内に書き終える。一筆書き(?)をモットーとしている。一気に書き下ろす。そうしないと勢いが出ないから。
プロットを作っていた時期もあるけど、結局は作らなくなった。字数だけ決めて、大まかな構成のみで書き始め、書き続け、一気に書き終える。
だから初稿が上がるまでは短いのだが、でもそのあとが長い。
推敲にやたらと時間が掛かる。
文章というのは直し始めるときりがないのである。
もっとよいリズムを、だとか、もっと端的で、しかし深みのある表現を、だなんて求めてゆくといつまで経っても脱稿しない。
短いものでも一週間、長いものなら一ヵ月は初校に掛ける。
直したものを読み直し、当然また直したくなり、再校にさらに一週間なり一ヵ月なりを掛けてしまう。
初稿の段階でたいていは音読して妻に聞かせる。あるいは最近だとAIに音読してもらって妻と二人でそれに耳を傾ける。

妻に感想をもらう。
「つまんない」
と言われたらもうその原稿は捨てる。
「わかんない」
と言われたら、むむむ、と思って書き直す。表現を砕く、開く、足したり引いたりする。
「おもしろい」
とは滅多に言われないが、言われて初めて推敲の段階に進むのである。つまり、推敲されることなく打ち捨てられし骸の数は数えきれない。
生き残り、推敲に掛けられ、直されまくった文章をまた妻に読んできかせる。と、ショックなことに、妻はたいてい言うのである。
「最初のと、どこが変わったのかあんまりわかんない」
キャラクターはまずいじらないし、ストーリーもほぼほぼ初稿のままであることが多い。
だから妻には違いがわからないのかもしれない。
エピソードを削ったり増やしたり、あるいは順序を入れ換えて読みやすくしたりもするが、しかし僕は、そこらへんを重視しているわけでは全然なくて、もっぱら文章のリズムや表現のブラッシュアップに心血を注いでいるのだけど、そのあたりのことこそ妻には「どうでもいい」ことらしい……。
上手な文章にも、リズミカルだったりメロディカルだったりする響きにも、気の利いた表現にも妻はまったく(かどうかは定かじゃないが、まあ大方)興味がないのだ。
魅力的なキャラが、先を読みたくなるような展開に晒され、かつ納得し得る結末に導かれてくれたらそれでもう十分、みたいに感じている節がある。

エンタメ作品の編集を手掛けてきた僕だから、そんな妻の感性を尊重しないわけがない。でも僕が残したいのは、『百年後に読まれても恥ずかしくない程度に恥ずかしい』(←その意味はたぶんいずれ語る)文章なのである!
ゆえに妥協はしないのだ。
妻のお眼鏡に(実際の妻は裸眼の人だが……)かなった文章を、時間を掛けて磨き上げ、自分のビームを照射しても朽ちない類いのものに鍛え上げてゆく。これが僕の推敲であり、創作のスタイルなのである。
焼きものに似ているかもしれない。形ができてのち、それを焼き上げてゆくまでが創作なのである。
釜焼きには長い長い時間が必要なのであった。
そんなふうにして今も書いているものがある。
うまく仕上がるようなら世に出してみたい、ような気もする。
僕にしか書けないものを書き、時間を掛けてそれを磨き、うまくいったらそれを遺すのだ。
小説、といっていいのかどうかわからないけど、僕が作りたい文章はそういう文章なのである。
『最後の八分』に負けないくらいにピュアな、すなわち微笑ましいくらいに恥ずかしい文章を、あと何本かは遺して死にたい。

と、そんなふうに思っている。
けど、まあ力まず、成り行きでテキトーにやってゆこうと〈堅く〉〈固く〉心に決めている!

文庫本を買わせていただきます😀!
