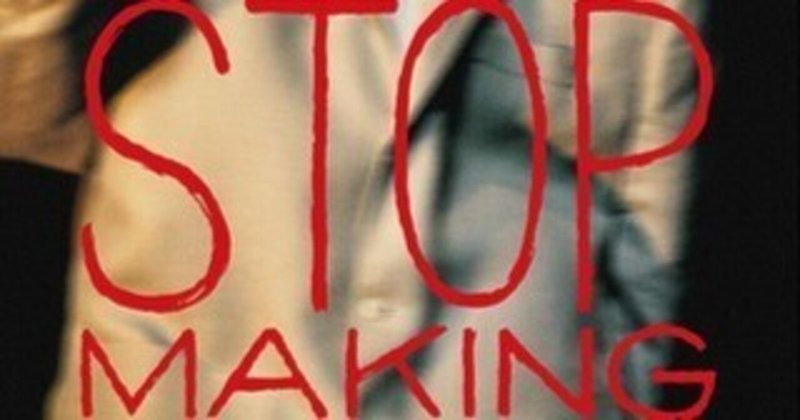
魂が燃えて輝く -ライブ音楽名盤5選
音楽の魅力の一つに、ライブ演奏があります。勿論、録音スタジオで緻密に仕上げられた録音作品も素晴らしい。しかし、人が沢山いる前で演奏することは、演奏者には多大な負担をかけつつも、音楽に張りと緊張感を与えます。
今日はそんなライブを録音したライブアルバムの傑作を5つ紹介したいと思います。素晴らしいライブアルバムは沢山ありますが、今回の選考基準は、色々な仕掛けやハプニングによって、演者のポテンシャルが最大限までに発揮された作品、にしました。
また、いつもと違い、ジャンルで分けず、私の好きな、クラシック、ロック、ジャズの作品から選んでいます。どれも素晴らしい作品なので、楽しんでいただけますと幸いです。
トーキング・ヘッズ『ストップ・メイキング・センス』
まずは、このロック音楽のライブを。パンクシーンで最も知的といわれた、ニューヨークのバンドが残した1984年の作品です。
『羊たちの沈黙』で知られるジョナサン・デミが、ライブ映画として監督しており、ロック映画史上有数とも言われる素晴らしいライブ映画になっています。
トーキング・ヘッズは、パンクから始まり、アフリカの民族音楽的な要素を含むワールド・ミュージックを取り入れた多様な音楽性を背景に、ナンセンスすれすれの摩訶不思議な歌詞を、ボーカルのデヴィッド・バーンが震えるような歌声で歌い上げる、80年代を代表するバンドです。
このライブは、構成が素晴らしい。まず、デヴィッドがラジカセとギターを持ってきて入り、一曲目を一人で歌います。
次の曲は、ベースのティナが入り、2人で。3曲目はドラムのクリスが入って3人で。そして、ギターのジェリー、バックコーラス隊やパーカッションが入っていって、どんどん音楽が膨らんでいきます。
実はこのライブ映画は、客席の観客の顔を全く映しません。ライブがクライマックスになって、ラストの曲になった時初めて、笑顔の観客の様々な姿が映され、舞台には、ライブを支えていたスタッフクルーとバンドが挨拶します。
つまりこれは、このバンドの音楽が成長して広がる様を、そのままライブの進行に合わせた作品なのです。
最初はデヴィッド一人の孤独な呟きが、バンド仲間を得て、様々な人々の力を引き寄せ、多様で豊かな音楽となり、多くの人を笑顔にする。そんなバンドの生きる(ライブ)歴史が再現されているのです。
ロックに興味がない人でも、その驚異的な活力にあふれた音楽と映像を味わうのは、素晴らしい体験となるでしょう。
ディヌ・リパッティ『ブサンソン音楽祭の最後のリサイタル』
大人数の素晴らしい生命力の音楽の後は、一人きりの、命をかけたライブを。
ショパンのワルツを得意として、ピアノの吟遊詩人と呼ばれた、夭逝の天才ピアニスト、ディヌ・リパッティが最後に演奏したライブ演奏です。
リパッティは、悪性の腫瘍が末期まで進行し、このブサンソン音楽祭では、痛み止めを何本も打って、何とかステージに上がったといいます。
しかし、音楽自体は、そんな事情を全く感じさせない程に、意外にも力強く進んでいきます。透明で粒の立った音色は彼の特長がよく出ています。
やや早めのテンポを聞いていると、ゆっくり弾いていては、痛みを余計感じてしまうのだろうかとも思ってしまいます。しかし、その鬼気迫るような美しいうねりで、聴く者全てを金縛りにします。
このアルバムの最後のショパンのワルツを弾き終わった後、実はもう1曲弾く予定でした。しかし、楽屋に戻ったリパッティは、あまりの苦痛に立ち上がることが出来ず、そのまま、終演となりました。そして、二度とピアノを弾くことのないまま、3か月後、弱冠33歳でこの世を去ります。
所々もつれているように聞こえる部分もありますが、これ程戦慄を誘う演奏は稀です。多くのクラシックファンが、名盤に挙げる作品です。
同時に、単に天才の最後の作品というバイアスがかかっているだけでは、と言われることもあります。確かに、そういう面はあるでしょう。
しかし、最近、私はそれでもいいのではないかと思っています。
私たちが体験する音楽や絵画や映画は、ただの音や画像の連なりではありません。私たちは、音や色の連なりの向こうに、それを創る人たちや時代の空気を感じることで、それらの芸術を、表面的な音や色の情報以上に、豊かに想像して、受け取る。
夭逝の天才が最後に振り絞った音楽という前提を受け入れることで、私たちは、単なる曲以上の音楽と人生を感じる。これこそ、ある意味、AIには絶対創れない芸術ではないでしょうか。
だって、AIは死なないのですから。
マイルス・デイヴィス『フォア・アンド・モア』
ジャズも素晴らしいライブ名盤が沢山あるのですが、このマイルスの作品を。
とにかく、最初の『ソー・ホワット』から、とんでもないスピードで進みます。爆速というか、テンポだけでなく、全員が何かに追い立てられているような切迫感で一気に駆け抜ける。並みのロックでは太刀打ちできないレベルのスピードなのです。
なぜこんなアルバムが出来たのか。実は、メンバーの証言が残っています。この録音のライブの、ステージに上がる直前の舞台袖で、マイルスが、今日の演奏のギャラは、全額寄付すると、一方的に宣言したというのです。
当然、メンバー全員が激怒して、そのままステージに上がることに。そして、殺気立ったこの演奏が生まれたと言います。
おそらくは、マイルスは、わざとこの宣言を行ったように思えるのです。
メンバーは、ハービー・ハンコック、ロン・カーター、ジョージ・コールマン、トニー・ウィリアムズと、いずれも芸達者で、この時点でかなりのライブを重ねていて、アンサンブルも抜群でした。
しかし、人間、同じことを安定して続けていると、音楽に刺激がなくなってしまう。音楽に新鮮さを吹き込むため、彼らを怒らせたのではないのでしょうか。
そうしても信頼は壊れないという確信もあり、彼らなら対応できるという冷徹な分析もできていたのでしょう。ジャズの帝王マイルスの面目躍如といったところです。
とはいえ、流石にギャラについては、ちゃんと決めておいたほうが良いとは思います。
デヴィッド・ボウイ『ジギースターダスト・ライブ』
ロックのライブ映画では、1973年、ボウイのグラム・ロック期の作品も挙げたいです。
ボウイは、「ジギー」という宇宙人のキャラを演じることに疲れ、このライブが始まる前に、マネージャーと、バンドの要のミック・ロンソンにだけ、最後のコンサートであることを告げていました。その、取り憑かれたような熱唱による鬼気迫るパフォーマンスの、貴重な記録となっています。
ボウイだけでなく、ロンソンの長尺に暴れまわるパワフルなギターも最高で、スタジオアルバムより格段に優れていると言えます。
そして、そんな二人の胸の内を知らず、熱狂する観客の恍惚とした表情もまた素晴らしい。彼らが「生きた」最高に美しい記録となっています。
ブルーノ・ワルター『マーラー交響曲第9番』
最後は、クラシックのライブで締めましょう。ブルーノ・ワルターが1938年にウィーン・フィルを指揮したマーラー第9番です。
この時期、ナチスがオーストリアを支配し、ユダヤ人だったワルターは、追われるようにスイスに亡命することになります。その直前のライブです。
ワルターは、後年アメリカで暮らし、コロンビア交響楽団による、明るく美しい数々のアルバムで知られました。しかし、ここでは、物凄いパワーを音楽にぶつけています。
ワルターの師匠でもあったマーラーの、喜怒哀楽を全て詰め込んだような交響曲を、驚くほど大胆なテンポの伸び縮みで歪めながら、一気呵成に進めていくのです。
自分が育ってきた美しい過去は、もう蹂躙されようとしている。その最後の別れを告げるかのような、強い彼の感情の投影が、長いワルターの音楽活動の中でも、随一の名演を引き出したのです。
ライブ音楽がなぜ素晴らしいかと言うと、それは、人が目の前にいて、その人に何かを伝えるという、音楽の根源がそこにあるからに思えます。
私は機械で創られた音楽も好きですし、素晴らしい作品があると思います。
しかし、ミュージシャンが自分の魂を燃やして、その場にいる人に何かを伝えようとしているかのような、こうした生の音楽も、人間にとって、一つの重要な滋養であるように思えるのです。
どれほど機械が発達しようと、AIが発達しようと、私たち人間は変わらず、何かを伝えたい、受け取りたいと願っているのですから。
今回はここまで。
お読みいただきありがとうございます。
今日も明日も
読んでくださった皆さんにとって
善い一日でありますように。
次回のエッセイでまたお会いしましょう。
こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。
楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
