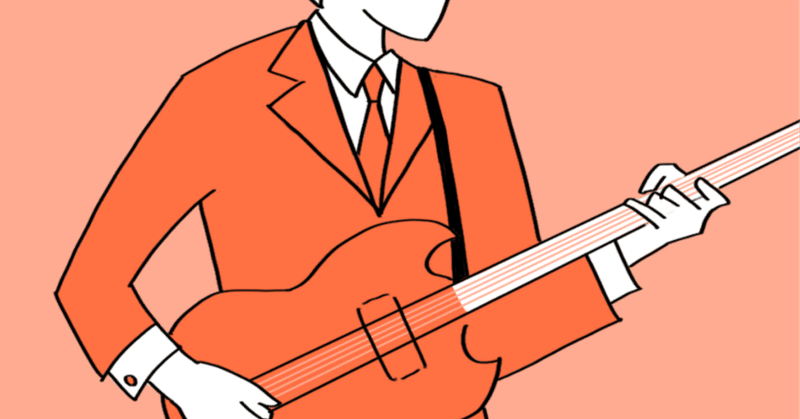
【エッセイ#11】バーズと一つのロック音楽スタイル
ココ=シャネルは、「私が創ったのは、モードではなく、スタイルだ」と言いました。モードとは流行であり廃れるが、スタイルとは普遍的なものであると。おそらく、優れた芸術やエンターテイメントにもまた、流行を超えた一つのスタイルがあります。
音楽も勿論、民族音楽から、クラシック、ロック、ヒップホップに至るまで、そうした優れたスタイルを数多く持っています。それは曲そのものの場合もあれば、曲を演奏する形態の場合もあります。そして、それらが一つのスタイルとして根付くには、多くの偶然と、本人たちの継続の意思が必要になってきます。
その例として、ロックバンドのバーズ(The Byrds)を挙げましょう。1964年にロジャー=マッギン、ジーン=クラーク、デヴィッド=クロスビーらによって結成されたこのバンドは、5人組のバンドとして活動を始め、1965年、ボブ=ディランのカバー曲『Mr. Tambourine Man』でシングルデビュー。
この曲が全米・全英で1位になり、華々しいデビューとなります。その後も『The Bells Of Rhymney』や、『Turn! Turn! Turn!』といった楽曲をヒットさせました。

元は、鳥(Bird)を表す美しい宣材写真
洗練とユーモアのある一つのスタイル
彼らは一般的には、フォーク・ロックと言われるジャンルの開拓者として知られています。
当時ボブ=ディランやジョーン=バエズといったフォーク・ミュージックが人気を博していました。彼らはいわゆるトラッド・ミュージック、民謡に基づいた素朴なメロディを使って、アコースティック・ギター1本で弾き語りという形で、社会的な問題を扱う歌(プロテスト・ソング)を歌っていました。
また、それとは別に、当時ビートルズが登場してチャートを席巻し、彼らを真似てエレキ・ギターでロック音楽を演奏する粗削りなロックバンドが雨後の筍のように、登場しては消えていました。
バーズのフォーク・ロックは、文字通り、このフォークと、ロックを融合させる試みでした。歌詞とメロディはディランたちが歌ったフォーク・ソングを使い、演奏はロックのリズムで、エレキ・ギターによって行う。
中心人物のマッギンは、フォーク・ソングを愛好しつつ、ビートルズの革新的な音楽、特に、そのエネルギーや見事なコードチェンジといった音楽的な豊かさにも惹かれたと語っています。それゆえに、フォーク・ロックという新しいジャンルのスタイルを創ることができたのでしょう。
ではそのバーズのスタイルとは、具体的にどのようなものか。まず、イントロで、マッギンの12弦ギター(普通6弦のギターに高音の弦を張ることで、澄んだ響きが生まれるギター)がアルペジオを奏でると、ドラムのブレイクと、ベースが入ってきます。
前奏が終わると、いきなりサビのメロディを、マッギン・クラーク・クロスビーが、一糸乱れずハモりながら歌いあげていき、そのままの勢いで突き進んでいきます。
メインボーカルのマッギンのへなへなとした歌声と、クラークのしっかりと誠実な歌声、後にCSN&Yでも活躍するクロスビーの高音、それとエレキ・ギターの細かいアルペジオとが溶け合って、清潔なサイケデリアとも言える浮遊感を出しています。それは確かに美しいのですが、実のところ、本当にこれだけです。毎回こうなのです。
実は、バーズのこのフォーク・ロックは、彼らの独創というわけでもありません。12弦でなくても、ギターアルペジオのイントロだけなら、ビートルズが既に初期の『You Can’t Do That』や『Ticket To Ride』といった楽曲で、彼らに似た雰囲気を作り上げていました。
バーズのアルバムに対して、「音楽的には何ら新しいものはない」と厳しい言葉を寄せた評を読んだことがあります。それは全くその通りで、そもそも、フォーク・ソング自体が、殆どスリー・コードで演奏できるレベルの、楽理的には幅の狭いものです。
ビートルズは、マッギンの言う通り、初期の粗削りなロックンロールから、どんどん変わったコードを取り入れて、それまでにはないジャンルの音楽を作り上げていきました(サイケデリック・ロック、プログレッシブロックからハードロックまで、その後のあらゆるロック音楽のジャンルの萌芽が、彼らの音楽にはあります)。
こうしたビートルズの創造的な一側面を、バーズが引き継ぐことはありませんでした。中期にはカントリー音楽を取り入れてみたりもしましたが、結局のところ、12弦ギターのアルペジオと、マッギンのよれよれになった歌声による、中庸なロック音楽は何も変わりませんでした。メンバーの脱退や加入も頻繁で、新しいことを試す余裕もなかったのかもしれません。
これは以前、テレマンの項で書いた、「どれも同じに聞こえる音楽」と言えるでしょうか。そういう部分は勿論、あります。しかし、同時に強調しておきたいのは、彼らが後世に与えた影響についてです。
彼らの音楽は、とにかく真似しやすいのです。スタイル的には、簡単なギターのアルペジオを練習したギタリストに、何の変哲もないベースとドラム演奏ができる、リズム隊がいればよい。プログレやメタルのような、変態的とも言える超絶テクニックなんて必要ありません。ボーカルとそれをサポートするコーラスを揃えれば、3人か4人の小編成で、ハーモナイズされた、麗しいロック音楽を奏でることができます。
それは、フォーク・ロックと呼んでいいのですが、今やフォークに限らない広がりを見せているように思えます。個人的には「アルペジオ・ロック」と呼んでみたいと思います。勿論これは、ロックの歴史の教科書には載ってない、私の造語です。
アルペジオ・ロックの特長は、細かく刻むアルペジオが、ある種の気品を醸し出してくれることです。ロック音楽の歴史とは、電撃的なエレキ・ギターのリフ(ジミ=ヘンドリックスやガンズ・アンド・ローゼズのような)がメインストリームなのですが、こちらは寧ろ、ピアノの伴奏を思い出させ、ほどよく上品な感じがします。
それはプログレのようなクラシック音楽との融合とかではなく、クラシック音楽が持っていた、安心感、親密さ、心落ち着くハーモニーといったものを、初心者でも付加できるもの。いわば、心地よさの魔法のフォーマットです。
バーズはまさに、このフォーマットの元祖であり、スタイリストといって良いでしょう。なぜなら、ビートルズやディランは、あまりにも才能があって、どんどん古いスタイルを捨て、新しいスタイルを進化させていったからです。
バーズにはそれができなかった。それゆえに、同じことをずっと続けるしかなかった。また、彼らのスタイル自体、同じことを続けやすいものでもありました。例えば、ひたすら世の中を攻撃し、呪詛を繰り返すパンクやメタルは、かなりの消耗をして続けるのも大変ですが、バーズはそうではありません。
ここに一つのスタイルを巡る逆説があります。スタイルを作り上げるには、必ずしも才能があるだけではなく、たとえ時代遅れになっても信じたものを貫く態度、長く続けるためのある種の偶然が必要になってきます。そこには才能が限定されていることも含まれます。
ダ・ヴィンチや、ピカソ、ビートルズやマイルス=デイヴィスは真の天才です。あらゆるスタイルを創り出し、自分を変化させていきました。しかし、あまりにもスタイルを変えているため、彼らの全ての時期を肯定することは難しい。
そして、彼らをヒーローと崇めたとしても、スタイリストとしてお手本にするのは難しい。なぜなら、自分のスタイルを完成させた途端に、破壊して捨て去っていくのが、彼らだからです。
バーズにはそんな心配はありません。一つの確固としたフォーマットがあって、誰でも真似できるくらい容易なのだから、それを自分なりに変化させていけばいい。こうして、一つのスタイルが誕生し、多くの人が身に付けようとしました。
アルペジオを練習して、コーラスを追加していく。ネオアコ・ギターポップ・パワーポップ・インディーロック。様々なジャンルが派生して活気づきました。それは、バーズが創ったものが偉大なスタイルであることの証左です。それらは決して攻撃的で格好いいメインストリームのロックではないけど、ロック音楽の重要な一部でした。
ロック音楽や、そこから歴史を受け継いだヒップホップ音楽は、反抗、反体制の音楽とも言われています。それは全く正しい。ただ、そうした大文字の歴史に馴染めない人間も、別にこの世を呪いたいわけではない人間も、世の中にはいます。
そうした人間に、それでも生きていく喜びをたった3分間で味合わせてくれる、そんな魔法こそ、バーズが創りあげた音楽であり、スタイルです。巨大な才能はないかもしれないけど、小奇麗でお洒落にまとまっていて、口ずさむだけで自分の希望になってくれる。音楽的に狭かろうが、ワンパターンであろうが、ダサかろうが、何度聞いても多幸感を与えてくれる、至福の音楽の一つです。
最後に、いつもと少し趣向を変えて、私の好きなアルペジオ・ロックを少し挙げておきましょう。勿論、ジャンルでまとまっているわけではなく、ある種の雰囲気で選んだものです。
<The Byrds『She don’t Care About Time』>
バーズの中でも一番好きな曲。少し愁いを秘めたハーモニーが心地よい。
<R.E.M『The Sidewinder Sleeps Tonite』>
正統派のフォーク・ロックを受け継いだカレッジバンド。彼らの大ヒットアルバムの中から、地味だけど伸びやかな一曲。
<Richard & Linda Thompson『Wall Of Death』>
イギリスでトラッド音楽をもとに独創的な音楽を作り上げたデュオ。ダークな曲調も多い彼らの中では、とりわけポップな明るい名曲。
<The Smiths『William, It Was Really Nothing』>
ネオアコの代表格。不穏な歌詞もいいけど、ボーカルのモリッシーのクルーナーとしての能力も素晴らしい。冒頭のイントロはまさに街に降り注ぐ雨音を示す。
<The Rembrandts『I'll Be There For You』>
アメリカの大ヒットドラマ『フレンズ』の主題歌。1分に満たなくてもドラマの雰囲気を全て表せる。
<Northern Portrait『Criminal Art Lovers』>
北欧のネオアコバンド。良く伸びる上品なボーカルと、爽やかなメロディが美しい。
<Official髭男dism『Pretender』>
ここ最近でバーズ濃度がかなり高いと思う大ヒット曲。アルペジオの質感もそうだが、清潔感のあるボーカルとコーラスがまさに正統派。
今回はここまで。
お読みいただきありがとうございます。
今日も明日も
読んでくださった皆さんにとって
善い一日でありますように。
次回のエッセイでまたお会いしましょう。
こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、マガジン「エッセイ」「レビュー・批評」「雑記・他」からご覧いただけます。
楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
