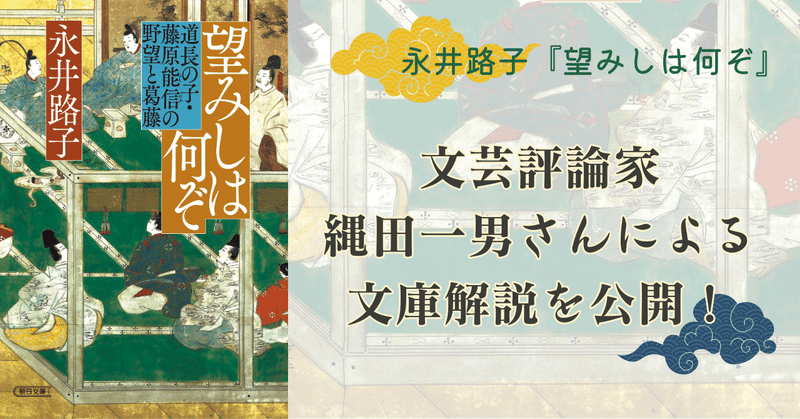
永井路子さんの『この世をば』に連なる歴史巨編『望みしは何ぞ』/文芸評論家・縄田一男さんによる文庫解説を公開
永井路子さんの『望みしは何ぞ 道長の子・藤原能信の野望と葛藤』(朝日文庫)が刊行されました。摂関政治から院政への橋渡し役をはからずも演じた、道長の四男・藤原能信。藤原摂関家と天皇家を中心に、皇子誕生をめぐる権力抗争を、道長の背中を追いかけ、王朝社会の陰の実力者となった能信の生涯を通して描いた傑作歴史小説です。文芸評論家の縄田一男さんが寄せてくださった文庫解説の全文を掲載します。
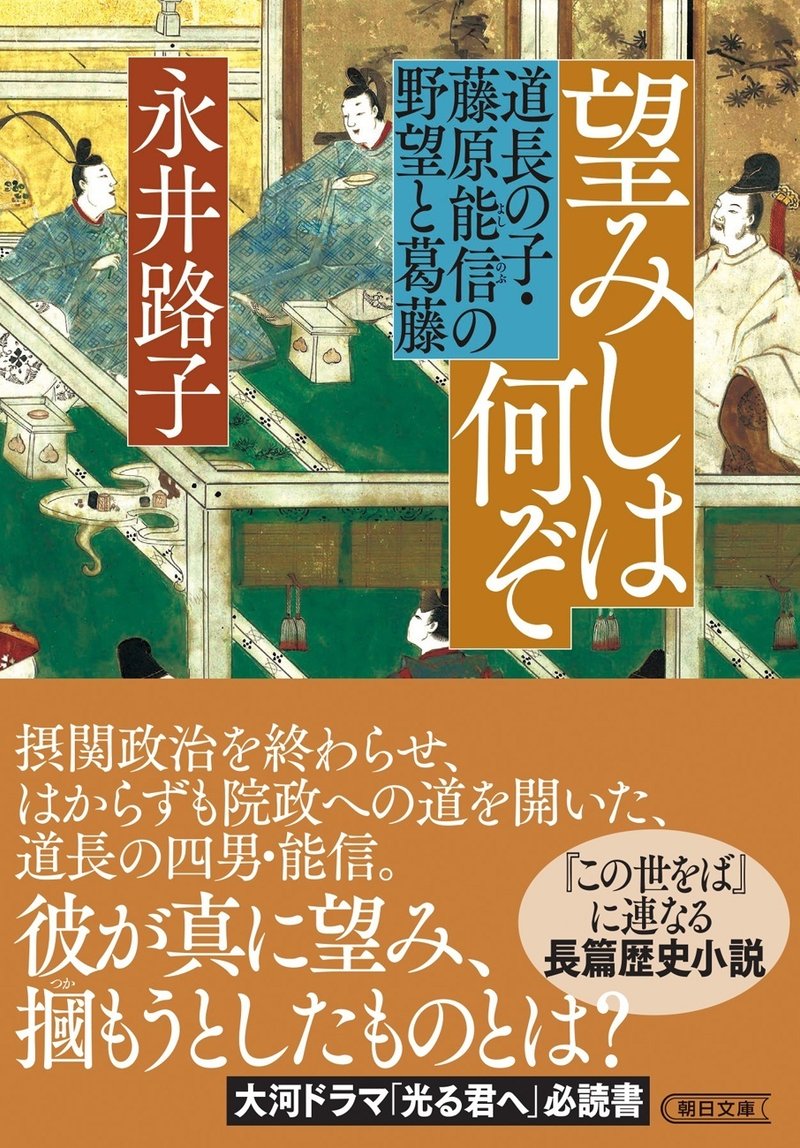
私たちはよく過去の歴史を何々時代といった名称で区分し、更にそれを細かく区分けしようとするが、本来、歴史は生きた連続性の中にあり、作家が1つの時代をまるごと捉えようとした場合、1篇の作品では収まり切らないという事態が生じて来る。
永井路子の“平安朝3部作”、すなわち、『王朝序曲――誰か言う「千家花ならぬはなし」と』『この世をば』、そして本書『望みしは何ぞ』は、そうした書き手の要請がもたらした必然の産物であった、ということが出来よう。
『望みしは何ぞ』は「中央公論文芸特集」の平成4年秋季号から6年冬季号にかけて10回にわたって連載されたもので、平成7年3月、中央公論社から刊行された『永井路子歴史小説全集 第6巻』に新作長篇として収録された。独立した単行本は平成8年3月の刊行である。
藤原道長が栄華を極める賀茂祭の行列からはじまる本書は、まず第一に前述の『この世をば』を別の側面から眺める面白さを持っている作品として読者の眼に映るのではないのか。
『この世をば』は、従来、権力の権化として、傲慢、不遜とマイナスイメージばかりが先行して来た藤原道長を「幸運な平凡児」として規定、その人間的内面に迫った意欲作で、第32回菊池寛賞を受賞した。道長といえば4人の娘を后妃として天皇の外戚の地位を確立、藤原北家の最盛期を招来した人物として知られているが、実のところ、はじめの20年間は兄たちほど出世の機会はなく、兄や政界の実力者が相次いで病没する中、あれよあれよという間に第一の実力者にのし上っていってしまう。
しかしながら、作者のいうように「鼻高々の権力者」ではなく「ペシミストで人間的な弱さがある」道長は、出世した後も様々に一喜一憂を繰り返し、「……何たること、何たること」という口癖は生涯変わることはない。が、これは表面には決してあらわれることのない彼の内面の貌である。照れくさそうに口ずさんだ一首の歌――「この世をばわが世とぞ思ふ望月の 欠けたることもなしと思へば」が後世に喧伝されてしまったことにより、その悪しきイメージが固定化していく。
そして道長の真実が伝わらない、という点では、彼の息子たちにとっても、それは同様である。特に父と同じく政界のトップへと進出していった頼通や教通とは母親の違う、屈折した心情の持ち主、本書の主人公である藤原能信の場合は――。能信にしてみれば、父は固い鎧をつけた一筋縄ではいかない人物であり、その分らなさは作品の前半「戯れ歌」の章で、道長が前述の「この世をば――」の歌を詠む際の能信の述懐、「――やりすぎましたなあ、父君」というそれに如実に示されていよう。
特にこの箇所は『この世をば』のクライマックスシーンと同じ場面を扱ったものであり、能信の述懐に続く「道長の当惑げな表情も、実資の狡猾な褒めあげかたも忘れられて、あの下手な歌だけが独り歩きすることだろう」というくだりは、道長と能信という父と子の関係を端的に捉えるばかりでなく、前作を継承しつつ、扱う対象を冷静に相対化する作者の複眼的視座をあらわしており、誠に興味深い。
が、無論のこと、『望みしは何ぞ』がそれのみを意図して書かれたものでないことはいうまでもない。本書のみならず、“平安朝3部作”で一貫して描かれているのは〈政治〉に他ならない。永井路子が直木賞を受賞した『炎環』以来、戦中派の体験を軸として政治と権力のあり方を歴史の中にさぐっていたことは周知の事実であろう。“平安朝3部作”を作品の背景となっている時代順に眺めてみてもそのことはいえる。
『王朝序曲――誰か言う「千家花ならぬはなし」と』に描かれているのは「権威と権力が分割されながらも密着していく、という、ある意味では特異な、それこそ日本的、としか呼べない政治形態」、すなわち、「象徴天皇制の祖形」の誕生である。作品は、平安朝は延暦13年の桓武帝による平安遷都ではなく、薬子の変後の嵯峨朝からはじまるという史観を打ち出しつつも、その嵯峨天皇の病める心に楔を打ちこむかたちで、権威としての天皇、権力としての政治を司る藤原冬嗣という、つかず離れずの体制が生まれる過程を活写していくのである。
そして副題の“千家花ならぬはなし”にこめられた逆説、王朝の美しさではなく、優雅にして酷薄な素顔を描こうという姿勢は、『この世をば』において、道長を中心とした王朝カンパニーの裏面を描くことによって、『源氏物語』的な華やかさと手を切ってこの時代を眺めようという主張と通底している、といえるだろう。実際、この時代には、極めて洗練されたテクニックを必要とする権謀術数と、或る意味では現代よりも残酷な政治性が存在していた、と作者はいう。
そして『王朝序曲』では、従来、律令国家から王朝国家への転換期であると考えられて来た平安朝とは何であったのか、というテーマが、更に『この世をば』では、藤原道長を軸として外戚政治が頂点を極めた摂関体制の実態が描かれて来たわけだが、それでは作者が本書で追求したものは何であったのか。
本書でも〈政治〉がテーマの1つとなっていることは、作品の冒頭から藤原氏内部における水面下の抗争ともいうべき、鷹司系と高松系の対立を物語展開の根幹に置いていることからも明らかであろう。そしてその対立の結果、陽の当たらない高松系の1人である能信は、兄頼宗から「――何を望んでいるのかね」と問われていることを感じながらも、その屈折した心情にふさわしく、いわば勝ち目の出ない賽子ともいうべき、〈美しき不運の種子〉=三条帝と妍子との間に生まれた禎子の命運に己れを託そうという姿勢を顕著にしていく。
そして結果からいえば、そうした負の情熱を持ち続けることによって能信は時代を大きく変えてゆくことになるのである。作者は全集版付記で次のようにいっている――「冬嗣は藤原氏北家の礎を築いた人物であり、道長はこの時代の代表的人物として誰知らぬ人はない。が、能信の地位は権大納言どまり、二人に比べれば大分見劣りする。/しかし、この時代の真の主役は、頼通や教通ではなく、能信その人である。彼の意図したのは、あるいは父に倣って摂関制の中心に坐ることであったかもしれないが、結果においてはその枠組をはみだして、院政期へ移る橋渡し役をつとめることになった」と。
自らの予期しないところで摂関政治を院政へと譲り渡してしまう能信――本書の読みどころは、その「不条理の体現者」である能信の軌跡を、産む性としての女の問題に絡めた点にあるのではなかろうか。生霊死霊を云々する「低俗な怨霊の世界とは、まったく別の世界にいるのだ」と思いながら、外見の華やかさとは裏腹に、実はそれ以上の苛烈な争いを展開しているのが王朝世界である。しかも一見、権力を握っているようでいて、実は男児を産むか、女児を産むかという女の性に生殺与奪の権を握られている男たち。能信が実際は男と女のどちらが翻弄されているのかと、半ば狂おしい笑いの中から「いや、たいしたことじゃない。しかし考えてみればおかしな話じゃないか。みんなが、よってたかって、女の股の間を覗きこんでる」という箇所は象徴的である。
そして、更にこの女の性が、後に禎子が東宮入りの際に示した「――嘘なんて許さないわ」という態度にはじまって、不運にうちひしがれる母とは別の魂のあり方を育んでいったという、無自覚的なものから自覚的なそれへと転じた時、時代は単に政治の面ばかりでなく、今一つの転換期への可能性を孕みはじめたのではないのか。能信の養女茂子は、そうした新たな動きの中に放たれた1つの楔に他なるまい。
そのように考えていくと、能信とまったく違う生き方を選んだ兄顕信や「よく保つ」という受戒の言葉を最後に死へ旅立つ妍子、王朝の四季を彩る花鳥風月、そしてやがて来たりくる武士階級の台頭といったことに思いをはせつつ、私たちはもう一度、原点に立ち戻ってこう問い直さぬわけにはいかないだろう。
能信の望んだことは何だったのか、いや、歴史は彼に何を望んだのか、と――。
確かに本書は、“平安朝3部作”の完結篇として、摂関政治が院政へと移行していく過程を見事に捉え、かつ、この3部作は、一見、きらびやかな王朝を舞台にしていながら、一方で現代史への視座、すなわち、高度経済成長からバブル狂奔にかけて様々な汚点を残した戦後史へのそれをも内包している、ということが出来よう。が、そればかりではなく、作者はこの作品の中に、それに優るとも劣らぬ小説としての名場面を用意している。「夜梅の雪」の章で、しみとおる雪の冷たさも忘れて能信が己が野心を新たにするシーンを思い起こしていただきたい。そしてあの時、彼が「――飛礫か」と、思わず首をすくめた時に後頭部にはしった痛みは何だったのか。或いは、それを理解することが、本書を真に読んだ、ということになるのかもしれない。
さて、作者は前述の全集版付記で、能信に関心を持ったきっかけは『この世をば』執筆中に『大鏡』の別の面白さ、すなわち、この1巻が実にさりげなく能信の活躍を文中にすべりこませ、その存在を印象付けていることを発見、『大鏡』は能信に近い人によって書かれたのではないか、と発想したことに依ると記している。そして更に岩波書店の〈古典を読む〉シリーズの1冊『大鏡』の執筆を経て本書の完結までに要した時間がちょうど10年。これは歴史の連続性の中に平安朝を描こうとした作者の探究が、その真摯さのうちに絶えることなく続いていた良き証左であろう。味読していただきたいと思う。
(1999年、中公文庫刊行時の解説)
追記――朝日文庫刊行にあたり
永井路子の後期の代表作は、『この世をば』(1984年)『王朝序曲――誰か言う「千家花ならぬはなし」と』(1993年)『望みしは何ぞ』(1996年)と続いた、“平安朝3部作”である。この3作が、ある意味で、それこそ日本的、としか呼べない政治形態、すなわち象徴天皇制の祖形の誕生を示している。
さらに“千家花ならぬはなし”に込められた逆説、王朝の美しさではなく、優雅にして酷薄な素顔を描こうという姿勢は、道長を中心として王朝カンパニーの裏面を活写する事によって『源氏物語』的な華やかさと『望みしは何ぞ』を二重写しにする視座を手に入れたと言えよう。
『望みしは何ぞ』『この世をば』の双方のクライマックスシーンは“この世をば――”の歌で1つに結ばれている。それを詠んだ藤原道長は、従来権力の権化として、傲慢、不遜とマイナスイメージばかりが先行しているが、永井路子は「幸運な平凡児」として規定、作品の中でその人間的内面に迫っている。
2024年のNHKの大河ドラマ『光る君へ』では、弱い立場で人の痛みの分かる人間として描かれ、主人公・紫式部(まひろ)と心を通わせながらも時代に翻弄される群像の一翼として登場。今後“光る君”へなれるのか。
ちなみに、永井路子は、杉本苑子と共にわが国の女性歴史作家の草分けである。
生まれは東京市本郷区。1944年、東京女子大学国語専攻部を卒業。戦後、東京大学で経済史を学んだ。1949年、歴史学者の黒板伸夫と結婚、同時に小学館入社。司馬遼太郎らと同人誌「近代説話」に参加。同誌に発表した連作『炎環』で52回直木賞を始め、菊池寛賞、吉川英治文学賞を受賞。2016年には第27回大衆文学研究賞・大衆文化部門を、黒板伸夫・永井路子編『黒板勝美の思い出と私たちの歴史探究』が受賞。晩年まで意欲的に執筆を続けていた。2023年1月27日没。永井路子の死は文壇にとって大いなる損失であった。
