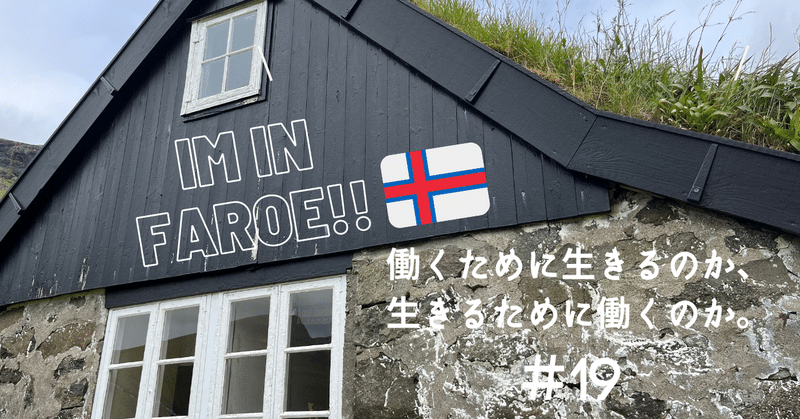
働くために生きるのか、生きるために働くのか
北欧デンマークへやってきて早四ヶ月が過ぎようとしている。
noteを書くのを怠っていたが今私はフェロー諸島に住んでいる友人の元へやってきた。
Nordfyns Hojskoleを卒業し、次のHojskoleが始まるまで約1ヶ月半の夏休み。
デンマークのサマーハウスで1週間の生活、そしてフェロー諸島で1ヶ月の生活。
毎日私の中にある常識がひとつ、またひとつとひっくり返るのだから面白い。
日本の生活、そして北欧諸国の生活。
それぞれが価値として持つ「当たり前の考え方」はまるで対極にあるようだ。
フェロー諸島で今、私はまさに「暮らしている」。
(高校の時の友人に盛大に甘えさせてもらいながら)
「暮らしている」からこそ、学校での生活では見えてこなかった、
「そこに住む国民の暮らし」がリアルに感じられる。
本当にこの経験を与えてくれた友達に感謝の気持ちでいっぱいだし、これからもよろしくお願いします。笑笑
仕事は16時退勤、夏休みは1ヶ月。
友達はフェロー諸島で働いているが、毎日の退勤時間は16時。
家と職場も近いから16時半には必ず帰宅。
北欧の夏は日照時間が長いからそこから日が暮れるまで約7時間。
なんと、、、!
「仕事終わったらなにしようか」
これが毎日の悩みになるじゃないか!!!
そして極め付けの夏休みは1ヶ月!!
友達の友達のフェロー人(ややこしいな笑)はこぞって飛行機へ乗って欧州旅行に旅立った。
(何かの本で北欧は夏に日照時間が長く、冬は短いため、有給休暇は夏に3週間ほどまとめて取る人がほとんどということが書かれていた。そして家族と、恋人と、友達と、一人で、ゆっくり夏を満喫するらしい)
ふと、友達が働いている時間に自分の働き方を振り返ってみた。
「20時に部活動指導が終わって、そこから少し自分の仕事をしたいから、21時に帰宅して、、、ご飯を”適当に”済ませて、シャワーを浴びて22時。明日も朝早いから0時には寝ようかな。」と、正味毎日の自由時間は2時間といきましょうか。
生粋のフェロー人に帰宅後はなにするの?って素直に質問を投げかけられたけど、
「食べて、寝る、それだけだよ!」って言ったら
「趣味の時間はないの????」と返されました。
お、おう・・・
youtubeとか見てたら睡魔に襲われて寝るかな。。
最近、趣味が増えたなあと思っていた。
デンマークへ渡航してからというものの
動画編集、お菓子作り、料理、編み物、ジュエリー作り、ランニング、筋トレ・・・
いろんなことをやることが増えた気でいたが、これらは今まで興味がなかったわけではなく、「やりたいきもち」はあるものの時間が取れなくてできなかったものたちに過ぎないということに気がついた。
私は今までも、「やってみたいこと」は山のようにあったし、だけどどこかでそんな気持ちに蓋をして、働いてきたのかもしれない。
まあそれなりに寝る間も惜しんで動画編集とかしていたこともあるけどね笑
「カフェorティー??」
デンマークへきて、何度かAirbandbという宿泊サイトを利用して民泊を経験した。
どこのお家も洗練された北欧デザインであたたかみのある、居心地の良い空間だった。
人口密度の違いが大きく影響しているのだと思っているけど、どこのお家も生活してて圧迫感のない広さが十分にあり素敵なのだから、旅の一つの楽しみになっている。
フェロー諸島へ来てからというもの、友人の友人のお宅(だからややこしいね笑)にほぼ毎日のように遊びに出掛けている。
だって、仕事があっても16時には帰ってくるし、なんてたって今は夏休み、お昼に訪ねようが、夕方に訪ねようが、夜に訪ねようが、必ずお家に上がらせて頂けて、
「カフェorテー??(フェロー語)」と聞かれる。
つまり、「玄関先でちょっと立ち話を」どころなんかではなく、
「家に上がってゆっくりお話ししようよ」が大前提の文化なのである。
家と家をハシゴする日なんかはコーヒーと紅茶でお腹タポタポになって帰宅する。笑
そして当然、それ(コーヒー・紅茶タイム)をするための「空間作り」が当たり前のように家に存在する。
どこの家もロイヤルコペンハーゲンだのの名だたる北欧食器ブランドのコーヒーカップ・ティーカップが当たり前の装備である。
ここ、フェロー諸島は「毎日の暮らしを整える天才」がわんさかいる国。
ダイニングは大体6〜8人がけだし、どこの家もお茶菓子・コーヒー・紅茶は切らさず用意されているし・・・それでいてお客様が何人入ろうとも窮屈に感じない広いお家。
なんか素敵だなあ、私もいつかのいつか、大切なお友達を気軽に招ける素敵なお家空間を作りたいなあとか思ったところで、横浜の一人暮らし時代に友達が来たらテーブル足りないから段ボールをひっくり返してテーブル代わりにしてたのを思い出して反省。笑
本題「働くために生きるのか、生きるために働くのか」
私の3年間の社会人生活は間違いなく前者だった。
働くことこそが私の生きがいであり、だからこそ自分がやりがいを持てる仕事に就いた。
だから毎日が100%仕事でも楽しくて、充実していて、満足していた。
休みがなくたって、幸せだった。仕事で成果を出したときは嬉しかった。
その代わり犠牲にしていたものは(犠牲にしているつもりはなかったけど)「自分の時間」。余暇活動と呼ばれるものは限られていた。
これはアメリカの資本主義的な働き方、成功こそが人生で最も価値がある。ってやつなのかもしれない。そうやって生活をしていく中で、自分の心がすり減り、見えない疲労が溜まっていくのかもしれない。
ヨーロッパには後者が体感として多い。生きるために人々は働き、生きるために最低限必要なお金を稼ぎ、16時過ぎにはみんな帰っていく。そして家族や恋人、友人たちとの時間を大切にしたり、趣味の時間をとっている。まさにワークライフバランス。
でもこれが実現できる背景は、「企業レベルの努力の上」だとは私は思わない。もはや「国レベル」。国や社会全体の常識で、決まりを作って、国民はその決まり通りに働き、休みは休みできちんととる。1日8時間、週40時間以内の勤務時間は守られるべきで、よっぽどの理由がない限り残業をしてはならない。
一年間のワーホリ生活を始めてみて気づいたことがある。
時間があると様々なことに興味が向き、一度試してみようと気軽にトライでき、向き不向きを確認し、体験・経験した上で続けるかどうかを意思決定できるということ。心に余裕があるなかで、ゆっくりたちどまって判断できるということ。それはつまり、自分の未来の可能性を広げる時間になる。私は現状維持があまり得意ではない。それよりもいくつになっても、肩書きが変わっても、アップデートされ続ける人生を送りたい。
そのためにはやはり、24時間の中に「余白」って必要なのではないか。
そんな当たり前のことに気が付きつつあるワーホリ生活。
働くことも大事だけど、同じくらい休むことも大事。
毎日が「すべきこと」「しなければならないこと」でいっぱいになってはならない。
「したいこと」「興味あること」「好きなこと」そんな時間も取れるといい。
日本もいつか、そんな時代が来るのかな
全てはバランスだと気づいたところで、実際問題何をどう努力すれば、自分が自分らしく生きていけるバランスを取れるというのか。
それはもう個人の努力ではどうにもならない。
国や社会の常識をもひっくり返す必要があると私は思う。
やはりデンマークは社会制度がしっかりしているのだ。
その社会制度をシェアしてくれよ!と個人的にもわかっているんだけど、長くなってしまったので、日本の未来が明るいことを願って、終わりにしたいと思う。笑
また、今度。
本当にたくさんの魅力的な制度を生活の中で目の当たりにしているから、これをシェアさせてください。気ままに・・・
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
