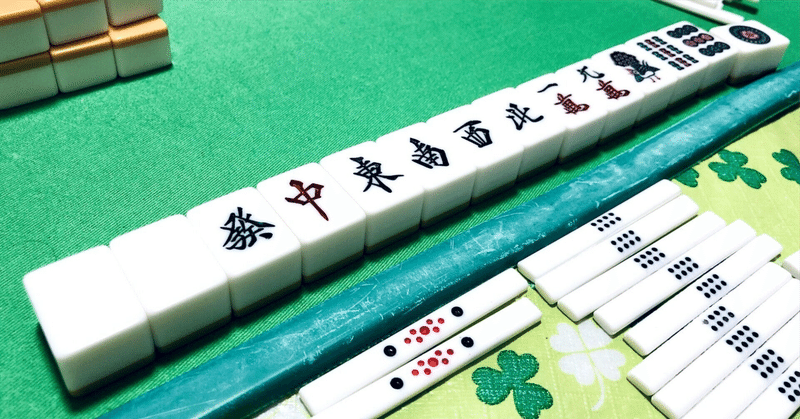
絶対にルールを守るアウトロー (小説「麻雀放浪記」レビュー)
昭和50年代には2千万人いた麻雀人口が、2018年は580万人だそうだ。ゲームでやったことがあっても、リアルで麻雀牌(パイ)を握ってやったことがあるという人は、案外少ないんじゃないだろうか。今回紹介したい小説「麻雀放浪記」は、リアルの麻雀、それも賭け麻雀の世界の話だ。タイトルだけを見ると、リアル麻雀をやったことがない人が本書を読んでみようと思う人は少ないと思う。リアル麻雀のイメージが、タバコ臭い、ルールが複雑だ、ゲームのように勝手に点数計算をしてくれないので面倒、など良くない。しかし本書は、タイトルだけで敬遠するのは勿体ない、麻雀のやったことがない人でも十分に、いや十二分に楽しめる作品だということを強調したい。
舞台は終戦間もない昭和20年から始まる。着るものも住むところも食べ物も、まだ充分に行き渡っていないような時代。そんな時代に賭け事を生業とし、熱く生きる博奕打の物語だ。賭け麻雀を中心にして、様々な博奕打ちの登場人物たちが、それぞれの技(イカサマ)を駆使して、激しい生き残りの戦いが展開される。
本書の作者阿佐田哲也は、実際に博徒の経験があり、実体験からくるリアリティーが本書の魅力の一つだ。
ここで麻雀を知らない人のために簡単に説明したい。麻雀は原則として4人で行われるテーブルゲームだ。4人のプレイヤーがテーブルを囲み、トランプのような要領で、自分の手札(麻雀では麻雀牌)で役(やく)という組み合わせを作っていく。これを数回行い。最終的に点数が一番高い人が勝ち。というゲームだ。さらに最近のリアル麻雀と、当時の麻雀で大きな違いも指摘しておきたい。現代のリアル麻雀は、全自動卓と呼ばれる、麻雀専用のテーブルで行うのが一般的だが、本書の時代にはもちろんそんなハイテク機器はなかった。136枚の牌を手で並べていたのだ。手で並べるのだから、今よりずっとイカサマの介入がたやすくなっていたのだ。
話を戻そう。本書に書かれていることを一言で表すならば、本物のアウトローとはどんな人間なのかということだ。アウトローの性質、アウトローの哲学、アウトローの生き方を説明している。本書で書かれるアウトローは、辞書的な意味の「法律を無視する人」「無法者」「無頼漢」と若干異なる。本書で語られるアウトローは、社会の常識、世間のルールは破るけど、自分のルールは死んでも守る人間のことだ。ただの無法者、ルール破りの人間をアウトローとは言わない。「自分のルールは死んでも守る。」ことが、必要十分条件に追加されている。
例えばこんなシーンがある。主人公の「坊や哲」と「ドサ健」「出目徳」「女衒の達」(これら呼び名もワタシ的に格好良くてグっとくる)の4人で戦っているシーン。出目徳が天和(てんほー)という役(やく)を2回連続であがるシーン。天和(てんほー)とは、最初に配られた牌で既にあがっているという、確率33万分の1※のかなり難しい役(やく)だ。 (※http://www10.plala.or.jp/rascalhp/mjmath.htm#6 )それを2回連続であがるのである。どう考えてもイカサマとしか思えないドサ健は、証拠は無いがインチキな手に金は払えないと激昂する。そこで出目徳はこんな事を言う、「インチキだから払えねえってのか。よおし、上野に健っていう勇ましい博打打ちがいるってきいたが、そいつがそう吐かしたんだな、インチキだから払えねえってな」と。こう言われたドサ健はどうしたか。金を堂々と払うのだ。どう考えても常識外。普通の感覚ではありえない。しかしドサ健の自分のルールでは、博打に負けた金は払わなくてはならない。たとえイカサマだとしても、イカサマが見抜けなかった自分が悪い。という思考なのだ。世間の常識である「建前」でなく自分のルール「本音」で生きる、刹那的だが激しい生き様がアウトローなのだ。
なぜ筆者は、このような生き様を描こうと思ったのか?私はこう想像する。戦後に青春時代を送った筆者は、世間のルール「建前」が180度変わるのを目撃した。昨日まで「天皇は神」と言っていた人たちが、今日は「天皇は人間」だと言う。昨日まで「お国のために生きろ」と言っていた先生が、「これからの日本は民主主義だ」と教える。さらに戦後最大の「建前」である日本国憲法もこの時期に出来上がった。「建前」はコロコロ変わる。そんな世間の「建前」が信じられなくなったのではないだろうか。そこで筆者は、「本音」で生きるアウトローの道を選択したのでないかと考える。そしてこの戦後間もない時期は、「本音」で生きる人達が、筆者たち博奕打だけではなく、数多く現れた時代だったのではないだろうか。
また本書では、「本音」で生きることがアウトローの道であり、人間の素晴らしさだと訴えるとともに、本音で生きるアウトローたちが、建前の社会で生きる人々から受ける風の厳しさも描かれている。その向かい風は、段々と日本社会が復興していく過程で、人々が会社などに所属していき、社会のルールなども整備されていくと、社会のルールを破って生きていくことが困難になっていく。また自分のルールを頑なに守って生きていくよりも、適当に社会に合わせ、適当に建前と本音を行き来するような人間が増えていく。
3巻にこんなシーンがある。1巻から7年後、とある麻雀店。メンバーは坊や哲、銀座のクラブのホステス「春美」、「ドサ健」、何代も続いた金版彫刻の店の御曹子だという「安さん」の4人。ドサ健は、安さんがイカサマしていることを疑い用心深く見張る。それにより安さんは調子を落とし大敗する。安さんはお金の持ち合わせが無いということで、ドサ健にお金の代わりに車の鍵で負け分を払って帰る。後から店を出た坊や哲は、帰り道に安さんの車が無いことに気づく。車の鍵は偽物だったのだ。1巻でドサ健がとった態度とは180度違う、ズルいやり方だ。それを見た坊や哲は、以前のようなやり方では、勝負に勝てないことを悟るとともに、本物のアウトローがいなくなっていくことに寂しさを覚える。
「麻雀放浪記」は全4巻あり、4巻の時代は昭和30年ごろになっている。1巻から10年進む計算だ。このたった10年の間でも、戦後の日本社会の復興とともに「建前」が着々と幅を効かせるようになる。例えば主人公も会社勤めになって、社会のルールに従わざるを得ない場面も登場する。しかし作者は、やはり「本音」で生きる本物のアウトローを懐かしみ、その生き方を肯定する。私は、この本を読み返す度に、その本物のアウトローへの憧れを思い出し、「建前」と「本音」への自身の体重のかけ方が適切かを自戒する。そして大抵「建前」へちょっとかけ過ぎなんじゃないかと反省することになる。そして戦後から75年経った現在、検事長が賭け麻雀で辞職しても退職金は5900万円貰えるらしい。辞めるという建前だけで、社会が納得しているようだ。納得していなくても、どうにもならなければ納得しているに等しい。その事が大問題にならないのも、現代の「建前」の幅の効かせ方が長大なことを思わざるを得ない。自分自身も含め、現代の日本人はもっと「本音」で生きるべきじゃないのかと考える。そのために、ぜひ一度本書を手にとってみることをオススメする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
