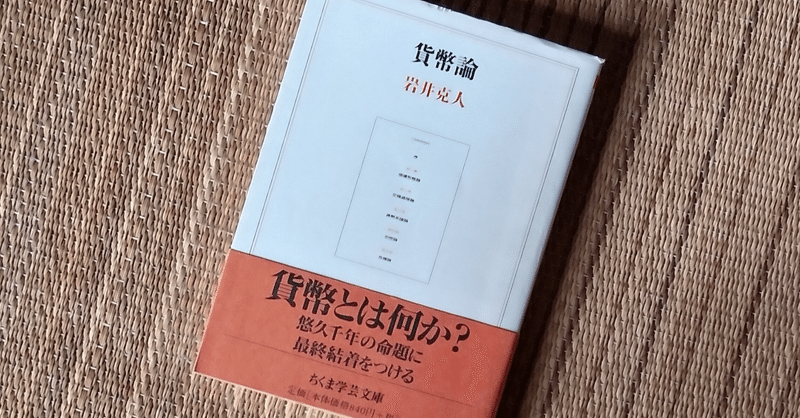
「呪い」の言葉に効用はあるのか?③:《クルアーン》「棕櫚章」をめぐって(第3回/全4回)
お金にまつわる不安
「棕櫚章」第1節には「人を呪わば穴二つ」的含意がついて回ることは、第2回の論考でみたとおりであるが、しかしなお、アッラーはあえてこれを読ませているのではないかと思われる節もある。第2節から見えてくる財のあり方がその入り口になる。
《(最後の審判では)何の役にも立たない。お前の財貨も、お前の稼いだものも。》
人はなぜお金を稼ごうとするのか、貨幣を貯めようとするのか。それは、未来に対する不安のせいだという。食べ物を買物でしか調達できないとするならば、とりあえず、明日の食事の分がないと不安。給料をどこかからもらっているとするならば、食費が次の給料日の前までの分ぐらいは確保できていないと不安。食費だけではない。そのほかにもいろいろある。誰かと暮らしていればその人の分も、子どもがいれば子供の分も。お金は投機の手段というのが、現在の貨幣の姿。将来の不安を少しでも解消するべく、どんな事態に対しても手が打てるように、とりあえずお金を貯めていく。
ところがである。みんながお金を貯めることにだけ注力すると、誰もお金を使わなくなり、市場からお金が消えてしまうし、したがって市場もどんどんやせ細って行ってしまい、しまいには市場自体が終焉を迎えることになる。そうならないためには、市場には不純物あるいは外部が必要だと岩井克人は主張する[ix]。つまり、社会主義でもよいし、無利子銀行でも、逆に高利貸でもよいということであろう。とにかくそういう不純物なり異物の混入が市場には必要なのだ。
たとえば、古代ギリシャのアテネのみが資本主義を享受していた「点」の時代から、「線」の時代、そして地中海やインド洋といった「面」の時代になっても依然として外部の方が大きかったのだが、グローバル化した資本主義にはもはや外部がなくなってしまったという。不純物とは切り離されている貨幣を持つ市場経済は常に崩壊の危機にある。純粋性を求めればその世界は崩壊すると岩井は主張する[x]。
「外部」ではなく「ガイブ」
資本主義を崩壊から救うのが外部の存在だとするならば、「財貨も、稼いだものも何の役にも立たない」世界の存在は、まぎれもない外部である。そこでは貨幣の蓄積性も流動先行性も全否定されているからである。棕櫚章の第2節が提示するのは、資本主義を存続させるための究極の外部の提示でもあるのだ。
つまり、このような世界あるいは世界観、あるいは来世観が人々の意識あるいは無意識の中にしっかりと根付いて、何らかの形で現世に外部を造り出せれば、欲望の資本主義は、極度な純粋化を免れて、自らが崩壊――究極的にはこの世が終わる最後の日――に突き進むような危険は遠ざかる。
そうすれば、蓄積した資本によって、将来の物質的な欠乏に対する不安を少しでも払拭し、あるいは、より豊かな社会を作るための少しでも利潤を生みだしてくれる新しい技術の開発・革新も進むというものだ。
他方、人口が増え続ける限り、常に外部は生み出されるのであるとするのなら、壊しては作り直すという軍需も含むとどまるところを知らない欲望の経済活動の拡大に地球環境と、人間とその社会の方が持ち堪えられなくなって、リアルに最後の日の危機が迫るという状況も想起できる。
外部ならぬガイブ(الغيب 幽玄界)、すなわち、楽園、火獄などの目に見えない世界の次元の全面化か。
棕櫚章2節の現代的意義はそうしたことへの気づきにあるのかもしれない。
「一」なるものの世界
ところで、資本主義は単純な引き算の世界だ。収入から費用を引いていくら残るのか。わかりやすい引き算の普遍性。差異のあるところに利益あり。もともとは自由になるために獲得した貨幣。しかし貨幣への偏愛がすべてを飲み込んで、ついに貨幣の重力に引きつけられ、身動きが取れなくなってしまっている。
お金は無から有を生むと言われることがあるが、正確には、お金は有を有に変えることができるであろう。たしかにお金を持っていれば、今まで自分の手元にはなかったモノを手に入れて、自分の手元に置き自由に使うことができる。たしかに無が有になっているが、根源的には、誰かの手元にあったものが、売買を通して、自分の手元にあるようになったのであるから、有から有である。
無から有をつくることを「創造」というとするならば、それをなしうるのはいったいいかなる存在なのか。「創造主」という考え方を持つ宗教なり文化に親しい人であれば、それは「創造主」の業であると言うに違いない。宇宙の創造や地球の創造、どんなに財貨を積み上げても、その創造自体を買うことはできない。地球上の陸地のほんの一部を買い、あるいは宇宙をほんの短い期間だけ旅するといった程度のお金であれば工面は可能はあるとしても、それ以上は、お金ではどうにもならない。
一見すると人間が作ったように見える事象においても、有から有ができたような場合であっても、それも創造主の手の中で行われたこと。この世に私が生を享け、今日まで、こうして生きていられることすべてが、創造主の創造の賜物なのだ。そして、今この瞬間も生き続けられていること、今日ここでお話ができていることにも創造主の創造は及んでいる。そう、創造主は刻々と創造を行っているこのことに気づけると世界の景色は変わる。灰色の世界に色味が差す。同じ景色に息吹がよみがえるのだ。
ところでこの景色は、その色彩の世界に気づくかどうかは別としても、第一義的には、お金を払うことによって交換ができたり、貯めたお金があれば再現ができたりという類の事柄ではない。お金に変わるような、つまり稼げるような仕事ができたり、才能があったりすると、稼げない者は存在する価値がないと考えられがちだ。価値がないのではない、価格がつかないのだ。価値は、交換や売却が不可能なその価格のつかない部分の上に乗ってはじめて価値となりうるのにもかかわらず、価格がつかないことと価値がないことが同一視されるし、同一視してしまうのだ。いるだけで、生きているだけで価値がある、価格で表されないからこそ価値があるというのに、本来はそれで十分なはずなのに、当たり前すぎるからなのか、人間が先ばかりを急いで前のめりになっているからなのかはともかく、そういう価値が忘れ去られてしまうのだ。
ただの「1」だが…
しかし、創造主は知っている。そのことにまずは価値があるということを。一日一日を生きて重ねていけていること自体に価値があるのだ。人は危難に見舞われたときには「助けてくれ」と必死に祈るが、危難を逃れたときには、その祈りが事態を動かしている創造主に届いたからこそ助かったのに、創造主に感謝することはまれである。とは言いながらも、神社等への参拝の末に、受験に合格し、商売に成功した人がお礼参りに出かけることは珍しくない。祈りを引き取り預かっていてくれる場所があれば、人は、感謝も忘れないのだ。
創造主の究極の姿は、おそらくただの「有」である。しかもあらゆる可能性を潜在的に含み持つ「有」である。ゼロかイチかと言われれば、イチ。アッラーフ・アハド(純正章)である。定冠詞がついていないことから明らかなように、たった一つというよりただの一である。したがって、どこかに1なるものが存在するというありかたではなく、どこに行っても1なるものの手中にある、その一なるものが顕在化し展開している姿がたとえば私たち自身であるという形で、私たち自身が1の表れなのであるから、どうしてもその1のことは忘れられがちになる。
貨幣が投機の手段であることさえ了解されていれば、それが貝殻から、金になり、安価な金属片になり、もっと安価な紙になり、ついには暗号的な数字にさえなる。創造主も「ある」ということさえ了解していてもらえるのであれば、太陽や月、あるいは山や海、人の姿になぞらえられることもあるし、具体的な英雄が、あるいは、秀でた能力を持った普通の人が神とよばれるようになることもあるけれど、クルアーンでは、ただの数字「1」にすぎない。
神の命令は人の命令
それは比べるもののない「1」。それこそ不変と言えるが、あるかどうかは、その軌跡(展開後の有り様)以外にその存在を確かめようがなく、しかもその軌跡にはさまざまな不純物が付着していてそちらの方が見えやすいために、どうしても忘れられてしまう。したがって、「信じる」という行為に頼らざるを得ないし、「祈る」という行為を継続することによって、それを定着させていかざるを得ないため、どうしても「信じる者」と「信じない者」の間に線を引き、信じない者を外部化(非難)することによって、何を信じているのかより、信じること自体を強化して、「1」なるものが「あること」を確保しようとするがために、信じるものと信じない者との間に線が引かれ、しばしば対立が生まれ、戦争や殺し合いの原因にもなってきた。
こうなると信じないのかも含め、何を信じるかの違いが、歴史上しばしば戦争を引き起こし、それが加速度的に純粋化し、外部がつぶされ続けてきたことも頷ける。なにしろ、「1」を解釈しているのは人間たちだ。アッラーにとって不純物も異物もない。すべては彼の創造物だ。となると人間が決めた異物を徹底的に飼いならそうとする純粋化の果てに待っているものは人間の破滅か。アッラーはすべてを御存知。
参考URL:
[ix] BS1スペシャル 「欲望の資本主義特別編 欲望の貨幣論2019」(後編)7月14日(日)23:00放送。NHKオンデマンド。
[x] BS1スペシャル 「欲望の資本主義特別編 欲望の貨幣論2019」(後編)7月14日(日)23:00放送。NHKオンデマンド。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
