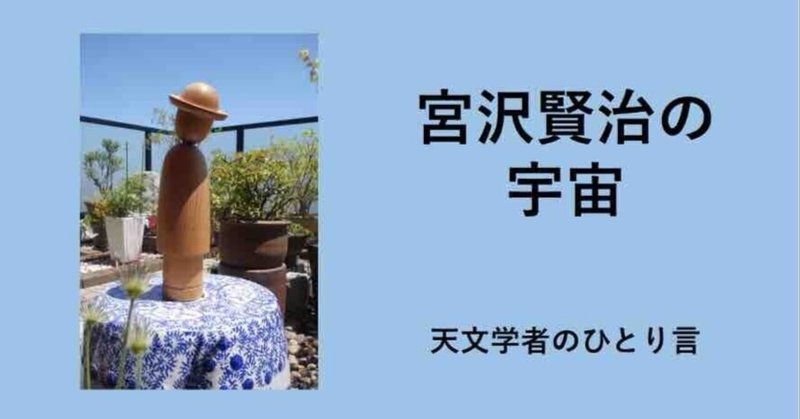
宮沢賢治の宇宙(34) 「第四次延長」、再び
「第四次延長」
note「宮沢賢治の宇宙」(33)賢治の四次元観https://note.com/astro_dialog/n/n620f6082a5f4
前回のこのnoteでは賢治が作品の中で用いた「次元」という言葉に基づいて、賢治の四次元観について紹介した。アインシュタインの相対性理論の影響が色濃く反映されているが、賢治は時代の最先端を走っていた作家であると感じる。なぜそうかと言えば、賢治は賢治独自の言葉遣いを取り入れたからだ。
一番よい例は「第四次延長」。不思議な言葉だ。これは『春と修羅』の「序」に出てくる。
すべてのこれらの命題は
心象や時間それ自身の性質として
第四次延長のなかで主張されます (『【新】校本 宮澤賢治全集』 第二巻、筑摩書房、1995年、10頁)
前回のnoteでは次のような説明をした。
「それ自身の性質」という言葉があるが、「それ」はその直前の「時間」を指している。したがって、「第四次」は時間を意味する。「延長」という言葉が続くが、これは未来を表す。つまり、「これらの命題を、今後考えていくことにしよう」と解釈できる。
恩田逸夫の『宮沢賢治論』
数年前、『銀河鉄道の夜』を読み始めた頃のことだ。まずは、作品のみならず、宮沢賢治という人についても知っておいた方がよいと思った。そこで、書店や古書店巡りを始めたところ、非常にたくさんの賢治関係の本があることを知った。考えてみれば当然だ。〔雨ニモマケズ〕を知らない人がいないほどの超有名な作家だ。作品論や賢治論がたくさん出ていて不思議はない。そんな頃、出会ったのが、恩田逸夫(1916-1979)の『宮沢賢治論』だった。全3冊、ハードカバー、箱入りでしっかりした作り。迷わず買い求めた(図1)。

第1巻は「人と芸術」、第2巻は「詩研究」、第3巻は「童話研究 他」。賢治の人物像から詩・童話の作品まで全分野をカバーしている。こういう本は私のような賢治初心者には大変役立つ。
賢治の作品に出てくる「第四次」という表現だが、「四次元」という意味で用いられているのは一回だけである。そのほかは、「第四次」は時間として用いられている。このことは恩田によって指摘されている(『宮沢賢治論 2 詩研究』(東京書籍、1981年)。また、「第四次延長」という表現には単なる時間ではなく、永遠性を込めているのではないかとも推察している。
ところで、この本には二人の編者がいる。賢治研究で有名な原子朗と小沢俊郎だ。恩田は生前、優れた賢治論を雑誌には発表していたが、なんと一冊も本を上梓しなかった。そこで、恩田が没したあと、原と小沢が恩田の原稿を精選し、三巻の『宮沢賢治論』にまとめたとのことである。
成瀬関次の『第四次延長の世界』
西田良子による『宮沢賢治 その独自性と同時代性』 (翰林書房、1995年)を読んでいたら、驚くべき発見が報告されていた。それは成瀬関次の『第四次延長の世界』という本の存在だ(発行は大正13年2月8日)。重要な点は、この本が『春と修羅』の出版の前に出ていたことである。「第四次延長」という言葉は賢治が最初に使ったのではない。成瀬だったのだ。
西田によれば成瀬の考えは以下のようにまとめられる。
第一次延長:長さ、一次元の世界
第二次延長:広さ、二次元の世界
第三次延長:立方体、三次元の世界
第四次延長:時間ではない。人間の知覚を超えた「第六官」や目前にないものをこころに思い描く千里眼的な「想像力」という意味。時間や空間の制約を受けない「思索の世界」、現実世界より優れた「理念の世界」という意味。 (14-28頁)
「第四次延長」は時間ではないとしている。相対性理論に基づいた考えではなく、オリジナルな考えである。この点は、先ほど紹介した恩田の議論(単なる時間ではなく、永遠性を加味する)とも繋がる。
果たして、賢治が成瀬の本を読んだかどうかは不明だ。しかし、賢治が成瀬とは独立に、しかもほぼ同じ時期に「第四次延長」という言葉を造ったというのは、確率的には低い。賢治がもし成瀬の本を読んでいたら、大きな影響を受けたことは想像に難くない。それにしても、第一次から第四次まで、すべて「延長」が付け足されている。「第四次延長」に関して言えば「Fourth Dimension」の訳語であるとしている。それならば「第四番目の次元」なので、特に延長を付け足す理由はないのだが。
西田良子の四次元に関する調査
西田による『宮沢賢治 その独自性と同時代性』(図2)では、第1章が「宮沢賢治の<四次元意識>の形成」となっており、成瀬の「第四次延長」も含めて丁寧な議論がなされていて大変参考になる。

西田は賢治作品に出てくる「四次元」関係の文章をまとめてくれている(表1)。

先ほども述べたが、「第四次」は時間であるとしてよい。
私たちは日常生活では「空間」のことは意識しても、あまり「時間」のことは意識にのぼらない。「空間」は目に見えるが、「時間」は目に見えないからだ。賢治には「時間」が見えていたのだろうか? 少なくとも、賢治の意識は「空間」より「時間」に重きを置いている。それが賢治作品に独特の個性を与えているのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
