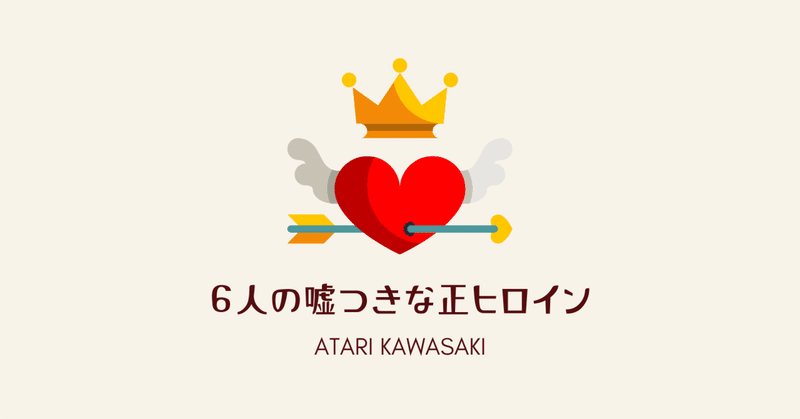
7 大女優の武器
栞から逃げるように別れ、僕は帰途についた。
自室でラットを眺めるが、相変わらずケージの中を忙しなく走り回っている。
僕はシアタールームに向かいプロジェクターで映画を映し出した。なんだか頭を空っぽにしたくて、ド派手な爆発以外まったく見どころがないと言われる一昔前のスパイにした。
それを眺めながら、僕は今日学校でのことを思い返していた。
まずは朝、僕が学校に行こうとすると一華がマンションの前にいた。彼女は王沢の血を引くものは大変そうだと言った。彼女はまるで何かを知っているかのように、僕に笑顔を振りまいた。
クラスにつくと、教室では僕の席の前で夢羽が泣いていた。正確に言えば僕が泣かせたのかもしれないが、彼女が泣く理由はいつも不明だ。
調理実習でも相変わらず彼女は泣いており、一方で珊瑚とは楽しく話せた気がする。珊瑚や苺は、一緒にいて居心地がいい存在だと感じる。
放課後は栞にラットの飼育を紹介してもらった。彼女は過剰に自分を下げてしまうところもあるが、それも慣れてくると彼女の味に感じつつもある。
また全体的に、苺は隣の席なので喋る機会が多い。
一番接触がないのは双葉だ。次のパーティまでに彼女を知っておくことも重要だろう。
それにしても、ただでさえ転校したばかりだというのに慌ただしい一日だった。ただ新しいクラスに溶け込むだけでなく、特定の女の子たちを詳しく知って、誰が自分にとってもっとも相性が良いか見極めなければならないのだ。
頭を枕に埋める。想像以上に気疲れしていたらしい。僕はいつの間にか微睡に落ちていた。
「御坊ちゃま、ここにおられたのですね!」
「うわびっくりした! なんだよ、月夜か」
「なんだよとはなんですか、付き人が帰ってきたというのに」
知らないけどさ、普通付き人の帰宅って主人を起こしてまでするものなの?
「いやー今日はバスケ部を見学してきたんですが、真面目に活動していて流石に大都学園という感じですね。でも私はガツガツ練習する部活より、男女一緒に楽しむサークル色の強い奴がいいかなー」
知らねーよ。
時計をみると、まださっきベッドに倒れてから数分しか経っていない。
「それを報告するために僕を起こしたの?」
「いえいえ、お嬢様からご伝言を承りまして。城悠双葉様からのご連絡です。『明日、お時間があれば放課後、ドラマの撮影に招待します』とのことですが、いかがいたしますか?』
「……ええ、すごいな? ドラマの撮影なんて見たことないよ」
「ええ、私もとても楽しみです」
いやほんと、楽しそうでなによりです。
ということで翌日の放課後である。
僕と月夜はなぜかリムジンに乗っていた。双葉は撮影があるときは大概それに乗って移動しているらしい。リムジンの中にはテーブルがあり、進行方向に対して横向きで座る。世の中には変な車があるものだ。
「私は他のクラスだからさ、怜君の気を引くのすごく不利じゃん。だからさ、こうやって時間を取ってもらったの。そう思ったら二人きりじゃなくてびっくりではあるんだけどね」
「ええ、すみません。御坊ちゃまが一人では心細いというものですから」
「言ってないが」
この付き人は悪びれもせずそんなことを言うが、仮面の下の表情が見えず何を考えているかわからない。
「付き人って言うけどさ、二人はずっと一緒なの? いつから?」
「僕が十歳のときからの付き合いだよ」
「すごいね。学園もずっと一緒だなんて。そもそも同じ学校の同じクラスに手配するなんて、王沢はやっぱりることが違うわ」
「はい! 御坊ちゃまのおそばにいられ、王沢のお世話をさせていただくことができ、私は大変幸せです!」
お世話はしてないだろ。
「……まぁ正確にはずうっと一緒っていうわけでもないけどな。たまに、半年くらいふらっといなくなるんだ」
最初に僕の元に現れたときも、一年位たったら「準備があるので」とどこかに姿を消してしまった。そして、数ヶ月経ったらまたふらっと現れた。この大都学園にくる前も、半年くらい消えていた。そういえばその間学校に通っていなかったわけだけど、大都学園の授業についていけるのだろうか。
「半年とかいなくなって平気なの? ボディーガードも兼ねてるんじゃないの?」
「正確には、危険が近いときに御坊ちゃまのおそばに仕えているとも言えますね。離れているときは、それが問題ないという判断だったのでしょう」
そうだったのか。
「ふうん」
双葉はと言えば、聞いておいてずいぶん興味なさそうな返答だった。
撮影は、都内の海岸で行われるようだった。
大量にカメラなどの機器とそれを使うスタッフが忙しそうに作業をしている。分単位のスケジュールらしく、近づいて話しかけたりすることはできない。ただ離れたところで、その様子を眺めるだけだ。
撮影に向かう際に双葉は僕に言った。
「私を逃したらもったいないっていうの、わからせてあげるから」
遠くから見ても、確かに彼女は凄まじかった。例えば彼女のメイクを直す女性が横に立つと、もはや別種の生き物かと言うほどにそのスタイルが際立つ。顔が小さく痩せているのに程よく胸があり、そして目が大きくて遠くからでもどんな表情をしているのかがはっきりわかる。
なるほど、これがオーラというものかと思わされた。
カメラが回り始めた
砂浜に静寂が広がる中、監督の指示が飛ぶ。
「アキラ、ユキ、もっと近づいて。はい、スタート!」
役名で呼ばれる二人は、緊張した面持ちで互いに見つめ合っていた。それはこちらまで緊張させるような、張り詰めた演技だ。
「ユキ、僕が初めてお前に話しかけたの、覚えてる?」
俳優が言った。彼の声は風に運ばれて、どこか切なげだった。
「うん、もちろん。あの日のことは忘れられないよ」
双葉の返事は柔らかく、彼女の目は潤んで見えた。
「怖かったんだ。いや、正直いまだってこわいよ。大切な相手とはなすのは、いつだって。それを壊してしまいそうで」
「……アキラ、私だって、怖いんだよ」
二人は少しずつ顔を近づけていった。カメラマンはすごく緊張しているように見えた。しかしカメラやガンマイクは、役者の集中力のまえには不干渉だ。
「関係を、壊したくない」
「私も……」
言葉が交わされるたびに、二人の距離はさらに縮まっていった。
僕の隣で、月夜がささやいた。
「これはすごいですねぇ」
「……ああ」
僕はその光景を見ながら、双葉はなんて大胆なことを考えるのだと驚嘆した。それはあまりにも素敵な光景で、彼女はこの瞬間世界で一番魅力的な女の子だった。
そしてそれは、僕が手を伸ばせば届く女の子なのだ。僕の宝物が、知らない誰かに奪われるような感覚に襲われた。それは錯覚に違いなかった。それでも僕は、心臓の早鐘が止まらずに息がしづらくなった。
双葉は誰かとキスをした。
なんだかとても喉が渇いた。
僕は遠くから傍観者として、じっと見ていた。
その世界に、僕はいなかった。
まだまだ撮影は続くそうで、双葉と話している時間もないので僕たちは帰ることにした。
双葉の運転手が家まで送ってくれたので、リムジンでの帰りは楽なものだ。
「これほど素敵なお嬢様と結婚できるのであれば、男冥利につきるでしょうねぇ」
呑気な顔で月夜は言った。もっとも表情は見えないが。
「ああ、そうかも」
彼女は誰もが憧れる女の子。きっと画面を通じて、世界中の男を虜にさせる女の子。彼女を手に入れれば、きっとどこに行っても羨まれるだろう。
でも僕は、思うのだった。
「別にトロフィーワイフを探してるわけじゃないけどな」
「ほほう、御坊ちゃまはそう考えるのですね」
訳知り顔で頷く月夜はなんだかムカつくな。まぁ、月夜にムカつくのはいつものことだと思う。別に双葉のことと、この心の中のざわめきは関係がないのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
