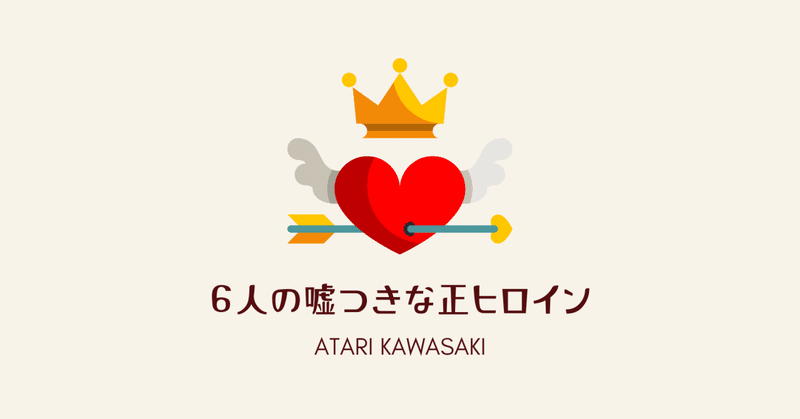
1 王沢の伴侶選び
ドレス姿に着飾った六人の少女が目の前に並んでいた。
それはそれは煌びやかで、もしここが宵闇だったとしても月明かりの代わりになる。
一様に着飾り、ただしそれぞれが思い思いの表情を浮かべている。とっておきの華やかな笑顔、穏やかな表情、興味なさそうにそっぽをむく顔、少し悲しそうな目元。
それぞれの想いを抱えてそこにいる。誰もが自分の想いに正直に生きた結果としてそこに立てるわけではない。
当然、僕もそうだ。僕だって少女たちを目の前に並べて、こんな風に見せ物小屋の客みたいなことはしたくはない。
だからこれは天災なのだ。あまりにも美しく、退廃しており、蠱惑的な天災。
少女のうちの一人が僕の目の前に歩み出た。
「王沢怜(おうさわれい)くんですね。初めまして。会えて嬉しいです。あたしは大喜仰一華(だいきぎょういっか)。一華(いっか)って、下の名前で読んでくれると嬉しいな」
「一華……さん」
「ふふふ、さんなんていらないよ」
「じゃあ、一華」
「ありがと、怜」
ふふっ、と上品に笑う一華の瞳に、思わず僕は吸い込まれそうになる。
真っ赤なドレスに身を包んだ彼女はさながら炎の華で、胸元までざっくりと見せた白い肌が網膜に焼きつかんとする。僕の視線は柔らかそうなそれに引きつけられそうになるが、なんとかそれを拒否して焦点を顔(かんばせ)に合わせた。
お人形のようとはこのことだ。
まんまるでクリっとした目に、小ぶりな口と鼻。北欧の血でも混じっているのか、髪は色素が薄く金色に輝いて見える。
「あたしにはできることなんてあんまりないけど、でもね。怜くんとこれから仲良くなりたいって思ってるんだ。だから、これはその印」
一華は僕にもう一歩近づき、僕の腕にしがみつくようにした。彼女の胸の柔らかさが服越しに伝わり、僕がそれをなんのことか理解するよりも早く、頬に温かくも柔らかい感触があった。それは微かに震えていた。
何分にも感じる一瞬を終え、彼女は再び僕の目の前に戻る。そして、太陽のような笑顔で言った。
「これからよろしくね。怜」
「あ、ああ」
「……ふふふ、びっくりしちゃったかな?」
「いや、何というか……」
頭をぽりぽりと掻いて、一息つく。僕は緊張して彼女の目を見ることはままならなかったので、鼻のあたりを見ながら言った。
「ずいぶん、頭が高いな、と思って……」
「……え? ズガタカ……何?」
何を言われたかわからなかったような表情で、彼女は首を傾げた。
僕は仕方ないので改めて説明する。
「僕は王沢怜だよ? 王沢財閥の総帥、王沢豪一郎の息子なんだ。わかってる? 政財界の魔王、王沢豪一郎のご子息様。生まれながらにしてサラブレッドなんだ。だからこそ、君たちはこうやって群がっているわけなので、本来なら触れるのも恐れ多い存在のはずの僕に、あろうことか口付けをするだなんて、それって対等だと思ってるってことだよね? それはあまりにさ、あまりに不遜だと思わない?」
「……そんな、あ、あたし……」
「だいたい、まずなんというかさ、距離の詰め方っていうの、もっと勉強した方がいいよ。僕にだって心の準備ってものが――」
「御坊ちゃま、それくらいになさってください」
僕の言葉はお付きの少年によって止められた。
「え、いや、ああ、なんで?」
タキシード姿の少年は名前を片側月夜(かたがわつきよ)という。同い年で同じクラスに通う、僕の幼馴染であり付き人だ。目元から鼻まで隠す白いマスクを常にしており、彼と出会った誰もがユーチューバーだと勘違いする。
そんな月夜に止められ、一華は顔を真っ赤にして列に戻っていってしまった。
あれ、僕また何かやっちゃいました?
目の前に並ぶ六人の少女は僕のフィアンセ候補。僕はこれから、彼女たちの中から一人結婚相手を選ぶことになる。
なぜそんなことになったのか、話は一ヶ月前にさかのぼる。
高校二年の三月で、花粉症で目が痒くなる季節のこと。
僕は四月から新しい学園に転入することになっていた。転校は急に決まった。というより、それは天から降ってきた。
「豪一郎様より、転校せよとの命令を承りました。御坊ちゃまには来月より、私立大都学園に編入していただきます」
「大都学園? 何でまた」
「そのお心は窺い知ることはできませんが、転校するにあたってもう一つ命令がございます。このリストのお嬢様の中から結婚相手を選び、互いが十八を超えたタイミングで結婚せよとのことです」
言葉の意味はわかっても、内容が頭を上滑りした。
月夜が渡してきたタブレットを受け取ると、そこには確かに少女たちの顔写真とプロフィールのようなものが映し出されていた。
大都学園は日本屈指の進学校として知られ、また非常に学費が高い。奨学金を受け取る苦学生を除けばほとんどが大金持ちで、つまりこれはお嬢様のリストである。
「なんの冗談だろうね。こんなお嬢様たちであれば、まだ高校生の段階で勝手に知らない人を結婚相手にあてがわれたくはないだろう」
それなのに、こちらが選び、結婚せよなどという指示は、とても現実のものとは思えない。
父は王沢豪一郎。彼は確かに、財閥の巨万の富を手中に納め、日本の政財界を操るフィクサーではある。しかし僕の母は妾、というか浮気相手だし、なんなら僕は豪一郎に会ったこともない。
それなのに、僕が十歳のとき同じクラスに転校してきた片側月夜という少年は、「豪一郎様の命により、今日より派遣されました。御坊ちゃまのお目付役になります」と、十歳とは思えない礼儀正しさで僕の元にやってきた。それから、度々彼の口を介して父の命令が下されるのだ。
最初の命令はこうだった。
『王沢の誇りを持って生きなさい』
なんだそれは、と思った。
今まで顔も見せなかったくせに、何を言っているんだと。僕がどれほど寂しくて、父親がいないことで惨めな思いをしたか知っているのか、と。僕の母の苗字は佐々木である。でも、僕は王沢だ。どんな取り決めでそうなっているかは知らないが、そのことでどれほど母が寂しい思いをしているのか、知っているのだろうか、と。
しかし、同時にそれは父から初めて貰った言葉でもあった。
そして、自分は王沢だった。浮気相手の子にも関わらず、僕に王沢という苗字を与え、尚且つ、それを誇りにしろだなんて。
寂しそうな母には申し訳ないが、それ以来僕は、自分が王沢であることに誇りを持って生きているのだ。
十歳から付き人のいる生活を送るクラスメイトは少ないだろう。一方、母の元で暮らしていたときは生活費なんて受け取ったこともなく、僕は公立の学校で普通の生活を送っていたなんでもない少年だ。
「お嬢様方だって、それぞれ恋愛を謳歌したいだろうに。僕が選んだら『はい』と言って僕と結婚するだなんてことありえないよ」
「まったくです。まさかお嬢様方も、結婚相手がこんな偉そうで捻くれた奴が王沢だなんて夢にも思わないことでしょう」
「いやめんどくさくてごめんだけど、本当は少しだけフォローして欲しかったんだ」
「しかし、無理を通せば道理が引っ込むのが王沢ですから」
僕の戯言には付き合ってくれない。付き人なのに。
それはともかくとして。
「仮に無理を通せるとしてさ、僕が結婚することで豪一郎が得をするとも思えないし」
「それはどうでしょうか。今、豪一郎様の嫡子である跡無(あとむ)様は非常に評判の悪い方です。恐れながら、彼は王沢の器ではないとのもっぱら。であればこそ、御坊ちゃまのような非嫡子から王沢のすべてを引き継ぐものを選ばざるをえないのであれば、早いに越したことはありません」
「だとしても、何で結婚の斡旋を受けないといけないの?」
あくまで想像ですが、と前置きして月夜は言う。
「王沢の後継ともなれば十九の年から英才教育を受けねばなりません。もし恋愛に興じるのであればそれまでに済ませておけ、という豪一郎様の優しさを感じます」
「リストから選ぶ恋愛……ね」
僕は王沢という家名に誇りを持っている。
しかしまた、それだけの人間だ。勉強は人並みにできはしたが、特別というほどではない。運動神経が良いわけでも、人を惹きつけるカリスマがあるわけでもない。
「もちろん、不可解ではあります。でもこれはチャンスではありませんか」
「チャンス?」
「はい。御坊ちゃまは明確に王沢の後継争いに巻き込まれたのです。一つひとつ課題をクリアすれば、いずれ豪一郎様へのお目通しも叶うでしょう」
確かに僕は豪一郎に会いたかった。
僕は彼に言ってやりたかった。そして、僕は一発殴ってやりたかった。母は苦しんでいたのだ。女で一つで、頼るあてもなく僕を育てることを。ただ苦しい姿を隠そうとも、僕が寝た後に泣いていたことを知っている。また会いたいと、豪一郎の名前を呟いていたことを知っている。
僕は、王沢の誇りを胸に抱いている。
その上で、僕の親は母だけだ。僕は豪一郎に言ってやるのだ。
僕は母の息子なのだと。
王沢の誇りを胸に、僕は豪一郎に宣言するのだ。
僕は三月半ばに大都学園のほど近くのマンションを与えられ、そこで月夜と住むよう指示された。受付スタッフがエントランスに待ち構える高級マンションだ。こんなところに僕が住むなど、正直イメージができなかった。
慣れない引越しの片付けと月夜との二人暮らしに明け暮れる中で、すぐさま学園での生活が始まった。大都学園までは徒歩で五分もかからず、マンションの敷地を出たらすぐに学園前通りで、投稿時間にはたくさんの生徒たちの姿がある。
そこではオーソドックスなブレザーとチェック柄のズボンやスカートの男女が桜並木を通り抜ける。着崩す生徒は少なく、きっちりと着こなす生徒が多そうだ。僕が少し前まで通っていた公立高校の生徒たちよりも、皆表情に余裕があり背筋が伸びている気がする。というのは逆に僕が緊張しているからそう見えるだけかもしれないが。
学園の門を潜ると、またしても街があるかのように様々なビルが立ち並ぶ。ここが高校の敷地だとわかっていなければそれは校舎には到底見えないだろう。
僕は月夜に導かれ目的の校舎に向かい、職員室で担任の女教師と落ち合い、その後教室へ。教室の前面にあったのが粉だらけの黒板ではなく巨大ディスプレイだったことに、今日一番驚いた。
僕は教壇に立たされ、隣で教師が言った。
「話していた通り、新学期から転入生がふたり加わります。それじゃあまずは王沢さん、自己紹介を」
タッチペンを渡される。どうやらディスプレイに手書きで文字をかけるらしい。
「王沢怜と言います。親の都合で引っ越すことになりまして、本日より一緒に勉強します。話しかけてくれたら答えるし、仲良くしたかったらどうぞ」
挨拶を終えたが、クラスメイトはポカンとするばかりで芳しい反応は返ってこなかった。まさか、王沢という名字で僕が王沢豪一郎の息子だとピンときて緊張してしまったのだろうか。
「御坊ちゃま、発言が随分上からなのは性分なのでしょうがないとはいえ、言い終わったら一礼くらいしたらどうです? 少なくとも教室全体を睨みつけるよりいい印象を持たれると思いますよ?」
「ああ、確かに」
別に偉そうにしていたつもりはないが、頭を下げるのを忘れていたらしい。一礼すると、パラパラと拍手が起こった。
「皆さん、仲良くしてあげてくださいね。では次、片側さん」
僕と交代で、月夜が教壇に立つ。
「みなさま、初めまして! お会いできるのを楽しみにしておりました。私は片側月夜と申します。王沢怜の付き人です。怜ともども、みなさまと仲良くできることを心より願っております。勉強は得意ですが、世間には疎いので色々教えてくださると助かります。よろしくお願いいたします!」
「そのマスク、何?」「ユーチューバー?」「ファッション奇抜すぎだろ」
何人かの生徒が思わず月夜の印象を口に出してしまう。というかよくタキシード姿で学校来れたな。しかも仮面に手袋つきだ。
「付き人って、王沢君ってすごいの?」「よろしく! なんでも聞いてねー」「一緒に野球部入らんかー?」
ただ、僕の挨拶よりも明らかに反応があるのがどうも釈然としない。僕が主人なのに。
僕は廊下側の三番目の席、月夜はクラスの真ん中に近い席に座ると、月夜は周りの生徒にワイワイ話しかけられていた。
一方僕に話しかけてくる人はいない。なんだか釈然としないな。僕は教科書を机に詰め終えると手持ち無沙汰になり、机に肘をついて時間を待った。
月夜はずいぶん楽しそうだ。
……ああ、挨拶練習しておけばよかった……。
「怜君」
と、そんな僕に隣の席の少女が声をかけてきた。ツインテールというのだろうか、髪を苺のヘアゴムで二つ結びにしており、その上童顔で高校生にはとても見えない少女だった。手をふりふりウィンクして、小さな声で言った。
「隣の席なのですね。私は独田苺(どくたいちご)。苺って呼んでください! 仲良くしてくださいであります」
「あ、ああ。構わないよ」
僕は慌てて笑顔を作った。
「な、何か苦いものでも食べたでありますか?」
「いや、気にしないで」
笑顔の作り方、練習しておけばよかった!
一人ぼっちになりそうだったので、話しかけられたのは正直嬉しい。しかし、その対応が上手くできないのがもどかしい。
「とにかく、困ったことがあったらなんでも苺に聞くのであります。いつでも相談に乗りますですよ」
「頼もしいな」
いうと、苺は無邪気に笑った。
その日、休み時間のたびに月夜はクラスメイトに囲まれて楽しそうにしていた。一方で僕は、苺が話しかけてくれたのでなんとか初日を乗り越えられた。
それにしても、挨拶一つでこうも転校初日が変わるとは……。月夜はあんなに変な仮面をつけているのにクラスに溶け込めるなんて、そんなにコミュ力があったなんて知らなかったぞ。
「いやー、楽しい学園生活になりそうですねぇ、御坊ちゃま」
「それはそれは、何よりだ。でも、あれだけ人に囲まれると煩わしいだろう。僕は親しい友人もできたし、静かな学園生活が送れそうで幸先がいいよ」
「負け惜しみ、お疲れ様でございます」
こんな付き人、います?
「もっとも、御坊ちゃまのお楽しみはこれからでしょう。今夜、お嬢様方との対面が楽しみですねぇ」
「楽しみ……ね」
それは元から予定されていたスケジュールで、転校初日の夜に僕の住むマンションでパーティが開かれるとのことだった。
夜。
僕はそれらしい服なんて持っていなかったから制服のままだったのだが、集まった少女たちが皆ドレスアップしていたので息を呑んだ。薄暗くした部屋の中、間接照明で照らされる彼女たちは輝いて見えた。
だから、緊張していた。
最初に名前を呼ばれた少女、大喜仰一華にちょっと失礼な物言いになってしまったのも、燃えるようなドレスアップをした美しい彼女に緊張してしまっただけなのだ。
さて、パーティの続きである。
「次は、城悠双葉(じょうゆうふたば)様。前にお願いします」
促されて僕の前に立つ少女は、一言で言うならモデルさん。身長が男子の平均くらいあり、すらっとしていて足が長い。グリーンのチャイナ風のドレスを着ていて、彼女のスタイルの良さを浮き上がらせる。姿勢が良く、長い黒髪は照明に照らされ、シャンプーの広告に使われそうなほどはっきりと天使の輪を浮き上がらせていた……と言うより、シャンプーの広告で見たことある気がするんだけど。
「王沢怜君、初めまして。双葉です。私は怜君と、この中で一番分かり合えると思うから期待していてね。きっと素敵なカップルになれるよ」
それはそれは、本当に購買意欲が掻き立てられるような笑顔で彼女は微笑んだ。
「どうして?」
「だって私は、城悠凛子の子供だから」
城悠凛子。その名前を知らない日本人はほぼいないだろう。
大女優、城悠凛子。
彼女は齢を重ねるごとに深みを増すその美貌と、幅広い役柄をこなす卓越した演技力で観客を魅了し続けている。長いキャリアを通じて数々の映画賞を掠め取り、国内外問わず名声を確立、映画界のみならず、テレビドラマや舞台においてもその才能を発揮し、多くのファンに愛されてきた。最近は社会活動にも力を入れており、生き方そのものが女性にとっての憧れであり、まさに時代を象徴するアイコンである。
押しも押されぬ大女優。
その娘が芸能界デビューした、と言うのは噂程度には知っていた。しかし、その方面に詳しくはないため、名前だとか、見た目だとか、そういったものは知らなかった。でも、間違いないだろう。だって僕は彼女をシャンプーの広告で見たことがある!
「有名人の二世って、それだけで偏見があるでしょ? そういうのって、ほんとうんざり。どう? 私たちって気が合うに決まっているの」
「え? それって僕が『二世っていう偏見に晒されて世間を恨んでる』って決めつけてるってこと? 不敬……では?」
「……は?」
涼やかな作りの美人は、コミカルな演技をするみたいに口を広げた。
「僕たちはまだ出会ったばかりだよ? それなのに、すでに僕の内面をこうだって決めつけてさ、それに当てはめて判断しようとしたわけでしょう? それってぜんぜん順番が違うよね。まずは相手を知ることをすべきだし、それ以前に相手も自分と同じように器の小さい人間だって決めつけるだなんて視野が狭すぎて転んじゃうんじゃ――」
「御坊ちゃま、いい加減になさい」
「は?」
ふと冷静になって見ると、目の前の双葉は目尻に涙を湛え、一つ瞬きするとそれが溢れた。
女の子を、泣かしてしまった!
「ちょちょ、どうして泣くのさ。僕、またなんかやっちゃいました?」
双葉はぎりりと奥歯を噛み締めた。
「私、絶対に怜くんを惚れさせるから」
泣きながらではあれど、彼女は強い意志でそう言い切った。くるりとターンし、少女たちの間に戻る姿はランウェイでも様になりそうだ。
とにかく、双葉の自己紹介は終わったらしい。ううむ、うまくいかないな。
「それでは次の方、お願いします」
言われ、ぴょこぴょことやってきた黄色いドレスの女の子。
「初めまして、怜ちゃん。とっても緊張してます。変なこと言っても気にせんといてな」
言葉に関西の訛りがある少女は、緊張していると言いながら緊張感を感じさせない。ふわふわの髪や、ふっくらとした頬。狸顔は愛嬌があり、抜群な美人ではないが安心感を与えてくれる。
「こちらこそ、変なことを言ったとしたら緊張のせいだから気にしないで」
「はは、よう言うわ! 女の子二人も泣かして、その言い訳弱すぎやねん」
「泣かせたいわけじゃないんだけど」
「わかってるで。あと、ウチは打たれ強い方やから、何でも言ってな〜」
「それは、助かるよ」
「ウチは鐘梨珊瑚(かねなしさんご)言います。先に言っとくな。ウチめっちゃ貧乏やから、怜ちゃんと結婚できたら玉の輿やねん。でもな、そんなの関係なく、怜ちゃんと仲良くできたら嬉しい。楽しみにしてます。これはお近づきの印やで〜」
彼女は僕に色紙をくれた。デフォルメされた僕と彼女の顔と、「A PARFECT MUTCH!」という横文字が入っている。「A PERFECT MATCH!(お似合いのカップル)」のスペルミスかな?
「イラストが上手なんだな」
「ううん。こんなんやけど、めっちゃ時間かけて丁寧に描いただけ!」
彼女は手をふり、楽しそうに少女たちの中に戻っていた。
そんな姿に、僕は好感を覚えた。彼女は自分のことを貧乏と卑下していたが、そういう子の方が自分は気が合うのかもしれない、などとまだ何も彼女たちのことを知らないのに思ってしまう。
ただ、一人の女の子のことをずっと考えているわけにはいかない。
すぐさま月夜に促され、次の女の子が僕の前に立つ。
「あの……ええと、ええと」
小さなモジモジとした声が聞こえ、さぞ控えめな少女なんだろうと思い彼女の全身を見た。
「うわ、ぜんぜん控えめじゃないな」
「すみませんっ。何か失礼がありましたでしょうか!」
びくりと彼女は声をあげたが、違います。ごめんなさいこちらが悪かった。
僕は彼女の胸部に目を見張った。胸部とは、いわゆるおっぱいだ。ノースリーブのシンプルなブルーのドレスは、もはやそれを強調するためにきているとしか思えない。彼女が申し訳なさそうに頭を下げるたび、タプタプとそれが揺れ、見えてはいけないものが見えそうになり僕は急いで目を逸らした。
「いや、ぜんぜん失礼とかじゃないよ、気にしないで」
「いえ、きっとわたくしが何かおかしなことをしてしまったのでしょう。ダメですよね。ダメなんですわたくし、本当に。きっともう怜様に嫌われてしまったのでしょう。ああ、なんて最悪。もう嫌です!」
「いや嫌ってないよ本当に」
両手で顔を覆っている彼女は、肘に挟まれ胸がぎゅっと潰れており思わず視線がそこに吸い込まれそうになる。ダメだ……視線を逸せ!
僕は慌てて声をかけた。
「ところで、まず名前をいうのが礼儀ってもんじゃないの?」
「ああ、たいへん失礼いたしました! わたくし、香澄栞(かすみしおり)と申します。父が政治家でして、父のお師匠様のそのまたお師匠様が王沢豪一郎様だとお聞きしています。ああ、そんな縁故を持ち出すようなことを言ってはダメですよね。卑怯なんです私。本当に。ごめんなさいすみません!」
卑下と自己批判でわちゃわちゃしている彼女だが、その度に揺れる彼女の魅力に僕は惹きつけられ続けた。いや、見たいわけじゃないんだよ! ただ、目に入っちゃうんだよ!
「父も怜様にご挨拶がしたいと申しておりました。その、是非とも家族ぐるみの付き合いができれば幸いでございます」
また頭を下げるその下に、ぶるぶる揺れるおっぱい。いや、もはや完全に見ずに視線を逸らし続けるのは逆に失礼に当たるし、これは不可抗力なんだよ!
ただ、ともかくとして、こちらは実の父、豪一郎に会ったこともないためその願いを叶えられるかはわからない。
「それは難しいかもしれないな」
「ああー」
彼女は膝から崩れ落ちた。
「やっぱりわたくしは嫌われていたのです! それは最初からわかっていたことではありますが、しかし自分の未熟さに心が耐えきれません! お父様、お母様、こんな娘でごめんなさい。本当にわたくしはダメな子なんです〜!」
「そんなことは――」
「そんなことはございませんよ。さぁ、おつかまりください」
そう言って、月夜は栞に手を貸した。彼女は立ち上がり、鼻を啜りながら「すみません」と謝った。月夜はエスコートするように彼女を少女たちの間に戻す。
おい月夜おまえ、彼女の胸見てないだろうな。
「さて、それでは次の方に参りましょう」
促され、ちょこちょこと小走りで出てきたのはピンクのドレスをきた小学生?
細かなフリルや装飾の多いそれは、彼女の小ささと相まってまるで魔法少女のコスプレをしているように見える。
「放課後も会えて嬉しいのです。怜くん!」
その顔は、よく見ると見覚えがある。
「あ、苺!」
ドレスアップしていたためまったく気づかなかったが、それは確かに教室で隣の席の彼女だった。彼女は僕の手をとって、ぎゅっと握りふりふり。
「実はね、苺は朝から気づいてたのでありますよ。今日の午後出会う苺の王子様が、怜くんだって! 本当はすぐにそのことを伝えたかったけど、でもそれはフライングな気がしたからずっと黙っていたのであります!」
「びっくりしたよ。学校とはぜんぜん違ったから」
「ふふふー、大人っぽい苺にメロメロでありますか」
「いや、むしろ余計に子供っぽいんだけれど」
「なぬ! は!」
苺は自分の胸元を抑えて僕を睨みつけた。
「た、確かに苺は、栞ちゃんみたいな爆弾は持っていないであります」
「いや、そういう意味じゃないんだけど」
「まぁいいであります。これから怜くんは、苺しか見えないくらいメロメロになるであります。ねぇ、怜くん。ちょっといいでありますか?」
いうと、苺はこっちこっちと僕にジェスチャーしてきた。顔を近づけろということらしく従うと、僕の耳元で彼女はつぶやいた。
「苺はこれから成長期なのであります。まだ未熟な苺から熟れ熟れの苺まで、怜くんに味わって欲しいであります」
「な、何言って――」
「冗談でありますですよー!」
苺はちろりと舌を出して、少女の列の中に戻って行った。
いや、驚いてうまく反応できなかった。それにしても、まさかこんなお子ちゃまみたいな子にからかわれるとは……。
これで全員だったか。いやまて、これで五人?
「それでは最後の方、どうぞ」
月夜に促され、闇の中から浮かび上がってきたのはとても地味な女の子だ。前髪が長く目元が隠され、顔もよくわからない。しかも、首周りも隠れた長袖のドレスは、原色ばかりの他の子のドレスと比べると明らかに地味だ。
彼女は、カツカツと僕の前までやってきたが、下を向いたまま一向に顔をあげない。
「どうかしたのかな? できれば顔を見せて欲しいのだけど」
僕はそう促したのだけど、彼女は一向に顔をあげてくれなかった。僕は他の女の子たちを見やる。今日は最初の顔合わせでそれが終わっているため、みんな手持ち無沙汰のはずだ。
「時間も無限じゃないんだからさ、早く顔を見せてよ。他の子の時間だって使ってるんだ」
「…………オボ……ヒック……ヒッヒッヒ」
少女は相変わらず顔を伏せたまま目元を拭っていた。
……まさか、泣いてます?
え⁉︎ 泣くタイミング、あった⁉︎ あと泣きかた独特だな!
「御坊ちゃま! お嬢様へのパワハラはおやめください!」
「え、僕何かやったっけ?」
「そんなきつい言い方では、どんな素敵なお嬢様だって恐怖を感じてしまいますよ!」
月夜は彼女の背中をさすりながら「大丈夫ですか?」と尋ねていた。しかし、彼女はヒックヒックと嗚咽をあげるばかりで、うまく言葉を喋ることができない。
「しかたないですね、お嬢様に代わりまして、私がご紹介に上がりましょう。彼女は宮仕夢羽(みやつかえむう)様です。一部上場企業にお勤めのお父様と専業主婦のお母様を持ち、頭脳明晰、文武両道のとても優秀な方です。夢羽様、何か追加することはございますか?」
夢羽と呼ばれた少女は、なんとか首を横に振った。
「怖い時間は終わりですから。さぁ、戻りましょうね」
……なんだか釈然としない。
月夜が夢羽を少女たちの並びに戻すと、くるりと僕の方に向き直った。
「さて、ここに揃いますのは王沢豪一郎様さえ認めた世にも素敵なお嬢様方! 御坊ちゃまはこれらの数日間の学園生活でこの中から王沢に相応しい、御坊ちゃまに相応しいフィアンセをお探しいただきます!
「御坊ちゃまはその過程で、人間というものを知ることになるでしょう。傷つくこともあれば、大いなる喜びも知るでしょう。
「豪一郎様より言伝です。
「『他人を求め、自分を顧みよ。その繰り返しこそが、王沢を王沢たらしめるのだ』
「さぁ御坊ちゃま、王沢になる準備はできていますか。お嬢様方、王沢の方翼を担う準備はできていますか。
「王沢の伴侶選び(キングスフィアンセハント)。ここに開幕を宣言します!」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
