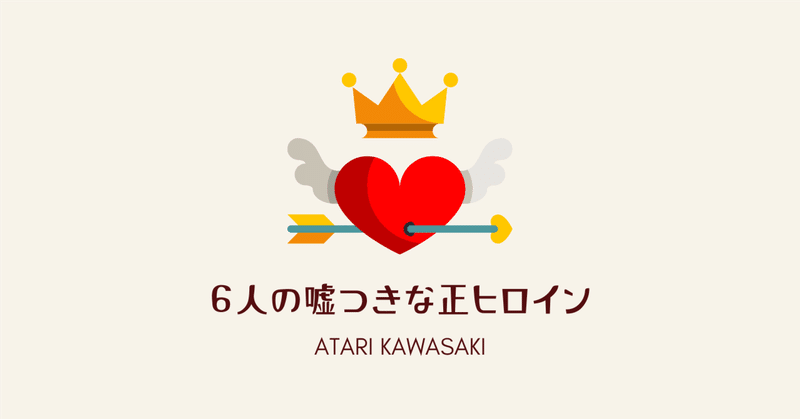
3 王族の特権
「4日後、再びパーティを行います。御坊ちゃまはそこで相応しくない少女を一人指名し、フィアンセ候補から外して差し上げてください。いつまでも御坊ちゃまの首輪付きでは、お嬢様方にも失礼でしょう」
との月夜からの指令により、僕は学園生活を通じて少女たちのことを知っていかねばならなくなった。
真新しいベッドで目を覚まし、僕はだだっ広いリビングへと出ていく。
家具が備え付けだったマンションのため、ソファーやテーブルから紫とオレンジの渦のような謎の絵画までいい感じに配置されている。
もういい時間だが、部屋には僕一人だ。仕方がないのでキッチンに移動し、パンをオーブンに入れて焼く。このオーブンもブランドものなのだろう、外はカリッと、中はふっくらと焼き上げてくれる。
焼いている間にレタスをちぎって軽いサラダを準備し、目玉焼きを焼いたところでそろそろだろう。
僕は月夜の寝室に向かいドアを蹴り開けた。
「おい、逆では⁉︎」
「……ファぁ、御坊ちゃま、おはようございます」
「いやおはようございますじゃなくてさ、ここに引っ越してから毎日僕が朝ごはん作ってるわけじゃない。それっておかしくね? だっておまえ、付き人じゃん? 僕、主人じゃないの?」
「古い価値観で凝り固まっていては成長は望めませんねぇ」
「おまえ、日が経つとともに仕事が雑になってるぞ」
「そんなことより朝ごはんですね! さぁ、参りましょう」
ウキウキとダイニングに移動する後ろ姿を見送ると、もはや咎める気にもなれない。
いや、これも仲良くなったと解釈できるのだろうか。昔はもっとわきまえた少年だった気がするのだが……。特にこのマンションに一緒に暮らすようになってからのだらけっぷりはもはや子育てしている気分だ。僕が主人なのに。
ダイニングチェアに座り、僕はバターの溶けたパンをひとかじりした。相変わらず外はパリッと、中はふっくら。最高だ。
「ところで御坊ちゃま。本日より登校はお一人でお願いいたします。いつも私が隣にいるのは、御坊ちゃまの学園生活の障害になるかもしれないですからね」
「いいけど、おまえは何のために僕と同じ高校に?」
「あ、御坊ちゃま、パン少し足りなかったので、もう一枚焼いてください」
「え、ああ」
僕は立ち上がり、キッチンに向かう。一体僕はなにをしているのだろう。
食事が終わると「では私は先に行きますね!」と意気揚々と月夜は飛び出していった。もっとも、僕につきっきりで彼自身の青春を味わえないのは本意じゃないので、別に構わない。構わないが、釈然としないのはなぜだろう。
ダイニングの皿を片付け、そしていざ登校だ。ただ登校といっても、マンションから学校までは歩いて三分なので非常に楽だ。
エントランスを出ると、そこには少女が一人立っていた。
「お、おはよ! 怜、一緒に学校行こ!」
長いブロンドにはっきりとした顔立ちの少女は、制服に身を包んでも昨日のドレスから見劣りしない。
「一華」
「あ、やったー! 名前覚えてくれたんだね!」
「まぁ、そりゃ」
たったそれだけのことで嬉しそうにされると、こちらも照れてしまう。
一華は僕の隣に並び、「行こ!」と太陽のような笑顔を見せた。
「わざわざ僕の家の前まで来たんだ」
「ぜんぜんわざわざじゃないよ。通り道。あ、ひょっとして頭が高かった?」
からかうように一華は言った。
「いや、そんなわけじゃないけど」
「よかったー! 一人で行けって言われたらどうしようと思ってたんだ! そうなったらもう、あたしノーチャンスじゃん? まぁそれでも諦めないけどねー」
僕たちは並んで歩き始めた。
「ほら、あたし昨日あんまりうまくアピールできなかったからさ、どうしようか考えたの。そしたらさ、ひょっとしたら朝だったら一緒に歩けるかなって思ったんだよね。他の子もいるかなって思ったけど、あたしだけだった。ラッキー!」
そうやって好意を向けられることは、嬉しいと言うよりもむしろ困惑だ。何せ僕たちは出会ったばかりで、互いのことをよく知らないのだから。
「一華はほんとうに僕と結婚したいの?」
「……ええー? ひょっとして意識してる?」
「そういうわけじゃないけどさ」
すらりとした体型に程よく胸があり、顔が小さくてどんなタレントと並んでも見劣りしないだろう。六人の女の子は皆可愛いが、彼女はその中でも絶世の美少女の一人だと思う。
僕が王沢だったとしても、それだけで僕と結婚したい理由になるのだろうか。
「うん、したいよ。話がきたとき、直感したの。あたしはこの人と結婚するんだって。そりゃ、情報でしか知らないよ。知ってるのは、王沢の血を引いてるってことと、普通の人として生活してるってこと。あと、写真くらいだった」
その言葉に、当然だという想い半分、がっかりする思い半分。
「王沢の血を引いてる普通の人と、結婚したいと思ったわけだ」
「あたしは知ってるの。王沢は大変だって」
そんな話は、昨日も聞いた気がした。でも、別の少女からだ。
「双葉と同じようなことをいうんだな」
日本屈指の有名人の子供は大変、というのは確かに双葉とは分かり合える部分かもしれない。なにせ彼女は大女優、城悠凛子の娘なのだ。
でも、一華はどうだろう。もしかすると、有名企業社長の両親を持つ彼女は他人から指を差される生活だったのかもしれないが、それは双葉ほどではないのではないか。
しかし、彼女は首を振った。
「違うよ。その話じゃなくて、ああ、もちろんそれも大変だと思うけど! 王沢の血の話だよ」
話の流れに、どきりとする。
……王沢の、血?
「きみは、何を知ってるの?」
自宅から学園までは近い。喋るには短すぎる距離だから、気がついたらすでに校門に到着している。
一華は言った。
「教えてあげない。これは今日一日中あたしのことで頭がいっぱいになる魔法だよ!」
一華は友達でも見つけたのか、僕のそばから離れていった。
そして、その魔法は確かに効いた。
僕は一華のことで、頭がいっぱいになってしまったのだ。
それに初めて気がついたのは、僕が八歳のときだった。
直接的な原因は、母が買ってきたハムスターだ。寂しくなってしまったのだろう、ある日突然彼女はゴールデンハムスターを買ってきた。もともと動物が好きだったらしく、ペットショップに寄って可愛かったから思わず買ってしまったのだそうだ。本当は犬がよかったのだが、アパートがペット禁止のためハムスターにしたとか。いや、ハムスターもペットだろ。
ベーコンと名付けられたそのハムスターは、警戒心の強いタイプでなかなか人に懐かなかった。特に母は両手で掬うように手に乗せようとしてもいつも指を噛まれ、「これじゃ世話できないよ〜」と僕に泣き言を漏らし、けっきょく世話は僕の仕事になった。
にもかかわらず、である。ある日彼女は「燻製くんで〜す」と言って新しいハムスターを買ってきた。
小さなケージに、二匹のハムスターである。ベーコンは警戒心が強いタイプだった。燻製は小さくて臆病だった。すでにケージはベーコンの縄張りになっていたからいっそう燻製には居心地が悪かったのだろう。燻製はケージの端っこで震えていることが多かったし、たまにベーコンと出くわすとベーコンが燻製に噛みつきかかった。
本当は同じケージで育てること自体が間違っている。でもそれは今だからわかる話で、ケージをもう一つ買うような権限も機転も、当時の僕にはなかった。そもそも育てていない母はそんな問題を認識していなかった。
餌の時間が特にかわいそうだった。燻製はいつもそれにありつくことができなかった。近づこうとすると牙を剥き出しにして威嚇するベーコンに恐れをなし、燻製はベーコンが終わった後の食べ残しにありつくことが限界だった。
これは、どっちにもよくないだろうなぁと思っていた。僕はかわいそうに震える燻製を抱え上げ、頭を撫でた。それはつまり両手で包み込むような状態で、そうすると僕は燻製の『居場所』が明確にわかったのだ。
居場所?
居場所である。
そんなの手の中にいるのだから当然だろうと思うかもしれない。『居場所』、と言うのがわかりづらければ『立ち位置』と言い換えてもしまおう。その目に見えない何かが、僕は形あるものとして触れられるきがしたのだ。
それは超常的な感覚だった。訳がわからなかった。
訳がわからない中で僕は、燻製のことがわかった。
燻製は燻製の価値観の中で、自分をとても低く見積もっていたのだ。自分をとても弱く、価値がない存在だと見定めていたのだ。
僕は、自分がおかしいと思った。
なぜ、ハムスターの感覚を明確に理解できるのか。そもそもハムスターがそんな感覚を持っていると考えるのも馬鹿らしい。あるいは、言葉のない動物はそういった群の中での上下関係により敏感なのかもしれないが。いずれにせよ、今感覚として流れ込んできたそれは、少なくとも僕の知識にはまったく裏打ちされていなかった。
ハムスターの感覚がわかるなんておかしい。
わかるから、わかった。それだけだ。
ただし、わかったのはそれだけではなかった。
おそらくそれは動かせる気がした。
燻製の中の燻製の『立ち位置』を、僕は変えられるという想像に取り憑かれた。
妄執と言ってもよかった。
僕はなんの根拠もなく、燻製の頭の中をいじれると思ったのだ。ただし、包まれる燻製の『立ち位置』は確かに触れられ、動かせる実感がある一方で、どこに動かせばいいかはわからなかった。自信がなく、自分を下に見積もっている燻製。単純な話、せめてベーコンと対等にしてやりたいのだが。
ベーコンと対等にしてやりたい。
……そうだ。
ベーコンだ。ベーコンも同じように、『立ち位置』を動かす感覚を得られないだろうか。僕はケージを開けて、べーコンを両手で彼を包み込んだ。燻製と同じように。すると、その感覚が再来した。
ベーコン『立ち位置』が手に取るようにわかる!
燻製の『立ち位置』。ベーコンの『立ち位置』。その二つが浮かび上がることで、それぞれの位置関係が三次元化した。
それぞれの『立ち位置』を持ち上げ、僕は二つを近づけた。暗闇の蛍のようなそれは、近づくとともに同じ水平の上になった。
僕はベーコンをケージに戻す。
それは空想が基の行為だったとしても、なぜか僕には確信があった。
二匹の大好きなりんごのかけらを、僕はケージに入れた。二匹は互いを邪魔することなく、仲良くりんごのかけらを食べ始めた。その日以来二匹は仲良くなり、ベーコンは燻製を威嚇することはなくなった。それは、たまたまその瞬間に二匹のハムスターが仲良くなっただけの偶然と捉えることもできただろう。
ただ僕には、それを偶然だと切り捨てることはしなかった。
明確な、力だった。
王沢だからだ。たまに母が思い出し泣いている、王沢豪一郎。たまにニュースでも名前が上がる、王沢豪一郎。政財界の魔王、王沢豪一郎。
僕はおそらく、王沢豪一郎の子供だからその力があったのだ。
ハムスターによって気付かされたその能力は、僕が成長する中で何度か使う機会があり、ついには人間にも通用することもわかった。十歳のときに月夜が僕の付き人になり、彼はそれが王沢の血を継ぐものに授けられることがある特有の能力だと教えてくれた。
王族の特権(インペラトル・ライト)。
王沢の血を継ぐ僕の使える力。
この力が使えるからこそ、僕は王沢で、特別なのだ。
僕は力を使えば、人の『立ち位置』を恣意的に変えることができる。
僕は特別だ。
だからこそ、人に近づきすぎてはいけないのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
