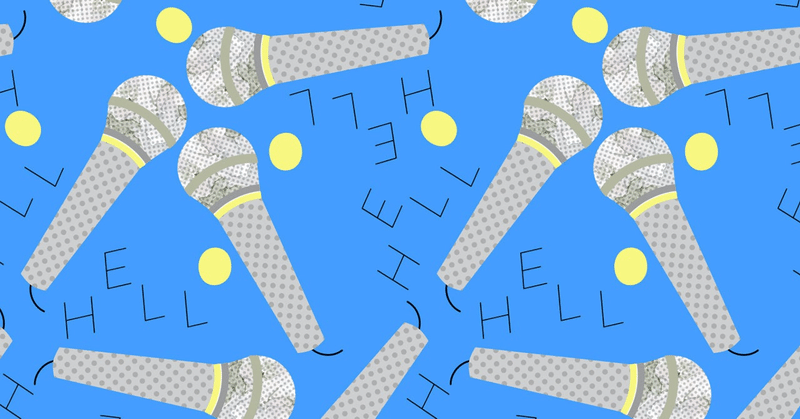
【小説】虹色歌灯~ニジイロウタアカリ~⑦
7.コタロウ:一月半ばのイエロー
この先に行ってはいけないと、立ち入り禁止の黄色いテープが警告する。
生きることが辛いと思ったことはあんまりなかったけど、アカリに言わせるとオレの人生は艱難辛苦らしい。
生後半年で母が失踪。父は養育不能なアル中で、一歳になるかならないかの頃に施設に預けられた。父親は年二回、誕生日とクリスマスにだけ、安物のプレゼントをもって面会に現れた。アルコールにやられているのがわかる灰色の肌と、血走った赤い眼をぎょろつかせながら、オレと目が合うとへらりと笑っていた。
小学校の高学年から一番長くいた施設は七人のユニット制で、時折出入りはあったけれど、いつも一緒に食事をとるメンバーは決まっていた。極端に不器用な子もいたけど、いたって素直な、内気な子が多かったように思う。だからオレは、学校でも施設のユニットでも、気軽に皆を笑わせるようなことばかりを言って過ごした。そういう役割が、求められているような気がしたんだと思う。
いつの間にかそれは自分の性格として染みついてしまった。笑っていれば、毎日は簡単に流れていった。
施設では学用品や、洋服とか身の回りのものは普通に買ってもらえていたし、特段つらいと感じるようなことはなかったけれど、アカリはオレの話を聞くたびに、傷や痛みのようなものを見出そうとするから、よくわからなくなる。……いや、今思えば、本当はつらかったのかもしれないし、そうでないかもしれない。いずれにしても、うまく言葉にできないまま、へらりへらりと適当に生きてきたんだろう。
暗いものを見ないふりをして。ふたをして。自分に向き合わずに。
――勉強できるんだから、大学に行きなさい。
いつからか、周りにそう言われるようになっていた。進学した高校は比較的偏差値が高いところだったし、施設から大学に行く子は少ないから、何となく期待をかけられているのを感じた。
週三ファミレスでバイトをしながら、施設出身児のための奨学金を受けて、進学の準備をした。推薦試験で地元の国立大学に合格すると、職員さんたちが涙を流して大喜びしてくれた。バイトと奨学金二つで生活するめどもできたから、入学と同時に施設を出て、安いアパートに引っ越した。
それから一年半くらいは、のらりくらりと暮らした。ファミレスはバイトの時間帯をナイトに移してちょっとのめり込み過ぎたけれど、アカリに出会ったときは本当に胸がどきどきしたし、歌は下手なりに楽しかった。一年の留年くらいなら何とかなるだろうと、気楽に構えていた。
――だから、どうしてこうなったのか、今でもうまく説明がつかない。
「あー、……」
最近、悪い夢をよく見るようになった。
バイト仲間や、サークル仲間。アカリ。オレの大切なものが夢に出てきては、いつも真っ黒に塗りつぶされていく。暗闇に張りめぐらされた、立ち入り禁止の黄色いテープの警告がたわんでいる。オレは向こうに行けない。いや、立ち入り禁止区域にいるのは、オレなのか。黒い闇の塊がオレの大切なものを踏みにじるのを、オレは見ているしかできない。
皆で歌っていたハーモニーが遠くに聞こえる。闇が迫って、皆が飲まれていく。これは夢だ。それでも暗闇は怖い、逃げたい。
汗をかいて、ようやく目が覚める。
「……ああ」
ゆっくりと起き上がる。ひとりきり。
ここは大学からも遠い、隙間風吹きすさぶ築三十五年の四畳半。一月半ば、木曜日の午後。今日で確か後期のテストも終わりだ。結局どれ一つも受けなかった。これでもう決定打だ。
「……ははは。ごめん」
誰に言うでもなく謝る。ぼろぼろのアパート、冷え切った部屋。布団の中にもう一度潜り込む。オレにやさしいのは眠気だけ。いや、そんなことはないか。
アカリ。
(ごめん、ほんとごめん)
何度謝っても、もう、きっと届かない。
*
人目をはばかりながら、既に日が落ちた冬のその日の夕方、自転車をこいで一時間かけて大学へ向かった。
事務の閉まるギリギリの時間を狙って、久々に大学に足を踏み入れる。相談内容を学生部に告げると、総務部の窓口へと回された。
帰宅したかったらしい職員さんが面倒くさそうに、学費の納入期限を説明してくれた。既に延納願は受理されていて、あと半月がデッドラインだと。半月過ぎると――除籍。大学にいた記録ごと消されてしまうんだそうだ。
奨学金は既に受けていること、留年で止まってしまった分があること。学生向けの教育ローンも紹介されたけれど、とてもすぐにはイエスと言えなかった。
「……さみぃ」
建物を出ると、キャンパス内はほぼ真っ暗闇だった。自分の居場所もよくわからずに立ち尽くす。寒さが忍び寄ってきたので、ぼろぼろの、くすんだ芥子色のダッフルコートの前を慌てて合わせた。
このコートも高校生の時に先輩から譲ってもらったものだ。大学生になってから服なんてほとんど買ってない。バイトしてもバイトしても、生活費、家賃、食費、スマホ代、学費の貯金。腹が減ってコンビニで何かを買うのにも気を遣う。うっかりファミレスで食事なんかしたら財布の中はすぐに心許なくなる。それでも腹は減る。金を貯めるのは難しい。
(働いたほうが、いいんだろうな)
周りの勧めで何となく進学しただけで、そこまでやりたい勉強もない。一人暮らしになって、どこまでも怠惰になっていく気がする。今まで施設の職員さんたちがやってくれていたことの多さと、自分の生活能力のなさに気付いた。
だったらせめて仕事くらいとは思うけれど。
(……でも、“あいつ”に職場を特定されたら、終わりだな)
一層冷たい風が、オレの横を吹いて過ぎる。全身から体温が奪われる。幼子のように、オレは暗闇が怖い。あいつがやってくる。悪い夢が見える。怖い、怖い、怖い――。
大学の門の近くまで足を速める。あそこには街灯がある。明るさが見えて、暗闇への恐怖がほんの少し薄らぐ。
そう、その明るい場所に、誰かが立っている。驚いたように、オレを見つめている。
「……コタ? コタなの?」
ぼんやりと光ってみる気がしたのは、アカリの白いコートだった。茫然とオレを見ている、その隣には、トモヤ。二人の視線がじっとオレをとらえる。
……そういえば、アカリとトモヤが最近ずいぶん仲がいいらしいと、アキヒロと冬のライブ後にちょっとだけ連絡したときに、近況を聞いていた。そっか、そうなっても仕方ないよな。そう思う反面、胸の中で何かがぐらりと沸いた。
(やべぇ)
込み上げたのは、怒り。嫉妬かもしれない。
でも、オレは何一つ話もせず信頼を裏切ったままで、アカリの隣にいる資格がないのは、わかっている。拳を強く握って耐える。胸の中、黒い嵐が吹き荒れる。逃げてきたのに、また闇に捕まりそうになる。
――どうしていいかわらないまま、オレは自転車置き場に向かって走り出していた。
「ちょっと、コタ!」
アカリの声を振り切って全力で走る。けれど、すぐ後ろからカンカンカン、と警報のような高い音。アカリのブーツのヒールが音を立てて近づいてくる。夢で何度も見た黄色い警告がまなうらを過ぎる。ダメだ、怖い。何が。わからない。
自転車置き場までたどり着く寸前、冷えた指先が鍵を取り落としてしまう。拾う指先がうまく動かない。追いつかれる。
「コタってば!」
肩越しに振り返る。闇の中に一筋輝く流星みたいに、アカリがまっすぐにオレの元に飛んでくる。何故か眩しくて、オレはその場でうつむいた。
「やっと、会えた……ずっと探してたんだよ。何度も学生部とか総務部とかも尋ねて、コタが来てないか確認したりして」
アカリが、込み上げる何かを飲み込むよう、呟く。表情はない。怒ってるだろうか。怒ってるよな。下を向きながらチラ見する。ずいぶん髪伸びたな、と思う。
「元気? やっぱり可愛い」
「馬鹿にしないで」
「してない。今はトモヤと付き合ってんの?」
今、そんなこと聞く時じゃないのはわかっていた。話すべきは自分のことだ、けれどぶっきらぼうに口にしてしまう。心がコントロールできない。
「違うよ。まだ、コタと、……ちゃんと別れてもないじゃない」
アカリの声が詰まる。
悲しませたくないのに、どうしたらいいんだろう。手を伸ばして髪を撫でたら、アカリが肩をそびやかした。突っぱねられる。
「中途半端にそんなことしないで。まだ何の話も出来てないよね? どうして急に引っ越したの、お金はどうするつもりなの。ちゃんと答えて欲しいこと、たくさんあるよ……」
アカリはぎゅっと口を引き結んだけれど、堪えきれない涙が目の縁にたまっている。声が反響してオレに突き刺さる。ああ、ごめん。
これ以上、どうやって逃げ続けたらいいんだろう。誰から、何から。頭の中はぐちゃぐちゃだ。
他にできることが見つからなくて、オレはそのままコンクリートに膝をついた。ひんやり冷たさが伝う。そのまま、地面に伏して土下座する。
「ごめん、ほんと、ごめん」
「ちょ、やめてよそういうの。そういうこと望んでるんじゃないよ。コタはほんとうに、あたしのこと、何だと思ってるの」
アカリがオレの両手を取って立たせようとするのを、今度はオレが突っぱねて、頭を下げ続ける。最低の気分だ。謝らないといけない。けれど本当のことを話していいのかどうかもわからない。巻き込みたくない。
オレは弱くてつまらないヘラヘラ男で、一人では何もできない。この胸の黒い嵐から、逃れる方法さえわからない。
(だけど、――助けてほしい)
心の中だけで言ったつもりだったのに、いつの間にか、声が漏れていたんだろうか。それとも。
何かが届いたりすることが、オレにもまだ、あるんだろうか。
そんな、奇跡みたいなことが。
「……コタ」
嗚咽をもらしていたオレと視線を合わせるように、アカリは冷たいコンクリートに膝をついた。きれいなコート、汚れないだろうか。そんなことを思っていたら、涙と鼻水でぐしゃぐしゃなオレの両頬が、あたたかな温度に包まれた。
涙ぐんでいるのに、アカリは妙にきっぱりとした顔をしていた。
「やっぱり何か、事情があるんだよね……? あたしじゃ、力になれないのかな?」
「……そんなことは、ない。でも、」
「じゃあ、ちゃんと話して。コタがあたしに向き合えないなら、あたしがコタの真正面から、ちゃんとコタを見るから」
二人で立ち上がると、膝から冷たさがすぅと抜けた。
アカリの手に手を添えて、オレはようやくうなずいた。情けない自分だけれど、この胸の黒い嵐を、追ってくる暗闇を、へらへら生きてきた報いを、全部逃げずに引き受けられたら。
アカリの手を借りて、今なら。少しだけ、それができる気がした。
*
アカリは、黙って部屋に入れてくれて、作り置きのカレーをあたためて出してくれた。
ここ数日ほとんど食べてなかった。いや、いつからまともな食事をしてなかっただろう。コタツで供されたカレーにがっついた。もうないよ、と言われるまで夢中で何杯もお代わりした。
「美味い。最高。幸せ。このまま死んでもいい」
カレーをたいらげるとようやく、思考回路が冷静になった。これ以上嫌われたとしても、今日こそちゃんと話をしなくては。覚悟する。
「……こんな時に、変な褒め方しないでよ」
アカリはちょっとむくれたり笑ったりしつつ、食後に紅茶を淹れてくれた。夏はよく、この部屋で心地いい紅茶の匂いを嗅いでいたっけ。今夜は、レモンを添えたはちみつ入りの紅茶。この部屋は、カレーの残滓とレモンのさわやかさ、それにアカリのシャンプーのいい匂いで満ちている。オレの数ヶ月にはどこにもなかった安堵感に、思わずとろんと眠りそうだった。
「……それで」
「ああ、うん。あのさ、その、……信じられないかもしれないけど、とりあえず、今から話すことに、嘘はないから」
「うん」
コタツの反対側で自分のカップをもてあそぶアカリの神妙な顔に応えて、オレは恐る恐る記憶を辿り始めた。
「……えっと、前期の終わり、まだ何とかアカリと一緒にテストを受けていた頃にさ。延納してた前期の分の学費を納めに行かないといけない日があって。
バイト代引き出して、ついでに振り込まれた奨学金も引き出して。あとは事務に納めにいくだけってところで、書類の忘れ物に気付いて、一回オレのアパートに帰ったんだけど」
あまり明確には覚えていない。暑くて、空気がゆらゆら揺らいでいた。戻ったオレの部屋の前に誰かが立っている。アロハシャツの、見慣れない人影。
その時、何が起ころうとしているのか、オレにはわからなかった。
「……コタロウ、ってさ。家の前に立ってたやつに、いきなり言われて、全財産、全部取られて」
いつかどこかで見た顔だ、と思って、ようやく思い至った時には、オレは廊下に叩きつけられていた。強烈な頬の痛みが一瞬遅れてやってきて、殴られたのだと気付いた。
「え、強盗……?」
「いや、違う。――クソ親父さ」
見上げた横顔が灰色で、こいつはオレの父親だとわかった。赤い目がぎょろりとオレを見て、そして、へらりと奴は笑った。
痛みの中で、財布の中のカードと有り金を全部抜かれるのを、オレは茫然と見ていた。鍵が拾われて、あいつが部屋に入り込んでいく。オレは、殴られた衝撃と目の前で起こっている出来事のショックで、その場から立ち上がれなかった。
――黒い嵐が去った後は、部屋中荒らされて、通帳も印鑑も盗られていた。オレはたぶん何時間も、起きたことの意味を理解できずに部屋に座り込んでいたと思う。
「翌日、バイト先行ったら、父親を名乗る男が今月分のバイト代を請求に来たと言われてさ。高校在学中から続けていたバイト先だったから、どこからか知られてしまったんだろうけど。……人生で、あんな怖い思いをしたのは初めてだった。ゾッとした。迷惑もかけたくなかったから、バイト速攻辞めた」
「うん」
「……それで、学費だけでもなんとかしなきゃと思って、アカリに、言ったよね」
「うん。三十五万、貸した」
「それをまっすぐ大学に持っていけていればよかったのにさ。……怖かったんだよね、オレ。ほんと、あいつが。ごめん、ほんと。パニックみたいになって、とにかくあいつから逃げたくて。それで、そのお金ですぐ引っ越して」
語りながら、指先が震えてくる。
とにかく、怖かった。ただ真っ黒い闇に怯えた。言い訳にしかならないのかもしれない。けれどオレはその金を握りしめて電車に乗り、大学から遠い駅の不動産屋に飛び込んでいた。すぐ引っ越せるところ、その日のうちに即金で契約した。何でもよかった。持っていた荷物も、ほとんど捨てた。
施設の職員さんには、一番仲の良かった人にだけ一度連絡して、父が来たこと、引っ越したこと、父と縁を切りたいことを伝えた。施設出身者の奨学金のことがあるから大学だけは行ってと言われたけれど、もうあまり意欲がないことや、学費を納めきれてないことを伝えた。
そして、オレは逃げた。
「それで、引っ越し先からほとんど出ないで閉じこもってた。夏のライブの前はもう、ほとんどまともに歌ったりできなかったし。何回か荷物取りにきたけど、引き払うためにこっち来た時、どこかでアカリに捕まったこともあったっけ」
「うん」
「とにかく、怖くて。巻き込むのも怖かったし、アカリに会えばお金の話になって喧嘩になるのもわかってたし、後ろめたくもあったし。ごめん、ほんとごめん。……これじゃ盗んだも同然だし、でも返すあても思いつかなくて、なんとかしないと思って焦って」
それでも、向き合って話す勇気を持てなかったのはオレの弱さだ。するべきことは謝罪だけではなくて、ちゃんとSOSを出すことだったのかもしれない。
「後期になって、皆、出席ヤバいよとか連絡してくれたけど、その日暮らしで金もなくって。ほんと、ごめん。なんかもうオレ、ダメすぎて。あとはもう、ずるずる学校来れなくなって、日雇いとか、クラブとかでバイトしながらとりあえず生きてた」
「……うん、とりあえず生きてて、よかった。そのあと、お父さんは?」
「今のところは、まだ」
「よかった」
アカリがコタツの対岸を出て、隣に来てそっと肩を寄せてきた。いつのまにか、あたたかい部屋なのに震えているオレの指先が、アカリに包まれる。レモンと蜂蜜と、そして甘いシャンプーの匂いが、近い。
「それで、単位はもうほとんどとれてないでしょ。これから大学はどうなるの?」
「たぶん除籍」
「除籍?」
「うん。留年とかじゃなくて、大学にいなかったことになるってこと。授業料が未納すぎてさ。ごめん」
「除籍……、大学から」
アカリが目をまんまるに見開く。その目からぽろりと涙がこぼれたので、オレはどうしようもなくて、ごめんと言いながらもとりあえず笑ってみる。
「……っていうかコタ、こんな時にもへらへらしてる場合じゃないでしょ?」
「泣かないでよアカリ」
「泣くわよ! 馬鹿!」
「まぁ確かに。じゃあ泣きなよ」
「何言ってんのよ! あんたが泣きなさいよ」
「んじゃ胸貸して」
アカリの身体を全力で抱きしめて、泣きそうになる衝動をこらえる。
「……真面目な話してるんだから、このタイミングで胸揉んだりしたら殺すからね」
そう言いながら、アカリは黙ってオレに抱きしめられてくれた。あったかくてやわらかい。この手をずっと握っていたかったのに、怖くて手放した。どれだけひどい状況とはいえ、絶対にやってはいけないことをした。
「本当にごめん。謝ってすむことじゃないけど。ごめん。お金は、何年かかっても必ず返すから」
「……なんかさぁ、あたし、コタのこと、絶対許せないって思って、最初はすごい怒ってたのね」
「うん」
「お金のこともあったから、訴えてやろうかとかまで考えたりもしたけど。成り行きでトモヤに事情を話すことになっちゃったんで、それで相談させてもらったりもしてたんだ。……でも、何ていうか。あたしがコタを許すとか許さないとか、そういうレベルの話じゃなかったってことがわかってよかったっていうか」
「ごめん、アカリ。ほんとうにごめん」
「もう、謝るのはいいよ。お金がどうとかより、その時にすぐ相談してくれなかったことの方が、あたしは悲しい」
「うん、ごめん」
「ごめんはもういいって」
「うん。……あ、でも、もう一つ謝っておきたくて」
ようやく重い荷物を下ろして、アカリと視線を合わせて向き合う。オレは弱い。弱すぎる。でも、ここから歩き出すしかない。
「十二月のライブ。アキヒロから連絡もらって、ちらっとだけ見に行った。アカリが歌ってたの見たよ」
「うん。……ステージから見えたよ」
「すっごい上手くなったし、きれいだったし。皆の歌も、一体感出てて良かった。ほんとは参加したかったけど、もうその時はボロボロで、合わせる顔もなくて。……本当は歌いたかったけど、参加できなくて、ごめん」
「うん」
アカリの手が、ゆっくりとオレの手を握る。以前は毎日のように抱き合っていたのに。あの頃は触れ合うのがこんなに心地いいなんて思わなかったのに。
「……やっぱり、アカリが好きだ。結婚して」
「……は?」
アカリが再び、零れ落ちそうなくらい目をまん丸くしたので、オレの方が驚いてしまう。
「いや、だから、今すぐじゃないけど。ちゃんとお金返すから、その後まだアカリに彼氏いなかったら、もう一回付き合ってほしい」
「ああ、うん、えっと」
「で、そのあと結婚してほしいって」
「冗談よね?」
「うん。でも気持ちだけは本気」
「馬鹿、いきなり何言ってんの! ……ぜんぜん意味分かんない」
「オレも」
えへら、と笑うと、軽く小突かれた。ははは、とから笑いすると、今度は真剣に向きなおられた。
「これからコタとどうなるかとか、ちょっと今は全然考えられないけど。……あたしは、コタの味方でいたいよ。力になれるなら、ちゃんと考えよう? これからのこと、一緒に」
「うん、アカリと結婚」
「そういう夢みたいなのじゃなくて! ……お父さんのことの対策とか、大学や将来の仕事のこととか、バイトやお金のこととか、そういうこと。考えよう。知らないこといっぱいあるから、調べたりもしないと。ちゃんと一緒に付き合うから。あたしだって、その、えーと、コタが好きだし、コタにちゃんと幸せになってほしいし、……できればその、コタと幸せになれたらもっといいし」
「アカリ! 最高! さすがオレの大好きな人」
「ほんと馬鹿! どんだけ心配したと思ってんのよ! 馬鹿!」
アカリがわっと感情を爆発させた。オレの話を、自分を抑えて聴いてくれていたんだとわかって、ますますいとしくなる。ぎゅっと腕に力を込めて、抱きしめあう。
飲み干した甘くてすっぱい紅茶のカップを、二人同時に、コタツの盤上に戻した。
コタツに足を突っ込んだまま、キスをする。しょっぱい涙の味がする。かけがえのない、オレにはもったいないようなこの人を、一生かけて大事にしたいと、心に刻む。まぶた、耳、頬、唇、首筋、やわらかい肌と、胸と、それから、それから。
足の指先まで、アカリの全身にくまなく、心を込めてキスをした。
*
暗闇も、警告も、今はもうどこにも見えない。見えるのは、オレの心に灯ったあたたかなアカリの色だけ。
「ねぇ、コタ」
「ん?」
「もう一回だけでもいいからさ、皆で一緒に、ちゃんと歌いたいね」
「……うん」
眠りに落ちながらアカリが言ってくれたその言葉を、胸に抱きしめる。いつかみたいに、アカリの隣で下手くそでも歌を歌いたい。ちょっと音を外してアカリににらまれたりするような、何気ない日々を取り戻したい。
暗いところから明るい太陽の下へ。変わりたい。アカリと一緒にいる未来を描きたい。
アカリの隣で、みんなのそばで、歌える場所へ、もう一度。
そして、そこがオレの居場所なんだと、確信したい。
**************************
NEXT:8.アカリ:三月初旬のレインボー へ つづく
全体目次
1.アカリ:四月初めのオレンジ
2.アキヒロ:四月半ばのブルー
3.トースケ:五月初旬のディープグリーン
4.ミライ:七月半ばのミントグリーン
5.トモヤ:九月上旬のパープル
6.ヨウタ:十二月半ばのクリスマスレッド
~間奏:年末年始の無色透明~
7.コタロウ:一月半ばのイエロー
8.アカリ:三月初旬のレインボー
よろしければサポートお願いします。これから作る詩集、詩誌などの活動費に充てさせていただきます。
