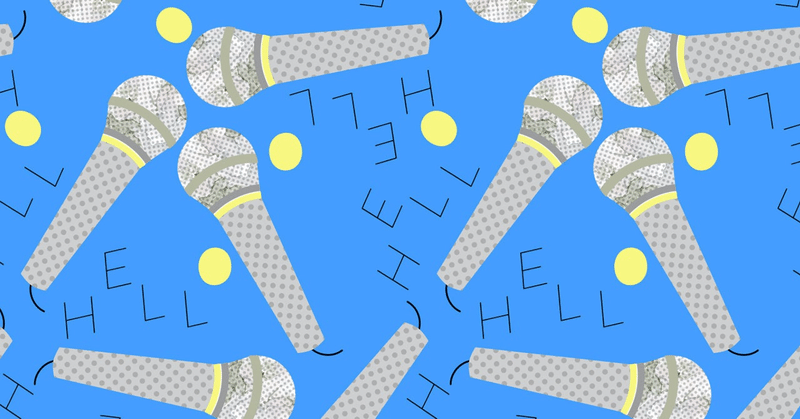
【小説】虹色歌灯~ニジイロウタアカリ~④
4.ミライ:七月半ばのミントグリーン
空っぽのわたしを、何かで、埋めたい。
大学に向かう電車の中で、うとうとしてわたしの手の中で、スマホがぶるりと震えて目が覚めた。ぴこん。音符をあしらったアプリから通知が鳴って、手元に視線を落とす。
“あなたの投稿に、コメントが付きました”
“あなたの投稿に、いいね!が押されました”
同じアプリからの、複数の通知。すぐに起動させて、コメント欄を覗き込む。
“すごい!”“癒される声。素敵なソプラノですね”
いいね十一件、コメント二件。
(少ない、なぁ)
久々に投稿した曲、結構自信があったのに。わたしは心の中で、ほんの少しやりきれなさを殺す。何度もネットにアップした自作の曲、自作の歌。ほとんど人に聴かれることもないままネットの海を流れて、数々の作品に揉まれて消えていく。
わたしなんて、この世界にいてもいなくてもいいみたいに。
「……あぁ」
隣に座っていた人がわたしを振り返る。ため息のつもりが、いつの間にか声が漏れていた。すみません、と小声で謝って下を向く。
――物心ついて以降、なりたいものはと聞かれたら必ず、シンガーソングライターだと答えていたと思う。
昔からわたしは、おっとりした変わった子だねと言われてきた。特に本を読んだり文章を書いたり、考えることに人一倍時間がかかる。体育の動作だってワンテンポ遅れる。皆と感じ方が、あるいはその速度が、異なっている。幼い頃は自分と人との違いをうまく言えなかったから、努力不足だと言われ続けた。
でも、歌だけは、ちょっと違った。
幼いころから、歌になら自分の心をきちんと込めることが出来た。歌う時だけは、堂々と自分をさらけ出すことが出来た。両親が撮ってくれた幼い頃のわたしの動画は、手作りの楽器を手に歌っている姿ばかりだ。
歌が生きがい、歌があれば生きていける。自分で作った歌を歌ってみたいと思うまでに時間はかからなかった。最初の曲作りは小三の時。中学・高校の時はこっそりオーディションやコンテストに音源を送ったりもした。
けれど。
ありきたり、平凡。――ほとんど誰の耳にも止まらない、わたしの歌。
電車の中から窓いっぱいの夏空を見ていると、いつの間にか心もからっぽになっている。なりたかったものなんて幻想じゃないか、と思う。
わたしには才能がない。トースケくんみたいな、圧倒的な声量と表現力が。
トースケくんの空まで突き抜けるあの声を初めて聴いた時、才能っていうのはこういうものなんだと痛感した。ヒロくんやトモヤくんのような適度な上手さじゃなくて、人の心まで大砲のようにまっすぐに飛んでくる、震源。粗削りなのに甘く響いて、信じられない密度でわたしたちを振動させるあの声。
最初に聴いた時にはただただ驚いて、わたしは持っているものをすべて取り落としてしまったのを覚えている。トースケくんも、コミュニケーションや感情表現が不器用で、わたしはずっと親近感を持っていた。けれど、万人を潤す才能を彼は持っていて、わたしはそれをもっていない。
たぶんシンガーソングライターになりたかったわたしは、ああいう風に歌を歌いたかったんだと、思う。トースケくんの自由かつ深みのある歌声は、わたしにとっては理想の具現だった。
夢が見られなくなったからっぽのわたしを埋めていく、彼。
(……わたしがトースケくんみたいだったら、違ったのかな)
強い憧れ、あるいは、激しい嫉妬。どちらなのかわからない。ただ、トースケくんの声を聴けば、からっぽなはずの胸は万力で締め付けられるみたいに、いつも痛む。
“あなたの投稿に、いいね!が押されました”
再び現れた画面の通知にため息が出る。
いいねが二十件になっても、百件になってもわたしはため息を吐くんだろう。わたしの声がトースケくんみたいにはなれないことは、わたしが誰よりわかっているから。
耳に押し込まれたイヤフォンからは、次のライブの候補の曲が延々とリピートされている。試験とレポートを片付けながら、わたしがリードヴォーカルを任された分の歌詞を覚えてしまわなくてはならない。でも、どの曲もうまく頭に入ってこない。このままだと歌詞どころじゃなく、前期の単位も軒並み落としそうな、深刻なからっぽさだ。自分が作った歌はおろか、カバーさえもうまく歌えない。
電車が大学の最寄駅に滑りこむ。
開くドアの向こうは激しい熱気。歌を歌って生きていきたいと息巻いていた、かつての情熱はどこへ消えたんだろう。
ため息。
今はただ空虚な胸を、彼の声と、真夏の暑い風だけが吹き過ぎて行く。
*
前期終わりのテストも近い土曜日の構内は、部活勢の遠い声と蝉の大合唱が混ざり合って、眩暈がするような不思議な反響を作り出していた。
わたしは日傘を手に、キャンパスの端の方にある第二図書館へ向かう。待ち合わせに少し遅れそうで足を速めると、一気に汗が噴き出した。
第二図書館前には、いつもの芝生広場。夏の日差しを受けて、芝は緑に萌えて生き生きと伸びている。中央には一本のクスノキ、その横に小さな噴水。初めて三人で歌い始めた場所。昨年の秋にはトースケくんを、コタちゃんを、そしてこの春にはアカリとヨウタくんを迎え入れた場所。
ここで歌ったのが、すべての始まりだった。
トモヤくんは音楽全般に詳しくて、ヒロくんとはアカペラのマニアな話までできるようだった。二人は、わたしは全然分からない、どこの国のなんとかグループのベーシストは初代の方がどうで二代目がどうだとか、熱くなって話していた。そして、トモヤくんは、わたしが何気なく「歌ってみたい」といった曲を、さらっと三声のアカペラの譜面にアレンジして持ってきてくれた(ほんとそういうところ、顔だけでなくて行動までイケメンだ)。
だから、晴れた日の金曜の夕方は、いつもここで歌うようになった。四限目が空きコマだったからっていうのもあるけど。
そこをちょうどその時間にいつも通りかかるのが、文学部のトースケくんだった。トースケくんは毎回自転車を止めて聴いてくれて、そのうちに声をかけて、自然と仲間になった。そして、同じクラスだったコタちゃんが入ってくれて。今年はアカリとヨウタくんが。
そのこと自体はとてもうれしいことなのに。
クスノキに近づく。蝉がうるさい。木の下の僅かな日陰で、よく見知った人影がわたしを待っていた。
「よぉ、ミィ」
突然くしゃくしゃと頭を撫でられて、戸惑う。ヒロくんの手が届かない位置まで身を離すと、ヒロくんはとても悲しそうな顔をした。
――もしかして俺のこと、嫌いになった?
ヒロくんから最初にそう聞かれたのは五月半ば、合宿の後だった。わたしは、首を縦にも横にも振れなかった。ヒロくんのことは嫌いじゃないけれど、どうしようもなくわたしを圧倒していく声に惹かれているのは事実だったから。
その日から、わたしたちは急にぎこちなくなった。
ヒロくんに、少し距離を置きたいと言えたのが六月。それから一か月と少し、専門の必修講義と週二回のサークルで顔を合わせるたび、ヒロくんは何かとわたしに話しかけ、注意を惹きたがった。そういうことがますますわたしの心を遠ざけたように思う。連絡の返信回数も減らした。自然や風景を撮るのが好きだったインスタも、ヒロくんに居場所や心を邪推されるのが嫌で、ほとんど更新しなくなった。
今日は、試験対策のプリントをコピーさせてほしいと言われて、図書館でレポートの本を借りて勉強するついでに、やむなくほんの少しだけ会うことにしたのだけど。
「一緒に勉強しない? ミィ」
「ううん。今日は一人で集中したいから。ごめんね」
「そっか」
「うん、それじゃあ、また」
「……ミィ」
ヒロくんの横を通り過ぎようとして、手を掴まれた。暑く、汗ばんだ手のひら。その感触が嫌だ、と反射的に思う。わたしはもう彼の傍には戻れないと、自分でわかる。
「俺、いったい何が悪かったのか、ちゃんと教えてほしい。直せるところは直したいし」
応えに詰まる。
ヒロくんと付き合わなければ、ここで歌を歌わなければ、トースケくんや皆に出会うこともなかった。皆でいることは大好きだから、それまであきらめたくないし、サークルを辞めたりしたくない。そのことがわたしの結論を長らく先延ばしにしてきた。
サークルの部長としてのヒロくんの行動力やリーダーシップを、とても尊敬している。仲間としての彼はとても素敵な人だ。――ただ、わたしにとっての特別な存在はあの声であることを、もうごまかせない。
「……好きな人が、出来たかもしれなくて。だから、一番大きな理由は、ヒロくんがわるいとかじゃなくて、わたしの心の問題だから」
ヒロくんの顔から血の気が引いて、表情がみるみるなくなっていく。今言わなくては永遠に言えない気がして、その言葉を必死で絞り出していた。
「ごめんね、もう戻れなくて。……わたしと、ちゃんと別れてほしいんだ」
*
――その後のことを、わたしはよく覚えていない。
気が付いた時には、大学から徒歩五分のアカリのワンルームマンションで、ガラスの丸テーブルに置かれた冷たいグラスを目の前にして、白いラグの上にぺたんと座り込んでいた。ミントのお茶らしい清々しい匂い。浮かべられたペパーミントの葉。氷がカラン、と溶けていく。
そして、涼しい空気に混ざってロフトの上から降ってくる軽いいびき。
「そういえば、アカリはコタちゃんと一緒に住んでるんだっけ?」
「ううん。コタもアパート借りてるよ。でも、最近はほとんどうちにいるから、向こうは解約するつもりなのかもだけど……」
「コタちゃん、前期の単位は大丈夫そう?」
「ははは……このままだとまた留年かもね、シャレになんない。毎日、夜になったらバイトして、明け方帰ってきて。昼間は別のバイトしてるか寝てるかだし」
アカリは、自分のグラスを持って、わたしの向かいに座る。わたしはぐるりと部屋を見渡す。白を基調にしたシンプルですっきりとした部屋の端には、フェイクの観葉植物が鮮やかな緑を呈していた。そしてその横に置いてあるキーボードには、次に皆で歌う予定の譜面が見える。
――ああ、そうだった。わたしは。
苛烈な太陽の下での先ほどの記憶が、ゆっくりと蘇ってくる。
「ごめんね、アカリ、本当に」
「大丈夫だよ。あたしが家にいてちょうどよかった。頼ってくれてうれしい」
あの後、ヒロくんはしばらく黙りこくっていた。
わたしは彼と距離を取ったまま、その場に縫い留められたように立ち尽くしていた。三十分くらいはそうしていたと思う。ヒロくんがそれ以上の会話をあきらめてその場から去るまで、ずっとそこにいた。
ヒロくんが去った頃には、暑さのせいで眩暈がひどくて、息が切れていた。動けなくなる前に、申し訳なく思いつつアカリにヘルプコールをしたら、大学内まで自転車で飛んできてくれた。たぶん、軽い熱中症になっていたんだと思う。涼しい部屋でゆっくり休ませてもらって、事情をだいたい説明して、今に至る。
「サークル、なくなっちゃったら、ほんとうにごめん」
「あやまらないでいいから。皆に続けたい気持ちがあれば、そのうち何とかなるって! まぁ、とりあえずは来週から試験だし、その後にでも話し合おうよ」
「うん……」
アカリは微笑んでくれるのに安心して、わたしはようやくミントの香りのするグラスに口をつける。香りが心地よく体に沁みていく。ほとんど一気に飲み干すと、アカリはお代わりを持ってきてくれた。水分を取り戻したわたしの目から、また水がこぼれ出す。わたしはからっぽのくせに、涙だけはよくあふれる。
アカリはわたしを慰めたいのか、しばらく視線をさまよわせていたけれど、あ、と思い立ったようにスマホを引き寄せた。画面を開いて、わたしの目の前にかざす。
その画面は、わたしにとってはとてもよく知っているものだったので、思わず涙が止まった。目を見開く。音符をあしらったアプリが起動する。
若草色のわたしのマイページが見えた。
「あのさ。これってさ、ミライだよね? インスタとID一緒だし、ミライの声すごい特徴あるからこれはと思って」
確認すると、もらっていたいいねの一つは、“AKARI”というユーザーからのものだった。
「えっ、アカリもこのアプリ、使ってたの?」
「高校の軽音の時に登録して、バンドの音源あげたりしてて。その後は聞き専なんだけど。たまたま漁ってた時に見かけて、もしかしたらと思って。っていうか、作詞作曲、すごくない? めっちゃ本格的じゃない?」
「ああ、でも、ぜんぜん。再生回数伸びないし、いいねやコメントも少ないし。前は、いろいろ賞の応募とかアップとかもマメにしてたんだけど、最近ほんとだめで。……っていうか、今ここで流すのやめて!」
アカリは慌てふためくわたしの目の前で、容赦なく再生をタップする。自分の声が流れて、耳を塞ぎたい。けれどアカリはじっと、それに耳を傾けてくれていた。
「あたし、この曲、好きだな。……ねぇ、これ、皆で歌おうよ?」
「いいね! オレの分も押しといて」
ロフトの上から突然低い声が降ってきた。コタちゃんが、寝ぼけ眼でにやっと笑う。それを受けてアカリが、楽しそうに目を見開く。
「そうか、じゃあ、次の八月終わりのライブで!」
「えええええええ! 無理!」
「わたし、歌ってみたいけどな、ミライの曲。もしできることがあれば、手伝うし」
「オレもオレも」
「コタは勉強優先。ちゃんと単位とらないとまた留年でしょ」
えへら、とロフトを降りてきて笑うコタちゃんの肩を、アカリが割と本気ではたいた。いてぇ、と声を上げたコタちゃんは、わたしがこれまでに見たことがある表情の中で、一番柔らかくて甘い顔をしている。
わたしは、アカリのスマホから、わたしのページと掲載している自作の歌詞を覗き込んでみる。ちょっと不思議な気分だ。トースケくんに出会ってから、少しずつ書き足したり直したりしながら紡いだ歌詞。まだ一番だけしかできてないその歌を辿る、わたしの声。
私たち、透明でいましょう
赤でも青でも緑でもなく
夕焼けの空を渡る
青い風が夜に溶けていく
濃い緑の森の奥
淡い緑の命が眠る
朝は何色 昼は何色 夜は何色
時の流れに 染め変えられて
濁り、混ざっていくなら
せめて 今は
私たち 透明でいましょう
赤でも青でも緑でもなく
私たち 透明でいさせて
水より風より太陽よりも
わたしの想いをトースケくんはきっと知らないだろうし、トースケくんの性格から言って、たぶん言わなければ気づかないだろうと思う。でも、憧れも嫉妬もすべてさらけ出して、自分の歌を歌えたなら。なんて。もしその時、アカリが一緒にコーラスを添えてくれるなら。
からっぽなわたしでも、前向きに、未来を夢見て歌を歌えるかもしれない。もう一度、歌に想いをもって、進めるかも知れない。
人からの評価なんて気にしないで、上手い下手を脱ぎ捨てて、心から心へ伝わるような歌を、全力で。そう、トースケくんみたいに。心の泉からこぼれた想いをやさしい歌に変えて、誰かの胸に静かに沁み込ませていけたなら。
その歌が歌えた時、わたしはわたしの夢を、新たに見始めるのかもしれない。
*
からっぽのわたしを、何かで埋めたい。――何か、じゃなくて、できるなら自分自身の夢と情熱で。
わたしはテストを死ぬ気で片づけた後、アカリとトモヤくんの力を借りて、曲をアカペラ用の譜面にした。アカリには三度下でずっと沿うように歌ってもらうアレンジで。
わたしとヒロくんが別れたことで、サークルが今後どうなるかもわからない。けれど、この曲は、これからも歌っていたいと思えるような歌になる予感がする。もう少し練習したら、自分でアレンジしなおして、どこかにまたアップしてみたりもしようかなと思う。二番も作って、最後まで仕上げて。そしていつか、ちゃんとたくさんの人に聴いてもらえるような形にしたい。
……これから冬まではまだまだ時間があるし、いろんなことが起こるんだけど。よかったらその間のことにも、ほんの少し耳を傾けていてほしいな。ほんの少しだけでいいから。
だって、この秋はたぶん、不協和音が聴こえてしまうだろうから。
**************************:
NEXT:5.トモヤ:九月上旬のパープル へ つづく
全体目次
1.アカリ:四月初めのオレンジ
2.アキヒロ:四月半ばのブルー
3.トースケ:五月初旬のディープグリーン
4.ミライ:七月半ばのミントグリーン
5.トモヤ:九月上旬のパープル
6.ヨウタ:十二月半ばのクリスマスレッド
~間奏:年末年始の無色透明~
7.コタロウ:一月半ばのイエロー
8.アカリ:三月初旬のレインボー
よろしければサポートお願いします。これから作る詩集、詩誌などの活動費に充てさせていただきます。
