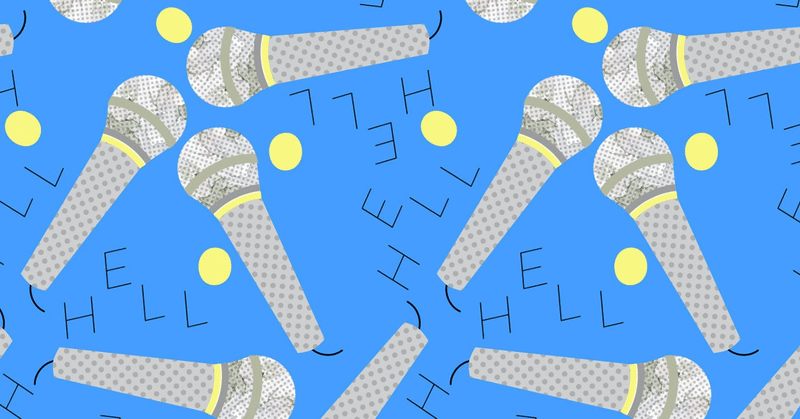
【小説】虹色歌灯 ~ニジイロウタアカリ~①
一浪の末、納得いかない進学をした宇田(ウタ)アカリ。
四月三日、アカリの二十歳の誕生日。大学生活に希望を見いだせず、新入生オリエンテーションを暗澹たる気分で過ごしていたアカリは、コタロウにサークル勧誘の声をかけられる。連れて行かれたキャンパスの片隅の芝生広場で、声だけを重ね合わせ生み出す音楽(アカペラ)で誕生日を祝われるアカリ。コタロウが誘ってくれたのは、昨年結成されたばかりの弱小アカペラサークル「歌灯(ウタアカリ)」だった。自分と同じ名前のサークルとコタロウに惹かれたアカリ。アカリとコタロウを中心とした7名の個性豊かなサークルメンバーは、歌声に彩られた季節の中、恋や想いを育んでいく。
目次
1.アカリ:四月初めのオレンジ
2.アキヒロ:四月半ばのブルー
3.トースケ:五月初旬のディープグリーン
4.ミライ:七月半ばのミントグリーン
5.トモヤ:九月上旬のパープル
6.ヨウタ:十二月半ばのクリスマスレッド
~間奏:年末年始の無色透明~
7.コタロウ:一月半ばのイエロー
8.アカリ:三月初旬のレインボー
1.アカリ:四月初めのオレンジ
運命なんてものがこの世にあるんだったら、それは、理不尽につける名前だと思う。
「一年生? 新入生だよね?」
大学の正門近くで声をかけられた時、そいつの後ろから強い夕陽が差していた。少し掠れた、ちょっと甘さのある低い声。人影は大きくて、やたらガタイが良かった。
「ええ、まぁ。そうですけど」
四月三日。――あたしの二十歳の誕生日。
だだっ広いキャンパスは今朝オリエンテーションに来た時と変わらず、人の出入りがたくさんあってごたついている。大きなメインストリートの両脇にたてられたたくさんのテントのそれぞれに、スマホやチラシを持った男女が待機して、不慣れそうな人を見つけては誰彼構わず声を掛けていた。いわゆる、サークルの勧誘というやつ。
逆光で顔が良く見えないそいつを、焦点が合わないまま全力で睨みかえしたけれど、そいつはひるまず、あたしの前に回り込んできた。やむを得ずあたしは足を止める。
「部活とかサークルとか、もう決めた?」
「……あたし、サークルにはどこにも入るつもりないので」
「そうなの? え、楽しいよ! 何でもいいからやりなよ」
「はぁ?」
一体何の勧誘だ、とその場を振り切ろうとすると、荷物を持ってなかった左手首をぐっと握られた。
「もちろん出来ればうちのサークルで!」
「あの、今日はもう帰るつもりなので」
そこで初めて、相手の顔が見えた。
そいつは人好きのする、にへら、とか、えへら、とか表現するしかない顔で笑うタレ目男だった(とりあえず、へら男と呼ぶことにする)。あたしがどれだけにらんでも、へら男はひるまない。
「高校時代、部活何してたの?」
「……軽音のボーカル、少しだけ」
「まじ! ボーカル大歓迎! 楽譜も読めるよね、決まり! ぴったり! 最高! ねえ、ちょっと寄ってってよ、今すぐ」
「え、軽音は絶対やらないです」
「オレら軽音じゃないから! 大丈夫!」
へら男はものすっごくうれしそうな顔をした。なんだこいつ、犬みたい。他人への警戒心の薄い人だなぁ。ある意味感心してしまう。
「あ、オレはコタロウ。理工学部の一年」
「一年? え? 一年なのにもうサークル入ってるの?」
「あ、去年も一年。今年は留年中だから、まだ一年生」
「……学業よりサークル優先なんですね」
「いやバイト優先。サークルは常時人手不足でね。だから、絶対来てほしいわけ! ね! オレを助けると思って」
「それで、いったい何のサークルなんですか?」
至極まっとうなあたしの問いに、へら男は、もはや人たらしとしか言えない笑顔で、思いっきり目じりを下げた。
「それはまぁ、来てのお楽しみ」
「――帰ります」
「ちょ、ちょっと待って! ずっととか言わないし、入部は気が向いたらとかでいいし。でもできれば四月十七日まで! 二週間! たった二週間でいいから力貸してほしい! ほんと頼むから!」
二週間。
その言葉は、あたしをほんの少しだけ立ち止まらせた。
一浪して入った、ある地方の国立大学の経済学部。第一志望や他の大学もことごとくダメで、三月になってようやく二次試験で何とか拾われたあたしは、住み慣れた東京を離れて一人暮らしになったばかりだ。親は家を借りる手続きと引っ越しに立ち会ったあとはすぐ、仕事があるので東京に戻っていった。誰にも喜ばれていない進学のような気がして、今でもまだ胸の奥が苦い。
新入生オリエンテーションを受けても、来週からの講義にこれっぽっちも意欲が沸かず、誕生日の今日を暗澹たる気分で過ごしていたのだ。
――二週間。
大学に見切りをつけるには、ちょうど良い区切りかもしれない。むしろもっとこの大学に失望して、はっきりと、大学をやめたり、仮面浪人したりと、意思を固められるかもしれない。
あたしが渋々うなずくと、へら男はとびきりの笑顔で目を輝かせた。
「じゃあ、説明、聞くだけ」
「よっしゃ! ごあんなーい!」
*
数分後。
あたしが連れてこられたのは、キャンパスの片隅、芝生の生えた広場だった。キャンパスマップによれば、第二図書館前広場、と書かれている。
芝生の真ん中には、大きなクスノキと、その横に小さめの噴水。ちゃぽちゃぽと水が空に押し上げてられては、オレンジ色の夕陽を反射してきらきらと眩しい。
「ここは……?」
「オレたち弱小サークルだから、部室とかもらえてなくてさ。で、ここがいつもの練習場所」
「……はぁ?」
へら男の言動から音楽系のサークルかなと思ったけれど、それなら楽器や機材の置かれた部室の一つもありそうなものなのに。まさか練習場所が空の下とは。疑念がふくらむ。
「で、あそこにいるのがメンバー」
へら男が指をさす先、噴水のふちに腰掛けた数人の男女が見えて、あたしは無意識に少し緊張する。
「どしたの?」
「あ、いや。……別に」
――部活やサークルに、いいイメージはない。
今日だってこの人懐っこいへら男にさえ捕まらなければ、まっすぐ一人暮らしの部屋に帰っていただろう。
中学までピアノを習っていて、高校は軽音部でボーカルを担当した。歌声にまぁまぁ定評もあって、いろんなバンドに駆り出された。でも気が付いたら、最初にバンドを組んだメンバーからハブられ、その後結局、部内全員からハブられた。……誰にでもいい顔しすぎとか、経験者にズバズバ物言いすぎとか、そういうことを先輩や部員たちにけしかけた人がいたらしい。それは、当時あたしが一番仲良かった友だちだったと、辞めてしばらく経ってから風の噂に聞いた。あんまり思い出したくもない。
ただのやっかみだったのかもしれないけど、とにかくあたしは部活から黙って消えた。学校も休みがちになったし、教室に一人でいる時間も増えた。
苦い経験が脳裏をよぎるのが止められないまま、へら男(そろそろ名前で呼んであげた方がいいか……コタロウだっけ)に促されて、噴水の前に押し出される。緊張を悟られたくなくて、ゆっくり呼吸する。
――長くても二週間の付き合いなら、どう思われたって別にいい。
「おー、コタ。可愛い子連れてきたんじゃん」
すぐにあたしたちに気づいて立ち上がったのは、がっしり系男子と、ふわっとした若草色のストールを巻いたロングスカートの女子。もう一人、細身の塩顔男子が噴水のふちに腰掛けているけれど、あたしたちを一瞥しただけで、本を読むのを止めない。
「わ~! コタちゃんが女の子連れてきた! 初めまして!」
「……」
「へっへっへ。オレもやればできる子!
……で、体育会系オッサンみたいなのが部長、音響担当のアキヒロ。にこにこしてる髪の長い女子が副部長のミライ。二人はオレと同じで理工学部。で、本読んでるのがいつも無口の変わり者、文学部のトースケ。あ、全員二年生、俺だけ二回目の一年生。
あと、細マッチョ眼鏡イケメンで、譜面作成を担当してくれてるトモヤってのが、別のところで学生勧誘中……って、戻ってきた。トモヤ! 新人だよ」
「おー、初めまして! ほんとここ何もないけど、ゆっくりしてってね」
感じのいい細身長身の眼鏡男子が、こちらに手を振りながら戻ってきて、さわやかな挨拶をくれた。
「一年だよね。どこの学部?」
トモヤに問われて、あたしは少し心臓を高鳴らせながら答える。
「経済学部です。……あ、えーと。実は二十歳です」
「え、年上?」
「違う。皆二年生なら、タメ。あたし一浪したから。そして、誕生日が今日だから、今日から、はたち」
「え、そうなの! おめでとう! えーと、……名前何だっけ?」
割り込んできたのはもちろんコタロウ。この男は、あたしに名前を聞くのを本気で忘れていたのだろうか。ちょっとあきれながら答える。
「宇田(うた)アカリ、です」
名乗った途端、トースケ以外の全員が、あたしに急に注目した。いきなり場が凍りついたように見えて、あたしは戸惑う。
「……あの、いま、なんて?」
おそるおそる確認してきたのはミライだった。ちなみにコタロウは、目玉を飛び出さんばかりに見開いている。
「え?」
「いや、だから名前、今なんて」
「宇田、アカリです。宇宙のウに田んぼのタで、アカリはそのまま」
「……ぶっ」
突然、コタロウがこらえ切れないという様子で吹き出す。困惑するわたしが視線をさまよわせると、アキヒロもミライもトモヤも目をまんまるくしてあたしを見ていた。トースケという人だけは、本当に全くこちらに興味を示さず本を読んでいたけど。
「本当にウタアカリちゃんなの? だったら、ちょっと本当にすごい……! わたし信じられない」
「俺は鳥肌が立った」
「本当にあるんだ、こういうこと。すげぇ」
「……え、何なんですか?」
こういうのが、嫌いだ。
自分だけ理由もわからず、いつの間にか盛り上がられて。高校の時を思い出してしまう。もしかして誰か、同じ高校の人とかがいるんだろうか。嫌な噂を流されていたりとか。
「あの、……あたし、やっぱり帰ります」
「いやいや待って、待って! ちょ、絶対待ってってば! もう、アカリちゃん、これ、運命レベルだから!」
「……はぁ?」
コタロウにまた、ぎゅっと腕を掴まれた。固定されて、身動きつかない。何が運命だ。あたしがこんな大学に来たのが運命なんて、理不尽がすぎる。
悔しさやらフラッシュバックやら何やらでいっぱいになっているあたしを差し置いて、コタロウはトースケ、と呼びかけた。
「トースケさぁ、アカリちゃん今日誕生日だって。あと、オレ全然サークルの説明とかしてないから、説明するより聴いてもらう方が早くね?」
「……?」
「だからさ、祝ってやろうぜってこと」
「……ああ、わかった」
ほとんど表情のないトースケが、本を置いて立ち上がる。
――それが合図だった。
アキヒロがポケットから茶色くて丸い笛みたいなものを取り出して、吹く。あの楽器なんて言うんだっけ。ハーモニカみたいなDの音がふわっと鳴り、そこに居た皆が急にハミングしてその音を確認する。
そして間髪を入れず、ーーぴしり。
芝生広場の空気を割ったのは、聞いたことがないほど大きなフィンガースナップだった。それを繰り出しながらトースケがワン、ツー、と呟くと、残りのメンバーが皆同じタイミングで鋭く空気を吸う。
息が合うってこういうことなんだと思った時、カミナリみたいな衝撃が落ちた。
「Happy Birthday to you」
あたしは多分、唖然としていたんだと思う。
まっすぐに突き抜ける声量が、ビリビリと宙を揺らし、あたしを震わせた。伸びやかなリードヴォーカルがまっすぐに心臓に届く。今までに聞いたことがないような声量、抑揚、完璧な歌声。
周りを歩いていた人たちまで、一気にこちらを振り返っている。
トースケのリードヴォーカルに覆いかぶさって、愛くるしい声でハーモニーを生み出すソプラノはミライ。ちょっと不安定にぶれるけれど、味のあるコードの重要な音を辿るバリトンパートがコタロウ(一瞬素敵に見えたのは気のせいだ)。そこに、重い音を出して皆を正していくアキヒロのベースが、ストンストンとはまっていく。イケメン眼鏡のトモヤはボイスパーカッション。初めて聞くその音はどう聞いてもドラムのリズムにしか聞こえなくて目を見張ってしまう。あの口、どうなってるんだろう? ジャジーなビートが皆の間をさりげなく揺らして過ぎる。
驚きが、あたしの全身を満たしていた。
この曲が誕生日を祝うあのメジャーな歌のジャズアレンジだと気付くのに数秒かかったし、これがあたしを祝っているということに気付くのにはさらに数秒かかった。
「Dear……、誰だっけ?」
「アカリちゃん!」
「聞いてなかったのかよ!」
トースケの真顔で突然歌が止まり、ミライとコタロウが突っ込んだところで、誰かが笑った。そのままハーモニーが全部笑い崩れて、曲はそこで終わってしまった。
何かちょっと、もったいない。ずっと続けばいいのに、なんて思ってしまうくらい。
「ああ、ごめん」
トースケは悪びれもしない。まだ戸惑っているあたしの前にアキヒロが進み出て会釈し、大きな声を張り上げる。
「何はともかくアカリちゃん、ハッピーバースデーってことで。そしてようこそ、昨年結成されたばかりの七星大学アカペラサークル、“歌灯(ウタアカリ)”へ!」
「……え? は?」
突然呼ばれた自分の名前に、思わず背筋がしゃっきりしてしまったあたしをみて、ついにアキヒロまでもが吹き出した。
「あの」
「ねぇ、すごい偶然でわたしたちもびっくりしてるんだけど。わたしたちのサークル名、“ウタアカリ”っていうの」
今度は、ミライの説明を受けたあたしが面食らう番だった。
そりゃ珍しい方の苗字だとは思っていたけれど、まさか下の名前まで含めて自分の名前のサークルがあるなんて思いもよらず。
「ってか、声かけたオレってすげぇ! 運命としか思えない」
コタロウは一人で盛り上がりまくっている。皆驚きつつも笑顔だから、ついあたしもつられて笑ってしまう。忘れていた拍手をすると、ミライが嬉しそうに微笑んでスカートの端を摘まんで会釈した。
「ありがとうアカリちゃん! それにしてもごめんね、コタちゃんいっつもこんな感じで。強引に連れてきたんじゃない? 迷惑じゃなかった?」
「あ、……うん。まぁ。大丈夫」
「っていうか、コタちゃん説明はしょりすぎ! そして音外しすぎでしょ~!」
「ミライ先輩ゆるしてくださいよぉ」
「先輩じゃなくて、コタちゃんが勝手に留年して後輩になったんでしょー!」
コタロウは全然悪びれない顔でミライに謝っているし、アキヒロはミライの肩にさりげなく手を回してるし(あれ、この二人、恋人同士っぽい?)、トモヤはあははと笑っているし、トースケは気が付いたらもう読書に集中しているし。マイペースな集団だ。
運命なんてありえない。こんな、あたしの望みの全く叶わなかった先に、運命なんて、そんな存在は認めたくもない。
けれど。
オレンジ色に染まる空の下、この空気は、自由気ままで、そこはかとなくあたたかくて、嫌いじゃない。
「ねー、いいよね? 十七日まで二週間、お試し入部ってことで。“歌灯”にウタアカリちゃん、仮入部!」
悪くないというのが顔に出てしまったのか、コタロウがすぐにあたしの横に寄ってきて、にへら、と笑う。
雰囲気的に断りづらい空気だったのは確かだけれど、ちょっと面白いからしばらくならいいかと、自分でも意外なくらいすんなりと、思えた。
「……普段やってる曲は? 譜面、あるなら貸して。人と合わせて歌うの、初めてだし」
コタロウがそうこなくちゃね、と指を鳴らす。何かちょっと思うがままにはめられて悔しい。でも何となく憎めない。
そんなことを思っていたら、――さらに爆弾が落ちてきた。
「ついでにさ、オレとも付き合ってみない? 悪いこと言わない、二週間だけでもいいから」
「は?」
「すっごい好みだから全力で声かけちゃったんだよ。ね、アカリって呼んでいい?」
「は、あの、えっと、あの、」
「いいよね? 嫌なら二週間以内に断ってくれればいいから!」
返事ができないままのあたしの頬は、オレンジの夕陽に染まったみたいな色になっていただろう。
*
運命なんてものがこの世にあるんだったら、それは理不尽さにつける名前なんだと思っていた。けれど、二十歳の誕生日の夕方に出会った運命は、思っていたよりも強烈で。
偶然にも名前と同名のサークルに出会い、さらに人生で初めての告白までされてしまったあたしはこのあと、……ああ、うん。その辺りの詳しい話は、もう少し後でゆっくり話すことにするから。
まずは、あの後すぐに猛練習して、二週間後の新歓ライブで披露したあたしたちの歌から、聴いていってよ。
*************
NEXT:2.アキヒロ:四月半ばのブルー へ つづく
全体目次(ページ上部にあるものを再掲)
1.アカリ:四月初めのオレンジ
2.アキヒロ:四月半ばのブルー
3.トースケ:五月初旬のディープグリーン
4.ミライ:七月半ばのミントグリーン
5.トモヤ:九月上旬のパープル
6.ヨウタ:十二月半ばのクリスマスレッド
~間奏:年末年始の無色透明~
7.コタロウ:一月半ばのイエロー
8.アカリ:三月初旬のレインボー
よろしければサポートお願いします。これから作る詩集、詩誌などの活動費に充てさせていただきます。
