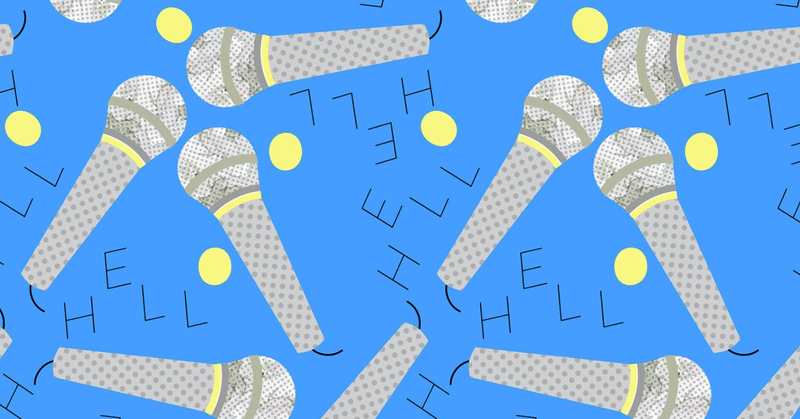
【小説】虹色歌灯~ニジイロウタアカリ~⑧
8.アカリ:三月初旬のレインボー
始まることも、終わることも、運命だなんて言葉で片づけたくない。
18:30。大学の正門に到着。
あたしは佇んだまま、後ろにそびえるキャンパスを見るとはなしにぼぅっと見つめる。
明日は確か、高校生が受験に来る日だ。一年前の自分を思い出しながら、会場の下見に来ている受験生らしい姿を数人見かけて、胸の中だけでエールを送った。
一年目の講義はそんなに専門的な話ばっかりじゃないから、正直未だ学部とか、将来の進路とかは見えてこない。けれど、高校生の時と違う学びと、新たな仲間と、一人暮らし。そして、いろいろありすぎた彼氏。この一年が終わろうとする今、この大学と、あたしと同じ名前のサークルに離れがたいぐらい愛着が湧いて、入学当初に思っていた仮面浪人なんて、もう考えられなくなっている。
現状を憎んでいただけの自分が、そんな風に変わるなんて、思いもよらないことだった。
正門の柱にもたれて、夜空を見上げる。
あたしは変わってしまったんだろうかと、ときどき考えることがある。環境が変われば、接する人が変われば。――自分ではどうにもできないことを運命って呼ぶのなら、自分と同じ名前のサークルで、仲間たちと出会えたのはもちろん運命だ。
でも、それだけじゃなくて。
近く深くで触れ合って、不器用さをさらけ出してぶつかって。そういうことが、あたしを変えて、あたしも皆を少しずつ変えたんだろう。生きているって感じさせてくれる歌声とハーモニーが、あたしを、あたしたちを。
……だめだ、ふとした拍子に、泣きそうになる。今はありとあらゆる感情が、涙につながってしまいそうで、あたしはそれをぐっとこらえる。
18:35。あたしの前に七人乗りのレンタカーが滑り込んでくる。
危なっかしく手を振ってくる、運転席のアキヒロ。助手席には荷物の運搬を手伝ったトースケ。そして、最後尾のシートには、バイト先から拉致されてきたコタロウの大きな影も見える。
「さぁて、そろそろ行きますか」
ひとりごちる。先ほど仕入れてきた人数分のミネラルウォーターと、昨日のうちに防音室から借りてきた譜面立てをトランクに突っ込んで、あたしは勢いよく車に乗り込む。
――これが、最後。
あたしたちはこれから、ラストライブを行う。
*
アキヒロがスムーズにスタートさせた車内の一番後ろ、コタの隣に座る。よぉ、とあたしを招く声は相変わらずへらへらしているけれど、その顔つきは以前より随分大人びて見える。
「……ちゃんといろいろ終わった? 手続き」
「うん」
後期試験の後、コタとあたしは本当に真剣にこの先を検討した。あたしから話を聞いてたトモヤと、それに面倒見のいいアキヒロも、いろいろ手を尽くしてくれた。
学生支援部の人にも手伝ってもらいつつ、今後の単位取得の計画や、学費の見積もり、今後のバイト計画とあたしへの借金返済を、コタとあたしは何パターンも検討した。すでに一年生で二留年、順調に行けてあと三年かかること、バイトに割く時間。留年や成績不良によって奨学金に制限がかかるものがあること。休学にもお金がかかること。
ぶぅん、と車が発進する。コタの肩に頭を付けて、あたしは聞く。
「後悔、ないの?」
「――ないよ」
コタは最終的に、退学を決意した。
学びの意欲も減退していたし、金銭面の工面を優先することにしたのだ。あたしは、コタの選択を応援した。
それから、コタは前に住んでいた施設の職員さんに付き添ってもらって、警察に被害届を出した。お父さんに対していろいろ複雑な想いがあるみたいだったけど、やっぱりそこはきっちりしたほうがいいっていうのが、彼自身の、そして一緒に考えて行動したあたしの、二人の結論だった。ちゃんと警察や第三者を立てることで、お父さんにもわかってほしい。そんな気持ちもあった。このあともちょいちょい聴取があるらしくて、面倒だとコタは苦笑していたけれど。今後何かあったときに警察を頼れる準備も出来た。
「よかったね。今日を落ち着いて迎えられて」
「うん」
退学も被害届も、コタにとってとても前向きな決断だったと思う。
夜が深まっていく。車の最後部座席の窓ガラスに、たくさんの街灯の残光が尾を引いて流れていく。
「どんな気持ち? 今」
「え、そりゃもうライブのことしか考えられないでしょ。めっちゃ興奮してる。楽しみ」
えへら、とコタが笑う。そう、出会った日から、このへらへらした笑顔が印象的だった。
あの日から、あたしはこの顔が好きだったんだろう。
*
「お疲れー!」
18:50。トモヤがそう言いながら乗り込んでくる。19:05。さらに別の駅でミライとヨウタをピックアップ。
いつもの七人が、揃った。
「なんか、今日が最後なんて、ちょっと信じられないよね」
「ほんと、そうだよね」
あたしと、ミライは、そう言い合う。
後期試験が終わった後、あたしたちは集まって、話し合いを重ねた。そうして今日を、七人全員で迎えることにした。
学生サークルとしての解散と、退学を決めたコタロウのお別れ記念の、最後のライブを。
――このメンバーじゃないと、“歌灯”じゃないと思う。
そう言いだしたのは、意外にもトースケだった。彼が、七人でいることをそんなにも大切に思ってくれるようになったことが、あたしは純粋に嬉しかった。
――俺も、この七人だっていうことを大事にしたい。
アキヒロが同意して、それにミライが強く強く、何度もうなずいた。コウとあたしは黙っていたけれど、トモヤとヨウタも笑って同意してくれたので、あたしたちは皆で、一区切りをつけることにしたのだ。
――最後は、ストリートライブにしようよ。
それを言いだしたのは、ミライだった。
それには、あたしとコタもすぐに賛成した。トモヤとヨウタも、この一年の成果を出そうと息巻いた。トースケも、外で歌うのは好きだ、と呟いてちゃんと意思表示をしてくれた。
そして、最後のライブに誰よりもやる気を溢れさせたのは、アキヒロだった。先頭に立って企画を立てて調整を行い、ストリートライブのための許可を取り、録音機材や集客、SNSでの告知など、率先して着々と積み上げてくれた。皆で歌いたいという強い願いがアキヒロを支えていたせいか、ミライとのやりとりもずっと自然になっていった。
アキヒロ、変わったね。あたしとコタは、そんなことを言い合っていた。アキヒロの変化に、ミライもすっかり明るい表情になり、練習のたびにあたしたちは、自分たちの歌声が深化しはじめるのを感じていた。
そして、今日が最後のライブ。名残惜しい気持ちもあるけれど、今はただ心が躍る。
*
19:20。到着。
大学の最寄り駅よりもずっと大きなターミナル駅の大きなロータリーで、アキヒロは車を止めた。すぐに降りて車の後ろに回り込むと、トランクを開けて自慢の機材を嬉しそうに取り出す。
皆で日程をそろえようとするとサークルの日、つまり平日の水曜日しか取れなかったのが残念だけど、ちゃんと機材を使う申請も届け出て、許可も取れた。
ターミナル駅の横の公園の端っこで一時間だけの、正真正銘のラストライブ。
「あれ、機材新しくしたの? いいじゃん」
「一年分のバイト代つぎ込んだぜ! マイクとシールド、あとスピーカーとミキサー……」
「ほとんど全部じゃない?」
アキヒロはニヤッと笑って、自慢の機材を一つ一つ丁寧に取り出していく。それをトースケが無言で拾い、マイクとミキサーをつなぐシールドをくるくると八の字巻にする。一本一本シールドの色は違っていて、七つ。赤、オレンジ、黄、黄緑、緑、青、紫。揃うとまるで虹のようだ。
音だしチェック。Twe、ツェー、あー、Ha-、うん。Si-。He-、He-、ツー、Woo。通りがかる人たちが、何が始まるのかとチラチラこちらに視線を投げかけてくる。前もって声をかけておいた同級生や、コタのバイト先の友人たちも駆けつけてくれた。
ミライが譜面台を立てて、通りを往く人々に見えるようにスケッチブックを開いて乗せた。
“七星大学アカペラサークル「歌灯(ウタアカリ)」、最初で最後のストリートライブ”
全員と目を合わせてから、トモヤとヨウタが紫と赤、両端の二本のマイクを取った。
ワン、ツー、スリー、フォー!
ダブルのパーカッションが体中に響くリズムを刻みだす。安定的なヨウタのバスドラム、スネア、ハイハットに、トモヤが押し込むタム、シンバル、変則のビート。通りを往く人が足を止め始める。
器用に機材をいじりながら、青のシールドにつながれたマイクから、アキヒロのベースが飛び込んでくる。Din,Do,Dowap,DO-dn.跳ね踊るベース。前よりもずっと、明るく確かな音。
あたしはポケットからピッチパイプを取り出して、コタと音程を確認する。そしてタイミングを合わせて、オレンジと黄色のシールドのマイクを手に取った。すぐに六度のハモリ。Woo-Woo,手をつないだままでいるように、距離は六度のまま、上がって、下がって。コードの音を崩さない。クレッシェンド、デクレッシェンド。バランスを崩さないよう注意して、リードヴォーカルを待つ。
ミライが黄緑を、トースケが緑のシールドのマイクを手に取り、中央へ。伴奏を待って、声を解き放つ。
冬の夜空にまっすぐに伸びていく、トースケとミライのツインリード。 アキヒロはその二人をしっかり音の底で支える。その声にはもう迷いはなくて、アキヒロもまたこの冬の厳しい季節を越えたんだと伝わってくる。両端のトモヤとヨウタのリズムは安定、二人の視線が時折楽しげに交わるのが見える。そして、あたしとコタもつかず離れず何とかバランスを保ちながら、この瞬間を飛んでいる。
ミライがいとおしげにトースケを見る。トースケはまっすぐに夜を見ている。ミライの声がトースケの声を夜空に追っかけて、やさしく重なる。
冬の風に乗って、あたしたちは今、どこまでも、どこまでも広がっていく。
「あたしたちは、アカペラグループ、“ウタアカリ”と言います!」
曲が終わった第一声、あたしは聴衆に向かって、自分の名前でもあるサークルの名前を、思わずそう叫んでいた。通りすがりの、ほんの少しの拍手に会釈する。
「寒い中、聴いてくれてありがとうございます! もう少し間、耳を傾けてもらえれば、幸せです!」
駅から、定期的に人が固まって降りてくる、通勤ラッシュの時間。
あたしたちは歌える歌を全て、歌い続けた。
好奇心に満ちた目でこちらを見る人、ほんの少しあたしたちを見つめてすぐ過ぎる人、若いっていいねというほんの少し侮蔑に満ちた囁き。一方で、足を止めて聴きいってくれる人、駆けつけてくれた学部の友達、リズムに体を揺らす高校生、ボイスパーカッションの妙技を凝視する人、トースケの声に圧倒されて口を開けている人、カメラを向けてくる人。
しんしんと冷え込む身震いするほど寒い二月終わりの夜空の下、マイクを掴む手は冷えたままでも、心はどこまでも熱に満ちていく。
時間は、あっという間に過ぎた。
「最後の曲です。メンバーのミライが作詞作曲を担当しました――」
夏に歌ったミライの曲、トモヤが今日のために全員で歌えるように編曲しなおしてくれた。まだ練習が十分じゃないその曲を、あたしたちは最後の曲として選んだ。
ピッチパイプを鳴らす。un-、皆が音を確認して、静かに歌いだす。
皆不器用で、弱くて、生きるのに必死で。だから寄り添って、七つの声で一つの曲を紡ぐ。舞台の上で浴びるスポットライトはないけれど、ここがあたしたちの居場所で、あたしたちの大切なステージ。今までの中で、一番そう感じられる。
隣には、黄色いシールドを揺らしながら歌うコタ。目が合うと、えへら、とまなじりを下げる。
ミライの書いた歌詞と曲をなぞって、声と想いは高まる。
私たち、透明でいましょう
赤でも青でも緑でもなく
夕焼けの空を渡る
青い風が夜に溶けていく
濃い緑の森の奥
淡い緑の命が眠る
朝は何色 昼は何色 夜は何色
時の流れに 染め変えられて
濁り、混ざっていくなら
せめて 今は
私たち 透明でいましょう
赤でも青でも緑でもなく
私たち 透明でいさせて
水より風より太陽よりも
あたしの恋、ミライの心、アキヒロの失恋、トースケの不器用さ、トモヤの臆病さ、ヨウタの無邪気さ、コタのこれから。
あたしたちはいつまでもこのままではいられない。
あたしたちは誰より、そのことをよくわかっている。だからこそ、この一曲が、声を合わせて歌う一回が貴重すぎて。
曲よ、終わるな。ずっとずっと続け。
何にも染まらないまま
透き通るあなたの横顔に
乱反射するプリズム
生まれた虹が世界を照らす
恋は何色 愛は何色 夢は何色
あなたの色と わたしの色を
重ね、溶け合わせたなら きっと
色とりどりの世界が、そこに
私たち 透明でいましょう
赤でも青でも緑でもなく
私たち 透明でいましょう
いつの日か 澄んだ虹になるため
ミライが書いた歌詞なのに、まるであたしとコタの曲のようにも聞こえる。きっと、トモヤも、トースケも、アキヒロも、もしかしたらヨウタも。この曲の一部を、自分のもののように感じるんじゃないかと思う。
曲が静かに終わっていく。いつの間にか、目の前には少しばかりの人だかりができていた。あたしたちは心を込めて頭を下げる。涙がこぼれる。込み上げる嗚咽を喉の奥で殺す。
コタは神妙な顔をしていた。泣きたいのをこらえるコタがこんな顔になるのを、この一年で何度も見た。トースケはいつもの涼しい顔。その分、ミライがぽろぽろと涙を零している。ヨウタは目をいっぱいに潤ませて、トモヤも少し昂った顔をしていた。
アキヒロが、Bun、と皆を鼓舞して強く深く、跳ねる。皆で寄り添って、最後のフレーズを歌い上げていく。
朝焼けの宙を走る
白いカラスが夜を切り裂く
濃い緑の森の奥
淡い緑の命が芽吹く
私たち 透明でいましょう
いつの日か 澄んだ虹になるため
曲が終わる。
ぱらぱらと降る拍手。そのうちにその音が少しずつ揃って、リズムを作りながら大きくなっていくのを、あたしたちは信じられないもののように聴いた。
ストリートライブに、アンコール。
ついにこらえきれなくなったアキヒロがすすり泣くのが聴こえてきて、あたしたちは皆で泣きながら笑って、笑って泣いて、もうどっち何だかよくわからなくなりながら、お互いの手を握って、肩を組んで、冬の聴衆に丁寧に頭を下げた。
そして、初夏の合宿の時、皆で涙するくらい感動したスローバラードを、最後にもう一度、歌い上げた。
空を割るトースケの声、目の前にいる人たちの胸まで届く軌道。
強く人を動かす力に寄り添って、あたしたちは一つの音楽を作り上げていく。あたしたちの拙い声、七つの色をしたそれらを合わせて重ねて、一つに。それぞれ色が違うからこそ、楽しんで生み出せる音の重なり。
アカペラ。
――いつの日か、澄んだ虹になれるように。
そんな願いを込めて。
*
ストリートライブがひとしきり終わって、あたしたちは茫然と片づけをした。全員、完全燃焼した後の快い疲れの一方で、足から忍び込んでくる冷気はなかなか断ちようがない。思い出したように震えながら、あたしたちは片づけを済ませた。
帰りの車内でも、あたしとコタは最後尾に乗り込んだ。コタは誰にも見えないようにこっそりと、あたしに手を伸ばしてきた。あたしは少し前方を気にしつつ、ためらいながらそれを握った。大きな手のひらは、冬の夜の中でもあたたかい。
車内のカーステレオから、次々と思い出の曲が飛び出す。そのたびに声を重ねて、あたしたちは歌う。突然過去のライブの音源が流れて、その下手さに耳を塞ぎながら笑ったりもしつつ。アキヒロやトモヤが、そっとコーラスを口ずさんだり。ヨウタが楽しそうにそれにボイスパーカッションを重ねたり。トースケとミライのダブルリード。あたしたちの間には、いつだって音楽が、歌声が溢れる。
不意に、コタの手があたしを引いて、耳元に囁いてきた。
「アカリ」
「うん?」
「あのさぁ、アカリ。やっぱり、大好きなんだけど」
「……うん」
「それから。いつかちゃんと学びたいことが出来たら、もう一回帰ってきたいなぁ、大学」
「うん」
「その時、歌う場所、あるかな」
「どうだろ。サークルがなくなっても、あたしたちが歌をやってればいいんじゃない?」
「そっか。アカリと皆がいるところに、帰ればいいのか」
コタは目じりをうんと下げて、満面の笑みを浮かべた。
「そうだよ、あたしと皆がいるところに、帰ってきたらいいよ」
大学への進学や、自分自身をなかなか受け入れられなかったあたしはもうどこにもいない。あたしは、誰よりも真剣にこの一年を生きた。そして、大好きな人たちと一緒に今ここにいる。
そして、誰かの帰る場所に、なれる。
そのことがうれしくて、あたしは自分からコタロウの唇に軽くキスをした。コウが目を白黒させる。
「好きだよ、コタ」
そしてあたしは、えへら、と笑った。
*
始まることも、終わることも、運命なんて言葉で片づけたくない。どんな始まりもどんな終わりも、自分たちの手で自分たちらしくできると知ったから。
そうしてあたしたちは、その日で大学サークル“歌灯(ウタアカリ)の活動に終止符を打った。
――そして、翌日から新たに、学生と社会人の混合バンド “虹灯(ニジアカリ)”として、七人で活動を再開することを決めた。
この後のことも、まだまだ話したいことはたくさんあるんだけど。そしてこの後、聴いてほしい歌や新しいレパートリーも増えたんだけど。……そろそろ時間だから、その話はまたいつか、ゆっくり。
あたしとコタがどうなったかって? あのあとも本当にいろんなことがあって、実は……って、それも次までとっておこうかな。
虹色になることを決めたこれからのあたしたちのことも、どうぞよろしく。
もし、いつかどこかで、ストリートで歌うあたしたちを見かけた時は、どうか少しだけ足を止めて、聴いていってね。
心込めて、七色の歌を紡ぐから。(了)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
歌い終えたマイクをそっと置くように、この世のどこかに彼らの物語をおいておきたいと思っていました。創作大賞の機会を借りて、noteに送り出そうと思います。長い物語を読んでくださって、ありがとうございました。
みんなのギャラリーから素敵なイラストをお借りいたしました。感謝します。
全体目次 ~よろしければぜひもう一周どうぞ~
1.アカリ:四月初めのオレンジ
2.アキヒロ:四月半ばのブルー
3.トースケ:五月初旬のディープグリーン
4.ミライ:七月半ばのミントグリーン
5.トモヤ:九月上旬のパープル
6.ヨウタ:十二月半ばのクリスマスレッド
~間奏:年末年始の無色透明~
7.コタロウ:一月半ばのイエロー
8.アカリ:三月初旬のレインボー
よろしければサポートお願いします。これから作る詩集、詩誌などの活動費に充てさせていただきます。
