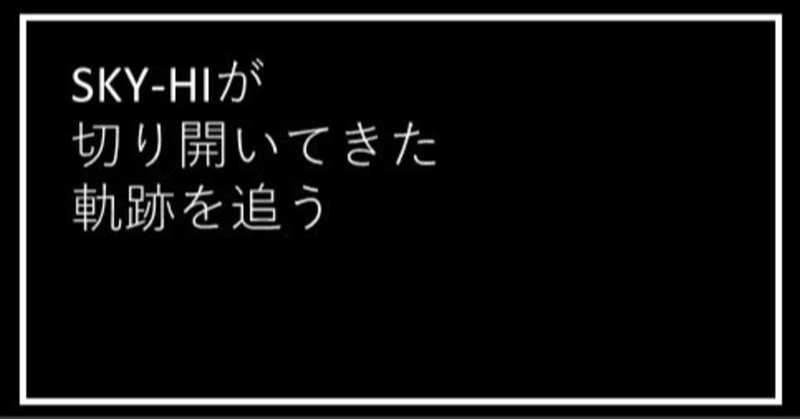
SKY-HI、BMSG設立とボーイズグループオーディション。彼が切り開いてきた軌跡を追う
2020年9月23日、SKY-HIにとって初となるベストアルバム『SKY-HI’s THE BEST』がリリースされた。本来であれば彼にとって思い入れの深い、6月17日に世へ放たれるはずだったこの作品。
「メジャーデビューから8年間の集大成」なんて書くメディアもあるが、メジャーデビューである2013年8月7日を起点に物事を考えるのは、間違いでこそないが”SKY-HIのベスト”として語るのに、いささか乱暴な気もする。SKY-HIにとってメジャーデビューは、ひとつの通過点でしかなかったからだ。
いうて、彼は19歳の頃からSKY-HIとして活動しているし(18歳というときもある)、SKY-HIとして初めてステージに立ったのは2006年2月22日だと証言している。SKY-HIのベストとして語るなら、ここのキャリアも無視することはできないだろう。
せっかくのタイミングなので、SKY-HIならびに日高光啓(だっちゃん)が歩んできた軌跡を整理したい。
avexが放置したという奇跡
「SKY-HIの奇跡っていくつかあるけど、そのひとつはavexが日高を放置したことだよな」。そうRHYMESTERの宇多丸が語るように、初期のSKY-HIはavex非公認のアーティストだった。いや、黙認といったほうが正しいだろうか。
2005年4月にAAAが正式発表された以上、彼はメジャーレーベルに所属するアーティストだった。プライベートでクラブに遊びに行ってもいい、趣味で音楽を作ってもいい。しかし、観客の前でパフォーマンスをするとなると、話は別。契約という大人の約束が、常に付きまとう立場にいた。
そんななかで彼は「リスクをとってでもラップをする」という道を選んだのである。そして、偶然近くにいた大人が「本当はダメなんだよ、でもやりたいんだろ?」という人だったのだ。
――渋谷FAMILYのステージに立てる。
SKY-HIの物語がひとつ開けた瞬間だった。
そして来たる、2006年9月13日。彼は渋谷FAMILYのステージに立っていた。お客さんの数は、5人。(なかには、KEN THE 390もいたらしい)
2時間前に、AAAとして武道館ライブを終えた直後のことだった。
色眼鏡との闘い
「ところでSKY-HI(日高光啓)って、アイドルなの? ラッパーなの?」というのは、この約15年間ずっと彼が向き合わされてきた話題だ。韓国であればG-DRAGON(BIGGANG)やMINO(WINNER)など、グループの一員としてもラッパーとしても認められている存在がいる。
しかし、日本においては、それがいない。SKY-HIが活動を始めた頃なんて、なおさら彼のような存在は稀だった。
ラップバトルではAAAであることをネタにされるし、聴く前に「アイドルの片手間でしょ」とスルーされることも珍しくない。どれだけ本気で向き合っていても、なかなかその事実は届かなかった。
――量と質は比例する。
「目で音楽を聴く人たちに真実を知ってもらうには、圧倒的な実力が必要だ」とでもいうように、SKY-HIはひたすらクラブに通った。バトルやサイファー、オープンマイクへ積極的に参加し、己の技術や感性を磨いたのである。
SKY-HIは、avexの秘蔵っ子でもなんでもない。クラブからのし上がってきた、たたき上げのラッパーなのだ。
『FLOATIN' LAB』で見せた、プロデューサーとしての片鱗
クラブへ通い己のラップと向き合い、時間を見つけては制作をし、ネットに曲をアップ。SKY-HIとして成し遂げたい未来を、何度も企画書に描いた。そのほとんどは、さまざまな理由のもと時代のなかに埋もれていく。2008年にメジャーデビューに対してまとめたものも、相手にされることなく一蹴されている。ようやく実現にこぎつけた企画こそ、2011年の『FLOATIN' LAB』だった。
2010年の日本のHIPHOPを代表する楽曲をビートジャックする「JACKIN' 4 BEATS 2010」、KEN THE 390「What's Generation」への客演は少しずつだが着実に、SKY-HIというアーティストへの風向きを変えていったのである。
2011年に作った企画書のなかで掲げた、インターネットプロモーション。これが、『FLOATIN' LAB』の草案だ。
「自らがメディアとなり、HIPHOPへの門戸を開く」をテーマにしたものの、既存のメディアと組んだらもっと面白いことができるかもしれない。そう思い、Amebreak編集長である11Zero氏にコンタクトをとり、タッグを組んで進めていくことになった。
重点は、2つ。1つはHIPHOPが持つ自由度の高さやフットワークの軽さが伝わるような映像を発信していくこと。アンダーグラウンドなところで文化が形成されていくジャンルだからこそ、限られた人の音楽という印象の強いHIPHOP。難しく考えず「楽しい」「かっこいいかも」と、直感で伝わるようなコンテンツを意識した。
もう1つは、ありそうでなかった組み合わせの楽曲を作っていくことだ。SKY-HIの頭のなかにあった「こういう掛け合わせ見てみたい」を、柔軟な発想のもと実現していく。
すでにネームのあるKEN THE 390やTARO SOULがアサインされたことはもちろん、若手であるRAU DEFも客演。一般からトラックも公募し、先人をリスペクトすると共に新たな才能へ光を当てる企画となった。
そして、2012年5月30日。番組として始まった『FLOATIN' LAB』は、アルバムとしてリリースされた。「オリコン50位以内に入れたら嬉しい」という思いを嬉しい形で大きく裏切り、オリコンアルバムデイリーチャート17位を獲得。彼が描いてきた未来が、絵空事じゃないと証明された瞬間のひとつとなった。
また、2012年6月17日に開催された「FLOATIN' LAB Release party Welcome to the "LAB"」も大盛況を収める。10人以上の客演がいながら、誰一人として欠員なし。着地点を決めないで面白いことを企んだ結果、想像以上のものを作り上げてしまったのだ。
この年には、雑誌『WOOFIN'』の「WOOFIN' AWARDS 2012」にて「BEST OF RAPPER」も受賞。時代がSKY-HIに気付き始めてきた。
レーベル「BULL MOOSE」設立
『FLOATIN' LAB』の話題が出た以上、このタイミングで語らなければならないのは、レーベル「BULL MOOSE」の存在だろう。『FLOATIN' LAB』リリースのためにできたレーベルという名目で始まったものの、今もなおSKY-HI自身が代表を務めるレーベルだ。
2015年リリースの『FLOATIN' LAB II』は、BULL MOOSEのコンピレーションアルバムという位置づけにもなっており、NIHA-CとMoroを世に輩出。また、かねてより親交のあったRAU DEFが現在(2020年9月時点)リリースをしているのも、このレーベルだ。
あまり表立って語られることはないが、今もなお「BULL MOOSE」は呼吸し続け、新しい才能を世に送り出さんとしている。最近でこそ作詞・作曲やプロデューサーとしても注目されているSKY-HIだが、彼の原点のひとつはここにあるといっても過言ではない。
BFQを形作った、群馬「CROSTAGE」
『FLOATIN' LAB』がリリースされ、熱視線を浴び始めた2012年。SKY-HIはダンサーを引き連れて、群馬「CROSTAGE」に出演し、ひとつの確証を得ることになる。
――まとまった。
現在、SKY-HIのダンサーとして知名度を誇るBFQ(BLUE FLAP QUARTET)は、この日にダンサーを務めた面々なのだ。
今思えば、MoneyがAAAのとき日高にダンスを教えていたり、BUZZER BROTHERとしてTAK-YARD、JUN、MoneyがSKY-HIとコラボしていたり、伏線はたくさん潜んでいた。
群馬「CROSTAGE」の日は、先の3人と共にSKY-HIのダンサーをしていたRYUTAがスケジュールの関係で欠席。白羽の矢が立ったのが、Moneyたちと同じチーム(BRUST)に所属し、イベントに先生として出演予定だったKensuke なのである。
初期こそ、SKY-HIダンサーズとして活動していた4人だが、「SKY-HI DANCERS WORK SHOP TOUR 2017」の初日にはBFQという名前を発表。現在では、YouTube チャンネルを持ちSKY-HIと別でも行動していくチームとなった。
コンサートの開催時に幕間として繰り広げられるセンテンスは、もはや人気コンテンツのひとつ。ダンサーとしてステージを華やかにするだけでなく、エンターテイメントの側面でも彼らの担っている役割は大きい。
センテンス
幕間のタイミングで行われる、ラップ×ダンス×コントのショーケース。その時々で、「監獄」や「家出」といったテーマを用いて展開される。ラップはSKY-HIが担当し、それに合わせてBFQのメンバーが芝居をしたりダンスをしたりする。
メジャーデビューとポピュラリティ
さて、SKY-HI本人の動向に戻ろう。
2013年、SKY-HIは『愛ブルーム/RULE』でメジャーデビューを果たした。クラブで叩きあげられてきた彼のこと、多くの人は鋭いリリックが光るクールなナンバーを想像したことだろう。
しかし、リードトラックとして打ち出されてきたのは、爽やかなディスコチューンの「愛ブルーム」。いわゆるラップやHIPHOPに興味がないような人でも、手を伸ばしやすいポップな楽曲だった。
――「愛ブルーム」みたいな(快活でポップな)曲を今作っておかないと、今後の闘い方がだいぶ限定されるんじゃないか
向こう10年を想像しメジャーに乗り出してきた彼にとって、戦術が限られてしまうのは死活問題。1週間もかからず完パケし、奇跡的に世に出せた作品こそ「愛ブルーム」だったのである。
振りかえれば、この2曲からポップ&ラップと向き合い、ポピュラリティと上手く付き合っていくキャリアはスタートしたような気がする。
HIPHOPの現場へ行くと「アイドルのお遊びでしょ?」といわれ、芸能・アイドル系には「あー、HIPHOPね(笑)」と反応され、時にはAAAファンから「だっちゃんは、ソロのほうが大事なんでしょ?」と言葉をかけられるようなことも。
そんな声のひとつひとつを、彼は行動でひっくり返してきた。
自分との折衷案を探し良質なポップソングを生み出し、ラッパーとして先進的なビートにもチャレンジし、ファンには変にメディアを通さず自分の言葉で語りかける。
だからこそ「売れたい」という話も、包み隠さず真っ直ぐ話した。予約をしてほしい、バカみたいに売れたい。武道館に立ちたい。
SKY-HIという船に乗ってくれたファンに対して、胸に抱いている思いを伝えられなくてどうするんだ、と。
ポップスターたる面もラッパーたる面も含めて、SKY-HIであり、日高光啓なのだ。そう伝えていく生き方は、この2曲が封切ったといっても大げさではないだろう。
なお「愛ブルーム」のMVは、「MTV VMAJ 2014」でBEST HIP HOP VIDEO賞を受賞。10代の頃からの夢をひとつ叶える結果となった。
182回リテイクした「スマイルドロップ」
SKY-HI至上、難産だった曲として名高い「スマイルドロップ」は、技術的にも精神的にも、ようやくたどり着いた1曲だった。
トライ&エラーを繰り返しながら、ようやく生み出した1st アルバム『TRICSTER』。この1枚が突きつけたのは、本当の意味でちゃんと届けたり広げたりするものが作れていないという現実だった。
――歌詞力じゃなくて作詞力を根本から見直さないといけない。書けるようになるまで、1回リリースを止めてほしい
フリースタイルやサイファーで鍛え上げてきた即興ラップの能力は、SKY-HIを別の側面で苦しめることとなった。ビートと韻に導かれるだけに終わらない、ちゃんと届いて広がっていく歌詞を紡いでいかなければ。
足りていないスキルを身に着けるため、SKY-HIは徹底的に「スマイルドロップ」と向き合った。ただでさえ制作は難航を極めているのに、追い打ちをかける信頼していた人の裏切り。
「今日もきっと答えは出ない」そう思いながらも、ひたすらに曲と向き合う日々。作り直すこと182テイク、季節はいくつも通り過ぎ9ヶ月もの時がたっていた。
SKY-HIが「スマイルドロップ」により得たのは、自分の深い感情をポップスとして昇華する能力だ。ラッパーとして、感情を吐露するだけに終わらない、多くの人と分かち合っていけるリリック。シンガーソングライター然とした歌詞を紡げることは、その後の彼にとって大きな武器となった。
死ぬことに生きることを見つけた『カタルシス』
SKY-HIのアルバムといえば、テーマ性をもった1つの作品というイメージが強いが、それを確立させたのが2nd アルバム『カタルシス』だ。
2015年の頭頃から、アルバム全体の脚本やプロットを完成させ、各曲を作っていったというだけあり、完成度の高さが凄まじい。すでにリリースした曲を寄せ集めて「アルバム出しました」とするのではなく、伝えたいものを明確に持って打ち出していく。プロデュース能力が高いSKY-HIだからこそ、作り出せた1枚ともいえよう。
「語る、死す」とカタルシス(精神の浄化作用)のダブルミーニングを持ち、死ぬことと生きること、そして愛することと向き合った誠実な作品であり、SKY-HI自身が1番気に入っている曲だと語る「フリージア」も収録されている。
「死にたい」と言って、
— SKY-HI(AAA日高光啓) (@SkyHidaka) January 12, 2016
「生きたくても生きられない人もいるのに!」って怒られた人いると思うんだ。
でも辛さや苦しさは人それぞれで本人にしかわからないから
「死にたい」って思っちゃうこと自体を責めたく無いのだ。
だからそれを「生きてて良かった」に変える音楽を作ったんだ #カタルシス
また、「死にたい」と思う気持ちを否定しない彼のスタンスは、このころ明確化されたようにも思える。怒りにも悲しみにも分類できない感情をこえ、自分自身の曲である「スマイルドロップ」や「カミツレベルベット」に救われた経験をしたからこそ、「生きててよかった」を導く作品にたどり着いたのではないだろうか。
手術を経て手に入れた、新しい喉
あまり表立って語られることはないが、2016年4月にSKY-HIは声帯結節の除去手術を行っている。本人にとっては「わざわざ発表するほどのことでもない」らしいが、この手術は明らかに歌手としての彼を好転させた。
そもそも声帯結節の原因は、声の多用、誤用による音声酷使だ。職業柄しょうがない症状ではあるものの、声帯に生じた腫れ物は声を出しにくくさせ、高音はなおのこと発生しづらい。
手術を行ったことは、全20公演にも及ぶ「SKY-HI LIVE HOUSE TOUR2016~Round A Ground~」を成功へ導くと共に、次作の『OLIVE』で豊かなファルセットの曲を生み出すことにも一躍を担った。
なお、2016年の夏ごろまでは、喉を上手く使いこなせず恐怖心から歌えなくなってしまっていた時期も。ボイストレーニングに通ったことで、結果的に歌も復活し、歌うことへの意識も変わった。
外部から求められ始めたプロデュース力
2016年頃になると、SKY-HIのプロデュース力の高さが徐々に世間へ認知され始める。その皮切りとなったのがMAGiC BOYZ、リュウトの「1,2,3」だ。コラボ楽曲ということもあり、フックはSKY-HIが自ら歌った。
その後も、吉田凛音やeillなどのアーティストを担当。なかでも特筆すべきは、さなりのプロデュースだろう。
そもそも、さなりはSKY-HIの「愛ブルーム」との出会いをきっかけに音楽へ足を突っこんでいる。いうならば「悪戯」は、憧れの人とさなりが臨んだ1曲なのだ。
SKY-HIのプロデュース力が世間に認められていることを物語ると同時に、後輩から憧れのアーティストとして名前があがるようになったことを強く示していた。
武者修行のRAGツアー
RAGツアーとして親しまれる「Round A Ground」が始まったのも、2016年のことだった。
死に物狂いの2015年を超えたことにより、メディアの対応もファンの感触も好転していることを感じたSKY-HI。そのまま勢いに乗って、よりキャパシティの大きなライブへ進むこともできたが、彼はそうすることをしなかった。
――調子がよくなってきた今だからこそ、もう一度足場を固めなくては。
メジャーデビューから3周年と聞くと順風満帆に進んできたように思えるが、インディーズ時代から考えると10年かけてようやくたどり着いた結果だ。少しずつ進んできたからこそ、着実に歩まなければ後々足元を掬われる。
――今の自分がすべきなのは、純粋に音楽を、歌を丁寧に届けることだ
そう考えて、DJ Jr.とBFQと旅に出ることにしたのだ。派手な演出もないし、SUPER FLYERSも一緒じゃない。
だけど、日本中にSKY-HIを、音楽を届けに行く。
彼は「SKY-HIが好きだけど、○○は遠くてライブへ行けない」という人を、決して見捨てない。「OK、わかった。じゃあ、ちょっとだけ待っててくれ」。
そういって駆けつけてしまうアーティストこそ、SKY-HIなのだ。
2020年はコロナの影響でツアー自体は延期になってしまったものの、「SKY-HI Round A Ground 2020 -RESTART-」としてオンラインライブを実施。Round 100を目指し、現在(2020年9月時点)でも続いている。
生きることに愛することを見つけた『OLIVE』
前作『カタルシス』が死と向き合うことで生きることを肯定した作品だとするばらば、『OLIVE』は生と向き合うことに誰かへの愛を見出した1枚だ。
2016年の秋ごろから着手し、2017年1月18日にリリース。生きるという意味のLIVEを含み、アナグラムで「I LOVE」 になるということから、タイトルは『OLIVE』に。実はLOVEが潜んでいるといて点でも、今作のイメージと合致した。
『OLIVE』で注目したいのは、大きくわけて2点。
まず1つは、SKY-HIの歌が大きく変わったという点だ。手術を経たことにより、歌いやすくなっただけでなく、歌うことへの心持ちも変化。それまでは、ラッパーとして歌うという意識だったが、本気で歌えるようになったのである。
結果的に、メロディーの良さを活かした鮮やかな作品が一気に増え、喉も整ったことからファルセットも多用するようになった。
2点目は、生きるというテーマに沿ってネオソウルやファンクを下地にしたサウンドを採用し、ライブで映えるバンド感のある曲を中心に構築している点。どの音楽ジャンルにも、伴った歴史は存在している。ソウルミュージックの持つ生命力に溢れた精神性は、再生を強く打ち出し本作のイメージに合致しったのだ。
また、8月に出演した「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2016」で成功を収めたことも大きかった。メジャーデビューの年である2013年に出演した際は、人を集めることができず大苦戦。自ら「敗北した」と語るほど、悔しい思いをしたが、その雪辱を3年ぶりに果たした。
なかでも「Double Down」は、冬フェスで盛り上がる曲を目指し作ったナンバー。SUPER FLYERSの強さが引き立つ、コーラス・ホーン隊ともに魅力的な1曲に仕上がった。
ラップであり、歌であり、バンド感のある作品、『OLIVE』。くだらないジャンル分けへ、一石を投じた作品だといえよう。
通過点としての日本武道館2Days
「えー、2年……だな。2年くれ。2015年にさ、日本武道館でやろうよ。SKY-HIのライブを。」
そう話したのは、2013年2月27日に東京 Zepp Diver Cityで行われた「SKY-HI TOUR 2013 The 1st FLIGHT」のこと。あの日から、日本武道館でのライブは、SKY-HIとFLYERSにとって約束のひとつとなった。
そして、来たる2017年5月2日、3日。約束は果たされることとなる。宣言から2年遅れての実現となった。
正直なところ、2015年にも2016年にも日本武道館でライブをする話はあがっていた。しかし、あえてやらないという選択をしたのである。
――今やっちゃうと、ゴールになる。もっと足場を固めて、ツアーファイナルとして日本武道館ライブをしなければ。
日本武道館というのは難しい場所だ。武道館アーティストという言葉があるくらい、立つのが特別な場所という印象がある。だからこそ、武道館を到達地点にしてしまうと、そこがゴールになりその後の活動がしんどくなってしまう。
約束から伸ばした2年間は、武道館をゴールではなく通過点とできるように自身を整えた期間だったのだ。
しかし、そのまま1日公演では2年間も先延ばしにしたのに味気ないし、いよいよの武道館となれば特別感も増してくる。だったら、10年分の思いをすべてぶつけきるために、いい意味で特別感を生まないために2Daysで公演しようということになった。
結果的に、日本武道館2Daysは次のキャリアに進む自分自身を彼にイメージさせ、新たなスタートとなる1日となったのである。
一連の活動を総括した2018年
10年後のビジョンを描き2013年にメジャーデビューしたSKY-HIにとって、折り返しにあたる2018年。ひとことでいうなら、彼が積み上げてきた5年間を一気に総括したような1年だった。
3月には初のコラボレーションベストアルバム『ベストカタリスト -Collaboration Best Album-』の発売、8月には完全セルフプロデュースのミニアルバム『FREE TOKYO』を無料配信、そして12月には4thアルバム『JAPRISON』をリリース。
コラボレーションでラップの面白さを魅せると共に、トラックメイカーとしての力量も発揮、彼の強みであるコンセプティブな作品を世に放つことで締めくくるというSKY-HIの美味しいところフルコースだ。
化学反応全部詰めの『ベストカタリスト』
「○○と××の科学反応」なんて書くと薄っぺらく聞こえてしまうが、実際にそう感じることばかりの1枚なので許してほしい。
SKY-HIというアーティストは、個人で魅力的なことはもちろん、関わる相手によって違った色を魅せてくれる人だ。後輩の前ではイイ兄貴然した頼もしさを感じさせるし、先輩の前では安心した表情で無邪気な笑顔を覗かせ、友人たちとはバチバチにぶつかっていく。まさしく、コラボレーションする人によって、今まで見たことがなかった化学反応を生み出していく人物なのだ。
コラボレーション総集編ともいえる『ベストカタリスト』が、リリースに至った経緯は2つ。
ひとつは、2017年の客演がメジャーレーベルものだったこと。MIYAVIとの「Gemstone」やCzecho No Republic「タイムトラベリング」などは、前年度にリリースした作品だ。
以前から客演は多く、正規で世に出ているもので50、ブートのような位置づけのものでも100をくだらない。振り返るのなら、話題性のあるコラボレーションが続いたこのタイミングで行くしかないと、思い切って企画物を作りあげた。
もうひとつの理由は、アルバムツアーじゃないツアーをやりたかったからだ。作品に準じた世界観のあるライブが、SKY-HIの強みであることは間違いない。一方でコンセプトを大切にしたライブを行っていると、なかなか演奏しない曲が出てくることも、また事実。
過去の曲たちを救える、自由度の高いライブをしたい。そのために、フルアルバムではない作品を世に出す必要があったのだ。
『FREE TOKYO』が創る、未来の可能性
2018年8月にリリースされた『FREE TOKYO』は、無料配信というフォーマットをとった。インディーズであれば”宣伝のために無料音源”というのも、珍しいことではないだろう。しかし、SKY-HIはメジャーレーベルで活動しているアーティスト。一般論的にいうならば、リリースにはお金が絡んでこないとおかしいのである。
それを、SoundCloudで無料ダウンロードできる形にしてしまうのだから、本人がすごいことはもちろん、許可を出したチームも異例だ。
また、彼が18,9の頃、当たり前にやっていた、ビートを使ってラップして、いろんなクラブやアーティストへ渡すということを、メジャーデビューから5年目のタイミングでやったということも意義深い。
SKY-HIにとってみれば、原点回帰ならびに現在地確認のひとつだったのだろう。フリーで手軽に聴けるので、ラッパー・トラックメイカーとしての評価、すでに応援してくれているファンへのギフトに直接的に繋がりやすい。
さらには、面白いものよりも利益1stなものへ傾いてしまっている、日本の音楽業界への警鐘ともとれる。
US, UK, モノマネなら御免被るわ
世界どこと比べても力の落ちた音楽家
音楽で世界が 変えられるかはわからない
が俺の音楽を求めたやつの手は離さない
上記は『FREE TOKYO』に収録されている「Dystopia」のリリックだ。この作品が、直接的なパワーを持つかはわからない。それでも、バタフライエフェクト的に何年後かの未来が変わっていくかもしれない。
『FREE TOKYO』は、彼自身を確認すると共に未来へ願いを託す作品となった。
愛することに戦うことを見つけた『JAPRISON』
死ぬこと、生きること、愛すること、戦うことを歌のテーマにおいているSKY-HI。死ぬことに生きることを見つけた『カタルシス』、生きることに愛することを見つけた『OLIVE』、そして愛することに戦うことを見つけた『JAPRISON』。彼のなかのテーマが一周し、3部作の結びになった作品こそ『JAPRISON』なのである。
『JAPRISON』の由来は、2つある。ひとつは、日本の息苦しい閉塞感を監獄になぞらえた、JAPAN+PRISONの意味。もうひとつは、日本にもかっこいいラップはあるという思いをこめて、JAPanese Rap IS ONを略してJAPRISONだ。
この作品で語られるべきは、流れを作った「New Verse」だろう。まだ『JAPRISON』の方向性が定まっていない頃に、元・天才(現、たなか)との口喧嘩をきっかけにできた1曲は、SKY-HIを教壇から引きずり下ろした。
『OLIVE』は、先生が生徒に言葉を投げかけているようなところがある。あまりにも正論で、あまりにも論理的。言ってることはわかるが、それが自分の隣にある歌かと言われたら少し遠い。簡単にいえば、綺麗ごとが多い作品だ。
「死にたい」を生きる理由にひっくり返して、苦しいときでも隣の人に愛をもって歩んできたSKY-HIだからこそ、生み出すことができた過去の作品たち。胸に迫る楽曲が多いのは事実だが、一方で彼は”こうあるべき自分”に知らず知らず縛られていったのである。
だからこそ、自分をさらけだし、弱さを認めることができた「New Verse」の存在は大きかった。弱くてもいい、ネガティブでもいい。今まで放置していた自分と向き合い、教壇から降りて生身で地に足をつけたからこそ、『JAPRISON』の曲は強いメッセージ性をもってリスナーへ届いた。
SKY-HIのこぶしは、前時代的な自慢やマッチョイズムではない。弱さも含めての自分自身だ。“人として”ステージに立ち続ける彼は、自分と向き合い自らをさらけ出すことを選んだのである。
また、リリースの翌年に行われた『SKY-HI TOUR 2019 -The JAPRISON-』も、ライブエンターテイメントの新たな可能性を魅せるものとなった。「ツアーのなかでも、断トツでお気に入り」と本人も豪語する今作は、ラップオペラで魅せる前半と「カウントダウンSKY-HI」を用いて音楽性を追求した後半の2部構成。
前半はアルバム収録曲を中心に展開しながらも、関連した過去の曲を混ぜこみ、よりストーリー性を追求した1時間へ昇華した。『JAPRISON』から解き放たれる物語を、ステージ上で鮮やかに描ききったのだ。
後半はBFQ、SUPER FLYERS総出のパーティー状態。いま思えば10曲20分のメドレーをやっていたのは、3部作の総括をしていたのかもしれない。「ナナイロホリデー」や「カミツレベルベット」など、ライブを華やかに彩ってきた曲たちが並んだ。
『JAPRISON』、『SKY-HI TOUR 2019 -The JAPRISON-』がSKY-HI に与えたものは諦念だ。字ずらだけを見ると、燃え尽きてしまったように感じるかもしれないが、全く逆である。
映画でも音楽でも本でも、"怒り"が昇華されたエンターテイメントは元来自分の原点で、JAPRISON〜そのツアーでShowとして完結出来た事は自分にとっては大きかった。
— SKY-HI(AAA日高光啓) (@SkyHidaka) February 3, 2020
おかげで本当にポジティブな意味での"諦念"が自分に今やっと住み着いてくれて、全てに対して前向きな気持ちでいたいと心から思う。
SKY-HI の原点である、怒りが昇華されたエンターテイメントを『JAPRISON』として完結したことにより、彼自身がフラットに整ったのだ。
「縛られたくない」と思っている時点で、すでに縛られている。自由というのは「わかってもらうこと」ではなく、「わかってもらう必要が一生ないと思えること」なのだと気づくきっかけになったのである。
状況に屈しない強さを見せた、オンラインライブ
全世界的にコロナが流行した2020年、多くのライブが中止や延期に追いこまれた。SKY-HI も例外ではなく、3月1日より予定されていた「SKY-HI Round A Ground 2020」は全公演自粛。2020年中にRound 100を達成するという目標も、あえなく絶たれた。
しかし、そこで失意に暮れるSKY-HI ではなかった。パンデミック期間、誰よりも積極的にオンラインライブをしていたのは、彼だったのではないだろうか。
SKY-HIライブ生配信(3月7日)
オンラインライブを封切ったのは、3月7日に開催されたスタジオライブだ。DJ.Hiroronとふたりでアグレッシブにパフォーマンスしていくさまは、昨年の夏にスクワッド体制でラップと向き合ってきた経験が存分に活きている。
不安が充満する世の中に、少しでもエンターテイメントで光を射そうと、いまできることへ彼が前向きに挑んだライブとなった。
SKY-HI自宅ワンマン
5月6日に開催されたSKY-HI自宅ワンマンは、その名の通りSKY-HIの自室から配信されたもの。自宅のスタジオに配信設備を組み、自分でカメラを切り替え、照明をいじり、自分の部屋から最高のライブを届ける。
オンラインライブは、生のライブと同じ感動を生み出すことはできない。だからこそ、今できる最高を作り出そうという思いはリスナーの心にしっかりと響いた。
We Still In The LAB
本来であれば、ベストアルバムの発売と共に観客を迎えてライブする予定だった6月17日。無観客になってしまったものの、8年前と同じ新宿BLAZEに彼は立っていた。
「We Still In The LAB」は、ライブハウスからできるオンラインライブを究極に突き詰めたもの。ステージだけでなくフロアも十分に使い、カメラワークにもこだわり、1本の長回しMVを見るような視聴感を与えた。
SKY-HI Round A Ground 2020 -RESTART-(7月19日)
7月19日に開催された「SKY-HI Round A Ground 2020 -RESTART-」は、初の有料オンラインライブ。
Zepp YOKOHAMAという巨大なステージを贅沢に使い、最新テクノロジーとリアルタイムライブの融合で魅せていく。1秒でもずれたらイメージが崩れかねない芸術作品を、緻密なクリエイティブにより作り上げた。
SKY-HI 実家ワンマン
一段と話題性があったのは、9月26日に行われた「SKY-HI 実家ワンマン」だろう。セットでも作り物でもない、本物の実家から配信されたワンマンライブにはSKY-HIの両親も出演。一緒にコール&レスポンスをしたり踊ったり、楽しそうな空気を増幅させた。
もちろん、カメラワークも手を抜かない。自宅ワンマンのときにはいなかったカメラマンを導入し、固定カメラ、手持ちカメラと様々なアングルからライブの様子を配信した。
また、この日は(株)BMSGの設立ならびにNovel Coreの移籍を発表。実家という彼のルーツになる場所から、新たなスタートを切ったのだった。
『SKY-HI’s THE BEST』のリリース
そして、来たる9月23日。『SKY-HI’s THE BEST』は、リリースされた。ラップ、ポップ、コラボレートの3枚構成になっており、全46曲と盛りだくさんな内容になっている。
この作品が、世に出た理由は2つ。
1つは、昔の楽曲に対して諸々思っていたことを解消するためだ。作詞しかり、作曲しかり、彼自身についても、変わり続けてきたSKY-HI。ストリーミングサービスや音楽の二次利用も当たり前になっている昨今、昔のものを聴いてもらう嬉しさよりも恥ずかしさのほうが勝るようになった。
年月のなかで積み重ねてきた経験は、「今ならこうする」「もっとできる」という手ごたえを彼に与えたのだ。
2つ目は、ポップスとしてのポピュラリティを得るための闘いと自分の本質的な部分を表現することのせめぎあいや調和に対して、ひとつピリオドを打ちたかったからだ。
今までは、対○○のようにいろいろなものと向き合ってきた。どんな現場にいっても違う色眼鏡で見られる存在として、そのカウンターを意識して制作を行ってきた面は少なからずある。
しかし、『カタルシス』『OLIVE』『JAPRISON』という3部作をこえた彼は、「わかってもらう必要が一生ないと思えること」が1番自由なのだと知った。諦念という感覚を受け入れたからこそ、わかってほしいと思っていた自分に決着をつける必要があったのだ。
なお、このアルバムにはコロナ禍で生まれた「#Homesession」も収録。変わってしまった時代に生まれた変わらない彼らの歌は、「SKY-HIとSUPER FLYERSがいるから大丈夫」という強い安心感を与えたことだろう。
SKY-HIのキャリアをいったん総括すると共に、次のフェーズへ橋渡しとなる1枚に仕上がった。
SKY-HI、次なるフェーズへ
そしてSKY-HIは、次なるキャリアへと進むこととなる。
(株)BMSGの代表として、新たな未来を切り開いていくのだ。
社名であるBMSGは、Be My Self Groupの頭文字をとり「アーティストやアイドルが「自分のまま」いれる空間を」という志がこめられている。また、Brave,Massive,Survive,Grooveという意味も併せ持つ。
中学時代から音楽業界へ身を置き、JAY-Zの「I'm not a businessman, I'm a business, man」という言葉に触発され、プロデューサーに憧れた少年は15年の時を経てスタート地点に戻ってきた。
インタビューで「プロデュースしないの?」と訊かれるたび、「今ではない」と話してきた彼にようやくその時がきたのだ。
『ベストカタリスト』の際に行われたインタビューでは、こんなことを語っている。
俺の世代はともかくとしてさらに下の世代の人たちがもっと自分のまんまで音楽とか芸能をやっていける時代になるといいなあと。
<中略>
俺の使命みたいなものがもしひとつあるんだとしたら、それは「逃げないこと」…だとちょっと違うかな、「目を背けない」の方が近いかもしれない。ジャンヌダルクみたいに何かに立ち向かっていくというやり方もあると思うんだけど、俺にとっての戦い続けることっていうのは「優しく寄り添う」とか「嫌なことまで含めて引き受ける」とかそういうことなのかなと。
15年間、誰に対してもどこに対しても、目を背けなかった彼だからできる選択なのだろう。目の前にいた5人を楽しませていたことの延長線で、もっと多くの人を楽しませていくのだ。
すでに彼が仕掛けるボーイズグループ、「BMSG Audition 2021-THE FIRST-」の募集は始まっている。
SKY-HI、日高光啓、そして日高社長が作り上げていく未来が楽しみでならない。
チップ気分で投げ銭いただけると嬉しいです◎ もっと素敵な言葉を届けられるように頑張ります。
