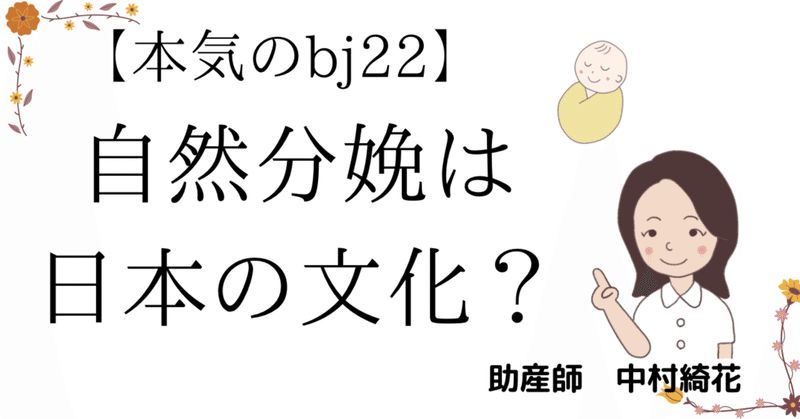
【本気のbj22】自然分娩は日本の文化?
Beauty Japan日本大会に出場している助産師の中村綺花です。
Beauty Japanの7つのコンセプトの中にある
Culture【文化】
このcultureについて助産師として何が伝えられるのか?考えてみました。

日本にいるからこそ気づかないことって沢山ありますよね。だからこそ、幅広い情報を取捨選択することは非常に重要だと思います。
これからお父さん・お母さん・おじいちゃん・おばあちゃんになる方に新たな価値観を知っていただきたく、今日は分娩についてnoteに執筆します。
最近の会話で衝撃な内容がありました
それは
「インドネシアはほとんどが帝王切開だよ。傷も綺麗で目立たないし、富裕層の証みたいな感じもある。なんで日本は下からの分娩が多いの?」と言ったものです。
日本では一般的に、普通分娩=経膣分娩と表現します。
現在は5人に1人が帝王切開ではあるものの、希望して帝王切開することはできず何かの“適応”がついたら帝王切開、といったところです。
産道を通って生まれてくることが神秘的なものとされ
下からの分娩が当たり前だという認知があります。
この時、私は
「なぜ“普通”といった表現をするのだろう?」
「経膣分娩が主流なことや帝王切開が選択制でないことは、ある種日本の文化であるのだな。」と感じました。
そして、経膣分娩においてもアメリカやフランスは多くが無痛分娩です。
(アメリカ7割、フランス8割と多い)
一方で日本は無痛分娩が普及はしてきているもののまだ6.1%です(2016年、日本産婦人科医会)
このように実際に、お産は国や歴史的な経緯によって変わる文化的な営為です。それぞれの国によってお産の方法や価値観は異なります。日本では当たり前とされていることが、他国とは大きく違っていることがあります。
日本の歴史を振り返りながらどうして現状こうなっているのか、日本の文化とともにお伝えできたらと思います。今回は【無痛分娩と自然分娩】を中心に書きます。
GHQによる助産師という仕事の変化
助産師は元々は「産婆」と言われていました。なんとこの産婆。江戸時代からあります。当時、女性が医術に関わるのはタブーだと考えられていたそうです。男尊女卑の考えがありました。しかし、江戸時代後期から女性の商売として認められていたのが産婆。この時代は特に高い身分ではなく、特別な資格がなくても出産経験があればなれたそうです。出産できる体の女性だからこそなれた職業。
面白いエピソードは、そんな身分が高くない産婆でも唯一「大名行列」を横切ることが許されていたとのことです。それほど、この頃から分娩は緊急性を要することが伝わってきます。
そして、戦後のGHQにより大きく助産師教育が変わりました。戦前の日本の産婆は医師なしにお産を担当する自律性の高い職となっており、看護婦とは別の独立した資格でしたが、GHQがアメリカ式に「助産師資格は看護師資格がステップアップしたもの」と変えて、助産師は看護師資格が必要となりハードルが上がりました。
そして助産所勤めの産婆はいなくなり、助産師教育を受けた助産師の多くは病院勤めから始まることとなります。
「自分たちは助産師なのに、医師の言う通りの仕事しかできないのか?」
助産師の自律性を再検討し、母乳育児やラマーズ法などの呼吸法を用いて医療介入のない自然分娩に力を入れるようになりました。
諸外国では無痛分娩を行なっていくわけですが、このとき日本は自然分娩で介助をすることが主流となっていき、無痛は流行りませんでした。
入院20床未満の「産科診療所」は日本特有の文化
まず日本人は病院を選ぶ際のポイントとして、
「産科病棟が入った病院」「産科診療所」「助産院」に大きく分けられます。
(私は前職は総合病院、現在は産科診療所勤務です⭐️)
この入院20床未満の産科診療所はいわゆる産科クリニックと言われるところです。ここでは年間300-500件ほどのお産を行います。
異常を指摘されていない、いわゆるローリスクの産婦さんは産科クリニックで分娩ができ、お食事や個室の環境、付属するサービスを選択して病院選びをされています。
日本では産科診療所などの小規模施設と、周産期母子医療センターや小児科(NICUやGCU)が併設された大規模施設との間で、ローリスク妊婦さんとハイリスク妊婦さんを分担し安全を確保しています。
2017年の「医療施設(静態)調査)厚生労働省」では産科診療所が1242施設、病院が1031施設であり、産科診療所の方が多いです。
実はこの産科診療所。小さいクリニックで出産できるのはアメリカでもヨーロッパでも少ない日本に特徴的な場所なんです。
これは日本の歴史が関与しています。
第二次世界大戦の際に軍医が多数養成されたこと、そして戦後に医師が国内の医療現場に戻っていくわけですが、この時ちょうど「第一次ベビーブーム」が起きました。それに合わせて「産科診療所」を開業したのが始まりだそうです。
それまでの日本の出産は「自宅」での分娩がほとんどでしたが、戦後は焼け野原でお産ができる自宅環境でなくなってしまい、施設での分娩が主流になっていったそうです。
欧米諸国では産科診療所にあたる小規模施設はなく、大規模な施設での分娩で分娩件数も多いため、麻酔専門の麻酔科医が無痛分娩の麻酔を行うことができます。しかし、日本の産科診療所では無痛分娩の麻酔を産婦人科医が行う施設がほとんどです。
麻酔に慣れていない、管理ができない場合には無痛分娩を取り入れることがまだまだ難しい現状があります。さらに日本では産婦人科医や麻酔科医の不足が指摘されています。
ニーズに応じて拡がりつつある無痛分娩
1970年代には日本でも無痛分娩を行う施設も出てきました。しかし「自然分娩」が主流だったので、胎児心拍モニターを取り、無痛分娩の麻酔をし、陣痛を起こす薬を使って・・は普及しませんでした。無痛分娩を希望する人は数少ない施設にいかざるを得ませんでした。2000年ごろまで無痛分娩はマイナーでした。お産をする人の大多数が自然分娩を推進していたからです。
2000年に入って少しずつ、少しずつ無痛分娩が広まりました。しかし、事故の報告が度々ニュースで取り上げられるようになりました。
そこで2017年に厚労省の特別研究班が作られ、無痛分娩の安全性を向上させるための提言をまとめました。この数年前の調査では無痛分娩の実施率はたったの3.5%だったのがここで6.1%に。全体数としては少ないものの一気に増えていることがわかります。そして2018年8月、研究班の提言を元に「無痛分娩関係学会・団体連絡協議会」が立ち上がり、無痛分娩に関する情報提供を行うなどさらに普及していくような環境が整えられつつあります。
現在は10%くらいになっているのではないかと専門家は言います。(北里大学、海野信也教授)
助産師向けの毎月刊行される助産雑誌『ペリネイタルケア』では最近【無痛分娩】を取り扱う記事が多いです。私が助産学生だった8年前は無痛分娩について学ぶことはありませんでした。しかしここ最近になって産科に従事する医療者に対しても習得する必要性のある分野に変化してきています。

日本人特有の価値観
「痛みを乗り越えてこそ母になる」
「一度は自然分娩を経験してみたい」
「親やおばあちゃんが無痛に対してよく思っていない。」
多くの人と会話するとこのような声が聞こえてきます。
実際に助産師の私も、「下からお産してみたい。」「陣痛の痛みはどんなものなのか経験してみたい。」という思いがあるのは事実です。日本人特有の考えなのかもしれません。しかし、最近無痛分娩を多くみていることもあり、「下から産むのなら無痛分娩にしようかな。」と思いが変わりました。もちろん状況によっては自然分娩や帝王切開を選択するでしょう。
ちなみに無痛分娩でも痛みをほとんど感じないケースもありますが、痛みを軽減することができても、多少の痛みや違和感を感じるケースもあります。どんなお産方法でもメリットとデメリットはあります。合う、合わないもあります。
その時のご自分の考え、思いを大切に、状況から判断すればいいのではないかと思います。
助産師としての私の想い
私は助産師として
【江戸時代から続く日本の自然分娩という文化】を大切に受け継ぎ助産をしながらも
新しい文化である【無痛分娩】を必要としている産婦さんにお伝えし
個々の価値観を尊重し、一生に何度もない分娩を支えていけるような人でありたいと思います。
文化だからこそ大切に、
しかし
文化に囚われて固定観念に苦しみを感じる人を少なくしたいです。
そのために必要なことは
【正しい知識の提供】
【言葉選びの選択を誤らないこと】だと思います。
助産師として正しい知識を伝えることが大切ですが、「こうあるべき」が妊産婦さんに伝わってしまうと押し付けになってしまいます。
妊産婦さんの想いを引き出せる、妊産婦さんの横で寄り添い、伴走する人でありたいと思います。
中村綺花
参考資料
・PRESIDENT Online 『無痛分娩という選択肢があるのになぜ日本人女性の9割は自然分娩なのか」https://president.jp/articles/-/47662?page=5
・平成29年(2017)医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況【20P 表21 分娩の取扱の状況】https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/17/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
