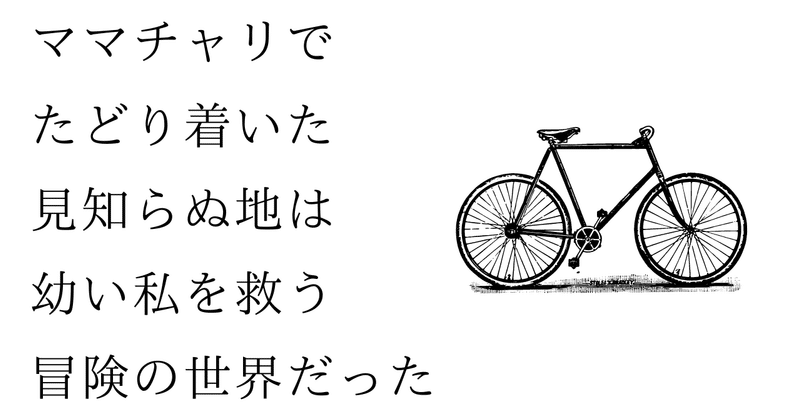
自然と冒険は私の救いだった
不快がべたつく梅雨。
やる気が削がれる灼熱の太陽。
引きこもりたくなる凍てつく吹雪。
自然は恩恵であるが、時期によっては猛威として人間に襲い掛かる。
常に自然に身をさらすことができない弱い私たち人間は、屋根、壁、床・・・自然との隔たりがある家で身を守り、生活を営んでいく。
命の危険に怯えることなく、平穏な日々を送るために。
だが、自分たちを守るその小さな世界にも、脅威が存在するとしたら。
小学校低学年の頃、私は北海道に住んでいた。
団地のように並ぶマンションに住んでおり、広大な敷地には芝生が広がる広場もあった。
道路一本挟んだ隣のマンションの敷地には、小高い丘があって冬にはそり滑りを楽しめる。
学校から帰れば、ランドセルを部屋に置いて外に駆け出し、草原を走り抜け、小高い山を駆け上る。
それが私の日常だった。
夕暮れ時になると、家に帰らなければならない。
沈む太陽が連れてくる闇夜には、美しい星が伴い、それは未来や希望だった。
けれども、夜の私の心は星の光も月の姿も見られないほど、不安に包まれた暗闇そのものだった。
家では、両親が諍いを起こす。
飛び交う怒号、非難、侮蔑。
やめてほしいと訴えても、「うるさい」と一蹴される。
そこに、愛はなかった。
それも私の日常だった。
夏休み。
子どもが家に一日中いる期間。
日中は何をしても自由だ。
厳しい冬のイメージが強い北海道だが、夏もなかなか暑い。
エアコンと扇風機をつけて、ダラダラと室内で過ごしたくなるものである。
けれども、私は外に出たかった。
いや、正確には家にいたくなかったのだ。
どれだけの炎天下であったとしても、関係ない。
外よりも、家にいる方が、命の危機を感じる。
弱い立場の幼子の生存本能が、猛威を振るう自然に私を向かわせた。
百貨店で買ったばかりのママチャリは、小学校低学年の身長に不釣り合いなほど、大きかった。
かといって、他の選択肢は幼稚園児の弟が使う三輪車。
少しでも遠く離れたところに行きたかった私にとって、選ぶものは必然的に前者になる。
敷地を出て、道路を走り、サイクリングロードに向かう。
汗が流れる、息が上がる。
サドルを一番下におろしても、ペダルを踏む足の長さはギリギリだ。
もう引き返そうか、そう思ったときに、目の前にブリッジが見えた。
私にとってその橋は、新しい世界への入り口に見えた。
そこに心惹かれ、希望を抱く。
心と魂が穢れていくこの世界から抜け出すことができる。
当時は言語化することはできなかったが、そんな感覚を抱いていたと今になっては思う。
たった一人、橋を渡る。
渡ったなら、その先も進みたくなる。
どんな世界だろうと、膨れる好奇心がエネルギーとなる。
ペダルはいつの間にか軽くなっていた。
まるで、呪いが解かれたかのように。
橋を越えてもサイクリングロードは続く。
そこは、まるで山道のように生い茂った緑に囲まれた、優しく、静寂な通りだった。
灼熱の太陽は木漏れ日となり、通り抜ける風は体の火照りを鎮める。
「よく来たね。疲れたでしょ」と優しく迎え入れてくれるかのように。
そよぐ風で揺れてこすれ合う葉の音は、脳裏にこびりついた両親のいがみ合いの声を中和してくれるかのように心地よかった。
久しく感じられなかった、母の温もりがそこにあった。
心身が整った私は冒険家に変身し、自転車を止めて小径を探検する。
まるでトトロが出てきそうな小さな森の広場には、不思議なお社がある。
崖を降りた川沿いでは、背が高い草を行く手を阻む。
手になじむ木の棒でかけ分けて道を切り開く。
短パンで晒されている足がチクチクするが、ひるまず進む。
川に反射する日の光は、宝石のようだった。
流れる水は澄んでいて、美しかった。
自宅から数十分の世界は、命にあふれ、胸躍る探検のフィールドだった。小さな世界で傷ついた私を癒し、奮い立たせる世界。
まるでゲームの経験値のように、生きる力を私はそこで獲得していく。
この世界で生きる私は、正真正銘の子どもだった。
こんな時間がいつまでも続けばいいのに。そう願った。
非日常の世界に身を置いていても、時の流れは元の世界と同じだった。
そろそろ帰らなければならない。
また恐ろしい夜がやってくる。
どれだけ楽しく、素晴らしい時間を過ごしても、その一夜は私のすべてを奪い去る。
親というのは、子にとってそれほどまでに絶対的な存在なのだろう。
そして、ある日告げられた東京への引っ越しの話。
見知らぬ土地に行くことはワクワクすることであったが、いざ引っ越してみると、以前のように冒険できる世界がないことに気づいた。
それでも自分なりに探検できるエリアを探したが、高学年になるにつれて、女子から仲間外れにされることの恐ろしさを知り、身を置くのが自然ではなく女子のグループに。
楽しい話題だけではなかった。
誰かを悪口が出てくることも。
家にいるような窮屈さを感じた。
新天地で暮らしが変わっても、喧嘩を超えた憎しみ合いともいえる両親のやりとりは、相変わらずだった。
物心ついたときから家をでる20代まで、私の日常であった。
自室に籠り、耳がおかしくなるほどの音量のヘッドフォンで音楽をかけたこともある。
年を重ねると私自身の暴力性も増し、物に当たってしまったことも。
どこにこの哀しみと、それが変換されてしまった怒りを持っていけばいいのだろうと、何度も悩んだことか。
あの当時も北海道に住んでいて、私の日常に冒険があったなら、私の人生はどうなっていただろう。
今となっては妄想の領域となってしまったが。
文・アイキャッチ:アヤトレイ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
