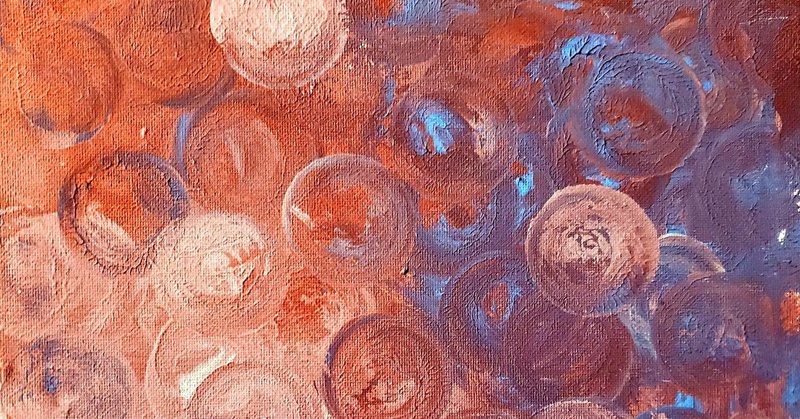
『ペンキ塗りのアイボリー』⑥ 水樹 香恵
〈前回までのあらすじ〉
人口10万を下回る小国クルールランドは、首都ルミエールを中心に放射状に街が発展しており、大きく3つの区域に別れている。その内、"自然と芸術の共存区域"であるシアンタウンにて、今は亡き両親の後を継ぎペンキ塗りとして生きる少女アイボリーは、この小さな世界の中で様々な人と触れ合い、次第に心の変化に気づいていく。幼なじみであるレストランの一人娘・ヴィオレを始め、ほんの少しの交流で成り立っていた彼女の生活は、徐々に彩りを思い出す。
アイボリーの前にいつからか唐突に現れた少年・ルドーは、本名を隠し、いつも偽りの皮を被って己を演じていた。自身に流れる血を恨み、父を恨み、祖父を恨み、この穢れを誰にも見せない様に、必死に抗い、もがいている。身近な人を、傷つけていると気付かぬまま。ただひたすらに拒絶し続けている。
アイボリーの妹・アイリスは、ある悩みと苦しみを抱え生きていた。誰にも打ち明けられない、重大な秘密。然し恋破れた傷心の中で、偶然通りすがった少年・オランジュに悲しみをぶつけて泣き崩れてしまう。騒ぎを聞きつけやってきたオランジュの母スィトリィに連れられ、アイリスは"アブリ"に一時的に保護される事になった。
7、轍に触れるアンデルセン
古く錆び付いた四輪が、ガタガタと上下左右に大きく揺れながら道を行く。
綺麗に整備されたアスファルトの上を走るだけで、どうしてこうも身体が浮くのだろう。下腹部を覆うシートベルトのみでは到底カバーしきれず、冷たい裸の天井に幾度と無く頭をぶつけた。座席のクッションは極限状態まで平らに潰れ、座骨をしきりに叩かれている様である。
普段何気なく繰り返していた公共交通機関の指定席での睡眠移動が仇になったか、アイリスは生まれて初めての乗り物酔いを体験する事になった。
「着きましたよ……あら、大丈夫?」
ガコガコと音を立て停まった車内にガソリンのすえた匂いが充満する。機械に関してさほど詳しい訳では無いが、命の危険を察知してアイリスは急いで車外へ飛び出した。
「慌てなくて良いのよ〜。爆発なんてしないんですから」
ふふふ、と上品そうに笑うスィトリィの表情すら恐ろしく思えて、アイリスは眉間に皺を寄せた。
「バカにされてる……」
ありったけの嫌味を込めてボソッと呟いた声は、どうやら彼女には伝わらなかったようだ。
「ほうら、ここが私達のおうち」そう言って踵を返したスィトリィの向かう先を見やれば、何度も繰り返し改築してきたのだろう、やけに凹凸の目立つ古びた屋敷がでんと構えていた。
「いつの間にか外の人達には"アブリ"なんて呼ばれるようになったけど、実はちゃんとした名前なんて無いんです。昔は土地毎に名前があったけれど、わざわざ自分の家に名前を付ける人なんて、相当なモノ好きしか居ないと思うのよ」
どう?と尋ねられて、アイリスはあからさまに不快な表情を浮かべた。同意を求められても困る。ほんの数分のドライブだったが、車内でも同じように持論と疑問符を交互にぶつけられるばかりで、まともな会話は成立していなかった。
アイリスが泣き止むまで、当たり障りの無い話で場を濁してくれたのならまだ良かっただろう。スィトリィの瞳は獲物を狙う蛇の様に、口元は刃物を携えた殺人鬼の様に、言葉は肌を突き刺す無数の矢の様に思えてならなかった。人の皮を被った獣だと言われた方が幾分か安心出来た程だ。とにかく、瞳の奥にある形容し得ない濁りが畏怖を助長させていた。
そっと背をさすられた時にはあんなにも暖かく安心出来た筈なのに、どうして今は底冷えする様な恐れを感じるのだろう。
アイリスは涙で赤く腫れた下瞼を指の腹で優しく抑えながら、季節外れの寒々とした追い風に背を押され、スィトリィの後を数歩離れて歩き出した。
何年も雨風に晒されてきたのか、所々朽ちてギシギシと音が響く外階段を上り、アプリコットベージュのウッドデッキを進む。向かって左手には窓の無い木製の壁が延々と続いており、右手には青々と茂る広大な芝生の向こうに地平線が覗いている。頭上を覆う分厚いトタン屋根の上には、昼寝中の数匹の猫が落ち葉と共に斑模様を描いていた。
飲食店のテラス席の様に広く開放的な空間には、形や大きさの異なるベンチが点々と置かれ、隅には簡素な喫煙スペースが設けられている。逆さに設置された錆びの目立つドラム缶の上には多種多様な空き缶が並べられており、その全てに零れ落ちる程の大量の吸い殻が詰め込まれていた。
「うぇぇ…………」
普段から苦い煙を侍らせている気難しいマネージャーの顔を連想して、アイリスはまたもや顔を歪ませる。身に纏うもの全てに煙草の匂いが染み付き、ありとあらゆる消臭剤を持ってしても拭えない程のヘビースモーカーだ。
おおよそ人をプロデュースする側の人間とは思えない目つきと態度をぎこちない社交辞令の皮でどうにか包み隠している。ともすれば懐から拳銃でも取り出しかねない装い。初対面の印象は最悪だった。蓋を開けてみれば何て事は無い、単に言動の荒い大人に過ぎないが、当時のアイリスからすれば極悪非道の畜生以外の何者でも無かった。とにかく接客には不向きな性分を持ち合わせた男である。
同じ業界に居て彼の粗暴さを知らぬ者は居ないだろうが、不健康極まりないニコチン中毒を含めこの先改善される余地は無いだろうと匙を投げられていた程だ。
つい先日の定期検診で医師からきつく注意を受けたと零していた。何を当たり前の事を、もっと酷く言ってやれ、と心の中で叫んだのをふと思い出す。
廊下の様に長いウッドデッキの突き当たりを左に曲がれば、道路からは完全に死角となる場所に立派な玄関があった。一般的な住宅のものよりも、ふたまわりは大きな扉である。色とりどりの小さなガラス達が、表面の凹凸を縁取る様にしてはめ込まれている。太陽光が屈折して出来た淡い光の粒が足元を鮮やかに照らしていた。
傷んだ金具を無理矢理こじ開ける様な甲高い音と、木の擦れ合う音が複雑に混ざり合い重たい扉が開かれる。
「ごめんなさいね。お掃除が行き届いていないんです」
貴婦人という言葉が良く似合う。スィトリィの丁寧な所作は先程までの態度とは異なり生まれや育ちの良さが窺えた。口元を右手でおさえながら、心底可笑しいとでも言うかの様に眉を下げて笑っている。
屋敷の中は外見から想像したものよりも遥かに狭く、息が詰まる程あらゆる物で溢れ返っていた。床には書類がぎっしり詰まったダンボールや厚手の毛布が無造作に置かれ、エスニック調のタペストリーやペナント、それにボロボロの衣類が壁一面を覆っている。元は吹き抜けでかなりの開放感があったのだろう。玄関から入ってすぐのホールは、言ってみれば巨大な暖炉の様だった。正に可燃物の肥溜め。築何年かは計り知れないが、よく火災を起こさず保っていられたものだと感心する。
「アブちゃんと二人で暮らし始めた頃は、もっとすっきりしていたけれど……みんな殺風景だの寂しいだの寒々しいだのと口々に在る事無い事言って、各々好きな物を置き始めたら……、いつの間にかこんな風になってしまったの。とってもカオスで愉快な空間でしょう?」
表面上は笑顔で居ながら、瞳は笑っていない。
「……なんか一応統一感は出てるし、カオスとは思わないデスケド」
アイリスは小さく答えながら、あぁ、そうか……とかぶりを振った。
貼り付けた笑顔も、どこかふわふわとして掴みきれない喋り方も、穏やかな声音も、こちらの心情を探る様な視線も全て、似ていた。
今は思い出したくなかった。父親の異なる姉、アイボリーに。
「……ねえ、お姉さんと喧嘩でもしたの?」
談話室に通されて開口一番にそう尋ねられ、アイリスはまた鼻の奥がツンと痛むのを感じた。
「おはなししましょう? 心が落ち着くまで、ずうっとここに居て良いんですから」
スィトリィがふっと目を細めて微笑む。
天井から吊るされた褪せた色のモビールが、彼女の声音に合わせてカタカタと笑い踊った。

――尋問を受ける囚人の様な気分だ。
✻
時を同じくしてアイボリーは、実家の荷物整理を着々と進めていた。
両親が急死したあの日から全てをそのままに放置してきたが、いよいよ決心せねばなるまいと重たい腰を上げたのだ。
父の書庫には数千を越える愛読書がずらりと並び、母の個室には大小様々な人形やアンティーク小物が乱雑に放置されている。
一人で暮らすにはあまりにも広すぎる家の中をぐるぐると歩き回り、アイボリーは長くため息をついた。
正直なところ、引き継いだ仕事が膨大にあり忙しない日々を過ごしていた、と、言い訳をしていたように思う。
助手的立ち位置で簡単な仕事のみを任されてきたアイボリーにとっては、見た事も聞いた事も無い様な複雑な作業ばかり。中途半端な知識で適当に手をつける訳にもいかず、かといって投げやりなままで終わらせる訳にもいかない。父の仕事仲間数人に大まかな技術は習ったが、独立して全てをやり遂げられるのかと尋ねられれば答えはノーだ。大きく複雑な案件は外部に引き継いでもらい、手元に残った小さな仕事だけを地道に、丁寧にこなし生きていこうと決めた。
それがペンキ塗りだった。
日毎違う場所へ行き、異なる物に触れ、無心で上塗りをする。
穢らわしい心を祓う様に。
痛々しい傷を包む様に。
哀しい記憶を閉じ込める様に。
他人との接触が殆ど無く、さほど重労働という程でも無く、生きていけるだけの最低賃金は保証されている。家と日替わりの職場を往復する日々。
アイボリーにとって、これ程天職な仕事は無いだろうと思っていた。何も望まぬ質素な生活。それだけで十分なのだと、本当に思っていた。
「思ってたのにな……」
ペンキ塗りの仕事を始めてから、アイボリーは物と触れ合う事が極端に増えた。物を物として扱うのでは無い。
ひとつの命として接すること。
触れて、愛で、声を掛け、時たまには歌を聞かせ、機嫌を伺いながら化粧をする様にローラーを転がせる。
物語の主人公を演じるように、大胆に大袈裟に振る舞った。それが楽しいと信じていたかった。
ーーいつからだろう。無機質と語らう事が、こんなにも苦しいと感じ始めたのは。
「……ルドーに出会ってからだ。……ぜんぶ」
少年が声を掛けてきた、冬のあの日から。
少し疎遠になっていた幼なじみともよく会話するようになった。新しい友人も出来た。険悪な空気を感じながらも自分から妹に話しかけた。大勢の人が集まる祭りに参加した。ほんの少しだけ身に纏う衣服に気を使った。
自分でも可笑しくて笑いが零れそうな程、"ちゃんと人間の生活が出来ていた"。
味気ない日々を変えるきっかけをくれたのは、他の誰でも無い、ルドーだ。
「……………………」
キニゴスパークでのやり取りを、ほんの少しだけ後悔している。
傷付けてはいないだろうか。
苦しませてはいないだろうか。
追い詰めさせてはいないだろうか。
「ずるいひと」アイボリーがそう告げた時のルドーの顔は、酷くくしゃくしゃに歪んでいた。一見すればイタズラを注意された幼子の様にも思えたが、その奥深くに、触れてはいけない壁の様な何かがあった気がしてならない。いつも涼やかに、飄々と振る舞う彼があれ程狼狽えるのだから、余程深い傷に触れたのだろう。
レストランアデッサでオランジュの涙を目の当たりにしてから、アイボリーはずっと気味の悪い胸騒ぎに駆られていた。真意が読めなくとも、常に優しく気遣える、そういった振る舞いを欠かさないルドーなら、誰が相手だろうと公平に触れ合えるのだろうと、身勝手な思い込みで知らずのうちに彼をラベリングしていたのかもしれない。
ルドーだって、ひとりの人間だ。
アイボリーは自室へと戻ると、安価で手に入れた硬いマットレスに腰掛けた。両腕いっぱいに抱えているのは、父の書庫にある鍵付き棚から拝借した古い児童書。
『クレール国物語 全集』。
繊細で色鮮やかな模様が描かれた豪華な外装箱に保管されている、全12巻、上下24冊から成る作品群である。1巻毎に主人公は異なり、画風や文体も多岐に渡る。父方の曽祖父が趣味仲間を集めて合作したものだと幼少期に教えられた。
当時はまだクルールランドが建国して間もなく、各土地の名すら与えられていない頃。これから先どのように発展してゆくのか、未来を想像し描き出した物語。皆の夢を織り交ぜて詰め込んだ宝物と言えるだろう。
『クレール国物語 全集』は自費出版で発行しており、制作陣に一人1セットずつ、一般向けに10セット販売していた。かなり希少な代物だが、この内の第12巻『オーロラ姫の冒険』だけは、莫大なアネクドートを抱え世に広まっている。
「この本に描かれた内容と酷似した事柄が、次々に生じている。預言の書では無いか?」とあらゆる専門家が口を揃えて語るのだ。事実、上巻で発生した自然災害が2度、下巻で発覚した事件が3度、現実に起きている。事件に関しては犯人の供述も曖昧な為、模倣犯では無いかという専らの噂もあるが、アイボリーとしてはこれを他人事とは思えなかった。第一、主人公の名前が祖母と一致している。挿絵にある少女の姿も、いつだか写真で見た幼い祖母と瓜二つなのだ。瞳の色、髪型、身に付ける服飾品から下瞼を引き締める特徴ある笑顔まで寸分の狂い無く。モデルだったのではないかと疑う程だ。然し、オーロラは母方の祖母であり、この児童書が描かれたであろう時代にはまだ産まれてもいない。
これを興味が無いと言えば嘘になる。
ただ、これ迄触れずにいた。
父と2人で過ごす事が多かった幼少期によく書庫に篭もり数多の本を読み耽ったが、この『クレール国物語 全集』だけは何故だか読む気にはなれなかったのだ。作風がバラバラで意識がまとまらない、というのもあるだろうが、何か、何かしら、触れてはいけないものがあるように感じたのだ。子どもがお化けを畏れるのと同様に、ただ意味の分からない悪寒に首を絞められていた。
今は、どうだろう。
もしこの本が真に預言の書ならば、現状を取り巻く整理のつかない感情たちの処理方法が分かるかもしれない。将又、その逆も然り。
「……」
薄手の毛布を手繰り寄せて、深呼吸をする。
救われたいのでは無い。
ただ何かに縋っていたいだけだ。
それだけの事だ。
分厚い表紙をめくり、茶に褪せた物語に目を通していく。
少女の誕生から始まるストーリーは至ってシンプルで、言ってしまえば在り来りな冒険譚だ。
齢10に満たない子どもをターゲットにしているのだろう。柔らかく溶け出す様な言葉遊びが随所に散りばめられ、独特のリズムが没入感を高めている。
淡い水彩で描かれた挿絵は極端に線数が少なく、必要最低限のものだけを映し、細かな部分は読み手に想像する余地を与えているように思う。
物語も中盤に入ると、舞台は少女の産まれた国へと戻り、小難しい大人達の会話が続く。この国が未来永劫栄えて行く為に。国民の生活を第一に考え。王配殿下に相応しい人材とは。唐突に始まる堅苦しい会話劇はおよそ子ども向けとは思えないが、見開きの全面を飾る華やかな装飾や細かな隠し絵が目を引く。おそらく、読む世代によって伝えたいメッセージ性が異なるのだろう。
「あ、ステンドグラスに猫の顔」
確かに、よく出来た仕組みだと思う。
読解能力のある大人はまとめられた文章をつらつらと追いかけ、未だ発達段階にある子どもは際限の提示が無い宝探しに興じる。正に物語の中の人物達と瓜二つな状況が出来上がっているのだ。
同じものを見ている様でいて、実際は別の場所を向いているーーこのところ幾度か体験した痛みによく似ていた。
「ふふ、」
アイボリーは事の可笑しさに吐息を零したが、次の場面展開でふと、ページを繰る手を止める。
夏の日差しが照り付ける浜辺で、麦わら帽子を被った少女がこちらを見て微笑んでいる。

周囲の物音が掻き消される程強く、耳鳴りがする。
ジワジワ、時たまに、キーンと。
意識すればジュッと何かが焼ける様な不快な音。
何故だろうか。
笑っているはずの少女の頬を伝う涙が見える気がした。
涙など、描かれてはいないはずなのに。
コッコッ。
1人だけの静かな家の中に、無遠慮なノックの音が響いた。
✻
「ありがとうございました〜。お気をつけて〜」
形だけの礼儀を投げかけて、ヴィオレは会計トレイとレジを整理する。
「いやー、ただいま、ただいま。今帰ったよ〜」
店内に残る最後の客を見送ると、ちょうど良いタイミングで父・セレガノが昼休憩から戻ってきた。
「おかえり。早かったじゃん」
小銭の擦れるキンと高い音を耳裏で感じ取りながら微笑めば、調理服の袖に腕を通しながらセレガノは大きく豪快に笑い返した。
「そうでも無いよ。ヴィオレちゃんの休憩が遅くなったら悪いじゃないか」「はいはい。そういう事にしときましょうね〜」
鼻歌でも歌うかのようにサラリと受け流して、ヴィオレはレジスターのドロアを閉じる。
「じゃ、アタシ休憩入るから」
「うんうん。ごゆっくりね〜」
厨房の脇を抜けて裏口の取っ手に触れたあたりで、「あ、そういえば」とセレガノが呟いた。
「あ〜……、名前をなんて言ったかな。ほら! あの〜、えぇっとなぁ……」
顎先に手を当てて、うんうんと考え込む仕草をする。
「何? 要件だけ先に話してよ」
「そう! ついさっき電話が来てたんだよ〜、ヴィオレちゃん宛にね。昔はうちにもよく遊びに来てただろう? ほーら! あの〜……」
「アイボリーでしょ。アタシ宛に電話なんてあの子くらいしか思いつかないわよ。ボケ始めてんじゃないの? しっかりしてよね」
「あ〜! そうだったそうだった。アイボリーちゃんね、うん。いや〜、こないだのコンサートは大盛況だったらしいねぇ!」
「…………それは妹サマだっつの」
「ん? どうかしたかな」
「いーや、ありがとね。掛け直してみる」
「うん、宜しく伝えといて〜」
「はいはーい」
「……はぁ」と大袈裟に息を吐き出して、ヴィオレはわざとらしく足音を立てながら2階の自宅へと向かった。
父・セレガノは確かに人は良いが、料理以外の事柄に関しての記憶力が非常に乏しいという難点があった。母との結婚記念日を忘れ品評会に出掛けた時などは、懐の広い母でさえ怒鳴り散らす程だった。"鬼の形相"という言葉がよく似合う。あれ程までに憤慨した母を見たのは後にも先にもこれだけだ。ワインの試飲で顔を真っ赤に染めて帰宅した父の胸ぐらを掴む母の姿は、恐らく今後一生忘れることは無いだろう。
「何度も世話んなってンのにその娘を忘れるたァね。仮にもあちらさんはアンタの娘の親友だぜ? ふざけんな……」
キュッとすぼませた口からブツブツと嫌味が零れ出す。
誰も居ないリビングのリクライニングソファに腰掛け、豪快に足を組み、スマートフォンのアドレス帳を開く。
ヴィオレの数少ない知り合いの中で、初めに表示されるのはいつもアイボリーの名だ。少女はその優しい性格に反しかなりの頑固者で、柔和な態度を取りつつもあまり自分の意見を曲げないタフな心を持っている。然しその執念強さにこれまでの貧乏生活が悪影響を及ぼしたのか、自分の身の回りのものに関してはどこかケチだ。ヴィオレが携帯電話を持てと何度説得しても聞く耳を持とうとしない。結果、アイボリーは未だに自宅固定の黒電話を愛用している。過剰で不確かな情報の波に純粋な心を浸すのはやや心苦しいが、だからと言って齢20に満たない少女を社会から断絶させて狭い世界に閉じ込めておくのは殊更に気が引けた。
「もしもし? アタシだけど」
「ヴィオレ! ふふ、あのね……」
受話器を両手で包み込む様に握る姿が容易に想像出来る。子どもらしくはしゃぐ声音に力が抜けて、ヴィオレは思わず笑みを浮かべた。
「で? 要件は何? アタシ今休憩中だから、とりあえずは手短にお願い」
「あ、うん、お疲れ様。えっと、アイリスがどこにいるか、知らないかなぁ、なんて、思って」
「はぁ?」ヴィオレは唐突に湧き上がる怒りのまま勢い良く立ち上がった。「なんでアタシがアンタの妹サマの居場所知ってなきゃいけないのよ。知らないわそんなの」
「そうだよね……あはは、ごめんね」
「何? ちょっと待って、今アタシはもの凄く冷静さを欠いてる。キレそう。アンタの妹サマが? 何。頼むから簡潔に終わらせて。スパッと潔く。何なら今!ココで! 殺して!!」
「えぇ……。落ち着いてヴィオレ、」
「落ち着いてる。嗚呼落ち着いてますとも、えぇ」
急激に血圧が高まっていくのが分かる。目を閉じて深呼吸をしながら、ヴィオレはゆっくりと腰を下ろした。
「えぇっと……ついさっき男の人がうちへ来てね」
「不審者が来たってワケ?! なんでその場でケーサツ呼ばないのよ! アンタって子は……!! ホントに……! ホントに……!!」
ダン!! と強く床を踏み鳴らす。また勢いで立ち上がってしまった。階下から薄らと父の窘める声が聞こえる。
「違うよ〜……、全然違うの。その人、エドニールさんって言ってね、アイリスのマネージャーさんらしいの。それでね、アイリスがコンサートの日から戻って来てないって言うから……居場所を知らないかって……」
「詐欺かなんかじゃないの? それか異常なファンとか。とにかく口じゃなんでも言えるんだから、信用ならないわ。フルネームは?」
「あ、名刺を貰ったの。えっとね、"エドニール・トウー・アスタ=ライ"さん。芸能事務所"アスタレイ"の代表取締役……あ、偉い人なんだね」

芸能事務所"アスタレイ"。通話をスピーカーモードにして検索すると、想像に反し丁寧に作られているスタイリッシュですっきりとしたホームページがヒットした。
事務所理念、代表の経歴・挨拶、所属タレント一覧、関連施設の住所・電話番号等……特に怪しい点は見当たらない。アイリスの名前と顔写真も載っている。苗字・年齢を始めとしたプライバシーに触れる部分は徹底して伏せられている。特集記事や添付写真、経歴の多さ、紹介ページのデザインの凝り具合を見るに、随分と優遇されているのだろうと推測出来る。
「……ふーん、偽名じゃなさそうね、どんな見た目してた?」
「えっ、凄い……もしかして調べてるの?」
「早く」
「あっ、うん。えーと、仕事で来てる訳じゃなさそうだったからあんまり参考にならないかもだけど、シャツは着崩してて、綺麗な黒髪で、目尻がキュッと上を向いてて……多分視力が悪い人なんだと思う。私を見る時にちょっと遠くを見る様な感じで、眉間にシワが寄ってたから」
「紹介画像がちゃんと外向きの顔してるから信憑性に欠けるけど、まぁ概ね本人と見て良さそうね。眼鏡はしてなかったわけ?」
「え? うん、外が暑かったから外したんじゃないかな。スーツの上着も手に持ってたし」
「そ、ならまぁそれで良いわ。で? 何よ。アンタの妹サマはまぁた家出して人様に迷惑かけてんのね」
「うーん、家出って言うのか……ちょっと分からないけど……」
「家出でしょ誰がどう見ても。甘やかしすぎよ。保護対象年齢じゃないの?」
「そんな、アイリスだってもう自分で決めて生きていけるよ」
「…………?」チクリ、と。頭の後ろから細い針で突かれた様な痛みを感じた。患部から血が溢れ出す様に全身から急激に血の気が引いて、ヴィオレは思わず身震いする。
「……いや、ちょっと待って。タイム。ごめん、一度よ〜く整理させて。……アンタの妹サマって、今、歳いくつよ?」
「え……? 5月が誕生日だったから、17歳……だと、思うけど……」
「だと思うって、適当ね。いやそうじゃなくて……!! 17歳? ソレ、本気で言ってるの?」
「えっ、うん。私の2つ下だから、間違いないはずだけど……」
"2つ下"。その言葉だけで、ヴィオレは酷く嘔気を催した。
「……嘘でしょ……、あぁ、嘘だと言って!! こんなこと……!!」
「ヴィオレ? ……どうかしたの? ヴィオレ……?」
食道を駆け上がる胃酸に耐え兼ねて、口元を強く抑えながら立ち上がる。電源の点いて居ない壁掛けテレビの画面に映る自分と目が合った。想像と現実の乖離で脳の内から溶けて混ざる様な、心地だ。
「……良い? アイボリー。良く聞いて。アタシ達が初めて会ったのは12年くらい前の、……春頃の事よ。アタシが9つで、アンタは7つだった。そうでしょ?」
「うん。うん、覚えてるよ」
「あの頃のアンタは、非の打ち所がないくらいの穢れの無い、綺麗な。……それこそ、絵に描いた様なお嬢さんだったわ」
「ふふ、そうかな」
「そーよ。毎度めかしこんでうちへ来てた。アンタの両親がうちの内装やら何やらやってくれてる合間に、アタシはアンタのお守り役だった。……あぁ、いや、待って、勘違いしないで。嬉しかったのよ。同世代の同棲の知り合いなんてそうそう居ないからね」
「うん、……うん。私も嬉しかった」
電話越しでも、声が微かに震えているのが分かる。これからヴィオレが言わんとしている事を、アイボリーは薄々勘付いているのだろう。
「……でも、それから半年と経たずにその生活はガラリと一変したわ。ある日唐突に、アンタは着飾るのを辞めて、仕事に合う様な機能性重視の服ばかり着るようになって、それと同時に、アンタの母親はめっきりうちへ顔を出さなくなった。何かあったんだろうとは思ったわ。子どもながらに。でもあくまでも他人の家庭だもの。干渉しないでおこうと思った。多分うちの両親も同じくね。いつの時期だったか明確には覚えてはいないけれど、そんな生活にも慣れてきた頃、アンタの母親は……ブランシュは、なんの前触れも無くうちへやって来た。大きな腹を抱えて。……ねぇ、なんて言ったと思う?」

「"もうじき2人目の娘が産まれるんです"……って」
幸せそうに微笑みながら。
(『ペンキ塗りのアイボリー』⑦に続く。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
