
78rpmはともだち #1 ~78rpmの歴史~
第1回のテキストで、私がYouTubeアカウントで【ターンテブル動画】を上げていることに、ちらっと触れた。
最初はバッハのレコード・オンリーだったが、10月以降は他の作曲家のレコードの動画も上げ始めた。
ご覧いただければすぐに分かっていただけると思うが、割合的にLPレコードでよりも、圧倒的にSPが多い。
「アナログレコード再ブーム」と言われている昨今、レコードプレーヤーが売れたり、「重量盤復刻LP」が発売されたり、中古レコード屋さんが盛況だったりと、アナログレコードに光があてられてはいるが、それはLPやシングル盤(ドーナツ盤)のお話であって、SPのことではない。
これからしばらく、SP=78rpmのことを徒然なるままに記していこうと思う。
そもそもSPって何?
LPは「LONG PLAY」の略。
1948年6月21日にコロムビア社から発売されたのが史上初のLP。
ポリ塩化ビニールを原料にした直径12インチの円盤に音溝を刻み、片面30分を収録できる。30分も収録できるから「LONG PLAY」。
では「その前の音楽記録媒体は何だったか?」「何に対して"LONG"なのか?」と言えば、それがSPだ。
しかし、SPは「SHORT PLAY」の略ではない。
それはそうだろう。LPが発明されるまでSP盤が片面5分程度しか収録できないからと言って、それを「短い」とは誰も思っていなかったのだから・・・。
SPは「STANDARD PLAY」の略だ。
「標準的な演奏」。
しかしこれも後付けで、LPが登場してからそう呼ばれるようになったに過ぎない。
「78rpmm」もしくは「シェラック」
世界的にはSPは「78rpm」とか「シェラック(Shellac)」と呼ばれている。
「78rpm」は「78 rounds per minute」の略、つまり1分間に78回転する、ということ。
LPが33と1/3rpm、シングルが45rpmだから、いかにに高回転であることか、お分かりいただけるであろう。
円盤直径はLPと同じ12インチ(LPのように国際規格が定まっていたわけではないので、メーカーによって多少の差異はある)だが、約5分で回り切ってしまう。LPよりも音溝(グルーヴ)の幅が広いので、LPの2倍強の回転数であっても15分はもたなく、5分で終わる。
左がSP(78rpm)、右がLP
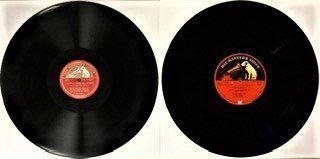
「シェラック」とは、カイガラムシの分泌する虫体被覆物を精製して得られる樹脂状の物質で、SPの主原料はカーボンや酸化アルミニウム、硫酸バリウムなどの粉末をこのシェラックで固めたもの。
これはLPの主原料、ポリ塩化ビニールと較べて、柔軟性に乏しく、もろくて割れやすい。ちょっとした衝撃で簡単に割れたり、ひびが入ったりする。
私も丁寧に扱っているつもりだが、これまで2枚を割っている。
SPの重さはLPが150g前後なのと較べて、280g(LPもSPも作られた時代やメーカーによって重さに差異はあるが)と倍近い。
130年以上の円盤形
歴史上、音を記録する物体を発明したのは、かのトーマス・エジソン。
それは 1877年12月6日の出来事で、この日は「音の記念日」にもなっている。
しかしそれは、円盤形のものではなく、真鍮の円筒に針で音溝を記録する、というスタイルだった。
その後、「水平に回転する円盤形」となったのは、 1887年、エミール・ベルリナーが「グラモフォン」を発明してからだ。「ターンテーブル」という概念=「蓄音機」が誕生したわけだ。
CD、DVD時代の現代まで130年以上受け継がれてきた「録音メディア、音楽鑑賞ソフトとしての円盤形」。
他の分野でメディアがどんどんと姿を変えていく中で、これはとても稀有のこと、不思議なことのようにも思う。
そして、私はそのクルクルと回る姿に愛着を感じ、【ターンテーブル動画】をシコシコと作っている。
本日はここまで。
78rpm(これからはこの単語で統一する)の簡単な歴史、素材について、でした。
おまけに今回も【ターンテーブル動画】をひとつ。
クラシック音楽に詳しくない方でも、一度は耳にしたことのあるはずのバッハの『G線上のアリア』(ヴァイオリンの4本の弦のうち、一番太いG線のみで弾けるようにアレンジされているから、こう呼ばれている)。
演奏は20世紀中頃に大活躍した天才(妖才?)ブロニスラフ・フーベルマンの78rpmで。
次回は「何故、私が78rpmに魅せられるのか?」「78rpmを聴くお作法」といったあたりを徒然なるままに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
