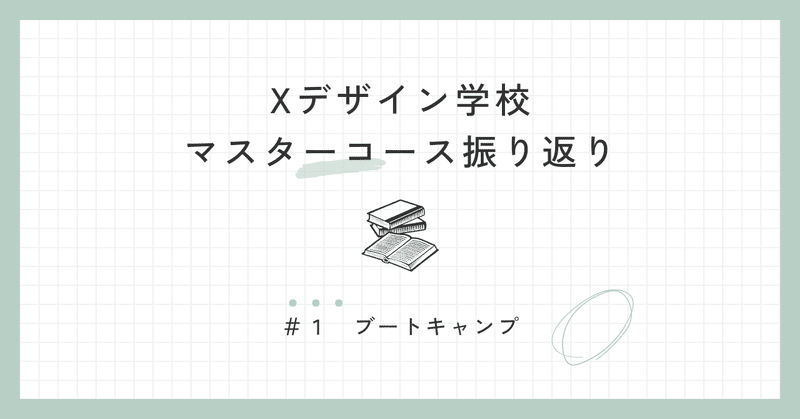
【Xデザイン学校マスターコース リフレクション】第1回ブートキャンプ
2022年度、ユーザーエクスペリエンス(UX)の知見を得ようと受講した「Xデザイン学校 ベーシックコース」。浅野先生の厳しくも学びの多い1年間を過ごすことができました。
本業「地方公務員」の自分にとって、縁が遠かったUX。学べば学ぶほど、行政の現場でも必要な知見であると感じています。
ベーシックの受講ですら「おっかなびっくり」でしたが、受講後も「学びつづけること」を実践しようと思案し、無謀にもマスターコースを受講することにしました。
講師は山崎先生で、トライアンギュレーション的に、UXの違った側面の学びを得られそうです。特に、山崎先生は和歌山県すさみ町をフィールドに、武蔵美生と地域の活性化に取り組み、地域課題にも目を向けておられ、行政職員としては一層期待が高まっています。
さて、その今年度第1回目が5月13日(土)にあったので、その振り返りを残したいと思います。
1.三方よしのビジネスデザイン
これから先、企業はユーザーだけではなく、ステークホルダー全体の便益を考えて活動をしていかなければならないし、ビジネスも社会視点を考慮しなければならないとのこと。
持続可能性が問われる中、企業のビジョンやパーパスは、ユーザーをはじめ社会や地域からも共感される=社会善であることが求められるということであろう、と理解しました。
さて、ビジョンやパーパスは一人称か三人称かの差はあるものの、創業者の熱い思いが言語化されたものです。BIOTOPE代表の佐宗邦威氏は一人の「妄想」からビジョンを構想する方法を「ビジョン思考」と著書で説かれています。(ご本人にサインを頂いた本が手元にあり、以前読んだのですが、再読しないと…)
個人の妄想が、社会全体の共感を得るほどに昇華されるまでには、紆余曲折がありそうです。
今回の課題企業、パナソニックのスローガンは「幸せの、チカラに」。
大企業ゆえにやむを得ないのかもしれないのですが、非常に抽象度が高く、いまいちピンときません。創業者・幸之助氏はどのように説いていたのか、そこから現在に至るまでどのような変遷をしてきているのか。
これからのグループワークで触れざるを得ない部分のようにも感じています。次回のインタビューの視点にもなろうかと思っています。
2.ユーザーを設定する際の基準
対象とするユーザーを考える際、2つの視点として「ボリューム」と「影響度」があるとおっしゃられていました。
どちらを優先するかは会社のやりたいこととの親和性とおっしゃられていたように思います。規模によらず影響度の大きなユーザー層に向けた戦略も採りうること。マスに向けた戦略を講じることが必ずしも正解ではない時もあること、興味深く感じたところです。
3.立ち戻って問い直すこと
デザイン思考の手法「ダブルダイヤモンド」における1つ目の拡散と収束は、正しい問いを見出すことが目的である。だからこそ、収束により見出した問いを再考し、「問い直す」ことが大切という点、大変興味深く感じました。
事例として取り上げられた、味の素社の冷凍餃子にまつわるエピソードは時宜を得ており、納得させられるものでした。
ただ、多くの場合「問い直し」は出来ていないとのことでした。確かに、収束により乱された「問い」の良し悪しは判断が難しそうです。どこまで問い直せば、納得感が高まるのか。根気も必要そうです。
4.エフェクチュエーション
「エフェクチュエーション」。経営学者のサラス・サラスバシー教授による理論で、成功している起業家の思考における共通項を説いたものとのことです。
いくつかある原則の中で特に記憶に残ったのは「バードインハンド」。自分が今持っているものを捉え直すということだそうです。
必要なもの全てを集めてからではなく、自分や自社のリソースを見定め、今あるもので始めること。
何かが無いからできない、と言い訳するなと言われているようで、ドキッとする言葉でした。
また、プロセスの一つ「レモネード」。成否は運に影響されざるを得ないので、常にポジティブシンキングということなのですが、根も葉もないように思えて、大事なことなのかもしれません。
5.プラットフォーム構想の初めの一歩
プラットフォームを構築する最初の一歩は特定のユーザーを想定することから。見落としがちなことですが、強烈にあるサービスを欲するユーザがいなければ、サービスは成り立たないわけであり、大切な視点だと感じました。
6.激レアさんのススメ
1〜5までは山崎先生の講義からの特に興味深かった点を列記しましたが、冒頭のチューター日野さん(ZHD)のお話も刺さるものがありました。
地方公務員の行政職(事務職)は概ね3年周期で異動を繰り返し、特定分野の専門性というものが身につきにくい職種だと感じています。(自分のキャリアも、土木→福祉→財政→ふるさと納税→観光(恐竜)と多岐に渡ります)
外部の専門性のある職種の方と接し、経験に裏打ちされた各分野の知見に触れるたび、3年ごとに更新される薄っぺらな知識で対応しないといけない立場におかれ、劣等感を感じることも多くあります。
一方、スキルの掛け合わせの発想で考えれば、独自性のある専門性を磨くことも可能であろう点をお示し頂いたようにも感じ、勇気づけられました。(行政×UXは、デジ庁や東京都で動きがありそうですが、地方ではまだ少なそうです)
就職して15年経ちますが、今一度、自分と向き合う時間も持ちつつ、今後についても考えていきたいと思いました。
7.最後に
マスターコースの受講はチャレンジの気持ちでいます。いよいよスタートを切ったので、1年走り切りたいと思います。
