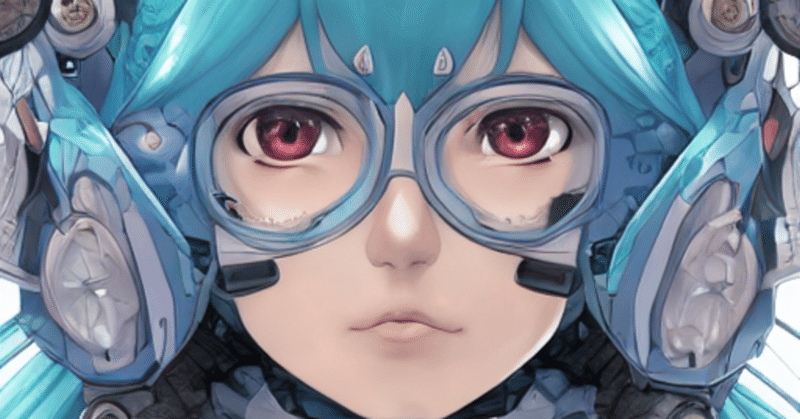
生物学を斬る#8 【階層性】
生物学には精密でミクロな階層から複雑でマクロな階層まで様々な階層が内在しており、大きな視点はより小さなモジュールへと分解することができる。
そして、それぞれの段階が詳しく研究されるとともに、その段階間のつながりも研究されている。
大まかに生物をミクロな系からマクロな系へと見ていくと、
(ミクロ)分子→生体高分子→細胞内小器官→細胞→器官→個体→集団→生態系(マクロ)
と階層化することが可能である。
それぞれの階層はその階層特有の役割を担っており、他の階層と区別することでその機能が分かりやすくなる。
例えば、一分子モーターのキネシンは細胞小器官の輸送などを行い、細胞小器官のミトコンドリアはエネルギーの産生を担っており、器官の肺は呼吸による酸素の取り込みに特化することで酸化的リン酸化によるエネルギー産生を可能にしている。
遺伝子とその働き、生命現象と物質、生物の体内環境と維持、生態系と環境など、生物学も階層ごとに区別して教えられることが多く、勉強する際は今どの階層について学んでいるのかを意識すると、混乱せずに内容が定着しやすいのではないだろうか。
また、下の階層のパーツが組み合わされより上の階層に行くにつれ、下の階層にはなかった性質が現れるという、創発特性と呼ばれる特徴も存在する。
大腸菌の構成分子をどんなに寄せ集めても細胞のように自律的に外界とやり取りを行って代謝経路を確立し、自己複製を行うような構造体は生まれない。
だからこそ本当の意味で生物を人工的に合成することが未だにできておらず、また無細胞タンパク質合成系であるPURE (Protein synthesis Using Recombinant Elements) systemが広く注目を集めた。
様々なアプローチから生物を合成しようと試みる合成生物学もこれからますます流行していく分野であろう。
生物学は、様々な階層が内在しており、大きな視点はより小さなモジュールへと分解できる。生物をミクロな系からマクロな系へと見ていくと、階層特有の役割を担う。他の階層と区別することで、その機能が分かりやすくなる。
サムネイル画像はとりんさまAI(@trinsama)により生成
