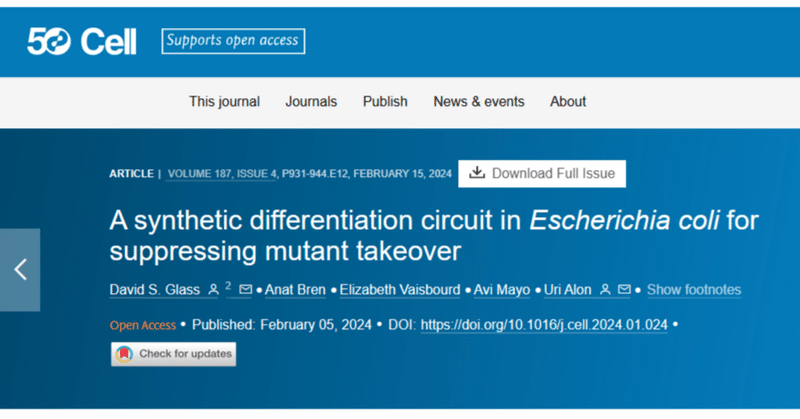
合成遺伝子回路による細胞分化の頑健性獲得
私たちは多数の細胞から構成される多細胞生物である。単細胞生物は一つの細胞で生命の維持に必要なすべての機能を実装する必要があるのに対し、多細胞生物では、全身に酸素を供給する赤血球、細菌やウイルスと戦うB細胞、脳内で情報処理を行う神経細胞など特定の機能に特化するよう細胞が分化することで、生命としてより複雑で高次の機能を実現することが可能となっている。
一方で、分化しないような突然変異を起こす細胞が生じると、そのような細胞は未分化のまま増殖し続けるため、細胞の分化は脆弱性を内在している。これは、突然変異により癌化した細胞が増殖し続けて正常な細胞を駆逐し、時に個体までもを死に至らしめることを考えると分かりやすい。
では、このような変異体の出現に打ち勝って分化細胞を維持する制御機構とは何なのであろうか?今回紹介する論文では、合成生物学的手法とシステム生物学的解析を組み合わせてこの問に答えている。
Glass, David S., et al. "A synthetic differentiation circuit in Escherichia coli for suppressing mutant takeover." Cell (2024).
A synthetic differentiation circuit in Escherichia coli for suppressing mutant takeover: Cell

Methods
図1では、二相性の適応度によって正の分化率を可能にする大腸菌の合成分化回路の実装が示されている。幹細胞(S)は分化率αで分化細胞(D)になり、1-αの確率で自己増殖する。分化細胞は死亡率βで減少するのに対し、幹細胞は減少しないので、分化率αを横軸に、幹細胞の適応度を縦軸にプロットすると、一相性の場合には分化率0が最適である(図1A)。一方で、分化によって利益が得られる場合は二相性となり、α>0で最適な適応度が達成される。

二相性の分化の達成のために、合成遺伝子回路が作成された(図1B)。合成遺伝子配列をインテグラーゼが切断すると、抗生物質の一種であるトリメトプリム(TMG)耐性が失われると同時にトリプトファン(trp)の合成に必須の酵素が産生される仕組みになっている。合成遺伝子回路はプラスミドとして大腸菌に入れられ、ランダムに分裂と分配、インテグラーゼによる切断が行われる(図1C)。プラスミドの細胞内での割合により、幹細胞、前駆細胞、分化細胞(のモデル)が生じる。インテグラーゼの発現を制御できるDAPGによって分化率を、trpとTMPによってそれぞれの分化状態の細胞の生存率を実験的に制御できる(図1D)。

Results
DAPGを変化させたときの細胞の増殖度合いで計測した適応度をプロットすると、モデルから予想された二相性の分布を再現できた(図1E)。また、各DAPG濃度における切断されたプラスミドの割合で計測される分化率をプロットすると、低いDAPG濃度においてはほとんどの細胞が幹細胞状態なのに対し、高いDAPG濃度においてはほとんどの細胞が分化状態であることが分かった(図1F)。これは、分化率が低いと幹細胞が多数を占めtrpが枯渇して適応度が低くなり、分化率が高いと分化細胞が多数を占めTMP感受性によって適応度が低くなるという、設計したとおりの適応度の二相性の挙動が達成されていることを示している。

図2は、異なる分化率の細胞で競争が起こった際にも二相性の適応度の下では正の分化率の細胞の割合が大きくなることが示されている。図1で分化率を変化させた際に細胞の増殖度合いが二相性になることが示されたが、細胞の分化の頑健性を示すためには、中程度の分化率の細胞が他の細胞との競争に勝てるか検証する必要がある。横軸に分化率(細胞内のインテグラーゼの活性度合い)を、縦軸にそれぞれの分化率の細胞の割合をプロットすると、trpの加えていない二相性の適応度の条件で競争させた場合は中程度の分化率が選択されるのに対し(図2D)、trpの加わった一相性の適応度の条件で競争させた場合は低い分化率が選択された(図2E)。

図3では、様々な環境条件に対して二相性の分化が頑健であることが示されている。様々な環境条件における適応度のカーブを適応度の最大値(赤)、単峰性からのズレ(緑)、最適分化率(青)で定量化した(図3B)。trpとTMP濃度を変化させた際の実験結果は、適応度の最大値や単峰生からのズレは徐々にパラメーターに依存して変化するのに対し、最適分化率はTMPが極端に低い場合を除いてほぼ一定の正の値をとることが分かった(図3C-E)。この頑健性の源を探るために、状態を変化させる細胞のロジスティック成長モデルを作成すると、定量的にこれらの3つの指標の変化を再現することができた(図3F-H)。異なるパラメーターでシミュレーションを走らせても、中程度の最適分化率は広いパラメーター範囲で実現されることが確かめられた(図3I)。

Discussion
本研究は、作ることでの理解を目指す合成生物学的アプローチに則り、大腸菌に分化回路を人工的に合成して埋め込むことで幹細胞、前駆細胞、分化細胞様の系統を作成した。この合成回路は、必須酵素の生産を分化とカップルさせることで、未分化の変異体が生存に不利になるように設計された。これは、未分化状態が増殖に有利だが、分化しないと必須の酵素を得られないという意味で、二相性の適応度によって変異体に対する頑健性を獲得しているといえる。この回路は様々な環境条件において長い期間正の分化率を維持できることが実験的に示された。
合成生物学では進化的時間スケールで安定して動作する合成回路が求められており、二相性にする等の適応度の改変は他の回路にも応用ができる。また、我々ヒトの幹細胞も様々な環境下で細胞数を増やしつつ分化する細胞比率を一定にすることで恒常性を保っていると考えられ、本研究のように前駆細胞が重要な働きをしている可能性が示唆される。
細胞を構成する分子のダイナミクスとその相互作用ネットワークを物理学的、情報学的に解析することにより生命に普遍的設計原理を見出すことを目指す学問をシステム生物学という。本研究はこの分野の第一人者で、有名な教科書も書いているUri Alonの研究室から出版されたもので、あまり理論面が前面には押し出されていないものの、普遍的な生命現象を単純化された実験系とそのモデルから理解しようという思想が垣間見えて面白かった。
参考文献
多細胞生物は細胞の特化により高次の生命機能を実現しているが、未分化の突然変異体が癌化するリスクも持つ。この問題に対し、合成生物学とシステム生物学を用いた研究が「Cell」誌に掲載され、大腸菌に合成分化回路を組み込むことで変異体の増殖を抑制し、二相性適応度を実現し細胞の分化頑健性を向上させる手法を提案している。この研究は、進化的安定性をもたらす合成回路の設計に新たな光を当て、システム生物学の観点から生命の普遍的設計原理を探求している。
サムネイル画像の出典:https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(24)00061-8
