
【近・現代の思想で今後の生き方を学ぶ】実存主義はヒューマニズムである

「ヒューマニズムの芸術 初期イタリア・ルネサンスの巨匠たち」ケネス クラーク(著)岡田温司(訳)

初期イタリア・ルネサンスの五人の巨匠、
ドナテッロ(ダヴィデ像)、

ウッチェッロ(サン・ロマーノの戦い)、

アルベルティ(絵画論(De pictura))、
「絵画論」レオン・バッティスタ アルベルティ(著)三輪福松(訳)

マンテーニャ(死せるキリスト)、

ボッティチェッリ(ヴィーナスの誕生)。

をめぐり、彼らの独創性や現代にまで及ぶ影響を鮮やかに描き出した本書。
ヒューマニズムは、すでに光を失った過去の思想にすぎないのだろうか。
「ヒューマニズム考 人間であること」(講談社文芸文庫)渡辺一夫(著)

破綻したのは個人主義的ヒューマニズムにすぎず、人間疎外が極点に達している現代こそ、人間性回復の転機をふくむものであると著者は主張する本書。
ヒューマニズム思想を歴史的にたどりつつ、現代社会におけるヒューマニズムの意義とあるべき姿を説く。
「実存主義とは何か」J‐P・サルトル(著)伊吹武彦/海老坂武/石崎晴己(訳)

「実存主義とは、一貫した無神論的立場からあらゆる結果を引きだすための努力にほかならない。
この立場はけっして人間を絶望に陥れようとするものではない。
しかし、すべて無信仰の態度をキリスト教徒流に絶望と呼ぶなら、この立場は本源的絶望から出発しているのである。
実存主義は、神が存在しないことを力のかぎり証明しようとするという意味で無神論なのではなく、むしろ、たとえ神が存在してもなんの変りもないと明言する。
~人間は自分自身を再発見し、たとえ神の存在の有効な証明であろうとも、何ものも人間を人間自身から救うことはできないと納得しなければならない。
この意味で実存主義は楽観論であり、行動の教義である。
キリスト教徒が自分自身の絶望とわれわれの絶望とを混同し、われわれを絶望者と呼ぶのはただ欺瞞によってである。」
【参考記事】
「極限の思想 ハイデガー 世界内存在を生きる」(講談社選書メチエ)高井ゆと里(著)大澤真幸/熊野純彦(編)

オーストラリアで、ターミナルケアの現場で働き、多くの方の死を看取ってきたブロニー・ウェアさんが記した「死ぬ瞬間の5つの後悔」では、
「死ぬ瞬間の5つの後悔」ブロニー ウェア (著)仁木めぐみ(訳)
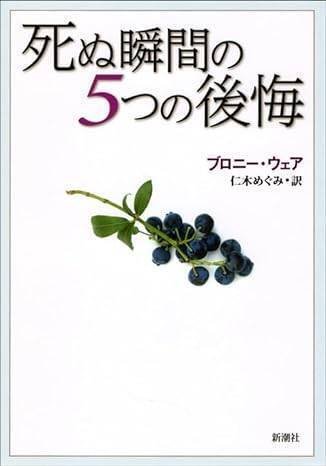
死ぬ間際の後悔として共通するものが大きく5つあると提示されています。
①自分に正直な人生を生きればよかった
②幸せをあきらめなければよかった
③働きすぎなければよかった
④思い切って自分の気持ちを伝えればよかった
⑤友人と連絡を取り続ければよかった
これらはまさに、生きている間に、日々死と向き合えなかった後悔とも取れる表現だと理解できます。
ハイデガーは、この世界に目的もなく生まれた人間は、ただ単に、存在するだけの事物とは違い、決断することで、自己を自由に選び取ることができる存在だと主張しましたよね。
何も考えずに生きていれば、簡単に没個性化・平均化していき、不安を紛らわしながら、安心して生き長らえることができるかもしれません。
その状況から脱して、死と向き合っていくことのは非常に難しいことです。
それは、没個性化から抜け出し、周囲と違う道に歩みを進めることにもなります。
すると、それまでよりも、さらに、大きな不安や孤独に苛まれることになるでしょう。
それらを引っくるめても、積極的に死を引き受け、強く生きることが必要だと、ハイデガーは説いたのです。
これは、現代人の心に深く突き刺さる一方、分かっていても、できないという大きな課題でもあります。
いつか死ぬということをしっかりと意識し。
今と真剣に向き合い。
本来の自己目的を選び取って生きていく。
それによって訪れる恐怖や孤独は、積極的に引き受けていく中で、自分の信念を貫く。
強い意志を持って、この世を去っていた多くの哲学者の存在は、その一人であるセネカ(ユリウス=クラウディウス朝時代のローマ帝国の政治家、哲学者、詩人。)が言うように、こちらから歩み寄れば、「心強い話し相手」になってくれたりします。
参考までに、セネカの言葉を引用しておきますが、こうした偉人たちの言葉も参考にしながら、日々を、過ごしたいものですね(^^)
「いかに多くの人々が汝より前進しているかを見るよりも、いかに多くの人々が汝より遅れているかを考えよ。」セネカ
「およそ惨めなものは、将来のことを不安に思って、不幸にならない前に不幸になっている心です。」セネカ
「ぐずぐずしている間に、人生は一気に過ぎ去っていく。」セネカ
「われわれの計画というのは、目標が定かでないから失敗に終わるのだ。どの港へ向かうのかを知らぬものにとっては、いかなる風も順風たり得ない。」セネカ
「運命は、志のある者を導き、志の無い者を引きずっていく。」セネカ
「我々に与えられた時間は、決して短いわけではなく、実はその多くを浪費しているだけなのである。」セネカ
「恐怖の数の方が危険の数より常に多い。」セネカ
「君が長生きするかどうかは、運命にかかっている。だが、充実して生きるかどうかは、君の魂にかかっている。」セネカ
「健康になりたいと願うことは、健康になることの一部分です。」セネカ
「治そうと思う者は、もう半ば治っている。」セネカ
「自分で怒りを抑えるには、他人の怒る姿を静かに観察することである。」セネカ
「修正の最初のステップは過ちの認識である。」セネカ
「人は常に時間がないとこぼしながら、時間が無限にあるかの如く振る舞う。」セネカ
「人生は短い。人間に与えられた時間は、束の間の虹のごとくである。」セネカ
「人生は物語のようなものだ。重要なのはどんなに長いかということではなく、どんなに良いかということだ。」セネカ
「精神には休養を与えねばならぬ。絶えず緊張を加えれば、精神の飛翔を妨げることになる。」セネカ
「誰かに起こりうることは、誰にでも起こりうることである。」セネカ
「知識を通して教えるには、長い時間がかかるけれども、具体例を通して教えれば、時間も短時間で済み、しかも有効である。」セネカ
「難しいからやろうとしないのではない。やろうとしないから、難しくなるのだ。」セネカ
「不幸な人の共通の過ちは、わが身に幸せが訪れることを、決して信じたがらないことである。」セネカ
「毎日をまったく違う人生と見なすべきだ。」セネカ
「労働が体を強くするように、困難は心を強くする。」セネカ
「老人が長く生きてきたことを証明するものを、年齢以外に何も持っていないことほど不名誉なことはない。」セネカ
さて、ここから、その当時に発刊されていた新書をテキストにして、今回は、「ヒューマニズム」について省みます。
【テキスト①】「アーロン収容所 西欧ヒューマニズムの限界」(中公新書)会田雄次(著)

[ 内容 ]
英軍は、なぜ日本軍捕虜に家畜同様の食物を与えて平然としていられるのか。
女性兵士は、なぜ捕虜の面前で全裸のまま平然としていられるのか。
ビルマ英軍収容所に強制労働の日々を送った歴史家の鋭利な筆はたえず読者を驚かせ、微苦笑させつつ西欧という怪物の正体を暴露してゆく。
激しい怒りとユーモアの見事な結合がここにある。
強烈な事実のもつ説得力の前に、私たちの西欧観は再出発を余儀なくされるだろう。
[ 目次 ]
捕虜になるまで
強制労働の日々
泥棒の世界
捕虜の見た英軍
日本軍捕虜とビルマ人
戦場と収容所―人間価値の転換
帰還
[ 問題提起 ]
ビルマ戦線で生き残り、イギリスが管理する捕虜収容所で過ごした著者の体験記である。
会田雄次氏はマスコミにも登場した西洋史学者。
サブタイトルの意味は、まえがきにある次の文章を見ればよく理解できる。
「想像以上にひどいことをされたというわけでもない。
よい待遇をうけたというわけでもない。
たえずなぐられ蹴られる目にあったというわけでもない。
私刑的な仕返しをうけたわけでもない。
それでいて私たちは、私たちといっていけなければ、すくなくとも私は、英軍さらには英国というものに対する燃えるような激しい反感と嫌悪を抱いて帰ってきたのである。」
「私たちだけが知られざる英軍の、イギリス人の正体を垣間見た気がしてならなかったからである。」
「それは恐ろしい怪物であった。」
[ 結論 ]
収容所のイギリス女性に対する見方は次の通りである。
「彼女たちからすれば、植民知人や有色人はあきらかに『人間』ではないのである。
それは家畜にひとしいものだから、それに対し人間に対するような感覚を持つ必要はないのだ。
どうしてもそうとしか思えない。
はじめてイギリス兵に接したころ、私たちはなんという尊大傲慢な人種だろうかとおどろいた。
なぜこのようにむりに威張らなければならないのかと思ったのだが、それは間違いであった。
かれらはむりに威張っているのではない。
東洋人に対するかれらの絶対的な優越感は、まったく自然なもので、努力しているのではない。
女兵士が私たちをつかうとき、足やあごで指図するのも、タバコを与えるのに床に投げるのも、まったく自然な、ほんとうに空気を吸うようななだらかなやり方なのである。」
だから、使役に来ている著者たちの前で、その女性たちは裸の姿を見せても何も感じないかのようだったのである。
イギリス人に対する感情は、以下のように激しいものがある。
「私たちは、ともかくもこういう英軍に対しては極度の反感を感じた。
まだ真正面からいじめられる方がよいくらいである。
15年を経た今日でも、思い出してくると私は激しい感情にかられる。
『万万が一、ふたたび英国と戦うことがあったら、女でも子どもでも、赤ん坊でも、哀願しようが、泣こうが、一寸きざみ五寸きざみに切りきざんでやる』という当時の気持ちが、こんなことを書いているとまざまざとよみがえってくるのだ。」
ビルマ人の死に対するイギリス人の反応をつぎのように受けとめる。
「明らかにここでは一匹のネズミが死んだのであって、人間が死んだのはなかった。
ヨーロッパ人がヒューマニストであるなら、いったいこれはどういうことなのであろうか。」
この残酷さを著者はヨーロッパ人の肉食に求めようとする。
「かれらはこの動物の屠畜とその屍体処理に馴れきっている。」
筆者はビルマ人にたいへん好意的な印象を抱き、この記録の内容からすればビルマ人も日本人にたいへん好意的に接している。
それは敗戦後もまったく変わらない。
ただ、著者も戦争中一度だけビルマ人の残虐さに接したことがあるという。
それは、瀕死の、あるいはすでに死んでいる日本兵から金歯を抜くビルマ人に気づいたときである。
そして、ビルマ人の残虐さに接したこの唯一の体験も、彼らの肉食と関連づけて理解している。
イギリス人の残虐さについてはつぎのような記述もある。
「日本軍捕虜に対する英軍の待遇のなかにも、私たちには、やはり、これはイギリス式の残虐行為ではないかと考えられるものがある。
そして、英軍の処置のなかには、復讐という意味が必ずふくまれていた。
問題はその復讐の仕方である。日本人がよくやったような、なぐったり蹴ったりの直接行動はほとんどない。
しかし、一見いかにも合理的な処置の奥底に、この上なく執拗な、極度の軽蔑と、猫がネズミをなぶるような復讐がこめられていたように思う。」
イギリス人に対する観察にも鋭いものがある。
「英軍の階級制度は日本とはちがって一般の社会構成をかなり性格に反映している。
一般人が応召した場合、短い訓練ののち、かれらはもともとの社会的地位にふさわしい階級をうけ、それに適合した兵種にまわされるのがふつうである。」
「伍長は職工組長、会計係は中尉、会計課長は少佐、工場長は大佐、技師は大尉や中少尉というふうである。
私はほんの少し英語ができ、ときどき通訳めいたことをやらされたので、二、三の将校からおまえは何者だと質問された。
『京大を出て、あるカレッジの講師をしている』というと、うそを言うなと叱られるのが常であった。大学を出た男が兵卒であるはずがない。
講師であれば中尉以上にはなる、お前はスパイ役か何かの特務工作員で英語の訓練をうけた男ではないか、と疑うのである。」
「下士官・兵との間には、これでも同じイギリス人かと思われるほどの差がある。」
「このこと自体別に不思議でない。
近代国家のなかで日本だけが特殊なのである。
戦後になって、戦前の日本の国家や社会に対し、ブルジョア国家だとか、独占資本の支配だとかいう定義がされているのを聞くごとに私は不思議に思った。
ブルジョア国家だったらブルジョアが軍隊も支配できるはずだ。」
「日本の社会はブルジョア社会ではなく封建社会、すくなくとも絶対主義社会である。
支配者は職業軍人である。」
イギリスの「士官と下士官・兵との差、とくにその体格の隔絶といってよい決定的な相違は目を見はらすほどのものであった。」
イギリス軍はインド兵を交えて戦っているわけであるが、「インド兵とイギリス兵が、何かの公的なな交渉以外に話を交わしているのも見たことはない。
よくまあインド人はこのような最高の侮辱に耐えられるものだなと感心するよりほかはない。」
日本人捕虜たちの管理のされ方についても触れている。
「このような軍隊秩序を維持させたのはイギリスの植民地支配から生まれた知恵であろう。」
「混乱をきたすであろう新しい秩序の形成をできるだけ抑えた。
階級の昇進さえもがおこなわれた。
終戦時、転属配属で原隊から離れていた私はもとのままの一等兵であったが、捕虜としての二年間に上等兵、兵長、伍長と昇進?したのである。
全員が下士官になったはずである。」
しかし、こうした旧軍の秩序を用いた生活のなかでも、戦時とは違ったタイプの人が一目置かれ、実際の生活のなかでも大きな役割を担っていく様子が記されている。
そして、不足するものを盗みでまかなう生活。
そのなかでも、芝居小屋をつくって、本物とみまがうような舞台装置なども備える。
[ コメント ]
もともと社会のなかでさまざまな職種に就いていた人々がその技能を生かして、ないものは何でもつくってしまう生活がそこにはあったのである。
【テキスト②】「フーコー入門」(ちくま新書)中山元(著)

[ 内容 ]
「真理」「ヒューマニズム」「セクシュアリティ」といった様々の知の「権力」の鎖を解きはなち、「別の仕方」で考えることの可能性を提起した哲学者、フーコー。
われわれの思考を規定する諸思想の枠組みを掘り起こす「考古学」においても、われわれという主体の根拠と条件を問う「系譜学」においても、フーコーが一貫して追求したのは「思考のエチカ」であった。
変容しつつ持続するその歩みを明快に描きだす、新鮮な人門書。
[ 目次 ]
序 現在の診断
第1章 人間学の「罠」
第2章 狂気の逆説
第3章 知の考古学の方法
第4章 真理への意志
第5章 生を与える権力
第6章 近代国家と司牧者権力
第7章 実存の美学
第8章 真理のゲーム
[ 問題提起 ]
フランスの哲学者ミッシェル・フーコーの展開した概念群を初期、「狂気の歴史」から、
「狂気の歴史 古典主義時代における」ミシェル・フーコー(著)田村俶(訳)

フーコー最後のプロジェクト、統治性のプロジェクトまでを取り上げている。
本書の思考とはフーコーの思考の軌跡を追い、フーコーという思想家の思想棚卸しを行うのではな<現在>に生きるわれわれが自分たちの生き方を問い直し社会を変革していく武器とするためである。
果たして私は武器を得ることが出来たのだろうか。
「狂気の歴史」では狂気が<神懸り>であり、人間が理性で見えないものを見る眼を神に植えつけられた。
が歴史とともに狂気が病となるのだ。
狂気が病となり精神医学と心理学が生まれる事となった。
精神病院が精神病患者を生み出し、狂気を批判の対象とした。
また人間科学の誕生から人間は発明され、近いうちに人間は終焉する。
学門は当たり前にあるものではない。
歴史の必要性が学問を産んだ。
私たちが当たり前に考えている知識や教養も学を考古学していけば成立した背景を紐解けるのだ。
[ 結論 ]
精神病院、福祉施設は時代のモード(流行)により左右される。
人里はなれた山奥に収容される患者。
数十年の社会的入院。
歴史が変われば地域で暮らす高齢者。
痴呆から認知症かみだーりから統合失調症。(精神分裂症から統合失調症)
外出の促進。
拘束から尊厳のある介護へ。
主体である精神病患者、高齢者は変わらない。
歴史が彼らを変えるのである。
「ニーチェ・系譜学・歴史」では真理。
「真理を語るものはだれか」
「真理とはそれなしにある種の生物が生きて生けないごみょう。」
真理はどうしても信じざるをえないものとして存在し現実の社会の権力的な関係において戦略的な機能を発揮すると解明する。
スターリニズム、カンボジアの虐殺しかり。
真理を舞台裏から眺める感。
が、これは難しい。
真理がそこにあるならすでに戦略的にもうどうしようもないよう私が組み込まれているのだ。
だとすれば後世の歴史で過ちを語られても私は避けることができないではないか。
逆説的に真理だから。
真理とされるものを舞台裏から覗けるよう構造を知れということか。
権力は外部から抑圧されて訪れるものではない。
人々が他人との関係性のなかか己の欲望を追求するなかで発生する場のようなもの。
権力が上から、外部にあるのではなく私たちがいる限り場として生まれるなら反権力は愚かしいことなのか。
福祉社会は美しいが福祉の名の下に国家が国民を管理している社会保障を理由に国民情報をよりいっそう収集しているのではないか。
またシステムに属さないことを望んだものには福祉が与えられないのだろうか。
また国家は従順な体をつくる。
福祉国家における疾病、出生率、死亡率の管理は一見穏やかな権力に写るがこれは経済コストの為労働力を効率的に確保する、国家の利益を守る権力である。
社会福祉に携わる人間が声高に社会保障の冷徹さを叫びヒューマニズムを説いても、全くの平行線なわけである。
国家は私たちから湧き上がった権力でしかないなら支払うコストに効果が見合うものでなければシステムとして不完全でしかないのだ。
「国家理性」国家は国家の力の維持そのものを自己目的としている。
「思想は生活していく上で役立つツールでなければならない。」とフーコーは述べている。
上に上げたのは私が特に気になったキーワードである。
私が実際にフーコーの思想概念群を理解したとは考えられない。
[ コメント ]
本書のヴォリュームでは仕方ないのかもしれない。
本書最後にフーコーは様々な支配を受けてういるわたしたちが今の真理を暴露し別の真理をみいだしよい関係ができる可能性を探れればとなんとも消極的に記されている。
私がツールとして得たのはマスメディアから発信される違和感を感じた言葉が「国家理性」や権力としての人格で述べられてる事に気づかされたということだ。
私をはじめ多くの個々人がミニマムに考えていれば分からないはずである。
だが国家はあるのだし解体されることもないだろう。
支配を善悪ではなくあるものとして捉えれば、分からなかった関係から他者として認められることまでは出来そうだ。
生活していくのに役立つまではいかないが括り付けられている見えない糸が目に映るようになった程度か。
あらぬ方向へ引っ張られるのにもう驚きはしない。
【テキスト③】「魔女狩り」(岩波新書)森島恒雄(著)

[ 内容 ]
西欧キリスト教国を「魔女狩り」が荒れ狂ったのは、ルネサンスの華ひらく十五‐十七世紀のことであった。
密告、拷問、強いられた自白、まことしやかな証拠、残酷な処刑。
しかもこれを煽り立てたのが法皇・国王・貴族および大学者・文化人であった。
狂信と政治が結びついたときに現出する世にも恐ろしい光景をここに見る。
[ 目次 ]
1 平穏だった「古い魔女」の時代(魔女の歴史 寛容な魔女対策)
2 険悪な「新しい魔女」の時代(ローマ・カトリック教会と異端運動 異端審問制の成立とその発展 ほか)
3 魔女裁判(魔女は何をしたのか 救いなき暗黒裁判 ほか)
4 裁判のあとで(魔女の「真実の自白」 「新しい錬金術」―財産没収 ほか)
[ 問題提起 ]
中世キリスト教国の異端審問の歴史における「魔女裁判」について記述されている。
<参考記事>
[ 結論 ]
「世界国家」統轄のために作った異端審問制度により、いつしか魔女は異端者であるものとされ、「魔女裁判」にて残虐な拷問・処刑を執行されるまでになった。
衝撃的だったのは、「ヒューマニズムと実証主義のルネッサンス時代は、一方では残虐と迷信の時代であった」との記述である。ルネッサンス時代は近代科学の始まりであり、多くの著名な科学者がいるが、彼らまでもが「魔女裁判」肯定派であったとは信じがたいことであった。
[ コメント ]
また、
1.知識はその所有者次第で最高の悪徳となる、
2.狂信と政治が結びついたときの恐ろしさを認識すべし、
3.科学の敵は宗教でなく神学的ドグマである、
を歴史的教訓として理解できたことはよかったと思う。
【テキスト④】「哲学の復興」(講談社現代新書)梅原猛(著)

[ 内容 ]
[ 目次 ]
生と死の哲学 思想の動向
知覚と想像力-「期待される人間像」をめぐって
実存主義の実存的批判
人間とは何か
生と死の哲学-文化の中の生と死
ニヒリズムの系譜
生と死の思想
サルトルの呪縛をのがれて
文明とは何か 平和の哲学序説
現代中国をどう見るか
欲望学の提唱
教育の原形にもどれ
進歩という幻想について
女性論に対する一つの視点
技術文明社会の崩壊
ドストエフスキーの予見と現代
人間に問われているもの
日本的自然観と近代文明
池井望『現代文化論』について
東洋思想の復権 東洋思想の研究のための覚え書き
西洋近代文明の超克
甦るべき生命の哲学は何か
近代哲学と仏教
日本思想の原点を求めて
東洋の生命観
[ 問題提起 ]
1970年前後に書かれた以下の五つの論考を収録する。
「生と死の哲学」
「平和の哲学序説」
「
サルトルの呪縛をのがれて」
「現代中国をどう見るか」
「日本思想の原点を求めて」
それぞれの論考は、素材は異なるが、基本的には同じことを言っている。
それは、物質的富と肉体的快楽の普及に貢献したヨーロッパ科学技術文明は、いまやその弱点をさらけ出し、人類を絶滅の危機に追いこんでいる、我々が生き延びるためにはこれからは仏教を中心とした東洋の哲学が必要である、ということだ。
具体的には、新旧約聖書の世界及び西洋近代科学の父・デカルトの哲学は生死を考えず、また、ヒューマニズムは人間、しかも実際には一部の人間のみの利益を優先するとして、現代における西洋文明の限界を指摘する。
そして、代案として、生きとし生けるものすべての殺生を禁じる仏教思想、東洋思想の必要性を説く。
また、日本の平和憲法の重要性を指摘する。
梅原猛の主張は二点。
西洋原理の限界と、それに代わる東洋原理の提唱である。
前者には私も賛成だ。
科学技術文明は、西洋の原理に支えられているが、この西洋の原理には、環境や平和、不殺生の要素が欠けている。
ではわれわれは生き残るためにどうすればよいか。
ここで私は梅原猛と意見が分かれる。
[ 結論 ]
梅原猛は東洋哲学を西洋哲学に代替させることを提案するが、私はこの考えには反対だ。
第一に、西洋原理の問題が20世紀後半にあらわになったのは事実だが、そのことは、西洋原理の限界を意味しているわけではない。
西洋原理のひとつであるキリスト教には、アーミッシュのように科学技術を拒否する考えもある。
また、イギリスのナショナル・トラストは大きな自然保護団体として有名だ。
あらゆる原理同様、西洋原理も不変ではなく、したがって「西洋原理はもうダメだ」と決めつけるのは公正でない。
第二に、西洋原理を東洋原理に置き換えればよい、という思考も短絡に過ぎる。
この考えはトインビーの文明史観(16世紀以来優位に立っていた西洋文明は、20世紀後半には他の文明に反撃される)に影響されているのだが、それでは今度はいつか、東洋原理が問題を抱えるであろう。
また、西洋の大きな抵抗も予想され、戦略的にも好ましくない。
「どの原理を選ぶか」ではなく、すべての原理を融合する方向を目指すべきだと私は考える。
東洋、西洋を含めたさまざまな原理が対話することによってよりよい思考が生まれるのではないか。
どちらか一方をとるという問題の立て方自体に問題がある。
60年代、多くの日本の知識人は中国の文化大革命を支持していたと聞く。
今ではちょっと信じられないが、本書を読む限り、梅原猛も文革を評価している人間の一人だ。
「現代中国をどう見るか」(「別冊・潮」1968年夏季号初出)には以下のような記述が並ぶ。
「中国が、マルクス主義を採用することにより、中国の近代化を行なうと同時に、反ヨーロッパの思想を自己のものにしたのは、賢明な歴史的選択であったようでした」(177頁)
「私は今の中国の巨大な歴史の歩みに、驚嘆と尊敬を禁じえません。
(中略)
いまや、中国は、ふたたび巨大な文化実験への歩みを、悠然と歩いているかに見えます。
マルクス主義によるヨーロッパ文明の移入とその克服、この道を中国は着実に歩いているのです。
それに対して、われわれはどうか。
われら、機を見るに敏な民族は、いまや明日の行方も知らぬげであります」(185頁)
「・・・われらが、その模範としたヨーロッパ諸国が、まさに、崩壊に向かっているからです。
そして、こういうヨーロッパ文明の悪を克服した新しい国づくりを、一時はわれらに遅れをとった中国は行なっているのであります。
中国は現在、まさにプラスの札をにぎっているかのようであります」(186頁)
梅原猛は、最終的には、マルクス主義も西洋思想の伝統に立っているために不十分であると批判するのだが、明らかに文革を評価している。
[ コメント ]
本書は、現在絶版のようだが、この文革評価が原因だろうか。
繰り返しになるが、梅原猛の問題は、「どの文明を選ぶか」という疑問を出発点にしてしまっているところにある。
彼は、西洋原理はダメだから東洋原理に代替すべきだと主張するのだが、これはサイードの言葉をもじれば「逆オリエンタリズム」である。
すべての文明が対話をし、よりよい価値観を見出していく、キャッチフレーズ的に言えば、「文明間の衝突ではなく、文明間の対話」、そんな方向性が21世紀には求めらるのではないだろうか。
【テキスト⑤】「和辻哲郎 文人哲学者の軌跡」(岩波新書)熊野純彦(著)

[ 内容 ]
『古寺巡礼』『風土』等、流麗な文体により、かつて青年の熱狂をかきたてたことで知られる和辻哲郎。
彼は同時に、日本近代が生んだ最大の体系的哲学書、『倫理学』の著者でもある。
日清戦争前夜に生まれ第二次大戦後におよんだその生と思考の軌跡は、いかなる可能性と限界とをはらむものだったのか。
同時代の思想状況を参照しつつ辿る。
[ 目次 ]
序章 絶筆
第1章 ふたつの風景(故郷 離郷 帝都
第2章 回帰する倫理(回帰 渡航 倫理
第3章 時代のなかで(時代 国家 戦後
終章 文人
[ 問題提起 ]
昨年の紅葉の季節に見たモミヂの色づきも、私にとっては、美しいと思う景色であった。
けれども、それは私ひとりの主観にあらず、多くの人々と共有される感覚である。
こうした、「共に有つ」ということを、深く掘り下げて思索した哲学者のひとりに、和辻哲郎がいる。
本書は、和辻の生い立ちから思想の展開、そして最晩年にいたるまで、その人生を丹念に跡づけたものである。
[ 結論 ]
ここには、和辻のエピソードが多々描かれているが、私は以下の2点に注目して読んだ。
第一に、著者の熊野純彦は、和辻の「間柄」とマルクスの「関係」論的視点の共通性を浮かび上がらせる。
「花は美しい」というとき、客体(客観)としての花と、美しいと思う主体(主観)とは、実は分離することができない。
「美しい花の存在の仕方とその花を美しく感ずる体験とは一つである」と和辻がいうとき、主客の統一を志向した初期マルクスの存在論とも重なり合う。
マルクスであれば、資本主義社会における「商品」の存在の仕方が、人間に「疎外」の感覚をひき起こさせるというかもしれない。
疎外論とは別の「物象化論」については、触れないことにしよう。
<参考図書>
「マルクスの物象化論[新版]」(シリーズ「危機の時代と思想」)佐々木隆治(著)

<参考資料>
「和辻は、マルクスの名を抹消するには、あまりに多くの視角をマルクスから学んでいた」。
両者の関係を考えることは興味深く、私は別に、ハイデガーのマルクス理解を読んだときと同じような感想をもった。
たとえば下記の図書。
「「ヒュ-マニズム」について」(ちくま学芸文庫)マルティン ハイデッガー(著)渡邊二郎(訳)

では、両者の差異はどこにあるのか。
「マルクスには存在して、和辻にかけていたのは、資本制的生産関係をめぐる細密な分析ばかりではない。欠落しているのは、国家の終焉という醒めてみられた夢であった。和辻はむしろ国家に多大な課題を負わせるにいたったからである」。
第二に、和辻と「他者」をめぐる問題である。
「ことばへの和辻の視点は」「奇妙なほどに『等質性』を前提」としており、「他者との関係としての倫理」が「ほとんど完全に欠落していた」。
日本の固有な文化、伝統、言語を重視するあまり、かえって民族の等質性を維持する方向に思索が向かってしまった。
戦後まで象徴天皇制を擁護した和辻の哲学・倫理体系に、検討の余地が残されている所以である。
もっとも熊野は、「戦中のほぼ全体をつうじて、和辻は反政府勢力にぞくしていた」とフォローするのだが。
いずれにしても「他者」の問題を考えることは、ひとり和辻哲郎のみを語るばかりでなく、この国の哲学的伝統そのものをどのように総括するかにかかってくる。
[ コメント ]
北鎌倉の東慶寺に和辻は眠る。
和辻の墓をそれほど気にかけることはなかったけれど、本書を読んで、訪れてみたいと思った。
【関連記事】
【近・現代の思想で今後の生き方を学ぶ】日本の思想
https://note.com/bax36410/n/n20714d54092b
【近・現代の思想で今後の生き方を学ぶ】政治思想
https://note.com/bax36410/n/n4e9207d28fab
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
