
【科学エッセイ】ユクスキュルの環世界
ユクスキュルの論点の主たる主張は、生物が個体によってまったく異なる世界(環境世界)を持つという点です。
それは、私たちが観察可能な蟻の行動範囲(地表)だとか、蜘蛛の張った巣(空間)とかいうものとも異なり、生物側からの視点で観察された生物が独自に持つ閉じた内的世界のことです。
ユクスキュルは、それをトーンと呼んでいます。
トーンというのは、主体が客体に与える意味づけのようなものであり、作用トーンや探索トーンといったものがあります。
例えば、森の中の一本の柏の木は、それぞれに違ったトーンが存在していて、以下のように、同じものでも状況によっては異なるトーンを持つこともあります。
①きこりにとっては効用のトーン
②森に迷い込んだ少女にとっては悪魔のトーン
③キツネにとっては保護のトーン
④カミキリムシにとっては食のトーン
こういった具合に、柏の木でも、生物ごとに異なる違った意味合いを持っています。
この考え方(環世界論)は、今でも、そうだと思いますが、デカルトの心身二元論に基づく生物機械論(※1)へのアンチテーゼと、生気論(※2)のジレンマから抜け出すための方策でもあったようです。
※1:
※2:
生気論と言うのは、人の体には科学的に証明できない【何か魂の様なもの】が宿っていて、それが体を動かしていると言う考え方です。
機械論と言うのは、人の体は物質の集まりで、すべては物理的・科学的に説明できるという考え方です。
そのため、ユクスキュルは、とても注意深く両方の考え方を批判しています。
意味が客体に備わった固有のものであるとするならば、仮に、タンパク質でできた機械に対して、魂を注入したものが生物ということになってしまいます。
逆に、世界は、主体のみで、主体、それぞれが世界を持っているものとすれば、主体の構造を問題にするパラドクスからは逃れることができなくなってしまいます。
それは、構造自体が主体の形成する環世界にしかないためです。
そして、主体の構造を問題にする時、主体自体、何かの環境世界であることになり、主体にプロポーズされてしまった存在を、ユクスキュルは、「意味に耐えるもの」と呼んでいます。
こうしたある種、絡み合った多重世界は、量子力学の多世界論(※3)を喚起しそうです。
※3:
多世界解釈(ベレットにより提唱された量子力学の観測問題の解釈の一つ)では波動関数を実在するものと捉え、したがって波動関数が示す重ね合わせ状態も異なる世界として実在すると考える。
このように多世界解釈は実在主義の立場である一方で、コペンハーゲン解釈(※4)は観測されない背後の存在については語らず、観測結果を予測できればいいという実証主義である。
【関連記事①】
【夜のお散歩】コペンハーゲン解釈の哲学的問題について
https://note.com/bax36410/n/n4998e3c02a50
※4:
量子力学での、粒子の存在に関する世界観の一つ。
粒子の位置や状態は観測されるまで特定できず、空間の各点ごとの存在確率の大小としてしか把握できないとするもの。
コペンハーゲンを中心に活動したボーアらが提唱したことから名付けられた。
しかしながら、量子論のような単純な重ね合わせ(※5)でないところが、この世界を、より豊かなものにしているのかもしれません。
※5:
重ね合わせの原理とは、ある粒子(量子)の状態が、複数の独立で排他的な状態(固有値)の重ね合わせで表されることです。
観測した場合は、どれか1つの固有値のみ観測され、これを「波束の収縮」と呼びます。
重ね合わせの状態は、単に「観測される前だから人間が知らない」のではなく、本質的に「確定していない」状態です。
そう、ワトソンとクリックがDNAを発見したのは、ユクスキュルが、これら一連の考え方を出していった時代から20年後のことだったので、ユクスキュルの観点が、如何に先進していたかがわかります。
すべての生物は、知覚の枠内でしか世界を認識できない。
私たちが客観的だと信じている、この目に映る世界は、世界全体から主観的にある一部分を型抜きしたものにすぎない。
日高敏隆氏の言葉を借りれば、以下の通りです。
「人間も人間以外の動物も、イリュージョンによってしか世界を認知し構築し得ない。そして何らかの世界を認知し得ない限り、生きていくことはできない。」(日高敏隆「動物の人間の世界認識」P195より引用)
「動物と人間の世界認識―イリュージョンなしに世界は見えない」(ちくま学芸文庫)日高敏隆(著)

さて、人間、動物、さらには機械にとって、「心とは何か?」という問いについて、心理学分野以外における心の科学の代表的な考え方が、実は、このユクスキュルの環世界であるのですが、生物(特に動物)に限っていました。
そこで、生物学から提唱された心を理解する考え方である環世界についての理解を深めるのに役立つ、哲学としてカントの学説、認知科学としてアフォーダンス、情報科学としてサイバネティクという考え方やAIからのアプローチについては、参考図書等から【参考資料】の通りです。
そして、ユクスキュルとクリサートが提唱するような「生物から見た世界」を見ることが、人間に本当に可能なことなのかについて、現代の心の哲学の土台であるネーゲルによる「コウモリであるとはどのようなことか」について、少し触れておきますので、興味の有る方は、【参考図書】の本を手にとってみてください(^^)
【参考資料】
①カントの認識論:
ユクスキュルの環境と環世界の考え方は、物理的な世界と主観的な世界を分けて考えるものとなるが、このような考えの基にあるのが、カントの認識論であると言える。
イヌマエル・カントは、18世紀のドイツの哲学者であり、代表作として「純粋理性批判」がある。
下記記事で紹介した通り、カントは、人間がどのように世界を認識しており、どうやってその知識を共有していくことが可能となるのかということに取り組んでいる。
【関連記事②】
【宿題帳(自習用)】「自由」研究
https://note.com/bax36410/n/nca990c0c9b65
具体的には、人間は主観の外に出て、客観的世界そのもの(物自体)を見ること、知ることはできないが、主観は個人差を超えた共通規格で持って生み出されるため、私たちの間では、お互いに共通理解することはできるという考え方を提案している。
カントの言うところの共通規格と言う部分が、ユクスキュルの言う感覚器官と運動器官であると考えられる。
カントは、人間の認識は、感性と悟性から生まれると考えている。
人間が環境の中から、対象を認識する際には、まずは、視覚、嗅覚、聴覚、触角、味覚といった感覚器官が刺激される。
感覚器官から生じる感覚は、空間と時間という軸に従って処理されていく。
例えば、りんごであるならば、赤くて、丸くて、甘い香りがするのだが、それがテーブルの中央に、いまあるといった具合である。
このように、対象が認識される際には、空間と時間によって整理され、このはたらきをカントは感性と呼んだ。
そして、空間と時間というものが、人間の外側にあるのではなく、人間の内にある感性が生み出すものだと主張した。
カントによれば、人間の認識が環境内の対象を感覚器官により、空間と時間で整理された上で、それが何であるのかを判断するのが悟性の役割とされている。
各感覚器官からは、様々な情報がイメージとして上がってくるので、それらを束ねて、「これは~だ」と判断すると考えられており、この機能を悟性と呼んでいる。
感性に加えて、この悟性にも人間において、個人差を超えて、共通する性質があるため、感性と悟性から生まれる認識を私たちは、共有し合うことができ、世界が成り立っているというのがカントの認識論である。
このように考えているため、人間は、それぞれの主観的世界や、科学的な知識を互いに共有し合うことができるのだという。
また、時間は、天体観測に基づいて、科学的に定義することができ、機械で目に見えるようにすることが可能なものであるという側面に加えて、生物が世界を認識する際に、それぞれの感性が生み出す主観的な体験でもあると考えられる。
時間は、一義的に定めることが可能な概念であり、時計として日常的な道具として一般的なため、人間の主観が生み出したものであると言われても、その考え方を理解するのは難しい。
しかし、カントの世界の認識に関する考え方に根ざすならば、対象を感覚器官で認識する際に、感性のはたらきによって時間情報が加えられたイメージを悟性のはたらきで判断していると捉えることができるため、時間は、主観的なものでもあるとも言える。
退屈さを感じているときには時間を長く感じたり、楽しさを感じているときには時間を短く感じたりすることを含めれば、カントの考え方に賛同することは難しくないかもしれない。
②アフォーダンス:
ユクスキュルが「生物から見た世界」を記した時代には、まだ登場していなかった考え方に、ギブソンによって提唱されたアフォーダンスというものがある。
これは大雑把に言えば、環境に導かれて行為が生じるというアイデアである。
例えば、ミミズの葉っぱの穴ふさぎについては、葉っぱの形が、ミミズに引っ張り方をアフォードすると説明される。
つまり、ミミズが意図的に行動しているのではなく、葉っぱの形によって、そのように動くことが可能となると解釈される。
このようなアフォーダンスということをギブソンは1950年代頃から使い始めたと言われている。
環世界という考え方に加えて、アフォーダンスという考え方も、生物種を超えて、心のはたらきを説明することができる考え方であり、文脈ごとに環境からアフォードされる行動が変化するという話になる。
つまり、ユクスキュルの作用トーンという使い方は、極めてアフォードするという意味に近いと言える。
環世界的に理解する場合の方がより内定な、主観的な体験を重視している表現となり、アフォーダンスで説明する場合は、より外的な、自動的な行動表出であるような意味合いとなる。
このように行動の原因を内的にもとめるか、外的にもとめるかで使用される言葉が違うし、重きがおかれるニュアンスも異なるが、おおよその意味では環世界とアフォーダンスは置き換え可能な面もある。
例えば、イソギンチャクの例は、イソギンチャクの形態が生み出している機能差であるため、その典型例であると言える。
③サイバネテックス:
人間と人間、人間と機械、機械と機械との間の情報のやり取り(コミュニケーション)には、共通して通信と制御における予測と予測誤差の修正をどのように実現していくのかという共通の課題があると考えたのが数学者であるウィーナーであり、通信と制御の観点より、機械、生物、社会について統一的に考えるための学問分野としてサイバネテックス(Cybernetics)を提唱した。
サイバネテックスにおける予測と予測誤差に関する議論は、現代のAI(Artificial Intelligence)技術の基盤となる考え方となり、人間、動物、そして機械(またはAI)における「心とは何か」について考えるためにも必要となる。
④AI:
人工知能とは、人工的に作られた人間のような知能のことを指し、また、つくろうとすることによって知能自体を研究する学問分野のことを指す。
心理学が人間を直接的に実験や調査で調べることによって知能を解明するのに対して、人工知能研究者はつくりながら考えるという構成論的なアプローチを取る。
人間の知能は、音声を認識する、形を認識する、次の行動を判断するなど、様々な機能が含まれている。
これらの機能を人間ができるのは、発達のプロセスの中で、学習して、身につけているからであり、人工知能においてもどうやって学習させるのかが鍵をにぎる。
現代において、目覚ましい発展が遂げている手法として機械学習とディープラーニングがある。
⑤心とは何か?:
AIは、画像認識、音声認識、傾向の分析(例えば、Amazonは買い物した傾向を分析して商品を勧めてくる)、運転、将棋など様々なことが人間の心がするように、時には、人間よりも優れた能力でやることができるようになった。
しかしながら、AIは、人間や生物が示すような完全に主観的な世界については表現することができていない。
例えば、AIは、人間と同じような感情を感じたり、その感情に基づいて、振る舞うことまではできていない。
あくまで、画像認識などの特定の機能を実現することができるようになったのである。
完全に人間のような心、知能に基づくようなものを目指す立場を強いAI、機能ごとに人間のように振る舞うことができるようなものを作る立場を弱いAIという。
⑥コウモリであるとはどのようなことか:
ネーゲルは、人間が人間以外の動物の主観的な世界を想像することができるかを考える際に、人間とは全く異なる感覚器官と運動器官を有しているような、例えば、コウモリについて考えた。
コウモリは、人間には聞くことのできない超音波を発生して、その超音波の跳ね返り(反響)を分析することで、空間を把握し、自分の位置や獲物との距離を知るという。
このような対象の捉え方を、人間は、通常はしない訳であるが、このような時(他には、犬の優れた嗅覚、ネズミのヒゲの機能など、人間にはない動物種固有な感覚機能は無数にある)、ネーゲルは、人間には、他の動物の主観的な世界を想像することはできないとした。
環世界という考え方を知ったいま、このネーゲルの考え方に対する反論として、私たちには、この世界を、どのように捉え、考えていきたいか?という問いに対する自分なりの答えを導いていくことが、とても重要ではないかと考えている。
また、ネーゲルは、生物の主観的な世界を想像することはできないとはしているが、その生物をその生物たらしめる何かが存在していることは認めている。
確かに、科学的な還元主義では、多様な生物の主観的な世界にたどりつけないかもしれない。
しかし、コウモリのソナー(音波の反響を分析して位置を知るようなレーダーのこと)の性質が科学的に明らかにされたからこそ、コウモリはコウモリたらしめられているとも言えるだろう(簡単にいえば、コウモリのソナーとは、コウモリらしさであるという考え方)。
しかしながら、コウモリのソナーの精巧な性質を知れば知るほど、人間ができる範囲をどんどんと超えて行き、その主観的な世界を想像することさえ、私たちにはできないというように考えることも可能となるとも言えるだろう。
私たちは、心を人間、動物、さらには機械にも感じることができる。
私たちに感じられた心、全てに実体があるかどうかはわからないが、様々な心の在り方の中には、単に、人間の知能では想像することもかなわないようなものもあるかもしれない。
このようにまだ心については、わからないことだらけである。
だからこそ、わからないことを理解することが第一歩であると考える。
私たちが今できることは、そこに心はあると信じて、科学的に調べてみるという姿勢をもつことだろう。
そして、様々な心と付き合って行く中で、心の理解は深まると推定できるのではないか。
ダニングクルーガー効果という認知バイアスにもある通り、人は自分の能力を過大評価する傾向がある。
自分に知識があると思ってしまうことによって、学ぶことを止めてしまったり自分を客観視できなくなる。
「わかったつもり」でいる人と「自分はわからない」という人では物事を吸収できる量が違ってくる。
「なんとなく」という感覚で物事を捉えてしまいがちである行為を止めて、「わからない」と認めてしまうことは、少し勇気のいることではあるが、わからないからこそ学び、知ることができるのであるから、例えば、心理学以外の世界で、動物種を超えて、心を考えるためのキーワードの理解に取り組み、各自が心とは何か?と繰り返し問う時間を過ごすことで、自分と対象(人や物事)の間に、とても良好な関係を築いていけるのではないかと考えられる。
「頭で考えるだけのことは、何もしないのと同じである。」宇野千代(小説家)
そして、考えることと行動することの違いは大きいし、そこから得られるものも違ってくる。
実際に自分でやってみなければ、ただ考えただけでは何も変わらないことから、考えていることを、実際に、どれだけ行動に移せたかを基準にしていきたい。
【参考図書】
「DNA―二重らせんの秘密」(みすず科学ライブラリー)ローレンス・レッシング(著)丸山工作(訳)

「生物から見た世界」(岩波文庫)ユクスキュル/クリサート(著)日高敏隆/羽田節子(訳)
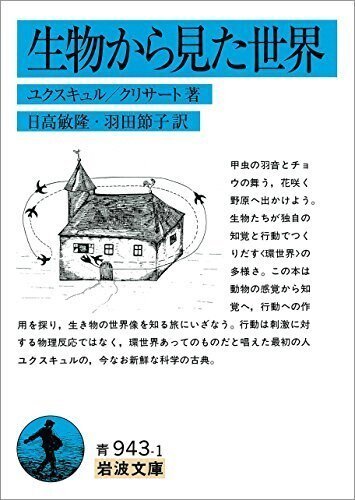
「コウモリであるとはどのようなことか」トマス・ネーゲル(著),永井均(訳)

【関連図書】
「世界を、こんなふうに見てごらん」(集英社文庫)日高敏隆(著)

「行動主義の心理学」ジョン・B. ワトソン(著)安田一郎(訳)

「流れを読む心理学史〔補訂版〕世界と日本の心理学」(有斐閣アルマ)サトウ タツヤ/高砂美樹(著)

「ゾウの時間 ネズミの時間―サイズの生物学」(中公新書)本川達雄(著)

「ダンゴムシに心はあるのか 新しい心の科学」(PHPサイエンス・ワールド新書)森山徹(著)

「〈弱いロボット〉の思考 わたし・身体・コミュニケーション」(講談社現代新書)岡田美智男(著)

「ダーウィンのミミズの研究」(たくさんのふしぎ傑作集)新妻昭夫(著)杉田比呂美(イラスト)

「知性はどこに生まれるか―ダーウィンとアフォーダンス」(講談社現代新書)佐々木正人(著)

「人間機械論 ―人間の人間的な利用 第2版 【新装版】」ノーバート・ウィーナー(著)鎮目恭夫/池原止戈夫 (訳)

「僕とアリスの夏物語 人工知能の、その先へ」(岩波科学ライブラリー)谷口忠大(著)

【参考記事】
松岡正剛の千夜千冊 生物から見た世界
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
