
【宿題帳(自習用)】知の相対化

ボルヘスの小説「学問の厳密さについて」には、実物大の王国の地図を作る地理学者が出てくる。
「創造者」(岩波文庫)ボルヘス,J.L.(作)鼓直(訳)

「詳しい地図を作ろうとすると実物大になってしまった。
人々はそれを「無用の長物と判断して、無慈悲にも、火輪と厳寒の手にゆだねてしまった」
地図は、そこに情報が載っているから有用なのではなく、そこから情報が抜け落ちているからこそ役に立つ。
現実の不完全な模倣だから役立つのである。
「君たちはどの主義で生きるか バカバカしい例え話でめぐる世の中の主義・思想」さくら剛(著)

シェイクスピアは、全てを相対化する目をもっていた。
自分だって笑うのだ。
「相対化する知性 人工知能が世界の見方をどう変えるのか」西山圭太/松尾豊/小林慶一郎(著)

「新版 貧困とはなにか――概念・言説・ポリティクス」ルース・リスター(著)松本伊智朗(監修, 翻訳)松本淳/立木勝(訳)

真面目な劇だと思われている『ハムレット』の中にも笑いは多い。
「ハムレット」(新潮文庫)シェイクスピア,ウィリアム(著)福田恒存(訳)

復讐を果たすために狂気をよそおっていたハムレットが、王妃の部屋で隠れていた家臣のポローニアスを刺し殺したと知った国王クローディアスは、自分が危険だと思って、ハムレットをイギリスに追いやることにする。
その理由を廷臣たちに説明して、「むつかしい病気はむつかしい手段によってしか癒されぬもの」という。
後に、墓掘りの道化が、このイギリス送りを、「気がちがったからでさ」と言ってのけ、「あそこじゃ気がちがっていても目だたねえ、なにしろみんな気ちがいばっかりだから」とうそぶく(第五幕第一場)。
ここで、当時も、今も、イギリス人は、大笑いする。
シェイクスピアは、自分自身を笑っているのだ。
独善的な人というのは、どこから得たかもしれない「信念」を絶対だと信じて「布教」する人の別名である。
自分の思想や研究は深い、と思っているかもしれないが、他人から見れば、赤ちゃん用のバスタブに浸かっているだけかもしれない。
自分の理論や思想の根拠というのを、洗い直して見ていないのである。
神のご託宣を大衆に与えるだけというような「司祭型」の学者では、今日のような錯綜とした文化状況にはうまく適合できない。
一元的パースペクティブでは、通用しない。
そのためには、学問や芸術領域を横断し、多様な地域の文化伝統を射程に入れる必要がある。
答えのない時代に必要な「知」は、「重箱の隅型」の学問ではなく、少し祝祭的な雰囲気もある「闇鍋型」の研究である。
ジル・ドゥルーズの言葉でいえば、ツリー型の「知」を求めて、枝葉末節を研究するのではなく、リゾーム(根茎)型の「知」である。
そこでは、すべての起源や「中心」を探し出すことはできない。
西洋哲学は、すべての起源や目的となる究極的な存在を求めようとして成立したものであるが、変化することもなく、常に、同一に留まる「同一者」的存在を見つけることができなくなっている。
秩序をノモス、無秩序や混沌をカオスというギリシャ語で表すことがあるが、合理性を求めて、あまりにもノモス的な思考がはびこってしまった。
カオス的な思考をしなければ、正解のない時代を生きることができない。
これから必要とされるのは、「呪術師型」や「カオス型」の攪乱する「トリックスター」的な知識人である。
秩序や効率や目的に結びつけて行動する「司祭型」「ノモス型」では、答えなき時代を生きることができない。
大切なのは、遊び精神にあふれた文化英雄である。
ジル・ドゥルーズの言葉でいえば、「ノマド(遊牧地)」で遊ぶ「逃走する主体」ということになるだろう。
カオス研究の第一人者であるダヴィッド・ルエールは、「偶然はこの世界において本質的な役割を果たしている」と述べているが、私達に必要なのは、チャンス・オペレーション、つまり、偶然を活用することである。
山口昌男は、「知の旅への誘い」の中で、人間の生における光と影の部分を対比させ、影の復権による「全体知」の回復の必要性を説いている。
「知の旅への誘い」(岩波新書)山口昌男/中村雄二郎(著)

夢、無意識、祭り、極限状態、芸能、神話といったいくつかの人間的経験の枠組みを通して見てもわかるように、人間は、因果律論につじつまのあう方向だけに沿って生きているわけではない。
こうした様々な要素の一見非合理的に見えるが、理性的な次元だけでは、充実した全体的な生を営むことはできない人間の表面的な生の補充の営みになる。
仮に、こうした一見、でたらめと見える部分が影の部分だとすると、人間は、こうした影の部分との秘かな対話を試みないで、深い意味での統一を保つことはできない。
こうして山口昌男は、これまでの理性的なものと見られてきた<知>を、光と影の部分に区別して次のような表を作っている。
光の部分 影の部分
表層の意識の整合性 生真面目さ
因果性 理性
日常生活の現実 現在
司祭的知性 イデオロギー
ことばの論理 一元的現実
中心 深層の意識の旅
笑い 荒唐無稽
狂気 祝祭の現実
始原の時 道化型知性
想像力 肉体の論理
多元的現実 周縁
文化も人間も言葉も影があるから面白いのであり、光だけのタテマエだけの一元的な世界で生きてはいけないのである。
20世紀の芸術家たちが模索したことも、知の相対化である。
意味のあるものを分解して構築しなおすことで新しい物を生み出そうとした。
「脱構築」(「ディコンストラクション」deconstruction)と呼ばれるものである。
「デリダ 脱構築と正義」(講談社学術文庫)高橋哲哉(著)

「脱構築」(思考のフロンティア)守中高明(著)

「言語的思考へ 脱構築と現象学」(講談社学術文庫)竹田青嗣(著)

「脱領域・脱構築・脱半球 二一世紀人文学のために」巽孝之(監修)下河辺美知子/越智博美/後藤和彦/原田範行(編)

「論理パラドクス・心のワナ編 人はどう考えるかを考える77問」三浦俊彦(著)

「脱学校の社会」(現代社会科学叢書)イヴァン・イリッチ(著)東洋/小澤周三(訳)

「脱常識の社会学 第二版――社会の読み方入門」(岩波現代文庫)ランドル・コリンズ(著)井上俊/磯部卓三(訳)

「フランス現代思想史 - 構造主義からデリダ以後へ」(中公新書)岡本裕一朗(著)

「〈現実〉とは何か 数学・哲学から始まる世界像の転換」(筑摩選書)西郷甲矢人/田口茂(著)

グリコのキャラメルよりもオマケを愛する心である。
「人は何で殺してはいけないのか」と問う心である。
一つの答えを求めるのではなく、問いを見つめ直すことである。
分からない、というのも一つの哲学である。
何でも言われた通りに納得し、目の前の事象をそのまま受け取ってしまうのは惜しい。
寺田寅彦は、「科学者とあたま」という随筆で、頭の悪さを推奨している。
「寺田寅彦 科学者とあたま」(STANDARD BOOKS)寺田寅彦(著)

分かり切ったと思えることでも、立ち止まって考えてしまう。
科学者は、そうした「呑込みの悪い朴念仁(ぼくねんじん)」でなければならない、と書いている。
「寺田寅彦随筆集 第四巻」(岩波文庫)寺田寅彦(著)小宮豊隆(編)

「いわゆる頭のいい人は、言わば足の早い旅人のようなものである。
人より先に、人のまだ行かない所へ行き着くこともできる代わりに、途中の道ばた、あるいは、ちょっとしたわき道にある肝心なものを、見落とす恐れがある。
頭の悪い人足ののろい人が、ずっとあとからおくれて来てわけもなく、そのだいじな宝物を拾って行く場合がある。
頭のいい人は、言わば富士のすそ野まで来て、そこから頂上をながめただけで、それで富士の全体をのみ込んで、東京へ引き返すという心配がある。
富士は、やはり登ってみなければわからない。
目は、いつでも思ったときに閉じることができる。
しかし、耳の方は、自分では自分を閉じることが出来ないように出来て居る。
何故(なぜ)だろう」
「俳句と地球物理」(ランティエ叢書)寺田寅彦(著)
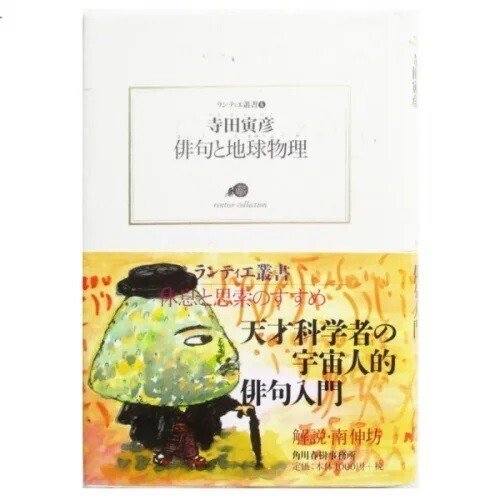
眠っていても危険を察知できるから、など思いつきの答えはできるかもしれない。
しかし、何となく見過ごしたり、気がつかなかったりしていることに疑問を抱く。
科学者に必要な才能は、分からないことを見つけることである。
もう一度いうが、セレンディピティというのは、日常化した思想を、思考法をもう一度見つめ直すことである。
松岡正剛のいうように、「知の編集術」と言い換えてもいいが、自分がどのような思想、思考法、文化に染まっているか見つめ直すことである。
その意味では、「知の相対化」であり、何よりも常識を疑い、他人のいうことを鵜呑みにしないことかもしれない。
今の人は、当たり前になっていて分からないだろうが、クリネックス・ティシューが出てきた時には、驚いたものだった。
柔らかさと丈夫さという相反する「常識」が2枚重ねにすることで解決されていた。
こんな簡単なことなのに、誰も製品にしなかったのである。
「起承転結」などという論理の運び方も日本独特だし、結論を周りからぐるぐると固めて行く手法である。
アメリカなどでは、ストレートに結論に向かって行く(同じ英語圏でもイギリスの論文とアメリカの論文ではストレートさが違う)し、ドイツでは、テーゼ→アンチテーゼ→ジンテーゼというように論理を進めていく。
イスラムの論理の進め方は、いまいち分からないし、北朝鮮の論理の進め方も、まるで違うようだ。
これに関しては、
Kaplan, Robert B. "Cultural Thought Patterns In Inter-Cultural Education."Language Learning,16(1 and 2), 1-20.
という有名な論文があり、次の通りである。
英語は、直線的パターンであり、セム語は、「並立構文」を使用する。
東洋諸語は、「間接性」によって特徴づけられており、「渦巻きのようにぐるぐる回る」といえるような「様々な脱線的な見方」をする。
ロマンス語は、脇道にそれたり、無関係な材料をとりいれる自由が大きいと特徴づけた。
ロシア語は、「構造的に関係している従属的な要素を挿入して拡充する」例だとしている。
論理というか談話の展開法も同じように考えられる。
【関連記事】
【雑考】垂直思考と水平思考
https://note.com/bax36410/n/nc041319885eb
【雑考】対位法的思考
https://note.com/bax36410/n/nef8c398b72cb
【雑考】複雑系思考法
https://note.com/bax36410/n/neaab25206650
【宿題帳(自習用)】ふと目を向けた風景、しゃがんだ時に見えるもの。
https://note.com/bax36410/n/nad27a9739ea4
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
