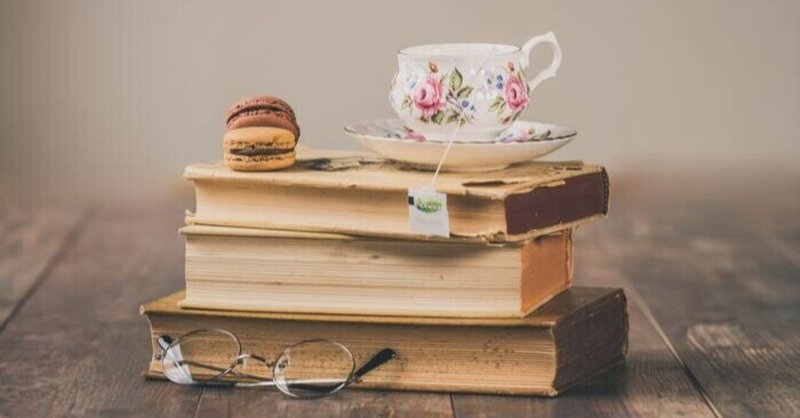
【本日の思いつきバックナンバー】「小牧幸助文学賞」版バックナンバー
【前書き】
自分の1日を、適宜、備忘録的につぶやいたり、メモ等を残しておくことで、今年の自分シーンへの振り返りのためとか、友人への近況報告になったりしてオススメかなって思います。
三日坊主でも続く日記と考えれば、案外、楽しいかもしれません。
つぶやくスタイルは、日記・随筆・エッセイっ風でも、五・七・五の俳句風でも、面白ければいいのかなって、そう感じます(^^)
みなさんは、日記・随筆・エッセイって、どんな違いがあると思いますか?
書いた本人が「これは日記」と言えば日記とも言えるし、「エッセイ」と言えばエッセイになるような。
例えば、エッセイは、随筆に似ているけれど、もうちょっと軽い感じのものって気がします。
だけど、自分の目でよく見たり、よく人のお話を聴いたり、読んだり耳にしたこと、その中で心の底から感動したり、感じたことを自分なりに深く考え、ある程度考えがまとまったら、ダラダラとした形ではなく、それをできるだけ簡単、明瞭にわかりやすく書き表すことが大切なのかなって気がします。
まあ、あまり堅苦しく考えずに、これまで、インプットしたものの中から、心に浮かんだことを、どんどん「エッセイ」みたいな形で表現して記事を書いてきました。
ここで、何かのテーマを日記・随筆・エッセイなどで書くことの意義を考えてみると、自分の思考を文章にして書き出すことで思考が整理できたり、それを読み返すことによって、自分の思考に対し客観的な視点を持てたり、そのため脳内だけで考えているよりも、より思考が進むといった利点があると思います。
そこで、必要な行動として、どんなテーマでも思考すること、書くこと、後で読み返すこと、読み返してまた考えること、また考えたことを書くことの繰り返し、要は、その習慣づけがメタ認知のために大切なんだなって、今回の作業で再認識した次第です。
振り返りは、とても大切で、書くことによる思考の外化・メタ認知の促進によって、自分ひとりの中で効率よく学習(=いろんな理解、思考)を進めることが可能になるなどの効果が期待できるから、みなさんも、お試しあれ!
さて、これまでに、その時々で、書けそうだと思ったテーマをベースにして、記事を書いていたら、結構シリーズ化していて、記事のストックも多くなってきたため、備忘録(バックナンバー)としてまとめてみました(^^)
【漫文】書物で世界漫遊
種村季弘さんの本に「書物漫遊記」なる異色の読書案内本があります。
「書物漫遊記」(ちくま文庫)種村季弘(著)

この本の内容を簡単に紹介すると、書物の頁を繰ると、そこから不思議な幻想世界への旅がはじまっているのが本。
何事もそうなんだろうけど、名著、奇書、珍本・・・価値があるかどうかなんてのは、人に訊くことじゃなくて、自分で決めることで書物めぐりの旅は続いていくはず。
また、角田光代さんの本に本との出会いのストーリーを描いた「さがしもの」という短編小説があり、
「さがしもの」(新潮文庫)角田光代(著)

その中のひとつの短編である「ミツザワ書店」のおばあちゃんの言葉に
「あんた、開くだけでどこへでも連れてってくれるものなんか、本しかないだろう。」
って言葉を聴くと、やっぱり、本って、すごいもんだなあ~って、素直に感心したり(^^)
日々の中で、私の中身が少しずつ増えたり減ったりかたちをかえたりするたびに、向き合う人やもの達との関係ががらりと意味をかえるんだろうね。
現実はドラマチックじゃないけど、まだまだ知らない世界はたくさんあります。
【関連記事】
文章を磨くには?
https://note.com/bax36410/n/n66a065882e28
文章から読者の五感に訴える表現法
https://note.com/bax36410/n/n62a5b1962dfb
【小品文】晴耕雨読(縦書きの国)
https://note.com/bax36410/n/n7e4d0c1ea2f4
【補講】テーマ「悪文」:短い語で十分なら
https://note.com/bax36410/n/ndc4356dc11bc
【「小牧幸助文学賞」版バックナンバー】
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(思わず考えちゃう近似式)
https://note.com/bax36410/n/n7481b1e546a8
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(ある日の朝)
https://note.com/bax36410/n/n7ebd07725ac7
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(雨の日の記憶)
https://note.com/bax36410/n/n126e9c45c205
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(夏の日)
https://note.com/bax36410/n/n3513bced71b6
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(罪悪感)
https://note.com/bax36410/n/n3a0f83c3f7b7
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(四季)
https://note.com/bax36410/n/nf825bfd7112e
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(かっこいい英単語を・・・(nine plus nine equals ?))
https://note.com/bax36410/n/n08baa3b4986b
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(思いがけない出来事)
https://note.com/bax36410/n/nf084d9245b78
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(俳句でつくる超絶短小説)
https://note.com/bax36410/n/nf3de6600b31b
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(換骨奪胎)
https://note.com/bax36410/n/nb99b094aedd3
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(思い出)
https://note.com/bax36410/n/n0e3d58c14a2d
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(楽府ぽくつくる超絶短小説)
https://note.com/bax36410/n/n841aac9ae38f
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(情景)
https://note.com/bax36410/n/ncb634e65cf4a
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(○○小説シリーズ)
https://note.com/bax36410/n/n9a72705125b9
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(世界)
https://note.com/bax36410/n/n9054fc7a4a57
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(断章)
https://note.com/bax36410/n/ne362aaa85915
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(朝食)
https://note.com/bax36410/n/n3623e2fc5f24
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(陰陽師)と【毎週ショートショートnote】強すぎる数え歌「急急如律令(急いで事を成せ)」のコラボ作品
https://note.com/bax36410/n/n0a67fc8e9d9b
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(追憶)
https://note.com/bax36410/n/n2c9ad79955d7
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(日常茶飯事)
https://note.com/bax36410/n/ndde0401abd07
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(あなたには世界がどう見えているか教えてよ)
https://note.com/bax36410/n/na889d8142d66
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(レミニセンス)
https://note.com/bax36410/n/n78f43dd8b060
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(叫び)
https://note.com/bax36410/n/n85cf15a6def5
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(不条理)
https://note.com/bax36410/n/nc639d04d33ba
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(4行定型詩的)
https://note.com/bax36410/n/n8e7931d9c02b
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(摩訶不思議)
https://note.com/bax36410/n/ne32c621408cb
【小牧幸助文学賞】20字小説応募作品集(日本語どうでしょう?)
https://note.com/bax36410/n/naca3ecf7c8dc
【コトバンク】
精選版 日本国語大辞典 「文学」の意味・読み・例文・類語
ぶん‐がく【文学】
〘名〙
① (古くは「ぶんかく」とも) (━する) 学芸。学問。また、学問をすること。
※懐風藻(751)序「旋招二文学之士一、時開二置醴之遊一」
※集義和書(1676頃)一「生付仁厚なる人は、文学せざれ共、孝行忠節なるものなり」 〔論語‐先進〕
② =ぶんしょうがく(文章学)
※百学連環(1870‐71頃)〈西周〉一「此文学なるものは如何なることより始り、如何なることに止るといふを論ぜんには、即ち Grammar なるものあり」
③ (━する) 芸術体系の一様式で、言語を媒材にしたもの。詩歌・小説・戯曲・随筆・評論など、作者の、主として想像力によって構築した虚構の世界を通して作者自身の思想・感情などを表現し、人間の感情や情緒に訴える芸術作品。また、それを作り出すこと。文芸。
※後世への最大遺物(1897)〈内村鑑三〉二「文学といふものは我々の心に常に抱いて居るところの思想を後世に伝へる道具に相違ない」 〔魏志‐王粲伝〕
④ 詩歌・戯曲・小説など文学作品を研究する学問。
⑤ 自然科学・政治学・法律学・経済学等以外の学問、すなわち、③や史学・社会学・哲学・心理学・宗教学などの諸分科を含めた称。
※風俗画報‐二四四号(1902)慶応義塾「新に大学部を置き、先づ文学、法律、理財の三科を教授し」
⑥ 令制で、内親王を除く有品親王に一人ずつ付けられ、経書を講授した官人の職名。主人の親王の品位により、相当位は従七位上より正八位下までの差がある。
※令義解(718)家令職員「文学一人」
⑦ 江戸時代、諸藩の儒者。
※日本詩史(1771)凡例「加レ之文学之職、賓客之盛」
精選版 日本国語大辞典 「小説」の意味・読み・例文・類語
しょう‐せつ セウ‥【小説】
〘名〙
① 民間に伝わる話や市中の話題を記述した、散文体の文章。正式の、改まった文章でないもの。中国の稗史(はいし)から出たもので、ふつうはある程度史実に基づいた話をさすが、あたかも史実のように見せかけた虚構の話をさすこともある。
※聖徳太子伝暦(917頃か)下「恐以二言不一レ経、覧者致レ晒、庶不レ遺二小説一、貽二彼聖跡一」
※俳諧・其雪影(1772)蕪村序「たとはば小説の奇なることは諸史のめでたき文よりも興あるがごとし」 〔漢書‐芸文志〕
② (novel の訳語) 文学形態の一つ。作家の想像力・構想力に基づいて、人間性や社会のすがたなどを、登場人物の思想・心理・性格・言動の描写を通して表現した、散文体の文学。一般には近代小説をさすが、国文学史では、古代の伝説、中古の物語、中世の草子、近世の読本などの散文体文学をもさす。
※西国立志編(1870‐71)〈中村正直訳〉一「その著はすところの書、小説あり、詩あり、戯曲あり」
※小説神髄(1885‐86)〈坪内逍遙〉緒言「我小説(セウセツ)の改良進歩を今より次第に企図(くわだ)てつつ、竟には欧土の那(ノ)ベル(小説(セウセツ))を凌駕し」
③ 自分の説をへりくだっていう語。俗説。
※蔗軒日録‐文明一六年(1484)六月二一日「東模書記求レ号、号希楷、作二小説一、不レ可レ道レ文也、狂言也」
④ 他人の説や世間に流布している説を非難の意をこめていう語。俗世の迷信。
※足利本論語抄(16C)里仁第四「朝夕は近き心ぞ。夕と取るは小説ぞ」
語誌特定のジャンルを指すものとして用いたのは、中国では①の「漢書‐芸文志」が古い。その内容は伝説や説話の類で、とるに足りない価値のないものととらえられている。日本では平安時代初期の「日本紀私記」や「聖徳太子伝暦」などに見える。
(2)近世に入り、唐話学の隆盛、中国の近代の文学に関する知識の浸透にしたがって、「小説」は、唐宋以降、特に明・清の白話小説を指すとともに、国文の戯作をも指すようになる。
(3)②について、novel 以外の関連する原語、fable, fiction, romance, story, tale 等に広げて考えれば、訳語としての「小説」は蘭学時代を含めて、坪内逍遙以前にもかなり一般化していた。
【後書き】
今さら読書のちょっとした覚書
https://note.com/bax36410/n/n07998af879d5
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
