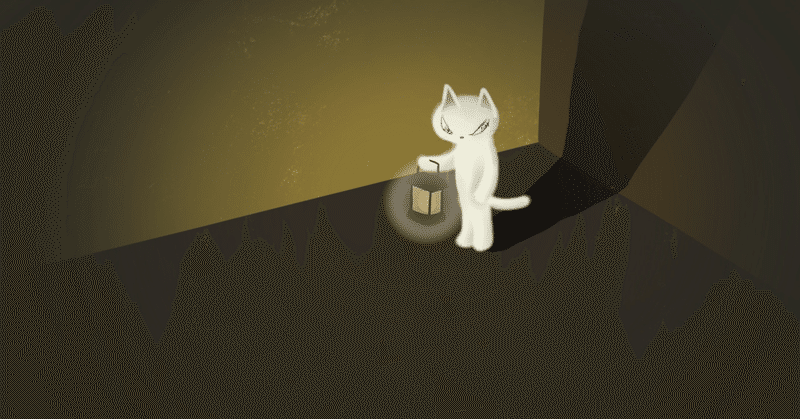
18禁じゃないスピリチュアル 緑のドア 〜暗中
こんばんは。id_butterです。
今日もただの脳内妄想、自己満足100%でお届けするので、必要のない人は全身全霊をもって避けてください。。。
▼前回
●アンside
真っ白な怒りにのっとられたわたしは、その後涙を流しながら、ヒース様にすらすらと嘘をついた。普段はヒース様と言葉を交わすのもやっとだったわたしの口から、ヒース様をどん底まで追い詰める嘘がすらすら出てきたのだから、憑依されていたとしか思えないけれど、これもわたしなんだろう。
サキ様がヒース様のあとを追って飛び出した時、とんでもないことが起こったとわかった。けれど、その時のわたしは笑いすら込み上げてきそうだった。真っ白な怒りにのっとられたまま自分が悪いことをしたなんて、これっぽっちも思わなかった。目に見えるすべてを、わたしと同じところまで堕としめ汚したかった。
わたしは、真っ暗な泥で満タンになった沼の底みたいなところで、息もできないでいた。
沼の底に差し込んだ一筋の光。
ふと我に返ったのは、アーニャ様の自殺を目撃した後のことだった。
アーニャ様の無事に涙を流している自分は、あの日以前の自分だった。
そんな自分がいたことすら、忘れていた。
アーニャ様にすがりつきながら命はあたたかいのだ、そうはじめて知った。
目を瞑って、自分を抱きしめる。
あたりまえだけど、わたしもあたたかいのだ。
わたしはわたしの中にいた。
かわいそうなわたしも、怒っているわたしも、抱きしめる。
わたしの中を支配していた真っ白な怒りは動きを止め、柔らかな光に変わっていた。
けれど、遅かったのだ。
アーニャ様の体から、いろいろな匂いがするようになったのはこのころからだった。
知らない服が増え、足が汚れていることすらもあたりまえになった。
目には何の感情も宿っておらず、その中はいろいろな存在が出入りする。
彼らはわたしという存在に何も注意を払っておらず、当然何も隠す気はなさそうだった。
恐怖はあったものの、逃げ出さなかったのはアーニャ様がどうしても愛おしかったからだ。たとえ空っぽでも。
過ごした日々の懐かしい残り香が、わたしの胸を締めつける。
痛くても、いいのだった。
わたしはわたしの中に在る証なのだから。
アーニャ様を喪う予感、どうしてもそれは消えなかった。
サキ様は、ヒース様は本当に気づかないのだろうか。
アーニャ様の形をした別人が目の前で笑っているというのに。
あの時のわたしに誰も気づかなかったのと同じ、ひとはひとなんてほんとうには見ていないのかもしれない。
目に映る世界が真実とは限らないのかもしれない。
●サキside
アンから聞いた話はすぐには信じられないような話だった。
今度こそ、口止めしたけれど、今回こそ必要ないだろう。
アンの中に起こったであろう何かには触れない。
けれど、今のアンは澄んでいて、嘘を言うようには見えない。
それは確信に近かった。
今度こそ間に合いたい。
焦る気持ちと、拭いきれない不安が重い。
先ほど城から届いた封書を開けて目を通す。
予想通り、塔の薬師候補者のリストだった。
出身地と年齢、経験、写真、薬師の師匠からの推薦状、情報が多すぎて余計に混乱する。どんな情報も「アーニャを傷つけない」保証をしてくれない。
何十通かの履歴書全部に目を通すのは時間がかかりそうだ。
そう思いながら、全部を持って立ち上がった。
ひとりで見るのはしんどいから、一緒にヒースにも見てもらおうと思ったのだ。
話しながら、考えよう。
アーニャのことを相談するかどうかも、それで決めよう。
とりあえず立ち上がって部屋をでる。
●ヒースside
部屋をノックする音がしたので、「どうぞ」と声を掛ける。
入ってきたのは、サキだった。
「ちょっといい?新しい薬師の件なんだけど。」
「もちろん。届いたのか?ああ、そこ座って。」
ちょうど気になっていたことだったので、サキに椅子をすすめる。
「一緒に見る、よね?」
そう言って笑うサキは困ってそうだった。
「そのために来たんでしょ。まぁ俺も何にもわからないけどさ。」
苦笑しつつも、思ったより分厚い紙の束に気が重くなる。
ふたりでとりあえず「あり」「なし」に分けていくことにした。
意見が「あり」で一致した場合だけ残すルール。
「なし」「あり」
「あり」「なし」
やってみたら、全然一致しなくて、残る履歴書がないんじゃないかと不安になるくらいだった。
残り10枚を切っていたとき、ふとある男の履歴書に目が止まる。
知っている顔だった。
サキと顔を見合わせる。
「あり?」「…ありでしょ、もちろん!」
その男は以前どこかの村で会ったことがあった。
じいちゃんの知り合いだったけれど、師匠についておらず独学で薬師になったという変わった経歴の持ち主で、何を考えているかよくわからないような男だった。そもそも「薬師」というカテゴリーに入っているかどうかも疑問で、変わった技術を持っていた。
村に住んでいるわけではなく山に住んでおり、週に数回村に降りてきて病人や怪我人を診るのと引き換えに食料や必要な物資と交換しているようだった。ぶっきらぼうでほとんど喋らなかったが、診察が丁寧なことは一目でわかった。あたりまえに腕がよく、村人から信頼されていた。
どことなくじいちゃんに似ていて、じいちゃんはなぜかその男を信頼しているように見えた。
じいちゃんが死んだときもその場に来ていたことを思い出す。
ありだ、そう思った。
思ったけれど、なぜか少しモヤモヤする。
じいちゃんとこの男はどんな関係だったんだろう。今更気にかかった。
そもそも、じいちゃんはなんでこの塔に出入りしていたんだ?
わかっていたはずのじいちゃんが知らない人間のように思えてきて、不安になる。
「…決まりかな。」
そうサキが念押ししてきたので、頷いた。
サキも不安そうに見えるのが不思議だった。
それなのに、他には選択肢がないことは明白なのだった。
「じゃあ、来てもらえるように連絡を取ってみるね。」
なぜか目の前にいるサキも見知らぬ女のように見えた。
見たことのない表情をしているのだった。
俺は何もわかっていなかったのかもしれない、なぜかそんなことを思う。
いつもの景色が、あたりまえの日常が、崩れ去っていくような予感がした。
▼続きます。
サポート嬉しいです!新しい記事執筆のためシュタイナーの本購入に使わせていただきます。
