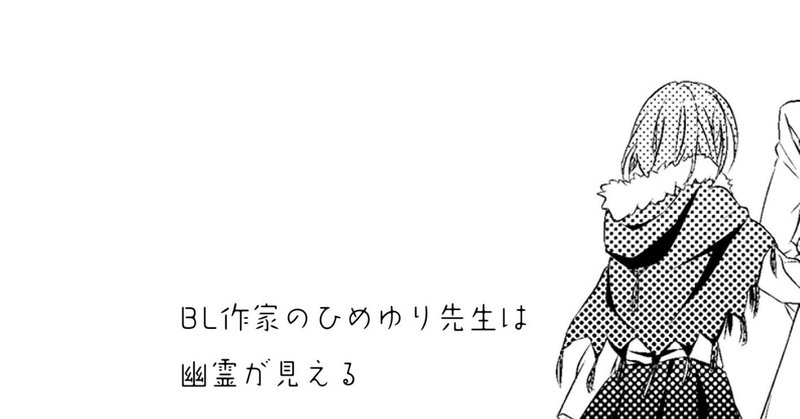
BL作家のひめゆり先生は幽霊が見える
BL作家のひめゆり先生は幽霊が見える。
でも、コミケ原稿の終わりは見えない。
「それでね、その、出るって評判の地下道の向こうにね! 見えたの! 白い服着た女の人が!」
ひめゆり先生のデスクの後ろ、作業用のちゃぶ台でそう言いながらベタ用の筆を握っているのは佐竹さんだった。ハイハイ、とひめゆり先生はいい加減にこたえる。
「こっちは黒い服だからベタよろしく!」
指先で飛ばしたペン入れ原稿を佐竹さんが慌ててキャッチする。
「ひめちゃん先生インク乾いてないよお!」
「乾いてないとかは甘え」
気合いでなんとかしなさい、とひめゆり先生はスパルタだ。
佐竹さんは大学の漫研サークルの後輩で、学食一週間分を報酬に夏原稿のアシスタントを引き受けてくれている。
サークル加入直後にスカウトしたのはひめゆり先生だった。平成も二十数年が経ち、アナログ原稿の手伝いが出来る平成生まれは絶滅危惧種保護対象となってしまった。
「先生、デジタル移行しようよ」
ベタがはみ出さないように神経を使いながら佐竹さんが言う。デジタルだったらバケツで一瞬なのに、とぼやきながら。「やあよ」とひめゆり先生はいつものように一蹴する。
「趣味のためにでかスペックのマシンも液タブも買いたくないもーん」
「iPadだっていいじゃん~」
「ATOKと一太郎搭載してから言ってちょーだい」
今は原稿で埋もれている、ひめゆり先生のデスクには、速さが取り柄のノートパソコンが一台ある。扱いはぞんざいだけれど、一応大事な仕事道具だ。
ひめゆり先生はBL作家であり、同人作家であり、女子大生でもある。最初の二つと、最後の一つは名前が違う。
「肩凝ったなー」
ベタを終えた佐竹さんが右肩を押さえて首を回す。その姿をひめゆり先生は振り返って見る。
「ねえひめちゃん先生ー、実際さー、幽霊にファブリーズってきくの?」
「気休め」
ひめゆり先生は手を伸ばして、佐竹さんの右肩を掴むと、時計の方を向かせた。
「でも、鰯の頭も信心っていうでしょ。佐竹さん、バイトじゃないの?」
「あっそうだった!」
慌てた佐竹さんが財布とケータイひっつかんで立ち上がる。
「んじゃ、バイト終わったらまた来るんでぇ、なんか必要なものあったらメールしといて!」
バイバーイ、と軽い調子で佐竹さんは1DKの部屋を出て行く。
「んーいってらっしゃーい」
伸びをしながら見送って、玄関のドアが閉まるのを見届けて。
ふぅ、と自分の左手、佐竹さんの肩をさわった手の平に息を吹きかけると、立ち上がって小さなキッチンに向かう。適当に塩で手を洗う。
「気休め」
でも、鰯の頭も信心からってね、とひとりごちて笑う。
佐竹さんは地下道で白い女を見たという。見ただけで放っておけばいいのに、ああやって吹聴するから、いつまでもすがりつかれるのだ。
キッチンの小さな窓から外を見ると、コンクリがゆらめくほど外は暑いようだった。
そのゆらめきの中に、歩いて行く、足だけ、が見える。
「夏が、来たなー……」
BL作家のひめゆり先生は幽霊が見える。
でも、それが本当に本物に幽霊なのかは、ひめゆり先生にもわからない。
ひめゆり先生のマンションの部屋が本格的な修羅場に突入して三日目。すでに足の踏み場はない。
時計は深夜の二時を回っている。ちゃぶ台では佐竹さんが一枚の原稿を眉を寄せて睨んでいる。
部屋には時計の音だけがしている。ひめゆり先生は、無音派だ。
「ひめちゃん先生、これ修正甘くない?」
佐竹さんが唐突に言うので、ひめゆり先生が振り返る。佐竹さんが持っていたのは、今しがた仕上げたひめゆり先生の原稿だった。流行りのジャンル。男同士。ちょうど、いたしているシーンだ。といってもひめゆり先生の原稿は大体がいたしているシーンだ。
でも、その中でも、結構渾身のシーンだった。
「えーそう? すごい頑張って描いたんだけど」
ちなみにひめゆり先生は、漫画作風は耽美かつハードだ。
「いやいやでもゲスト原稿でしょ?」
「そうだけどー……」
「あかんて!」
十八になったばかりのはずの佐竹さんは容赦ない。
「この夏また規制が厳しくなったっていうし、ひめちゃん先生のせいで頒布禁止くらったらどうすんの!? 炎上まったなし!!」
「直すわよお……」とひめゆり先生は項垂れる。
局部描写に過剰な修正をいれることは、ひめゆり先生には身を切られるよりつらいことだ。
私のきょくぶ……。丹精込めて描いた私の可愛いきょくぶ……。
ベタ修正をいれようとした原稿を、佐竹さんがもう一度取り上げる。
「どうせ合同誌ならスキャニングしてデータ提出でしょ。持ち帰ってうちでやっとくから」
個人誌収録する時にはこのままでもいけるかもしれないしね、と言う佐竹さんが、ひめゆり先生には天使に見えた。
睫毛もないけど眉毛も短いけど。
「お礼にコンビニいこっ!」
丁度お腹も空いてきて、絶好の夜食タイムだった。
「買い出しなら行ってくるよ?」
進捗を心配する佐竹さんが言うけれど。
「こんな時間に女の子ひとり歩かせられないよお」
物騒だしね、と言いながらひめゆり先生は伸びをする。少し歩いて気分転換をしたかった。
玄関先でひめゆり先生がむき出しの佐竹さんの腕に虫除けスプレーをかける。
「つめたっ」
「ファブリーズよりきくよ」
笑いながら二人で夜のコンビニに繰り出す。
十分ほど歩いた、近所のローソンは真白く明るい。ひめゆり先生はいくつかのお菓子と、飲み物を買い込む。佐竹さんはニキビを気にして栄養ドリンクも買う。
会計を済ませて袋を持って自動ドアの前に立とうとしたら、先に開いたので。
「あ、どうぞ」
ひめゆり先生が入店する気配をよけるために身をそらした。ら、佐竹さんが目を丸くしてたので、ん? とひめゆり先生が首を傾げる。
「ひめちゃん先生……」
スマホを持った佐竹さんがぽかんとしながら言う。
「今、だれもいなかったよ……?」
へ、とひめゆり先生が店内を見回す。確かに、誰かの、気配がしたはずなのだけど。
「先生、いこ」
ちょっと怯えたみたいに佐竹さんがひめゆり先生の腕に絡みついてきた。
可愛いなあとひめゆり先生は思う。ひめゆり先生は男×男至高主義者だけれど、ちゃんと女の子を可愛いと思う心も持っているのだ。
帰る道すがら、佐竹さんがひめゆり先生の耳元に囁く。
「ところでひめちゃん先生、あたしね、怖くて聞けなかったんだけど」
なあに、と優しくひめゆり先生が佐竹さんを見下ろす。
佐竹さんは神妙な顔をして言う。
「今やってるのゲスト原稿ってことは、個人誌は……」
にこっと明るく微笑んで、ひめゆり先生は残酷に言い放つ。
「これからだよ☆」
「うわーー!」
ぶっちゃけ幽霊より百倍怖い、と佐竹さんが嘆く。
ファブリーズも虫除けスプレーも、〆切にはきかない。
八月はもう、そこまで来ている。
ひめゆり先生は怖いものをたくさん見たことがある。
それでも一番怖かったものは何かと聞かれたら。
「そりゃーあんた……。オンリーイベントで何を間違ったか同日関西開催の別オンリーに搬入されちゃって……しかも気づいたの一般入場直前で……」
「ぎゃーー! 何それこわい!」
悲鳴をあげた佐竹さんがそのままテーブルにつっぷし次の瞬間寝息を立て始めた。
おいおいまだ23時だぜ、とひめゆり先生は思うけれど、仕上げ作業がたまるまで寝かせておいてあげよう、ととりあえず額の下になってる原稿だけ引き抜いた。
と、ひめゆり先生のスマホが着信を告げている。同じく地獄在中の同人仲間だった。
「へぇい」
ハンズフリーにして、机に戻りながらいい加減に返事をする。
『もうやだ聞いてよひめこ!』
携帯電話の向こうから、音量調節が馬鹿になったような友達の声。
さてはこいつも寝てないな、と一瞬で知れる。
『ここ数日ほんとラップ音がすごくて、寝ても寝ても金縛りでさあ!』
またその話か、とひめゆり先生は内心げっそりとする。同人仲間の彼女が借りている部屋が幽霊アパートであることはひめゆり先生はすでに何度も相談されていたことだ。
『どうしたらいいと思う!?』
「うーーん……」
作業用の椅子の背もたれに背中と首をあずけて、口を半開きにして天井を見る。
イマドキの幽霊は、通信機器とも相性がいいから、泣きそうな声を通じて、ひめゆり先生のスマホから灰色の煙が立ち上って頭上をぐるぐる回っている。
原稿前の徹夜続きが一番神経が過敏になってて、いろんなものが見える。でも、だからこそよくわからなくもなるのだ。
自分が見ているこれは、本当に「そういう」ものなんだろうか。
ただ、頭が、おかしくなった、だけじゃないのか?
「……金縛り、は、わかったけど」
かすれた声でひめゆり先生は言う。
「……あんた、原稿はあがったの?」
『まだ下書き』
その即答にひめゆり先生が沸騰した。
「寝るな!!!!!!!!」
電話に向けて叫んだら、灰色の煙も霧散する。
「金縛り以前の問題じゃ! おめーに寝る資格ねーーから!!」
『でもー! 怖くて原稿が進まなくて……!』
ダン、とひめゆり先生がデスクを叩いた。筆洗い用の水が震える。
その隣では、まだペン入れの終わっていない原稿が震えている。
『ひえ』
電話の向こうから、この世の終わりみたいに、恐怖に震えた声。
『印刷所からこの時間に電話……』
がっとスマホ掴んで、ハンズフリーなのにマイク部分に叫ぶ。
「幽霊がーーー!!! こわくてーー!!!! 原稿がーーー!! かけるかーーー!!!」
それだけ言って勢いよく切ったら、びっくりした佐竹さんが目をさまして言った。
「ど、どしたのひめちゃん先生」
「どーもしない」
レッドブルのポカリ割り、一気飲みして頬を叩く。
朝が本当の入稿デッドだ。
現実は大体、地獄よりつらい。
今年の夏コミも一応無事に本が出ることが決まった。神様仏様印刷所様。
イベントを翌日に控えて、ひめゆり先生はまだ原稿を書いている。一応ガワは小綺麗に整えて、イベント仕様にはしたけれど、ペーパーのため。
佐竹さんはただの泊まりだった。翌日の売り子要員で。
「新刊の予定も書くの?」
アプリゲームのガチャをまわす佐竹さんが先生の背中に尋ねた。
「いやー今回新刊一種だし……」
「じゃなくて小説の方だよ」
思わずひめゆり先生の手が止まる。
「あたしねー、ひめゆり先生、本当は小説が一番好き」
漫画も好きだけど、ってつけ加える佐竹さんに、ひめゆり先生は「……ありがとね」と振り返らずに答えた。
同人は、趣味だ。漫画原稿は、実入りがいいから書いている。あと、好きだから。
ひめゆり先生にとって、商業BL小説はもっとなんか、別のものだ。
「ね、ところで三日目お使い頼んでもいい?」
こっちが本命かとひめゆり先生が呆れた。
「いいけど今年は三日目こないの?」
「うーん。墓参り行くから実家戻れって叱られちゃってさぁ」
めんどくさい、とぼやく佐竹さんに、おー、行ってこい行ってこい、とひめゆり先生は手を払う。一日目の売り子さえしてくれたらなんでもいい。
「ひめちゃん先生はさー墓参りとか行かなくていいの?」
佐竹さんの問いかけに、ひめゆり先生はペーパー原稿から顔を上げずに言う。
「言ってなかったっけ」
なんでもないことのように、さらりと。
「あたし、親とかいないのよ」
小さい時に、家族みんな行方不明になってね、テンガイコドクってやつ。
「……ねーひめちゃん先生」
しばらく黙っていた佐竹さんが、ぽつりと聞いた。
「ご両親の幽霊とか、見たこと、ある?」
ひめゆり先生は手を止めて、空中を見上げながら答えた。
「それが、ないのよねー」
ずっと、もうずっと。
「全然ないの」
今はもう、両親の顔も思い出せない。
「……だから、もしかしたら、どこかで生きていてくれたらいいのになぁって、思うわ」
ひめゆり先生は幽霊が見える。
でも、それが本当に本物に幽霊なのかは、ひめゆり先生にもわからない。
ただ、それが幽霊でいい、と思っているから。
ひめゆり先生には幽霊が見える。
明け方ひめゆり先生は最後のトーンを張ってカッターを置いた。
「おっしゃーー!!!! キンコ行くわよ!」
「はーい先生!」
佐竹さんも飛び起きる。今日は決戦の日だ。
今、生きてる人間が一番強い。多分、それでいいんだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
