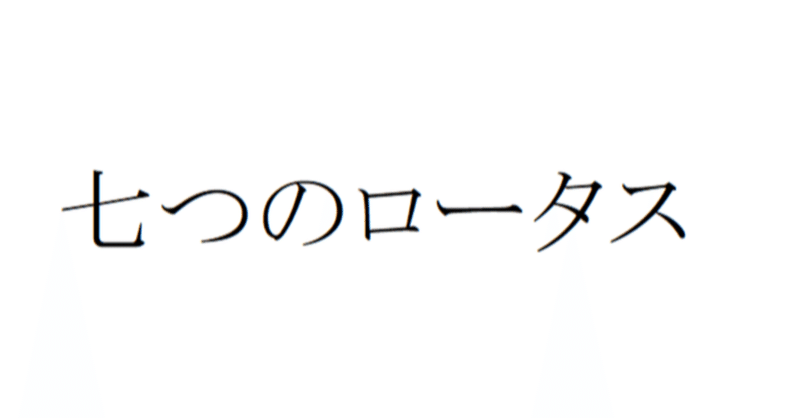
七つのロータス 第46章 スカンダルII
このまま全軍を率いて帝都に凱旋する。パーバティはスカンダルの言葉を、冷ややかな思いで聞いた。今までそれぞれの持ち場から多数の兵を引き抜いていただけでも、国境の守りは危険なまでに薄くなっている。一刻も早く兵を本来の持ち場に戻さねばならぬ時に、 無責任にも北方の兵を帝都まで連れていこうなどと。だが将軍や幕僚たちの前でそれを言う気はなかった。一兵も倒さずに、盗人に追い銭をやるようなかたちでご退去頂いて、なにが凱旋か。そんな言葉を付け足さずにはいられないと思ったからだ。夜中に黙って、自分たちだけで引き上げようか。そう考えていたところに、スカンダルの声が飛んできた。
「パーバティ殿、賛成していただけましょうか?」
「お断りだ」
思わず、そう答えた。スカンダルの嫌らしい微笑が引きつるのは愉快だが、困ったことになったのには変わりない。ここは肚を決めて言いたい事を言うしかない。
「本来の任地が気になる。こちらの仕事が片付いた以上、一刻も早く戻りたい。帝都で凱旋の式典に参列する名誉を軽んずるわけではないが、自分の名誉の為に国境の安全を危うくするわけにはいくまい」
スカンダルは笑顔を崩さないが、その口調に皮肉の色が混ざる。
「パーバティ殿は任務に忠実でいらっしゃる。武人として、帝都での凱旋式に勝る名誉はないと言うのに」
「敵に国境を破られる不名誉は、凱旋式の名誉で補うことはできまい。まして凱旋式で留守にしていたがために、敵の侵入を許したとなればなおさらだ」
スカンダルとパーバティ、二人の冷たい視線がぶつかり合った。
「将軍、わたしが指揮杖を持っているのをお忘れではないか」
「その指揮杖はプハラ奪回のためのもの。既に効力はない筈」
突然、スカンダルが高らかな笑い声をあげた。
「さすがパーバティ殿。感服した。名誉にも指揮杖の威光にも屈せず、帝国全体のことを考えておられる」
「考えているのは、自分の責任のことだけだ」
苦々しい思いも露わに答えると、スカンダルは手を打ってなおも言葉を続ける。
「けっこう、大変けっこう。将軍、試すようなことをして悪かったが、おかげで大変良い言葉を聞けた。そなたこそ武人の鑑だ」
息を詰めて見守っていた幕僚たちが、緊張を解いてゆくのがわかる。だがパーバティは笑顔の奥に、秘められた憤怒を見透かしている。
「わたしも自分の兵士をバグダに帰そう。臨時編成の一万二千の兵は、わたしが率いてグプタに帰す。この兵士だけでも凱旋式は充分やれる。パーバティ殿、そなたは必要な人数だけ連れて来ればいい。それなら国境にはなんの心配もあるまい。わたしと共に勝利の栄光を分かちあってもらえまいか」
いったい誰に勝利した?そう思いながらも、これ以上話をこじらせるべきではないと判断した。
パーバティが合意すると、スカンダルは解散を命じた。緊張から解き放たれた幕僚たちが、指揮官用の天幕から退出して行く。パーバティは天幕の出口をくぐりながら、スカンダルの視線を背中に感じていた。
朝霧の立ちこめる中、パーバティの部隊は天幕を畳み、出立の準備を進めていた。日の出前の薄明かりが、霧の中にぼんやりと満ちて、立ち働く兵士 たちの影は幽霊のように見える。パーバティはラムダと女騎士のラーナを連れて、作業の進み具合を確かめながら歩いていたが、撤収作業が終わると馬に跨った。
「整列でき次第出発する」
「将軍、スカンダルさまと帝都に向かわれるのでは?」
ラーナの驚き顔に、パーバティは声を出して笑う。
「あんな酔ったような話に付き合ってられるか。今は一刻も早く元の持ち場に戻ることだ」
同じく日の出前の一刻。バグダ守備軍も征北軍同様、出立の用意に忙しかった。宿営地の中では兵士たちが天幕を畳み、荷車に積みこむ作業に追われている。その中で指揮官用の天幕だけは、忙しく立ち働く兵士たちの声や物音と無縁だった。
「兵の入れ換えは滞りなく終わったな」
バグダ守備軍の五百人隊長たちが頷く。
「パーバティやガズニには悟られていないな」
「大丈夫です」
スカンダルは首肯する。帝都から送られてきた臨時編成の兵士は、バグダ守備軍に編入されたことに何の疑問も抱いてはいないし、バグダ守備軍の兵士たちは帝都に凱旋する部隊に組み込まれることを喜びこそすれ、疑問に思ったりはするまい。新編成の部隊のあちらこちらに少しずつ配置された兵士たち自身、バグダ守備軍が総入れ替えしていることには気づきようがない。
明日は帝都に向けて行軍を始める。それが全ての始まりとなるだろう。
パーバティが、日の出前に出立した征北軍とともに宿営地を去ったと知って、スカンダルは当然予測すべきことだったと思った。
「あの女らしい」
そう呟いてはみたものの、いざ事を起した時、北すなわち背後に敵を持つかもしれない、というのは気に入らない。一度は戻るよう使者を出そうかとも思ったが、 あの女がその程度で気を変えるとも思えぬし、余計な事をしてこちらの意図が露見しないともかぎらない。スカンダルは結局、パーバティを放置することにした。予定通りに全てが運べば、北から征北軍が駆けつける頃には何もかも終わっているはずだ。
たった今、宿営地から送り出したのは、本来の手勢であるバグダ守備軍。その内実は各五百人隊長を除いては、全てグプタから来た兵と入れ替わっている。彼等が全て宿営地から出れば、いよいよスカンダル自身が率いる一万二千の兵が、帝都への道をとることになる。
「行くぞ」
バグダへ戻る部隊を見送って、馬に跨ったのは、午に近くなってからだった。スカンダル自身が先頭に立ち、四列になった歩兵が続く。所々に騎兵が挟まって、弓兵、投石兵、遊撃兵らは輜重隊とともに最後尾につく。グプタへは通常の行軍速度で八日の距離。八日後には長年の望みが叶う。スカンダルはついつい馬を速めてしまいそうになるのを、押さえねばならなかった。望み。三年前、オソリオ征服帝の死の時には、巧く帝都から遠ざけられていたために果たせなかった望みだ。
プハラで敵を包囲していた間、そのことばかりを考えていた。プハラを奪回すれば救国の英雄になれる、皇帝の地位が一歩近づく、と。その時はこんなにも早く、機会に恵まれるとは思ってはいなかったのだが。まさか帝位を掠め取った男が、自ら口実を作ってくれると は。スカンダルは笑い声を口の中に押し留める。皇帝暗殺の噂は事実ではないかもしれない。しかし民衆が信じそうな噂が都合よく流れているならば利用すればいい。私は救国の英雄だ。指揮杖を持つ大将軍だ。ジャイヌを討てば、もはや自分が帝位に登ることに異を唱える者などおるまい。全てが自分のために動いている、とさえ思える。
街道の遥か先から、馬に乗ってやって来る者が見えた。互いに近づきながらも、その人物と出会うまでには長い時間がかかった。
「スカンダル様、帝都よりの使者にございます」
使者はスカンダルの姿を認めると馬を速め、近くまできて下馬した。
「何事だ」
「グプタにて変事。先帝ナープラ幼少帝暗殺の嫌疑を持たれた摂政のジャイヌは、皇帝陛下自らが差し向けた捕吏に手向かいしたため斬られました」
「なんだと!」
誰かに先を越された!その衝撃が脳天を撃った。我が望みはまたも絶たれたか。体から力が抜けて行く気がした。馬を止めたまま、何事も口にすることができず、長い間使者を見下ろしていた。
「ともかく、我らも帝都へ向かう途中。変わりなく道のりを進めることにしましょう。使者殿も、ぜひ同道していただきたい。道々お尋ねしたいこともあるかもしれません」
ようやくの思いでそれだけ言うと、馬を進める。使者も再び馬に跨り、スカンダルの左にやや馬を下げ気味に並んだ。
使者に口を挟まず、勝手に喋らせているうちに、新たな望みが湧いてきた。誰だかわからぬが、ネ・ピアかハジャルゴだろうか、ジャイヌを排除した相手は、新帝のパーラをそのまま担いだ。だがパーラはそもそも、先帝を暗殺したジャイヌによって擁立されたのだ。つけいる隙はある。そうだ、諦める必要はないのだ。 相手は誰かまだわからないが、ジャイヌとパーラを排除するつもりで立てた計画をそのまま進めればいい。必ずや帝位はこの手中に転がり込む。
スカンダルは一通りの話を終えた使者に質問を重ねながら、道のりを進めた。計画に訂正を加える部分を探すための質問だったが、何一つ微調整する必要すらなさそうだった。
もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。
