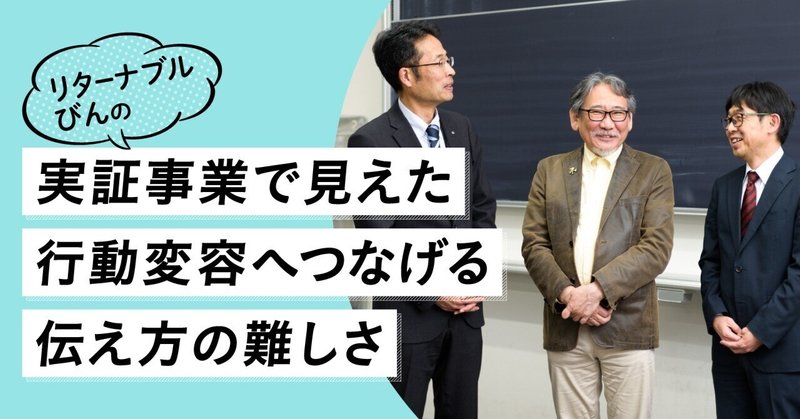
リターナブルびんの実証事業で見えた行動変容へつなげる伝え方の難しさ
私たち日本ガラスびん協会では、リターナブルびん・びんリユースの仕組みの価値を再発見・再定義する活動『SO BLUE ACTION』を推進しています。
今回はその一環として2022年から2023年に実施された、東京家政大学との産学連携の取り組みである、リターナブルびん・びんリユースの実証事業『be draw project』についてご紹介したいと思います。
本プロジェクトでは、東京家政大学の造形表現学科および環境共生学科の学生が、リターナブルびん入りミネラルウォーター『足柄聖河』を学内(板橋キャンパス)で販売し、校内におけるCO₂排出量削減効果の計測と可視化を試みました。プロジェクトのコンセプト策定、プロジェクト名称とロゴの開発といったデザイン制作からCO₂排出量削減効果の可視化まで、一連のプロセスを学生たちが主体となって実施しています。
このたび3月に終了した本プロジェクトについて、東京家政大学 造形表現学科の宮本真帆准教授(以下、造形表現学科 宮本)と環境共生学科の井上宮雄准教授(以下、環境共生学科 井上)、日本ガラスびん協会からSDGs推進ワーキンググループの辻委員長(以下、SDGs推進WG 辻)の3名で、内容を振り返っていただきました。

※be draw projectのリリースはこちら
https://glassbottle.org/glassbottlenews/3682
※足柄聖河についての記事はこちら
https://glassbottle.org/glassbottlenews/3453
※be draw projectの結果レポートは2024年6月に日本ガラスびん協会のホームページで公開予定です(2024年5月現在)。


出前授業の大きな反響を得て、
動き出した産学連携プロジェクト
-今回の「be draw project」を始めたきっかけを教えてください
(造形表現学科 宮本)
日本ガラスびん協会さんより、東京家政大学でガラスびんのSDGs貢献に関する出前授業を開催する打診を受けたことが最初のきっかけです。
学生には大学の授業だけでなく、さまざまな人の話を聞き、考える機会を持ってもらいたいと考えていたので、お話をいただいた時は「面白いな」と思い、お願いすることにしました。
私が受け持つ造形表現学科はデザインなどを学ぶ学科ですので、出前授業ではガラスびんを学ぶ座学のほか、回収されたガラスびんを細かく砕いたカレットを使ったワークショップも行ってもらいました。
この出前授業が学生にとても好評だったことから、出前授業を実施いただいた日本ガラスびん協会のSDGs推進ワーキンググループのみなさんと、大学のキャンパス中で実際にびんリユースの仕組みを構築し、どのような結果が得られるのか実証事業をしてみようという話になりました。
実証事業を行うためには学校全体を巻き込む必要がありますし、結果に対する考察も必要ですから、環境共生学科の井上先生にも協力を仰ぎました。

(環境共生学科 井上)
環境共生学科が目指しているのは、環境に優しい取り組みを自発的にできる人材の育成です。今回、宮本先生からお話をいただいた時、普段は関わりが少ない学科とのコラボレーションで産学連携プロジェクトを実施することは、学生にとって貴重な経験になるし、とても面白い試みだと思い、二つ返事で引き受けました。
(SDGs推進WG 辻)
私たち日本ガラスびん協会の出前授業の内容は、ガラスびんの原材料から製造工程、そしてリサイクル・リユースによるCO₂排出量削減効果にいたるまで多岐にわたっていますので、出前授業を行う大学や学科に合わせて内容を取捨選択して構成しています。理系の大学であれば製造工程をメインにお話しますが、今回の東京家政大学さんでは身の回りの生活にフォーカスしてお話ししたところ、とても良い反応をいただけました。その結果、実証事業を進めることができたので、とてもありがたかったです。

-今回のプロジェクトは学科のカリキュラムとは別に実施したのですか?
(造形表現学科 宮本)
東京家政大学では、学生の自主的な活動を単位として認める仕組みがあります。今回のプロジェクトも、学生が関心を持って自主的に取り組んでもらえれば単位化できますし、単位になれば、学生はより時間をかけて取り組むことができ、理解も深まります。
私たちは学生の関心をさらに高めるために、辻さんに実証事業の説明会をお願いしました。
(SDGs推進WG 辻)
最初の出前授業はガラスびんの一般的な知識を中心とした内容でしたが、今度はプロジェクトへの参加予定の学生を対象として、びんリユースの仕組みや環境負荷の低さなど、実証事業の内容に即しながら、リターナブルびんの可能性やガラスびんの魅力をより深く知ってもらえる内容にしました。

リサイクルとリユースの違いを
知るところから始まった実証事業
-学生はびんリユースの仕組みについて知っていましたか?
(環境共生学科 井上)
今回のプロジェクトに参加した本学科の学生の半数以上は、リターナブルびんを使ったリユースの仕組みをほとんど理解していませんでした。一方、プロジェクトで実施した本学学生に対するアンケート結果を見ると、びんリユースによってCO₂が削減されることについては半数以上の学生が知っていたようです。
(造形表現学科 宮本)
リターナブルびんについては世代間ギャップを感じましたね。
私たちが子どもの頃は、びんリユースの仕組みは当たり前に存在しており、飲み終わったガラスびんを酒屋さんに持っていけばデポジットでお金がもらえたので、みんな喜んで持っていきました。普段の生活で自然と、ガラスびんは洗って再度使用できることを学んでいたわけです。
今もリターナブルびんは数多く世の中に流通していますが、私たちの身の回りでは、びんリユースの仕組みを体感する機会は少なくなっています。学生たちは普段大学の授業で環境問題について学んでいますが、実はリサイクルとリユースの違いをきちんと理解できていないということが出前授業を通してわかったのです。

(SDGs推進WG 辻)
リサイクルをしても、生まれ変わった商品を最終的に捨ててしまうのなら、それは環境負荷になってしまいます。カラスびんは何度でもガラスびんにリサイクルすることができ、永続的に資源循環ができる。それこそがリサイクルの理想形です。そして、環境負荷軽減という観点をさらに突き詰めていくと、洗って繰り返し使うリユースの仕組みの重要さに気が付きます。
残念ながら、びんリユースの仕組みは社会から少なくなっています。学生が知らないことが悪いのではなく、私たち年長者がそういう社会にしてしまったのだということに気が付いて、反省しなくてはならないと思うのです。
(環境共生学科 井上)
今回参加してもらった学生、特に環境教育インストラクターの資格を取得している学生は、環境問題に対する意識がとても高く、たくさん勉強しています。
しかし、数多くの学生が実際には環境問題に対する行動まではできていない状態でした。だからこそ、「この機会を生かしたい」と意欲的にプロジェクトに参加してくれたと思います。

学生が苦労した
CO₂排出量削減効果の可視化
-プロジェクトを進める上で苦労した点を教えてください
(造形表現学科 宮本)
初年度は、『be draw project』というプロジェクト名称、ロゴとポスターの開発を行い、リターナブルびんの販売開始は11月からになりました。1年で一番ミネラルウォーターが売れる夏を逃してしまったことは、実証結果に多少なりとも影響があったかなと思います。

(環境共生学科 井上)
環境系の学生にとっては、クリエイティブ制作の現場に携われる機会はとても貴重なので、良い経験が積めて良かったなと思っています。クリエイティブの制作以外にも、この実証事業を通して学生の意識が変化したのか、行動変容ができたのかを調べるために、学生へのアンケートも行いました。
プロジェクトの最後には、実際に実証事業でどれくらいのCO₂排出量が削減できたかを分析し、可視化にもチャレンジしてもらいました。分析には、製品やサービスの原料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通しての環境負荷を定量的に評価するLCA(ライフサイクルアセスメント)という手法を用いたのですが、これがとても難しかったです。
学生にとって、LCAによる分析や考察は初めての取り組みでしたので、辻さんから提供いただいたツールや資料がとても助けになりました。
(SDGs推進WG 辻)
LCAの分析ツールに関しては、私たち日本ガラスびん協会と同じ業界団体であるガラスびん3R促進協議会が2021年にまとめたデータがありましたので、それを使っていただきました。
(環境共生学科 井上)
また分析結果に対し、「どのくらいCO₂排出量の削減効果があったのか」「この数値をどのように解釈すればよいのか」「そこから何を読み取り、報告書としてまとめればよいのか」といった点でとても苦労していたようですが、こうした経験はなかなか得られないので、学生にはとても良い機会になったと思います。

伝えて、アクションを起こしてもらうまでの間には
大きなギャップがある
-今回のプロジェクトを総括してください
(造形表現学科 宮本)
実証結果をまとめたところ、販売量およびリターナブルびんの回収率が想定を下回ったため、今回、CO₂排出量の削減という意味では目覚ましい効果は得られなかったことがわかりました。だからこそ、環境課題の解決は簡単なことではなく、工夫を凝らさなければならないということを学べたと思います。そして何よりも、人々の行動変容がいかに難しいかを学生自身が実感できたことに、大きな成果があったと思っています。
実証中は販売量や回収率を上げるために、「こうした方が良いのではないか」というアイディアが学生からたくさん出てきました。そこでいくつかトライしてみるのですが、なかなかな上手くいきません。
校内の全学生に行ったアンケートでは、半数以上がガラスびんの環境へのやさしさを理解していました。しかしリターナブルびんの購入にはつながらなかったのです。いま環境課題となっているものが、なぜ環境課題のままであり続けているのか、プロジェクトを通じて学生自身が痛感したことでしょう。
私の受け持つデザインの分野で言えば、「伝えて、アクションを起こしてもらうまでの間には、大きなギャップがある」ことを学べたのは貴重な体験になったと思います。
(環境共生学科 井上)
私の担当する学生の多くは、環境に対して危機意識を持っています。しかし、それがどれほどの危機なのかはぼんやりとしていたと思います。
今回、プロジェクトに参加したことで、危機感がとてもクリアになったのではないかと感じています。リターナブルびんによるCO₂排出量削減効果が具体的な数字として見えたことで、ガラスびんに対する見方が変わったという学生もおり、今後はガラスびんを積極的に利用したいという意識変化も起こすことができたと思います。
しかし、宮本先生も仰っているように、プロジェクトの当事者たちの意識変化はできましたが、学校全体での行動変容という点ではまだまだ課題が残りました。この難しさを知るということも含めて、学生の意識変化ができたのは成果だったと思っています。

(SDGs推進WG 辻)
私は今回のプロジェクトで、『足柄聖河』がバンバン売れて、CO₂排出量削減に大きな効果を発揮することを期待していましたが、いざ蓋を開けてみれば、一番ミネラルウォーターが売れる夏を逃してしまったとはいえ、販売量とリターナブルびん回収率が想定より低かったという結果を突き付けられました。
実証中、日本ガラスびん協会内でも「容量が多すぎるのではないか」「商品を変えてみよう」など、さまざまな意見が出ましたが、本プロジェクトはリターナブルびんの良さを知ってもらい、存在意義を高めることが目的ですので、今回のためだけの変更は意味がないと判断し、商品の変更は行いませんでした。
結果的には、ガラスびんの良さを知っても、知ることだけですぐに行動変容には至らないという現実が浮き彫りになりました。この本質に気付けたという点で、今回のプロジェクトはとても意義があったと思っています。
(造形表現学科 宮本)
もう一つ浮かび上がった課題に、ガラスびんの良さを理解しても、びんリユースの仕組みまでは理解できなかったということがあります。学内にある分別回収用のゴミ箱に、リターナブルびんが入れられていたケースがいくつもありました。分別回収とリターナブルびんの回収を同じものだと勘違いしたのだと思います。
リユースとリサイクルの違い、つまり、回収された先の工程をどうやって知ってもらうか。その部分まで理解してもらうのはとても難しいと思い知らされました。

予想と違った結果から見えてきた
リターナブルびんの可能性
-今後、リターナブルびんを普及させることは難しいのでしょうか?
(造形表現学科 宮本)
ポイントは口コミだと思っています。
プロジェクトに参加している学生は、出前授業を通してリターナブルびんへの理解を深め、周りの友だちにも伝えてくれました。しかし、口コミが彼らの周りで止まっていては、大きな流れになりません。その先へどうやってつなげていくか。その仕組み、伝え方を工夫することでまだまだ可能性があると感じました。
(環境共生学科 井上)
今の学生は環境問題へとても高い意識を持っています。
今回のプロジェクトへの熱量もとても高く感じましたし、この経験を糧に、環境問題に対する行動の大切さを実感できたと思います。こうした取り組みを継続することで、さらに学生の意識変化、行動変容の輪を広げていけるのではないかと感じました。
(SDGs推進WG 辻)
今回のプロジェクトを通して、伝え方、そして、その後のプロジェクトの浸透のさせ方にまだまだ工夫の余地があることを思い知らされました。
とはいえ、理解して行動に移した学生がいたことも事実です。今後は、伝え方に工夫を凝らすことで、プロジェクトをさらに力強く推進していけるのではないかという手ごたえを感じました。

造形表現学科
宮本真帆准教授

環境共生学科
井上宮雄準教授

SDGs推進ワーキンググループ
辻良太委員長
