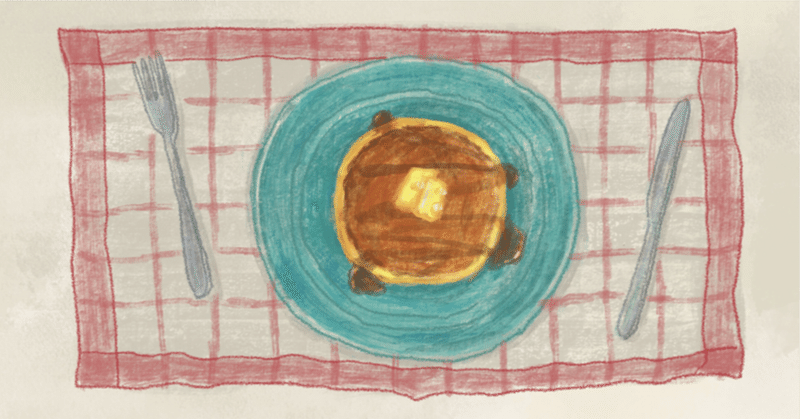
【小説】煩いの食卓
どれだけ、周りが己を否定しようと、自分だけは自分を守らなければと思いたかった。
「バスケなんか、楽しくやれてればそれでいいって思っちゃうんだけど」
つい、口をついて出た言葉に葵は驚いてしまった。彼はおそるおそる航希の顔を見る。いや、見ることはできなかった。汗が額を伝い、手に持っていた棒アイスから溶けた水滴が地面に落ちた。
「いや、それはそうとして、あんなきつい練習がんばってる俺らすごくね?」
「それはそう……」
落ちたアイスの水滴は元に戻らない。小さくなり続ける氷を葵は口に含ませた。熱くなった舌がアイスをどんどん溶かしていく。航希のため息が聞こえた。太陽が眩しく輝き、葵は真っ黒い影を伸ばした。
バスケ部の引退を目前に、葵のもとへその話はやってきた。彼の能力を見込んで、バスケ部が強いことで有名な大学からスポーツ推薦が届いたのである。時間を空けることなく部員の耳にその報せが入り、葵はすごいじゃないかと周りから囃し立てられた。もちろん、そのような話は彼にとってありがたいことだった。進路のことでとりあえず不安になることはないという状況に身を置くことができるのは、一般的な受験生から見れば十分に贅沢であるからだ。彼のそうした状況に嫉妬の目を向ける人間もいたかもしれない。そういうことで、一旦は部活に全力を尽くすことができ、葵はレギュラーの座を奪われることなく引退した。
大学の話によれば、秋までに入学するかどうかを決めてもらえばよいということだった。大学でもバスケを続けるのならば喜んで試験を免除してやるというのは、決して悪いものではない。甘い蜜のかかったパンケーキのように、魅力に溢れている。この皿が永遠に運ばれてくることを除けば。葵は書類を見つめながら、胃もたれを起こしそうになっていた。どうしたものかと机に突っ伏す。
航希はバスケを続けるのだろうか?
ふと、彼の脳裏にそんなことが浮かんだ。すぐに白旗を挙げないで、どこまでも隣に立とうと追いかけてくる航希のことが気になった。クラスが違うので引退してから会っていなかったが、葵は彼と話がしたくなった。
「逆に、バスケ続けないの?」
航希の返答はありふれたものだった。
「俺はおまえがバスケ続けるんだろうなって思ってて、だから大学でもバスケやろっかな……みたいなさ。ほら、大学どうしで試合があれば戦えるじゃん」
「あ……たしかに……」
その目には寸分の濁りもない。葵はそのような単純さに飽き飽きしていたが、同時に発言者が彼だからこそその単純さに救われる思いさえあった。自分がいるから、バスケをやる人がいるということ。スリーポイントシュートの練習に付き合ったり、葵の動きを完全に読み切りたった一度の瞬間ボールを奪ってきたりした航希の熱心さに嘘はない、葵はそう確信した。勝てないからなどと言って敬遠せずに真剣に葵と向き合ってくれるのだという希望が心の中に沸き立った。
「せっかく大学側から話をしてくれたんだから、やらないほうが悪いよな」
葵は航希を信じ続けることにした。翌日、書類に名前を書き、印を押してそれをポストに入れた。航希がバスケを続けるから葵もバスケを続ける。互いに切磋琢磨して技術を高め、試合でそれを見せつける。食べ飽きたパンケーキも誰かと一緒なら、新しい味わい方を見つけられるはずである。まだ見ぬ未来に思いを馳せる葵は、ひとり体育館でシュートを打ち続けた。
大学に入学した葵を待ち受けていたのは、苦痛だった。ともにスポーツ推薦でここに来た部員たちは葵よりも腕が立っていた。戦績を思い出してみれば、高校時代は県大会で優勝したものの、周りは全国大会で優勝を争っていたレベルの者ばかりで、あるいは海外にバスケ留学をしていた先輩もいるのだという。彼らに自由は存在しなかった。バスケひとつに心身を捧げた者たちだけがここにいた。そして、ここでも全国大会優勝を目標に掲げ、そのために部員たちはあらゆるものを投げ捨て、バスケに全てを投資した。時間、思考、行動、食べるものも見るものも。何から何までバスケに支配されていった。優勝するための積み重ねである。
葵はただ、バスケだけを続けるつもりで進学した。そのような精神統一を図らずとも彼は自身の技術が劣らないと思っている。最初こそは優勝するためなのだ、一試合でも多くできるようにするためなのだと取り組んだ。そうすれば、航希と再び戦えるはずだと信じたからである。こうして彼はバスケに身を捧げる人間になった。
このバスケ部には半年に一度だけ休みが与えられる。そうしたたまの機会に葵は航希と会い、近況報告会のようなものをしているのだった。
「俺もN大バスケ部に入ったよ。部員少なくて大変だったところに、俺らの代が入ったので、急にめちゃくちゃ増えて大変らしい」
「この前五大学合同練習試合でレギュラーで出れた!あのときのスリーマジでおまえに見せたかったわ」
「そういえば、俺のとこのマネージャーでひとりあの女優に似てる人がいてさあ……」
「なんかもう俺単位けっこう落としててヤバいんだよね、練習多くて勉強ぜんぜんできてなくて」
「で、さすがにもうバスケはいっか〜って言ってやめたんだよね、1年しかやってないんだけどさ」
「えっ」
あっさりと告げられ、葵はその事実を咀嚼するまでに時間を要した。
「や、やめたの?」
「おぉ、やめたやめた。うちのバスケ部強くないからおまえの学校と試合なんかできそうになかったのよ」
「はあ。そうなのか」
2年の夏だった。航希の所属するチームが弱いために、彼はバスケを続ける気力をなくしてしまったのだ。それならば仕方がないかと葵はやりきれなさを抱えながらも飲み込んだ。それにしても、精神的支柱を失ったことは確かではある。航希がいなくても頑張れるのだろうか、そのような不安が渦巻いた。この1年、葵はストレスですっかり気が削がれていた。それでも頑張れたのはバスケをする航希の存在があったからだった。とぐろを巻いた泥のような不安が心の奥底に鎮座する。テーブルの下で葵はひっきりなしにシャツの裾を掴んでいた。しわがつく。しわがついてもぎゅっと固く掴み続けた。
彼には彼の事情があるのだろう。そう割り切っていたものの、やはり本気で信じ込むには無理があった。葵は、航希と会うことに抵抗を感じ始めていたのだった。彼からメールが届く。受信フォルダが未読の通知で溢れている。携帯はひとりでに震え続けた。
なぜ、自分だけが縛られなければならないのだろうか。葵は自問自答を繰り返した。幼い頃から、運動神経が良いと褒められ、スポーツをすれば大抵のことはうまくできるこのセンスを、なぜ不幸だと思わなければならないのか。楽しくやりたいだけなのだ。周りの友だちはみな、葵を敵わない相手だと決めつけて去っていった。その度に、全力を出す自分が悪いのかと葵は自責の念に駆られた。バスケというスポーツと出会ってもなおその気持ちがなくなることはない。強くなるために苦しい練習や習慣にさらされることにも飽きた。そのような中で、航希という人間が葵の目の前に立っていたのだった。彼はいつまでも自分に立ち向かってくる人間だと信じたかった。そして信じた。信じて疑わなかった。
それがたった今破られたのである。泥のような不安に火がつけられた。轟々と燃えていく感覚が葵を覆った。不安は音を立ててバラバラと崩れ落ちる。パンケーキが運ばれてくるテーブルをひっくり返した葵は、隣から去っていく航希をじっと見つめた。
葵は、小さな広告代理店で働いて5年になる。最近はプロジェクトのリーダーを任されることが多くなってきた。また、コピーライティング術を徐々に体得してきて、賞をもらうことを目標にできるくらいに成長していた。仕事に対して純粋に楽しいと思えているのは幸せなことだろう。
「谷さん、次の企画のやつなんですけど。この映画知ってます?」
早足でこちらに駆けてきた映画好きな部下から差し出された資料を受け取る。10年ほど前に公開された洋画で、花火が星空に向かって打ち上がるシーンが印象的な作品である。
「あ〜。観たことあるかもな。あんまりだったけど」
「えっ!私これ好きなんだけどなあ」
友人関係が永く続かないことを描いたこの作品は葵にとってある種のトラウマともいえるものだった。高校時代のことなど記憶が微かにしか残っておらず、なぜそのような評価を下したのかも忘れてしまっていたが。
「これリバイバルするみたいで、また谷さんのチームで作るって話が出てました」
「そっか。これまた観ないとだね」
「今度は好きになってくださいよ?見どころ教えますから」
この作品を好きだという人間がこの部下以外にもう一人いた。葵はその人物を脳裏に浮かべてみようとしたが、忘れてしまったものは取り戻せなかった。
どんなスポーツをやらせても高い能力でこなすことのできる男はプロバスケ選手になるはずだった。だが、どこかで道を踏み外してこんなに小さな広告代理店で働くことになるとは、傍から見れば不幸も甚だしいところである。葵はバスケに向けるその善良さを事故によって失ってしまった。何かしらの突発的な事故。人々はそう考えることで葵の不幸を悔やんだ。
その夜、残った仕事を片付けた葵は帰宅し、ハイボールをグラスに注ぎ、次のプロジェクトの要である映画を観始めた。何の変哲もない物語が進む。少年2人が犯罪に手を出し、それでも友だちでいようと花火を背に約束を交わす。馬鹿だな、と思った。だが、あの日と違って悪くはないとも思った。いつか失われてしまうものだとしても、そのときが輝いていることに意味がある。葵はテーブルに頬杖をついた。ふっと笑みがこぼれた。何の因果か、自分をこのような不幸に陥れた人間がいる。それに恨むでもなく、ただその事実が存在しているということに安堵を覚えていた。その気持ちにおかしさを感じ、葵はいても立ってもいられなくなった。飲みかけのハイボールに卓上にあった蜂蜜をドバドバ入れだし、それを一気に飲み干した。クラっとするほど甘い。葵は、ぐらつく視界の中で、パンケーキを見た。
「もういいよ」
と呟くと、パンケーキはテレビの画面の中に吸い込まれていった。ダイナーにて座る2人の姿とともに、パンケーキが1皿置かれている。背の高い少年のほうがナイフとフォークを器用に使って分け始めた。そして、2人でそれを食べた。甘い蜜が染み込んだパンケーキは、とても美味しそうに見えた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
