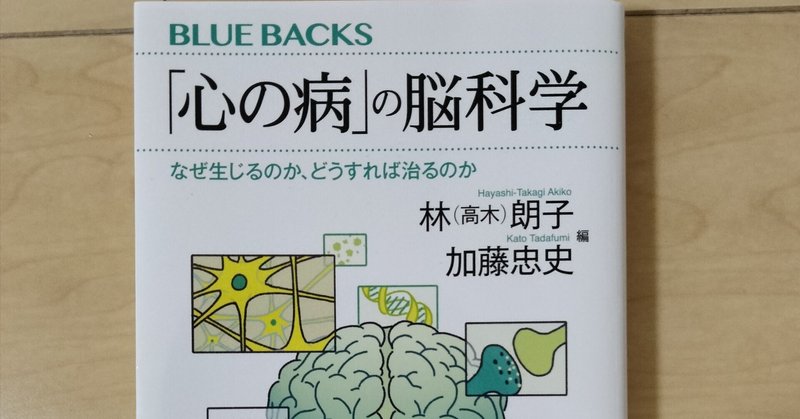
子どもに新しい友達が必要かもしれない
こんにちは〜😊青野です。
最近インスタの広告で、癒やし系ロボットの宣伝が多く上がるようになりました。
キャッチコピーとしては、会社のストレス軽減にとか、お年寄りの相手、子どもの遊び相手としてお勧めされています。
私は、ぜひADS(自閉スペクトラム症)のお子さんにこのロボットたちをお勧めしたいです。
おそらく定型発達の私にとって、挨拶することは、とても簡単なことです。子どもの頃から、親や先生にその様に躾けられ、指導されて育ったし、苦痛に思ったことはありませんが、世の中には、
人の目を見て挨拶することが、とても苦痛で苦手な人がいる
と言うことを、最近、学習しました。
それは、ちょっと照れ屋さん。と言うレベルではなく、本当に出来なくて、苦痛らしいのです。
私の人生の中で、そう言えば、あの人もこの人もASDだったのかも知れない。と思うことが増えました。彼らの共通点として、視線が合わないこと、人間関係が薄くなりがちで、孤立しやすい点があります。
人は、視線が合うことで、コミュニケーションを取っています。それは、何故かというと安心感が得られるからです。
そして、視線が合わないこと、挨拶が出来ないことのデメリットは、無視されたと、他人が思いやすい。ということです。子どもの世界だと、それがいじめにつながることもあると思います。(もちろん、環境が良くて1度も嫌な体験はしたことが無いよ。というひともいるかもしれませんが)
そして、その視線を合わせられない原因は、実は、脳の中の問題ということが、科学的にわかってきたということです。単に、内気だからとか、気持ちの持ち方ということでは無さそうです。
第11章ロボットで自閉スペクトラム症の人を支援する―人間には出来ない早期診断、適切な支援が可能に(p229〜)
■ASDの人たちにとって、人間の顔は刺激が強すぎる(p231)
私たちは言葉だけでなく、相手の表情や仕草から相手の気持ちや意図を読取りながら意志疎通をしていきます。そのような非言語的なコミュニケーションがASDの人には、難しいという特徴があるのです。それにより、周囲の人達から「空気が読めない」と思われ、生きづらさを抱えます。
図11−1
健常者の子どもは、人の顔と椅子を見るときでは活動する脳の部位が異なるが、ASDの子どもはどちらも同じ部位が活動していた
人間よりロボットとのほうがコミュニケーションを取りやすい(中略)
現在,ASDの治療の基本は、社会性やコミュニケーション能力の改善を支援する療育です。しかし、人との関わりやコミュニケーションが苦手なASDの子ども達を人間が支援することは、とても難しいという課題があります。(中略)
そこで、ロボットです。(中略)またロボットならば表情や声のトーン、仕草もASDの人たちにとって刺激が強すぎないように設定することが出来ます。(中略)私も人間とはコミュニケーションが苦手なASDの人がロボットなら旨く会話が出来る例を確認してきました。例えば、普通は家族ともほとんど会話をしない14才の少年がコミューというロボットと会話するようすを見て、彼のお母さんはとても驚いたといいます。普段は人の目を合わすことがほとんどないのに初対面のCommUの目を見ながら自分のことについて語ったからです。
今までの、支援は、親が寄り添う、子どもの精神的な回復を待つ、愛情を注ぐ。など、親御さんは、精一杯努力されてきたと思うのです。
それは、それで悪くはないのですが、もっと別の切り口で療育できて、お子さんが、自分らしく自由に生きられたら、素敵なことだと思うのです。
見えない障害は、病気ではないとは、言われますが、本人や親御さんは、とても辛い思いをして日々を過ごしていると思います。
適応障害やうつ病になる前に、科学的アプローチで、生きづらさを緩和出来るといいなと思います。
私の記事では、物足りない。もっと正確な情報をお望みの方は、ぜひ本書を読んで下さい。
私の叶えたい夢(1)は、日本を含む世界中の子どもが、子どもらしく、元気にのびのびと生きられる世界、そしてご機嫌な大人になって、愉快な老人になること。です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
