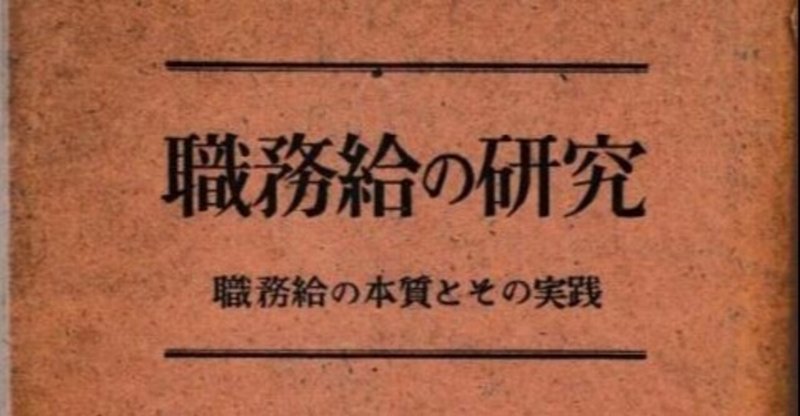
「ジョブ型雇用」について考えてみた(2)
前回の振り返りと今回の概観
前回は、職務給(ジョブ型)の議論が60年ほど前に盛んだったにも関わらず、メンバーシップ型の雇用になってしまったことに対して諸々の雑感を書いた。
今回は職務給を打ち出した日経連の議論・考えを検討してみたい。どのような問題意識があって職務給を検討したのか、そしてどのような点に課題を感じていたのかを紹介してみたい。
『職務給の研究』について
今回主に用いる史料は、『職務給の研究』(日本経営者連盟団体弘報部、初版、1955年)だ。こちらは、日経連(日本経営者連盟団体:今の経団連に近い存在だと考えてもらえればOK)が出版したものであり、しかも当時の日立製作所の給与課長が編集主査となっている。
なぜ今回こちらの史料を参照したいかというと、当時の経営層の問題意識などが透けて見えてくるためでもあるが、何よりも日立の給与課長が編集主査となっている時点で、次回検討する日立の事例を理解する助けにもなるだろうと考えたからだ。
(ちなみに他にも、諸々の研究も参照するが、最後にまとめておく)
職務給の導入に向けた問題意識
さて、早速だが、『職務給の研究』の中身を見ていきたい。
日経連は1950年代当時、以下のような問題意識を持っていた。もちろん、この当時の時代背景として、労働者側からの要求や電算式賃金のようないわゆる生活給、定期昇給制の採用等の要因があることを加味すると良い。
① 年功的な賃金構造
→年齢・勤続年数によって給与額が決まる賃金体系ではなく、企業活動の実態や、生産性とリンクした賃金体系としたい
② 同一賃金同一労働の未整備
→技術革新が進む中、新技術に順応する若年者と順応できない中、高年者との賃金格差を廃して、同一労働同一賃金としたい
③ 経営の合理化
→職務の難度/重要度に応じて適正な賃金格差を設定することで、公平性を担保し、モチベーションの向上や生産性の向上を図りたい
以上のような問題意識を持っていたため、日経連は職務給を推進しようと考えていた。職務給を導入することによって、「勤労意欲の向上を通して、生産性の向上、経営効率の増大を終局的に企図」したいと考えていたようだ。(前掲『職務給の研究』、P5)(田中恒行『日経連の賃金政策』、晃洋書房、2019年、P59)
職務給導入に対する障壁
日経連は以上のような問題意識から、職務給を導入しようと考えていた。しかし、一方で実際に企業へ職務給を導入する時の障壁も考えていた。大きく2つあり、「定期昇給」と「能率給(≒成果給)」の存在だ。
今回は後者の「能率給(≒成果給)」について考えてみたい。もう少し具体的に掘り下げてみると、「同一職務に就いている社員の間で能率(成果)が異なった場合でも職務価値は同一であるため、賃金も同一となるので、能率(成果)差を賃金に反映できない」という旨が記載されている。(前掲『職務給の研究』、P23、P443~P444)(前掲『日経連の賃金政策』、P60)
とても簡単に考えてみる。例えば、”おにぎりの検品”という職務を考えてみよう。この職務は年収400万円と設定してみる。この時、同じ”おにぎりの検品”という職務に対して労働者がA・Bと2人が従事していたとする。
この2人が1年間一緒に働いたところ、労働者Aは1年に10万個検品した。一方で労働者Bは1年に5万個しか検品できなかった。明らかに成果は違うが、職務給を厳密に運用すると、A・Bどちらも同一職務に従事しているので、年収は400万だ。どんなにAが頑張って検品の能率を高くしようが、5万個/年しか検品できないBと同じ月30万円の賃金となってしまうのだ。
ではどうするか。日経連は大きく2つの方策を考えている。
①同一職務多数給与制の採用
→これは、職務は同じでも評価結果によって賃金は変えるという方式だ。つまり、同じ職務であっても成果を評価して、賃金を変えようということだ。
②成果差を賞与に反映
→ベースの給与である職務給は同一にするが、成果差については賞与額に反映させるという方策だ。
(前掲『職務給の研究』、P23、P443~P444)(前掲『日経連の賃金政策』、P60)
このように、職務給を導入する際にも障壁はあることが日経連の中では特に議論されていた。
さて、一旦ここで現代に視点を戻してみる。ここまで見てみると、職務給(ジョブ型)では、成果を明確に反映しきれないということが見えてくるのではないか。あくまでも、職務給(ジョブ型)は職務に対して支払う方法なのであって、成果差を反映するものではない。むしろ、成果差が反映できないことが課題でもあるのだ。
となると、少し前の日経新聞を代表とする「ジョブ型を導入するということは成果主義になる」という主張が変だということがここからもうかがえるだろう。
次回予告
以上が、日経連が想定していた職務給導入に対する動機と、導入に向けた課題意識だ。現代と似たような議論をしていると気付くところがあるかもしれない。
ただし、ここでは、「やっぱり過去と同じ議論していたじゃないか。これに気付かないなんて勉強不足だ」と主張したいわけではない。
現代と通ずるような問題意識と、職務給導入の障壁を乗り越える方策が模索されていたにもかかわらず、なぜ60年前あたりでは職務給がしっかりと導入されなかったのかを考えてみたい。
そのため、次回は日立製作所を事例として、なぜ職務給がうまく導入できなかったのかを考えてみたい。
《本パートの参考書籍》
・日本経営者連盟団体『職務給の研究』、日本経営者連盟団体弘報部、第五版、1960年
・田中恒行『日経連の賃金政策』、晃洋書房、2019年
・幸田浩文『賃金・人事処遇制度の史的展開と公正性』、学文社、2013年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
