
DJ Boonzzyの選ぶ2023年ベストアルバム:40位〜31位
さて他の音楽ブロガーの人達もそろそろ発表し始めている年間ベスト・アルバム・ランキング。自分も一通り今年よく聴いた盤を中心に、改めて一通り聴き直して今年のランキングを何とか決めました。今年も昨年同様、『全米トップ40』のフォーマットに倣って上位40枚を4回に分けて発表しますので、お楽しみに。
2023年のアメリカの音楽シーンは、前半はSZAの『SOS』、中盤はモーガン野郎の『One Thing At A Time』が大ヒットしてアルバムチャートのトップに長期にわたって独占していた一方、Kポップ勢の躍進が昨年以上にめざましく、トゥモローXトゥゲザー、ニュージーンズ、ストレイ・キッズそして今週のATEEZと4組が全米アルバムチャート1位を決めたり(ストレイ・キッズは2回)、相変わらずラテン・パワーも強く、バッド・バニーとカロルGの全米ナンバーワンアルバムに加えて、今年はリージョナル・メキシカン勢が大挙チャートに押し寄せるという、まことに国籍的にも、人種的にも多様性満点のシーンになってました。それもこれもストリーミングやTikTokなどのSNSでのヴァイラル・ヒットが即ヒットにつながる構造が去年以前にも増して顕著だったことも大きな要因でしょうね。そんな中でも、年間を通じてレコード売上、ストリーミング、ライブ動員数と売上など全てにおいて他のアーティストを圧倒した、テイラー・スイフトの存在感は改めて凄いもんでした。一方やや残念だったのは昨年からうって代わって、2023年がヒップホップ勢の勢いが今一つで、今年を代表するヒップホップ作品、というのがあまり見当たらなかったこと(トラヴィス・スコットについては後ほど触れますが)。ドレイクも『Views』や『Scorpion』の頃の圧倒さは残念ながら感じられなかったしね。ということでまずは40位から31位まで。
40.I’ve Tried Everything But Therapy (Part I) - Teddy Swims (Warner)

SNSやサウンドクラウドが日常的にミュージシャン達が自分の作品やパフォーマンスをネットにアップするのに使われてる今の時代、いいのは昨日までまったくの無名だったけど実力があったり、すごい魅力を持った人達が突然シーンで有名になってしまうこと。このアトランタ出身のテディ・スウィムズもそんな突然登場してきたアーティストの一人。まだ30代なのにぽっちゃり体型で頭はほぼスキンヘッドで立派なヒゲを湛えたその風貌だと、一昔前なら「サザンロックの人?」と思ってしまうのだが、これがビックリするくらい魅力的な歌唱力を持ったブルー・アイド・ソウルなシンガーソングライターだったりするから、人は見かけで判断しちゃいけません(笑)。
もともとマイケルの「Rock With You」をカバーしたYouTubeの投稿がきっかけでその後もザ・ウィークンドの「Blinding Lights」、マーヴィンの「What’s Going On」、キングス・オブ・リオンの「Use Somebody」などいろんなカバーをアップしてきたという彼のテナーボイスの歌唱はとってもソウルフル。シングルヒットした「Lose Control」や「What More Can I Say」なんて70年代サザン・ソウル・バラードの意匠そのままなんで、ブルー・アイド・ソウル系のアーティストが好きな人なら一発で気に入るはず。一方オープニングの「Some Things I’ll Never Know」みたいなバラード曲も表現力豊かなボーカルでぐっと聴かせてくれるのに押しつけがましくなくて、こんな人が無名なところからいきなり出てくるなんて、やっぱアメリカは層が厚いなあ、と思わせられましたね。こういうのもアルバムチャートのブログやってなかったら多分アンテナに引っかかってなかったので、何か得した気分になった、そんなアルバムでした。
39.Micheael - Killer Mike (VLNS / Loma Vista)

2023年がヒップホップについてはイマイチの年だった、と冒頭に書いたように、ケンドリック・ラマーを筆頭に、昨年の自分のランキングでもデンゼル・カリーやブラック・ソートにナズといった面々が気合いの入ったヒップホップ作品を届けてくれていた2022年に比べると、ホントにこれ、という作品が見当たらないのが今年だったように思う。去年『King’s Disease III』で気を吐いていたナズは今年『Magic』シリーズを2枚も出してるんだけど、いずれも何だか中途半端感が感じられて、結局今年のランキングからは漏れてしまった。話題作、という意味でいうと5年ぶりのトラヴィス・スコットの新作もあって、最初聴いた時は「おっ」とも思ったけど、もはやあれはヒップホップではなくなってるし、それにしてはやりたいことがあまり定まってない感じで、今回何度か聴き直したけどこれも選外に。
で、今年唯一自分の上位40枚に入れたヒップホップ作品は、アウトキャストの片割れ、というか最近だとラン・ザ・ジュエルズの片割れのキラー・マイクのこのアルバム。これも前作から11年ぶりの新作で、もはや前作がどうだったかはあまり覚えていないのだが(笑)、今回のこのアルバム、何だかとてもキリッとしてるのが気にいった。適宜にそこここにオールドスクールなループが散りばめてあって全体の佇まいが何となく70年代ブラックスプロイテーション・ムーヴィーのサントラ風な感じなのもポイント高い。「Run」でキラー・マイクをアジるかのようなナレーションを聴かせる黒人コメディアンのデヴィッド・シャペルのナレーションなんかもそういう雰囲気を増幅してるな。そして一昨年のグラミー賞でリル・ベイビーの「The Bigger Picture」のパフォーマンスの時に表れて突き刺すような鋭いフロウを聴かせてくれたキラー・マイクの凜々しいフロウもなかなかいい。彼のフロウがかなり立ってるので、R&B系アーティストとのコラボ・トラックがやっぱり出来が良くて、カーペンターズの「We’ve Only Just Begun」の一節をループした、ジャッギド・エッジ(懐かしい!)を従えた「Slummer」や、Blxst(ブラスト)をフィーチャーした「Exit 9」なんかは特にいい。とかくヒップホップといえばトラップ、だった時代はさすがにもう過去のものになりつつあるし、こういう骨のあるヒップホップ・アルバム、2024年はもっと出てくれるといいな。
38.Broken By Desire To Be Heavenly Sent - Lewis Capaldi (Vertigo / Capitol)

自分の祖母の死を受けて書いた「Someone You Loved」が英米でナンバーワンの大ヒットになってブレイクした、ルイス・キャパルディ。彼のスタイルはその曲が収録されたデビュー・アルバム『Divinely Unispired To A Hellish Extent』(2019年全米20位、全英1位)からこのセカンド・アルバム(全米14位、全英1位)になっても変わらず、自らのほとばしるようなエモーションを絶叫型のボーカルで切々と歌う。テーマは今回「Forget Me」や「Wish You The Best」といった離れていった恋人のことを思う内容の曲に代表されるように、圧倒的に男女関係とその中でダウナーな状況に陥ったことによる感情を歌ってる曲が多いのは、本人が前作の成功以来メンタル的に厳しくなり、今年のグラストンベリーではステージで歌えなくなるほどの状況にあったことも多分大きく影響してるんだと思う。今年のフジロックでは、ある意味彼と同時期にブレイクして、よく似たスタイルながら、より人生と女性との関係についてポジティブなメッセージを歌い続けるアイルランドのダーモット・ケネディと両方見れると思ってたら、ルイスは残念ながらグラストンベリーの後、しばらくのライブ休止を発表してしまったのが残念。
そんなやや失恋や別れた恋人の歌だらけのアルバムだけど、このアルバムも前作で一緒に曲を書いたソングライター達に加えて、「Pointless」ではエド・シーラン、「Wish You The Best」ではJPサックス、「Leave Me Softly」ではマックス・マーティン、そして「How I’m Feeling Now」では昨年グラミー賞で新設の最優秀ソングライター部門を受賞したトビアス・ジェッソJr.など、当代の一流のソングライター達と共作してる珠玉の楽曲が並んでいることは間違いない。来年にもまた長ーいタイトルの新作(笑)が予定されてるらしいけど、今度はダーモットの向こうを張るような人生の喜びと希望に向けてのメッセージがこめられた楽曲もいくつか歌ってくれるといいね。
37.Rustin’ In The Rain - Tyler Childers (Hickman Holler / RCA)

2010年代、クリス・ステイプルトンやスタージル・シンプソンといったカントリー音楽に対してロック的なアプローチというか、少なくとも従来のスタイルのカントリー・シンガー達(例えばジェイソン・オルディーンとかw)とは似て非なる音楽的アプローチで音楽を作るアーティストが増えている。彼らの音楽はちょっと聴いた感じではこれまでのカントリー音楽とさほど変わらないように聞こえるのだけど、従来のカントリー・シンガーたちが、ストリートのトラップ・ラッパー達同様、パーティーのこととか、俺自慢のこととかを百年一日のように歌ってるのに対し、今のアメリカ社会の矛盾とそこに生きる苦悩と憂鬱だとかをいろんな視点から切り取った内容の歌を歌ったりしているところが大きく違うところ。クリスやスタージル同様、ケンタッキー州出身のタイラー・チルダーズも、当時のブラック・ライヴス・マター運動に反応して、「地方に住む白人の観点から」人種差別に反対するという重いテーマの前々作の『Long Violent History』(2020年45位)で知って以来注目してきたシンガーソングライターだ。まだ32歳だけど、楽曲のスタイルは基本ネオトラディショナル・カントリーと言われる、従来からのカントリー音楽の発声法と楽曲スタイルなので、ちょっと聴くとやや古臭く聴こえてしまう危険性もあるのだが、彼が重視しているという歌詞に目を通してよく聴くと、彼が独自のスタイルで表現しているSSWだということに気がつく。
以前は友達だと思ったのに、最近電話してもEメールしても返事くれないね、何か俺悪いことしたのかな、という今どきピュアな感じで切々と歌う「Phone Calls And Emails」、聖書のルカによる福音書第2章8-10はイエスの誕生を告げる空からの光を讃える内容のはずなのに、あの光は世界の終わりだと歌う「Luke 2:8-10」、君との愛があればどんな戦いでも頑張って耐えられる、と歌う美しくも切ないバラード「In Your Love」など、一曲一曲にストーリーがあって一冊の短編集のよう。その意味ではクリス・クリストファーソンの曲を原曲に忠実にカバーしている「Help Me Make It Through The Night」もまた然り。前述の前々作が、人種差別に抗議する、一曲以外は全曲トラディショナル曲を全編フィドルで聞かせるという内容だったし、前作の『Can I Take My Hounds To Heaven?』(2022年8位)も新旧のゴスペル曲8曲を3つの異なるバージョンで聞かせるという、意欲は大いに買うものの正直とっつき辛い作品でもあったので、今回のこのアルバムはシンガーソングライター、タイラー・チルダーズの真価を広く知ってもらうには絶好の作品だと思う。自分の音楽を「アメリカーナ」と呼ばれるのを嫌うタイラーがこれからも紡いでいく、唯一無二の音楽を僕は聴き続けたい。
36.In Times New Roman… - Queen Of The Stone Age (Matador)

QOTSAにノックアウトされたのは、デイヴ・グロールが参加したことで話題になった3作め『Songs For The Deaf』(2002年、全米17位全英4位)とあのパワフルなバンガー・ナンバー「No One Knows」だ。この曲なんて今でもライブでやられた日には頭空っぽになってモッシュしちゃう(あ、もう年だから無理かなw)くらい自分の音楽経験の中でかなり衝撃的な経験だったんだけど、その後の彼らのアルバムには何だかピンと来るものがあまり感じ取れずズルズルと来ていた感じだった。前作のマーク・ロンソン・プロデュースの『Villain』(2017年全米3位全英1位)のダンス・ロック的アプローチも今どきの試みではあったけど、あの「No One Knows」の興奮を知ってる自分には今ひとつ物足りない感じが残ってた(ジョッシュ・オムはこの時の意匠を使って2021年のロイヤル・ブラッド『Typhoon』ではいい仕事してるんだけどね)。そこにその『Villain』以来6年ぶりに届けられたこのアルバムは、何だか久しぶりにオンビートでラウドでノイジーなギターがロックしてる!という感じがあってちょっとうれしくなった次第。
冒頭の「Obscenery」から数曲続けて聴いて印象的なのは、ビートにぐっとタメが聴いていて、とってもヘヴィーながらグルーヴ満点の曲が多いな、ということ。最近めっきりハードロックっぽい音を聴くことが減ってきている自分なんだけど、このアルバム、特に「Negative Space」みたいな曲を聴いてると、自分は年を取ってハードなロックが聴きづらくなってきたというよりも、半端なビートやグルーヴがあまり感じられないロックに対する許容度が減ってきてるんだろうな、と思った。久しぶりに全10曲ダレることなく一気に聴き通せて、カッコいいロックへの高揚感を久しぶりに感じさせてくれるQOTSA、来年はやはり6年ぶりに来日するらしいんで、これは行かねばなるまい!
35.Kaytraminé - Kaytraminé (Aminé & Kaytranada) (CLBN / Kaytranada / Venice)

これはもうね、ただひたすら気持ちいいアルバム。ケイトラミネ、というのは、R&Bダンス・ミュージック系のハイチ系カナダ人プロデューサー、ケイトラナダと、ちょっとおチャラカ系のラップ・ヒット「Caroline」(2016年11位)で知られるラッパー、アミネによる、ワンタイム・コラボ・プロジェクト。この2人、このコラボやる前からお互いにアミネがケイトラナダの曲のリミックスやったり、ケイトラナダはアミネのミックステープの曲をプロデュースしたりと結構つながりがあったみたい。一時期自分がDJでよくかけていたレジー・スノウの『Dear Annie』(2018)収録のグルーヴィーなトラック「Egyptian Luvr」にアミネがフィーチャーされてたのは知ってたけど、プロデュースをケイトラナダがやってたらしい。道理で自分も気に入ってよくDJで回してたわけだ。
基本、ケイトラナダの作るオーガニックな感じのエレクトロR&Bトラックに乗せて、アミネがある時はつぶやくように、またある時はなかなかの切れ味のフロウでラップをかます、という構図なんだけど、先行シングルの「4EVA」なんか典型的だけど基本超が付くくらいレイドバックなグルーヴなのがホントに気持ちよくて、夏頃は結構パワーローテで聴いてたな。そのヴァイブはジャケの二人の写真にもよく現れてるけど、何でも二人でマリブの一軒家を借りて、2週間そこにこもってぶっ続けでレコーディングしてたらしい。昼はケイトラナダがトラック作って、夜はアミネがリリックを考える、って感じで。マリブっていう場所のレイドバックな雰囲気と二人の楽しんで作ってるヴァイブがバンバンに伝わってくるそんなアルバム。これからやっと寒くなろうという年末だけど、こういうのをバックにホームパーティってのもなかなかいいかも。
34.You’re The One - Rhiannon Giddens (Nonesuch)

ピーター・バラカンの番組で、Tボーン・バーネットのプロデュースした『Tomorrow Is My Turn』(2015) で初めてリアノン・ギデンズを知った時は、そのボヘミアンな佇まいから繰り出される清冽なフォークとゴスペルが一体となったような作風にとっても魅力を感じて、それ以来新作が出れば必ずフォローしてきた。ただそれ以降のアルバムを聴くと、『Tomorrow〜』で感じたようなどこか明るいところに向かって進んでいくようなイメージがちょっと影を潜めて、何となく雪国の曇り空の下でちょっと陰鬱な感じを漂わせるような作品が続いていたように思う。その感じはジョー・ヘンリーがプロデュースした『There Is No Other』(2019) と自ら現在のパートナーであるイタリア人ミュージシャンのフランシスコ・トゥリシとプロデュースした前作『They’re Calling Me Home』(2021)でも何となく残っていて、前者は陰翳のある音像で知られたジョー・ヘンリーだからそうなのかな、とも思ったし、後者はコロナ真っ只中だった、というのもあったのかもしれない。
今回のこのアルバムを聴いてまず嬉しかったのは、そういう陰鬱な雰囲気がすっかりなくなり、ジェイソン・イズベルと共演した躍動感あふれる「Yet To Be」や、夜明けの朝日に向かって力強く歩んでいくようなイメージのバンジョーが心地よいタイトル・ナンバー、そしてサザン・ゴスペル・ソウルのようにオーガニックなグルーヴ感で思わず微笑んでしまう「Wrong Kind Of Right」などのA面は特にとってもポジティヴなヴァイブとソウルフルなエモーションが如実に伝わる内容になっていたこと。そんなソウルフルなA面に比べて、B面はもう少しリアノン本来のトラディショナル・フォークな世界や、「Who Are You Dreaming Of」や「You Put The Sugar In My Bowl」のような往年のアメリカン・ソングブックのようなクラシックな世界観になっているけどそれも決して陰鬱な感じはなく、一枚聴き通した後は「ああ、アメリカ音楽の古くから現在に至るポピュラー音楽、トラディショナル・フォーク、R&B、ブルースといった伝統を現在にうまく換骨奪胎した素晴らしい作品だったなあ」と思わせる、そんな作品だ。そして今回全面プロデュースを担当しているのが、ここ10年であの故ボビー・コールドウェルとのデュオ・プロジェクト、クール・アンクルとの素敵なレトロ・ソウル・アルバム『Cool Uncle』(2014)を届けてくれ、最近ではニューオーリンズの超絶グルーヴ集団、タンク・アンド・ザ・バンガスのデビュー・アルバム『Green Balloon』(2019)をプロデュースしていたジャック・スプラッシュだ、というのもこのアルバム全体の明るいグルーヴ感に少なからず貢献しているに違いない。リアノン・ファンも、リアノンの名前を今回始めて聴いたという人にもおすすめです。
33.Everything Is Alive - Slowdive (Dead Oceans)
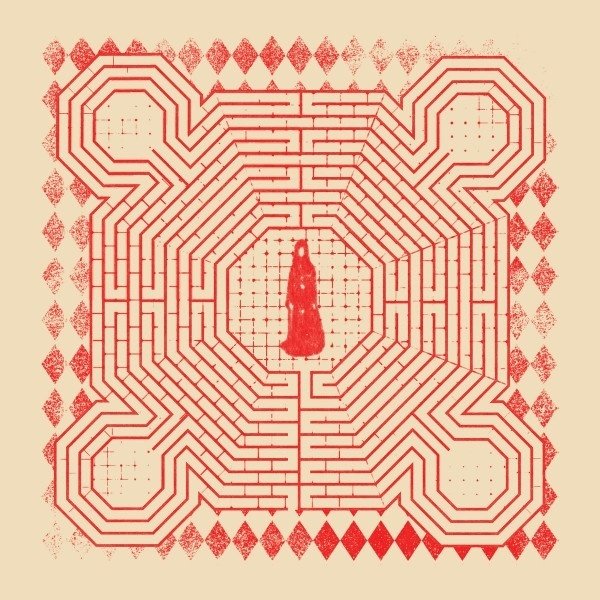
イギリスのレディング出身のこのスロウダイヴというバンドが最初活動して人気を呼んでいた90年代前半という時期は、自分がビジネススクールの学業で全く他のことに目を向ける余裕がなく、1993年に帰国してもしばらくは新しい仕事環境に慣れるのと、その新しい部署がいろんなことで無茶苦茶忙しかったこともあって、あまり洋楽に対する感度が高くなかった時期だったこともあって、このバンドが人気のあった当時のことは全く記憶にない(同様の理由で自分はストーン・ローゼズも体験していない)。バンドは1995年に一旦解散したらしく、1996年頃からミーンタイムという洋楽ファンサークルの運営に携わるようになる前に彼らはシーンから消えていたことから、自分がリアルに体験できるわけがなかったことになる。だから今年のフジロックに最近再結成したという彼らが出演するというのを聴いた時も特に感慨もなく、従って結局彼らのステージは観ずじまいだった。
ところがその直後9月に全米アルバムチャートに入ってきたこのアルバムをブログ執筆のために聴いたところ、その静謐で広がりのある、心をぐっと落ち着かせてくれるようなエレクトロな音像にすっかり引き込まれてしまった。彼らのことを「シューゲイザー・バンド」という記述が多いのだが、自分のシューゲイザーのイメージというのは、90年代半ばにノイジーなギターとひたすら神経を逆撫でするような楽曲を聴かせていたフガジみたいなバンドのイメージだったので、全然そんなイメージとは違うスロウダイヴのサウンドが気に入ってしまったというわけ。冒頭2曲のアンビエントな感じから一気にアップテンポながらドラマチックな展開の「Alife」なんかを聴くと、僕のもう一つの最近のお気に入りのUKバンド、ロンドン・グラマーなんかは多分このスロウダイヴの影響を受けてるんだろうな、というのを感じたし、男性ボーカルのボソボソな感じはこちらも自分の好きなザ・ナショナルを思わせる。とにかくシューゲイザーだか何だかはどうでもよくて、今年の秋口は彼らのライブを見損なったことを大いに悔やみつつ、このアルバムを繰り返し繰り返し聴いてた。そろそろ彼らの90年代のアルバムも聴いてみようと最近思っている。
32.Lahai - Sampha (Young)

サンファの名前を初めて知ったのは、確かソランジェのアルバム『A Seat At The Table』(2016)の「Don’t Touch My Hair」に彼の幻想的なボーカルがフィーチャーされてたのを聴いた時だと思う。ちょっとフランク・オーシャンっぽいエレクトロなこのトラックを共作・プロデュースしていたサンファというアーティストのことは、当時ヒップホップ・ヘッズの息子も知ってたことを聴いて何だか嬉しかったことを覚えてる。そのサンファのデビュー・ソロ・アルバム『Process』(2017)はその年のマーキュリー・プライズも取ったし、各音楽メディアの年間ランキングの上位に入った、自身が「ポリリズミックなオデッセイ(冒険の長い旅)」と呼ぶように、自分の出自であるアフリカン・ポリリズムも随所に顔を出す覚醒したコンテンポラリー・ソウル・アルバムだった(彼の両親はアフリカのシエラレオネからUKへの移民)。今回のこのアルバムは冒頭から聴き進めていくと、ドラムンベースっぽいビートの聞こえる「Can’t Go Back」などはあるが、前作の覚醒した音像に比べ、ドリーミーなシンセや生楽器やコーラスによる音像が聴くものの周りを包み込むサウンドトラックのような、そんな感覚を想起させる作品になっている。ある意味、最近のアメリカのブラック・ミュージックでは(フランク・オーシャン以外からは)聴くことのできない、そんなインスパイリングな音像が素晴らしい。
「ラハイ」というのは彼のお祖父さんの名前であり、サンファ自身のミドルネームでもある。彼自身によると、父親を失った息子である自分と、新たに娘を2020年に授かった父親である自分を見つめながら、それまで自分のことだけを考えていたところから、自分は娘がいい人生を送れるためにあとどのくらい生きていけるのか、と思い始めたことが今回のアルバムの題材になってるらしい。アルバム中盤の「Jonathan L. Seagul」はあの映画にもなった『かもめのジョナサン』で、おそらく息子から父親に成長した自分の人生の旅をあのお話に重ねてイメージした曲なんだろう。そう考えるとこのアルバム全体が内省的なテーマのミュージカルのキャスト・アルバムのようにも聞こえる。そんな中で、サンファのファルセットでドリーミーなボーカルがひたすら気持ちいいアルバムだ。
31.Falling Or Flying - Jorja Smith (FAMM)

最近はまた去年のマニー・ロングを始め、今年ブレイクしたヴィクトリア・モネやマライア・ザ・サイエンティストといったアメリカ人の質のいい女性R&Bシンガーが出始めているけど、そもそも国全体が過去から現在に至るまでアメリカ黒人音楽を昇華したロックンロールやブルース・ロックのアーティストや、白人のソウルフルなブルー・アイド・ソウル女性シンガーを輩出し続けているイギリスから出てくるR&Bシンガー達には、一段クオリティが高く、またクールなスタイルやジャズやゴスペル、ヒップホップも一体化されたような世界観を持つ者も多く、R&BファンとしてはUKシーンは常に目を離せないものになってますね。2010年代後半突然登場して、アルバム『Lost & Found』(2018)で衝撃的なブレイクを果たしたジョージャもそうしたアーティストの一人で、デビュー作にぞっこん参ってしまって以来(自分の2018年の年間アルバムランキング3位に入れてました)2作めをまだかまだかと待ってました。当時の彼女のファースト・アルバムも熱っぽくレビューしてる昔の自分のブログ記事のリンクを貼っておきますのでよかったら覗いてみてください。
今回のアルバムもそのファーストに負けずとも劣らない、ジョージャのしなやかなコントラルトのボーカルと、ロック、ジャズ、ヒップホップなどあらゆるスタイルの要素を一体化した楽曲の織りなす世界観が、魅力爆発の盤になってます。惜しむらくはリリースが9月末だったということでまだ聴き込みが充分じゃないのでこの順位にしちゃってますが、もう少し聴き込んでればトップ20には間違いなく入れられる内容。自分的には特に今UKで人気のラッパーの一人、Jフス(アデルとも仲いいことで有名)のレガトン風のラップをフィーチャーした軽快な「Feelings」から、イントロのエレピから前作の世界観に通じるクールなジョージャの歌が聴けるタイトル・ナンバー、ロックっぽい縦ノリのリズムが多分ライブでやったら無茶苦茶盛り上がるだろう「GO GO GO」、そして再び浮遊感満点なシンセをバックに夢見るようなジョージャのボーカルにドリーミーなコーラス隊が絡む「Try And Fit In」あたりの流れが最高に気に入ってます。何と言ってもジョージャのちょっと舌っ足らずっぽい感じのボーカルはそれだけでも魅力なので、ちょっとクールな感じのR&Bが聴きたい、という向きには全力でおすすめできるアルバムですね。
ということでいきなりちょっと書きすぎちゃった感のある(笑)年間ベスト・アルバムランキング、この後は21~30位行きます。何とか今週前半にアップしたいですがどうなりますか。お楽しみに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
