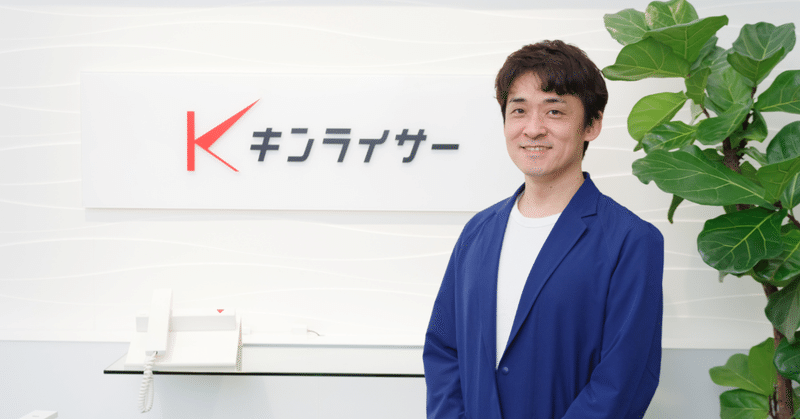
世の中のあらゆる要素を複合的に考える——株式会社キンライサー CMO 大川さんに聞く、これからのマーケターに求められる資質とは
デジタル時代の到来により、マーケティング施策は多様化しています。それぞれの領域における専門性が高まる一方、それゆえに領域間の連携が難しくなるなど、全体で見ると「分断」が生じているようにも見えます。
そうした「マーケティングの分断」を解消するために、『BORDERLESS MARKETING COMMUNITY(以下、BMC)』は発足しました。BMCは、第一線で活躍してきた有識者による基調講演やマーケティングに関わる多様なステークホルダーとの議論を通して、「真に全体最適化されたマーケティング」を探求するコミュニティです。
本記事は、BMCの会員からコミュニティに参加した感想を伺う「コラムリレー」の第二弾。取材を受けてくださったのは、株式会社キンライサー CMO(チーフマーケティングオフィサー)の大川さんです。お湯が出なくてお困りの方に対し、ガス給湯器及びエコキュートのスピード交換事業を中心に展開する同社は、テレビCMやインターネット広告などを用いて積極的にマーケティングを行っており、例年20%増を超える成長率を繰り返しています。
BMCに参加した時の感想をうかがいながら、大川さんが考えるマーケターに求められる資質について聞きました。
大川 真樹 様
株式会社キンライサー上席執行役員CMO。ITベンチャーでWebのクリエイティブやデジタルマーケティングに従事した後、当時カタログ通販が主体であった化粧品会社にデジタル中心のマーケターとして入社。後にEC化率50%を超える飛躍的な成長に貢献。同社のマーケティングやICT戦略の執行役員、子会社社長などを経て2021年よりキンライサーに参画。

必ずしも分断自体が悪いわけではない
——BMCは「マーケティングの分断」を解消することを目的に設立されたコミュニティです。これまでのキャリアの中で、分断を感じられたことはありますか?
新卒で入った会社でウェブデザイナーとして働き、その後マーケターに転身したあたりで近いものを感じたことがあります。デザイナーとマーケターの違いというんでしょうか。15年くらい前の話ですが、まだ右脳寄りの人と左脳寄りの人の間に壁があったように記憶しています。お互いなにをしているか分かりづらかったんだと思います。
ただ、個人的には「分断はそこまで悪いものじゃない」と思っているんです。
——どういうことでしょうか?
お互いのことを理解しようとするのは大事ですが、統合することを最初から目的にしてしまうと、理解しづらいけど素晴らしいアイデアが生まれづらくなってしまうと思うんです。たとえば、トップクリエイターが突き抜けたものを提示した場合、いきなり同じ目線で現場のマーケターが理解しようとしても、さすがに難しい。最初から同じ目線で議論したり共有したりしていたら、クリエイターの専門性や希少なアイデアが押し殺されてしまう可能性があるんです。
分断があることによってパフォーマンスが最大化することもあるという意味で、分断自体は問題ではないと思います。
ただし、まったく理解し合うことなくいつまで経っても分断し続けているとしたら、それは問題です。分断と統合を繰り返しながら物事を進めていくのが大切なんじゃないでしょうか。
——あえて分けることで専門性が発揮できることがある。興味深い指摘です。
他に分断と聞いて僕がすぐ思いつくのは、クリエイターと経営の間の分断です。経営メンバーには左脳よりの人が集まっていることが多いので、右脳的な感覚のことが理解されないことはよくあります。特に経営層の議論の場ではロジックや数字がどうしても勝ってしまうことが多く、それが目で見える範囲の思考に留まる要因となり、企業の弱みにつながりかねないと考えています。
そのため、これだけものや情報が溢れている時代には、デザイン思考やアート思考を経営に取り入れることは大切なことだと考えています。数字やスペック的な観点だけでは競合と差別化していくことが難しく、「なんとなくこっちのほうが好き」とか、「理由は分からないけど好感が持てる」といった感覚的なところが重要になってくるからです。
経営会議のような場でロジカルに議論しても、そうした差別化のアイデアは生まれないと思います。ある種、意図的に分断を作り、クリエイターが伸び伸びと自由な発想ができる環境を生み出すことも大切じゃないかと思うんです。

クリエイターは野生動物。存分に暴れてもらったほうがいい
——そうした環境を作る上で大切なことはなんでしょうか。
BMCの第4回イベントのなかで、Whateverの川村真司さんが話していたことがヒントになると思います。川村さんはクリエイターを「野生動物」と例えていました。常識にとらわれない発想をしたり、大胆な表現を考えたりするのが得意である一方、それが行きすぎてしまうこともあるという意味だと思います。
一方、経営メンバーや広告主は、目的や与件を定義してあらかじめ「柵」を用意する存在。クリエイターが思う存分暴れられるような柵を作れるかどうかが、力の見せ所だというようなことを話されていました。
僕は川村さんの「クリエイターは野生動物」という意見にはまったく賛成です。その上で、多くの事業者側の人が、柵を狭くしすぎているんじゃないかと思うんです。条件の指定が細かすぎたりして、クリエイターが力を発揮しづらくなっています。
柵はなるべく広く設定したほうがいい。クリエイターにぶっ飛んだアイデアを出してもらったあとで、経営側や広告主側が調整していくほうがいいクリエイティブが作れるんじゃないかと考えているんです。
——ある意味、用意された柵を超えるような、より良いクリエイティブを作ろうという考えですね。それにはクリエイター側にも、「経営に合わせる」「言われた通りやる」ではないマインドセットが必要になるように思うのですがいかがでしょう。
そうですね。そうしたマインドセットを持ったクリエイターと手を組めるのが理想だと思います。
外部のクリエイターに依頼する場合は、幅広いアイデアを持っている人を選べばいいと思いますが、どちらかというとインハウスのクリエイターのほうが、無難なものが出来上がってしまう傾向があるように思います。
なぜなら、インハウスのクリエイターは無意識のうちに「うちの会社や業界はこういうもの」という前提を持ちやすいからです。これは僕自身がインハウスのクリエイターだった時代の経験則でもありますが、それでは、ブランドを一気に躍進させるようなクリエイティブを作ることはできません。
実は、僕が入社した2年前のキンライサーにも似たようなところがありました。キンライサーはもともと大阪に根付いた地域密着型の施工会社をベースに成長してきました。その世界観がクリエイティブにも強く反映されてきた。
そこで、CMOとして赴任してからの1年は、その前提を取っ払うための取り組みをしてきました。全然違う業種の素敵なクリエイティブをインハウスの制作チームに共有したり、今までとは違う世界観を意識するだけでなく、ブランド企業とは一体何なのかを考えたりするようにしたんです。そこで弊社のクリエイターが自ら試行錯誤をした結果、広告やクリエイティブの表現方法はだいぶ幅広いものに変わってきたと思っています。
この変化はまだ途中経過で、いまは世界観を大きく広げただけ。この先、キンライサーがどういう世界観を目指すのかは引き続き検討しています。大阪の地元企業だった頃の親近感のような良さは残しつつ、違ったポイントでも個性を感じてもらえるような企業にしていきたいです。

マーケティングとは、社会を洞察して「完成形のイメージ」を持つこと
——大川さんが参加されたBMC第4回イベントでは「広告主、代理店、制作会社の全員で、広告の効果測定をするのが大事」という話もありました。その意見に対してはどう思われますか?
インターネット広告は多くの企業が綿密な効果測定をしているのに対し、テレビCMは効果測定がされない場合が多いですよね。できるに越したことはないと思いますが、テレビCMの再現性を高めるのは難しいと思うところもあります。
年がら年中CMを大量に出している企業は少なく、だいたいの企業がスポットCMを年に1回出すか、多くても2回くらい。テレビとネットの市場関係も変わっていくし、世の中の空気も変わるので、来年も同じ条件で広告を出すということ自体が難しく、成果も同じとは限りません。それにクリエイティブそのものや起用タレントも変わっているかもしれません。競合関係や広告枠の金額すら変わるので、費用対効果はなおさらわからない。
あまりにも変数となる要素が多すぎるため、さまざまな分析結果は参考として役立てつつ、これから広告市場がどう変わっていくのか、その中で自分たちが世の中にどう思われたいのか、世の中の何を変えたいのか、そういったことをイメージしながらクリエイティブやマーケティング戦略を組み立てていくことが大切です。
また、過去の分析はできたとしても未来の予測はなかなか難しいので、結局、半分は勘に頼るしかないのが本音です。
しかし、勘とは、ただの思いつきではありません。社会を洞察することで得たさまざまな要素を繋ぐことで生まれる「完成形のイメージ」のことです。たとえば、iPhoneを生み出したスティーブ・ジョブズは、最初から、街行く人みんながスマートフォンを持って、気軽に音楽や映像やゲームを楽しんでいる景色を想像できていたんだと思います。
さまざまなテクノロジーを取り入れ、クリエイターが活躍しやすいプラットフォームを作り、それがどのように結びついてマーケットが作られていくか、それが実現された世の中の情景をきっと感覚的に描けていた。その上で、指でなぞったり、タップひとつでアプリを落とし、その機能を行き来できたりするUIにしたんじゃないかと思うんです。きっと、「音楽をインターネットで聞く」「ゲームができる携帯電話」という断片的かつ現状の延長線上の発想を起点にプロダクトを作ったら、iPhoneとは違うものができているでしょうし、今のようには世の中が変わっていないはず。
彼から学べることは、現状の延長線上ではなく、未来の完成形のイメージを持ち、それに近づけていくためのマーケティング活動をするのが重要ということです。そのイメージを作るために、断片的な物の見方をするのではなく、ビジネス、テクノロジー、クリエイティブを含むあらゆる要素を複合的に考えて繋げていく思考がマーケターには必要だと思います。
——キンライサーさんにおいて、大川さんはどんなイメージを持ちながらマーケティグに取り組まれているんですか?
まだいくつかの軸で検討中ではありますが、給湯器の会社から「エネルギーインフラの会社」になることを一つのパターンとしてイメージしています。給湯器は一家に一台置いてあり、お湯をわかすために使うガス代は光熱費全体の3割程度です。キンライサーは「家庭のエネルギーインフラに密接に関わる会社」とも言えます。
そう考えると、マーケティングやクリエイティブも別の可能性が見えてくるし、外から見える姿も変わってくる。事業展開自体が変わる可能性があります。だからこそ、「給湯器の会社だからこうあるべき」という固定観念を取っ払おうとしているんです。

最適なテクノロジー・クリエイティブをビジネスに紐づける
——SDGsやサステナブルの時流を読んだ上で、会社やクリエイティブの方向性を変えていくんですね。では最後に、大川さんが考えるマーケティングの理想像についてお聞かせください。
マーケティングに限った話ではありませんが、ビジネスを成功させるには、経営にクリエイティブとテクノロジーを紐づけていく必要があると思います。それらがどう有機的に結びつくか、それらをどうビジネスに落とし込んでいくか。その選択自体がブランドやサービスの差別化に繋がってきます。
テクノロジー・クリエイティブというと、AIとかブロックチェーンとか最先端のものを思い浮かべがちですが、必ずしも新しいものを取り入れようという話ではありません。テレビCMや電話のIVRもひとつのテクノロジーですし、街中にある道路標識も立派なクリエイティブ。自社にとって最適なテクノロジーがIVRならば、それでいいんです。
マーケティングにおいて大切なのは、自社にとって必要なものを正しく判断できること。もちろんそのためには、最新のものから既存のものまで幅広い知識や組み合わせを知っておく必要がある。BMCがそうした知見を学んだり、領域や分野を超えて新しい発想が生まれるようなコミュニティになっていくことを期待しています。
さいごに
BORDERLESS MARKETING COMMUNITYは、広告主、広告会社、メディア、クリエイター、アナリスト、研究者など、マーケティングに関わるさまざまな専門性を持つプロフェッショナルが集まり、領域横断的な知見の交流を行うコミュニティです。会員の知見の交流を通じて、真に最適化されたマーケティングを実現するため、定期イベントの開催やFacebookグループでの活動をおこなっております。
BORDERLESS MARKETING COMMUNITYへのご参加をご希望の方は、以下のフォームより、会員登録ください。
https://borderless-mc.jp/#admission
■会員参加条件
(1)マーケティングに関わる業務に従事されているプロフェッショナルの方
※専門横断的な交流を図るコミュニティのため、広告主・広告会社・メディア・クリエイターなど、専門領域は問いません。
(2)BORDERLESS MARKETING の考え方に共感される方、実践したい方
■コミュニティ概要
名称:BORDERLESS MARKETING COMMUNITY(ボーターレス マーケティング コミュニティ)
理事:黒崎 太郎 氏(日本テレビ放送網株式会社 取締役 執行役員 営業担当データマネジメント室長)
佐々木 丈也 氏(三井住友カード株式会社 常務執行役員 マーケティング本部長)
戸練 直木 氏(カゼプロ株式会社 代表取締役)
手島 領 氏(螢光TOKYO/DESIGN BOY クリエイティブディレクター)
星野 崇宏 氏(慶應義塾大学 経済学部 教授 / 慶應義塾大学経済研究所 所長)
平尾 喜昭 氏(株式会社サイカ 代表取締役社長CEO)
設立 :2022年2月
会費 :入会金・年会費とも無料
Web :https://borderless-mc.jp
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
