
1990年のフリー雀荘(関西編)
先日の1990年のフリー雀荘が好評を博したので、続編を書いてみます。今回は大阪ローカルについて。またしても記憶違いとかは大目にみてください。正確な情報をご存知でしたら教えてください。
でははじまりはじまり〜( ̄▽ ̄〜)
ローカルルール
麻雀というゲームは、やるメンツや地域などで様々なローカルルールが存在している。
・完先かありありか
・赤ドラの枚数
・ドラを開ける枚数
・割れ目
・鳥打ち
・焼き鳥
・焼き豚
・焼き直し
・ご祝儀は一発、裏ドラ、赤ドラ、海底、河底、嶺上開花、チャンカン、役満、トビ、アリス、マネマンなどなど
・採用しているローカル役(マネマン、山から、初カン、鳴き一盃口などなど)
・数え役満のハン数
・採用している役満(十三不塔、流東北新幹線などなど)
とにかく枚挙にいとまがないほど、ところ変わればルールは変わる。真の麻雀強者とは、どんなルールにも対応して勝ち組に入る者。貴方の周りにもそんな強者はいないだろうか?
1985年の風俗営業法改正
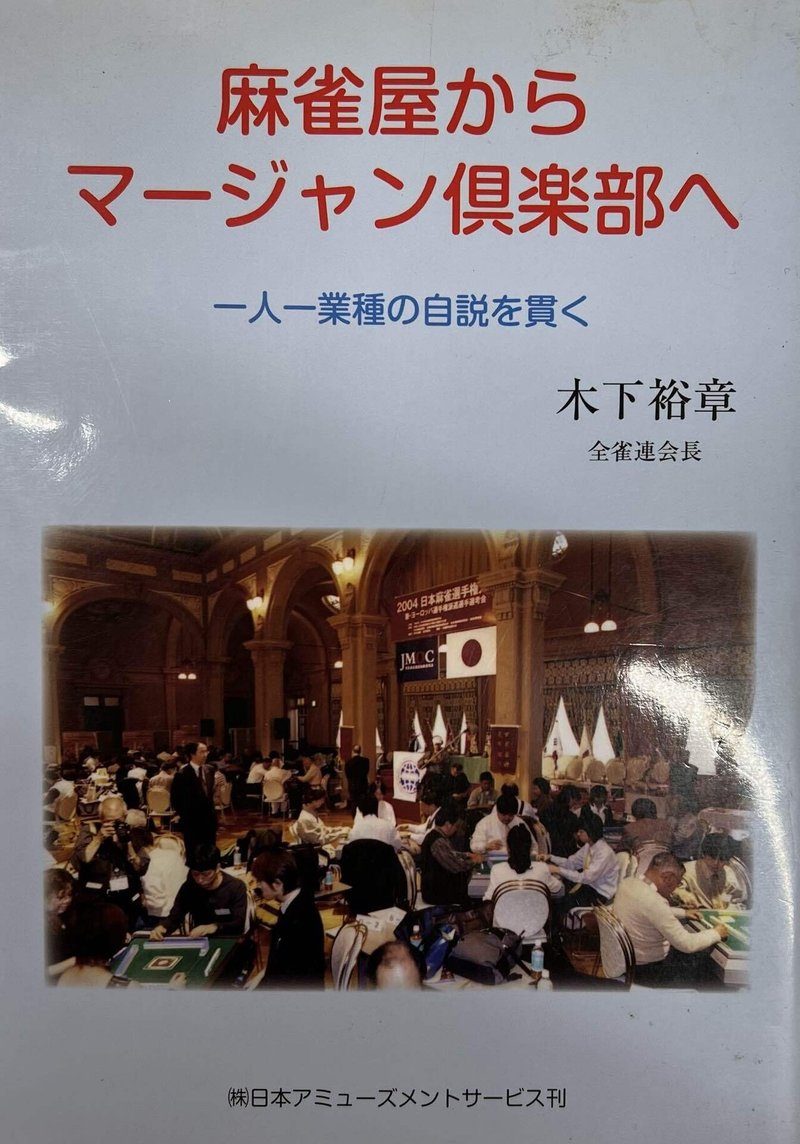

今から少しばかりは麻雀屋の歴史のお話です。つまらないかもしれませんが、現在に繋がるとても大切な話です。ぜひご一読ください!
元全国麻雀連合会会長木下裕章氏の著書「麻雀屋からマージャン倶楽部へ」(2012年発行)の中で、1985年(昭和60年)の風俗営業法改正の記載がある。飲食物の提供、営業時間の変更が認められた一方で、「七、Bルール(些少の賭け)が認められなくなり1円でも麻雀で賭けることが出来なくなった」とある。
このBルールとは所謂「ブー麻雀」。大阪発祥のこのスピード感のある4人打の麻雀は日本全国に伝播した。阿佐田哲也の麻雀放浪記や、それをコミカライズした哲也でそのゲームをご存知のかたもいらっしゃるだろうか。
そこから派生してスポーツ麻雀などという名称で営業していた地域もある。どちらも、今ではレッドリストに載りそうなくらいしかない。2022年現在営業しているのは日本中で10軒あるのだろうか?それに対して、関東地方などのフリーの4人打は「長麻雀(ながまーじゃん)」や「リーチ麻雀」と呼ばれた。
ブー麻雀は日本中でブームとなった。警察から認可された印が入っていたカードがあり、ゲームの成績に応じてやり取りする。パチンコ屋さんの3店方式のような回りくどさはなく、雀荘で換金できる。ブー麻雀は、つまり警察から認められていた賭博であった。
それが1985年の風俗営業法改正で禁止となった。これが今に至る「フリー雀荘」がグレーゾーンと化した始まりである。
ブー麻雀からの転換
2022年現在、パチスロ機の5号機の認可期限が終了して6号機へと移行した。その影響で廃業したパチンコ店が多数。同様に1985年の風俗営業法改正によりブー麻雀店は多数廃業した。そのままブー麻雀を続けた雀荘はもちろんあったが、中には業態転換した店もある。
・貸卓だけの営業
・リーチ麻雀
・サンマ
ブー麻雀のメッカ大阪では、ゲーム性からリーチ麻雀よりサンマへの業態転換する雀荘が多かった。それが大阪に4人打雀荘が少ない理由である。
2021年あたりから、関東地方でもフリー雀荘が生き残りをかけて4人打半荘戦から東風戦やサンマに業態転換しているのは、この時期とよく似ているといえる。商売人は逞しい。
また関西人はイラチ(せっかち)で派手好みなため、サンマのゲーム性(ゲーム時間が短く、大きな手があがりやすい)がその気質にマッチした。人気が出るのも頷ける。
4人打
1990年代の関西を代表するフリーの4人打は、大阪北浜の「麻雀大学」、扇町「ジャンプ」、神戸南京町「グッドラック」、京都「フォーユー」。近代麻雀の広告掲載もあり学生から年配の方まで集い連日大変賑わっていた。ただ、僕は1987年から1992年まで横浜にいたため初期の頃はほとんど行かなかった。1992年以後大阪にいたが、それほど通わなかった。理由は以下の特徴的な2点であった。
①順位ウマではなく沈みウマ
25000点持ちの30000点返し。チップなしルール。オーラスの子で現実的に狙えるのは満貫。もうひと頑張りしてハネ満。18000点未満だとやることがない。しれっとあがる意味はあるが、あがると空気が悪くなる。僕にとっては楽しくないルールだった。
②ボード精算

ボード精算と聞いても、経験したことがなければきっと想像もつかないだろう。わかりやすく説明するために具体的な例と一連の流れを挙げる。
入店時に1万円(点5なら+200とボードに記載?)を預ける
↓
ゲーム開始
↓
ゲーム料金を現金で先払い
↓
ゲーム終了
↓
メンバーが卓まで来て精算をする
23700点持ち
↓
四捨五入で24000点持ち扱い
↓
30000点返しなので-6
↓
30000点未満なので沈みウマの10000点がつく
↓
-6に-10を加えて-16
↓
メンバーが精算ボードに成績を記載
↓
トップ以外の3人分を記載したらトップを計算
(僕-16、Aさん-18、Bさん-25なら、トップのCさんは+59となる)
↓
メンバー「Cさんの59のトップでした!」と発表
これを繰り返すわけだ。200ptが無くなったら、次のゲームが開始してから追加を要求される。いまいち勝っているのか負けているのかもわからない。退店時には精算ボードをもとに精算。このまったりした関西ローカルが肌に合わなかった。
自分が楽しいと思える4人打順位ウマのフリー雀荘として開店したのが今のイーソー難波店5階の店舗だった。時は2000年6月(?)、満を辞して順位ウマ、チップありとした。
3人打(サンマ)
1990年、関西にサンマの店はすでにたくさんあった。4人打の店の10倍以上あったというのを関東圏の人達は信じられるだろうか?!4人打は近代麻雀に掲載された以外にもあるにはあるが優良店は少なく、あったとしても点10以上だった。
それに対してサンマの雀荘はいくらでもあった。大阪のミナミ(難波周辺)にはたくさんあった。道頓堀には雀荘ビルがあり、ブルース・リーの「死亡遊戯」のごとく、フロアごとにレートが違った。ただ映画は下から上に行くほど強い敵だったが、このビルは1階が一番レートが高かったらしい。そしてレートは点10以上。点20や点40、さらに上も存在していた。
サンマの雀荘で、東1局に親が子を飛ばしてゲームを終わらせることを「東東ブー(トントンブー)」と呼ぶ。これはブー麻雀からサンマへと業態転換したことに起因すると思われる。
大阪の関西サンマルール
実は当時の関西サンマルールには大別して2系統があった。それは地域とも関連していた。
キタ(梅田周辺)系
・5の赤ドラは2枚
・1000点加符
ツモあがりは4人打の点数に1000点を足す
例、親でハネ満
6000点に1000点を足して7000点
ミナミ(難波周辺)系
・5は全赤ドラ
・まるっぽまたは丸取り
ツモあがりしてもロンあがりと同じ点数
例、親でハネ満
18000点を2人で分けて9000点
キタ系とミナミ系では、ルールに差があった。キタ系では守備が効くが、ミナミ系では親にツモられているだけで飛んでしまう。ミナミ系ではストリートファイトよろしく、殴り合いの強さ、攻撃力が求められる。このルールの差は大阪府の南北の地域差とピッタリと合う。北部は上品で南部は野生味がある。
2022年現在では、もうキタ系ルールはほとんどなくなった。ミナミ系ルールに淘汰された。そして関東圏のサンマもミナミ系である。戦い続ける攻撃力、殴られても殴り返す精神的なタフさが肝要である。
今回は、店内の雰囲気なんかはなくて歴史を語ることに終始してしまいました。最後まで読んでいただき有難うございました!
もっと突っ込んだ話は好きを押してくれたら頑張ります!フォローも良かったらお願いします♪
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
