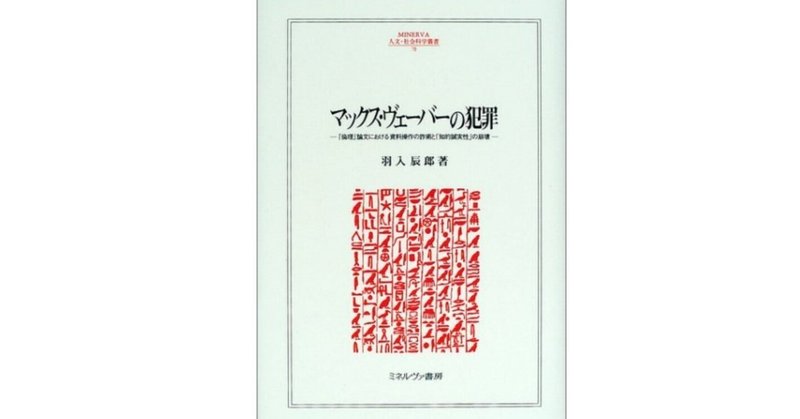
日本における学問の衰退と下流化,マックス・ウェーバー研究,羽入辰郎と折原 浩など
※-1 日本の大学・大学院における高等教育の不安要因
a) この記述は,現在まですでに溶融状態が顕著に進行させてきた日本の高等教育,この「凡人以下の学究(?)」までもわが物顔で闊歩する大学キャンパスの惨状というかその醜態を,あらためて考えてみようと意図している。
この本日の話題はくに,「日本における学問の衰退と下流化」のその具体的な姿を,マックス・ウェーバー研究に従事してきた「羽入辰郎と折原 浩」の論争「以前あるいは以下の〈学問的な問答〉」を素材に検討してみる。
本稿の記述は,2014年6月ごろになされた議論であるが,現在(2023年7月末)になっても継続的に,議論の余地を残したままの関心事であった。つまり,学的関心を向けつづけておく必要のある問題点が,以下に記述される。
以前になるが,佐々木力『東京大学学問論-学道の劣化-』(作品社,2014年3月)を店頭でみかけ,これは読むに値する本だという判断をし,実際に入手して読みはじめてみた。
この本は「現代日本の大学論」になっていた。また,日本の大学・大学院教育の重大問題である「大学の下流化・学問の下流化」を,日本の大学のなかでも〔いちおう〕最高水準だと思われている東京大学に勤務してきた佐々木力の実体験を通して語っていた。

パワハラあり,セクハラあり,アドハラありの最高学府(?)の実情は,読み物としても興味深い。だがともかく,数学を専修したあと,プリンストン大学大学院でトーマス・S・クーンらに科学史・科学哲学を学び,Ph.D.(歴史学)を取得し,東大に戻って教員生活に入ったこの著者の文章である。
もしかすると,大学の教員でもまともに勉強していない者には,「なにか・とても・嫌らしく」読むほかない中身,つまり,そういう程度にまで内容(教養・学識・文献など)がよく詰まっている著作になっていた。
つぎのアマゾン広告は古本であれば,191円(送料別)という価格が最安値で出ていた。興味ある人は一読を勧めておきたい。
ともかくさきに,紀伊國屋書店に出ている本書の宣伝にしたがい,その解説を聞いておこう。
★ 佐々木力『東京大学学問論-学道の劣化-』2014年3月 ★
1) 内容説明
斜陽の帝国=東大再生は可能か?! 近代日本の「国家貴族」養成所=東京大学は受験生のあこがれの的。だが,その国際的評価は低い。時の政府の「御用学者」を務め,原子力発電推進の中心的機構にして,異論を排除してきたこの大学に未来はあるのか。独立行政法人化以降,劣化の加速する東大内部の惨状を自身の処分事件と絡めて摘出する警醒と鼓舞のための書き下ろし。
2) 目 次
第1章 東日本大震災後の “国難” 状況の中,衰退の局面を迎えている日本の高等教育
1 新自由主義体制下でどのような姿勢で学問論に挑むのか?
2 東京大学教師歴三十年
第2章 「国家貴族」養成所としての東京大学-世界の大学の中の東大とその国策的在り方-
1 ブルデュー教育社会学と「国家貴族」
2 日本の学問のネオリベラル・アーツへの改変
3 現代日本の劣化の典型的一事例としての東大学問題
第3章 国立大学教員処分頻発とその実態
1 法人化後の大学で頻繁に起こるハラスメント処分
2 始まりの構図-2003年夏休み直前-
3 調査と停職処分の発令
4 追加処分の中,裁判闘争の準備
5 大学院担当の全面復権
第4章 原子力技術の国策的担い手としての東京大学
1 レッドパージは死せず
2 科学技術と現代政治
3 現代科学技術史の中の東京大学の役割
4「フクシマ以後」を田中正造学問論をもって照射してみる
第5章 未来の日本の高等学問のために
1「大局の明」探究に資する学問の原点への回帰を!
2 高等教育現場のモラル的再生を!
3 科学史・科学哲学という学問の未来
3) 著者紹介
佐々木力(ささき・ちから)--1947年宮城県生まれ,東北大学理学部数学科卒,同大学院で数学を専修したあと,プリンストン大学大学院でトーマス・S・クーンらに科学史・科学哲学を学び,Ph. D.(歴史学)。
1980年から東大教養学部講師,助教授を経て,1991佐々木力画像年から2010年まで教授。定年退職後,2012年から北京の中国科学院大学人文学院教授。東アジアを代表する科学史家・科学哲学者。
b) この佐々木力『東京大学学問論-学道の劣化-』そのものの紹介は,以上の程度で収めておき,本日の本題に入りたい。
ここではさらに,まえもって断わっておきたい点があった。
それは,佐々木力が,羽入辰郎『マックス・ウェーバーの犯罪-『倫理』論文における資料操作の詐術と「知的誠実性」の崩壊-』(ミネルヴァ書房,2002年)という著作に対して,
橋本 努・矢野善郎編『日本マックス・ウェーバー論争-「プロ倫」読解の現在-』(ナカニシヤ出版,2008年)や,茨木竹二『「倫理」論文の解釈問題-M. ヴェーバーの方法適用論も顧慮して-』(理想社,2008年)などが,羽入に対する批判を送っていた文献も念頭に置いたうえで,こう指摘していた点である。
東京大学大学院人文社会系研究家が公的に審査過程を経て博士号を授与した学問的 “業績” の質に関して〔いわねばならないこと〕……〔その〕もっとも重要なことがらは,いかに「大学院重点化」に学問的質が伴っていなかったかということである。
私は,もっと専門が近い科学史の分野で,同じ人文社会系研究科所属の教授を審査委員として論外の質である西洋科学の東アジアにおける受容についての論文で学位を受容された韓国人留学生の事例をしっている。その論文を基にした著書は公刊されてもいる。
付記)〔 〕内補足は引用者。
この文章が意味する〈実体〉はなにか?
1991年に開始した大学院重点化という教育政策が号令されてから,東京大学大学院を頂点とする日本の大学業界のなかに溢れだしてきた諸現象があった。それらについては,本ブログ筆者もすでに他の記述中でなんどか言及してきた。この「大学院関係の諸問題」のひとつとして,こういう事態が発生していた。
博士号を授与するに値する論文とは「とうてい感じられない,あるいは信じられないレポート」のごとき文章をまとめた,あるいは単なる習作風でしかない内容の論文に対して,とくに国立大学系の大学院が安易に学位を大量生産してきたのである。
実際のところ,筆者の場合でも,実に読むに耐えないような経営学関係の「学位論文」に接してきた。このごろの--ここでは21世紀に入ったばかりのころの話となっている--経営学の理論水準は,いったいどうなっているのか,若手の研究者がこの程度の水準でしか論稿をものにできないのであれば,斯学会の未来には希望がもてないのではないかという感想さえ抱かされた。
佐々木力『東京大学学問論-学道の劣化-』(作品社,2014年3月)の呈示してくれた議論は,本ブログ筆者が以上のように指摘してみた「日本の大学院」の質的な水準に関して湧き上がってきた〈疑念〉を,真正面より話題に挙げ,詮索するものになっていた。
※-2 マックス・ウェーバーに関する学問論争
青森県立保健大学教授羽入辰郎〔1953年生まれ〕が『マックス・ヴェーバーの犯罪-『倫理』論文における資料操作の詐術と「知的誠実性」の崩壊-』という書物を,2002年9月,ミネルヴァ書房から公刊していた。
本ブログの筆者は,社会科学研究に従事する立場から関心を抱いた,羽入の本書(定価¥4200-)を購入,読んでみた。その後,羽入辰郎は『マックス・ヴェーバーの哀しみ一生を母親に貪り喰われた男-』(PHP研究所,2007年11月)という新書版(定価¥700-)の著作も公表している。
羽入はこの『マックス・ヴェーバーの哀しみ』のあとがきで,こう断わっていた。
最後に折原 浩氏に言っておこう。
貴兄はこの本と見ると,羽入は自分の批判には一切答えずに,また別の本を出した,無責任極まりない,などと言ってくるであろうが,それは誤解であり,貴兄がそこで苛立つ必要な何らない。
本書を書き始める前の段階で,貴兄への反駁書『学問とは何か-「マックス・ヴェーバーの犯罪」その後-』と題した完成稿を,筆者はミネルヴァ書房にすでに提出しており,現在校正中である(205頁)。
ここに登場した折原 浩〔1935年生まれ〕は,東京大学教養学部教授を経て,名古屋大学・椙山女学園大学教授などを務めてきた人物である。折原の経歴をとおして有名な出来事があった。この経過を紹介しておく。
イ) 1968年~69年の東大紛争のなかで,文学部学生に対する「不当処分」問題をきびしく追及し,大学側と対立した。
ロ) 1987年のいわゆる「東大駒場騒動」事件。東大教養学部の助教授に推薦された中沢新一の学問業績について批判し,「賛成-反対」双方の書類を配布した。教授会の議決では異例の否決となり,中沢を推薦した西部 邁(1939-2018年)は,教授会に抗議して辞任した。
ハ) 2002年,羽入辰郎『マックス・ヴェーバーの犯罪』2002年が上梓されると,その内容をきびしく批判した書をつぎつぎと刊行した。その批判の対象は,羽入だけに留まらず,羽入的研究者を産み出したとされる現代の大学院制度にまで及んでいた。
それでは,「『倫理』論文における資料操作の詐術と「知的誠実性」の崩壊」という副題を付けた羽入辰郎『マックス・ウェーバーの犯罪』は,どのような主張を展開する著書だったのか。ひとまず,紀伊國屋書店のホームページに出ている「同書の案内」に聞こう。
『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』が出版されてから既に百年になろうとする。その百年間,ヴェーバーの誤魔化しは見逃され続けてきた。果たして人々が崇拝するほどにヴェーバーは正しかったのか。
本書は厳密なテキスト・クリティークにもとづき,その検証を試みる。ドイツ・ヴェーバー研究の世界に衝撃を与えた先鋭な研究の全貌が今初めて明らかとなる。
第1章 “calling” 概念をめぐる資料操作-英訳聖書を見ていたのか-(犯行現場としての『倫理』論文;ヴェーバーの主張とその分析 ほか)
第2章 “Beruf” 概念をめぐる資料操作-ルター聖書の原典ではなかった-( “Beruf” をめぐるアポリア;ヴェーバーによるアポリアの回避 ほか)
第3章 フランクリンの『自伝』をめぐる資料操作-理念型への固執-(フランクリンの功利的傾向;「神の啓示」の謎 ほか)
第4章 「資本主義の精神」をめぐる資料操作-大塚久雄の “誤読” -(「資本主義の精神」という魔術;「資本主義の精神」の構成 ほか)
終 章 『倫理』論文からの逃走 あのドイツ・ヴェーバー学界重鎮ヴィルヘルム・ヘニスをして恐怖せしめた驚愕の書。
はたして人びとが崇拝するほどにヴェーバーは正しかったのか。厳密なテ キスト・クリティークにもとづき,その検証を試みる。
ドイツ・ヴェーバー研究の世界に衝撃を与えた先鋭な研究の全貌が今はじめて明らかとなる。 《2003年度,第12回山本七平賞》受賞
※-3 折原 浩による「羽入辰郎」著作などへの批判
折原による羽入「批判」論に関しては,数多くの関係者がその論争〔ここでは,羽入自身の参入・関与はなかった段階での議論だが〕に参加している。2005年6月30日に折原自身が開設した,つぎのホームページを紹介しておく。
註記)http://www.geocities.jp/hirorihara/ ← このサイトは現在〔閲覧を試みた2016年5月以降〕閲覧不可である。べつに「折原浩のホームページ」というサイトがあった。
羽入によるウェーバー批判「論」の意図は,その題名からして明らかであった。ここでは,折原の立場を支持する論者の意見を紹介しておく。
羽入のヴェーバー読解および論文執筆の際の姿勢は不健全である。それはヴェーバーという権威を引き倒そうという悪意に基づいており,その予断に従って,原著者の意図や文脈に即さない「擬似問題」を自ら捏造し,巧妙にみせかけた不適切あるいは誤謬だらけの手法をもって,ヴェーバーの「知的誠実性のなさ」を発見したと息巻いている。
註記)http://hisphyussr.at.webry.info/200704/article_9.html このブログサイト:「ウェブリブログ」は 2023年1月31日 をもってサービス提供を終了していた。
〔羽入辰郎によって構成された自著〕書籍の内容は,ヴェーバーの上記の論文の主要な論点はほぼすべて無視し,筆者の都合のいいところ,論じたいところだけを断章取義的に抜き出して,筆者の勝手な論理を付け加えたものである。
その論点とは,「ヴェーバーが論文を書くにあたって,より1次資料に近い資料を十分に参照したかどうか」「ヴェーバーがどのような資料を見て,どのような資料を見なかったか」といった,はっきりいってどうでもよいことばかりである。
補注)本ブログ筆者にいわせると,この羽入辰郎のいいぶんは極端に過ぎて,学問の営為の世界から突き抜けていた。羽入の挙げたその論点はいずれも学問の手順としては重要・不可欠であるが,批判者のほうから「それらは」「どうでもよことばかりである」と受けとめられるほかない方向に走りこんでいたことじいたいに,むしろ問題があった。
〔本文に戻る→〕 万一,筆者の主張するところがすべて真実だとしても,そのことでヴェーバー の打ち出した仮説や理論の価値はまったく揺るぎはしない。 しかしながら,この著者が狙っているのは,ヴェーバーの「知的な巨人」というイメージをひたすら引きずりおろして,「世間では偉いといわれているヴェー バーなんてこんなもんなんだよ」という中傷誹謗による自己満足と,それに気がついたのは私だけですよ,といった自己宣伝である。
註記)「羽入辰郎『マックス・ヴェーバーの犯罪』徹底批判」,http://www.shochian.com/hanyu_hihan00.htm
その間〔2002年以降〕,羽入からの応答はまだないままであった。ただし,前述のように羽入は,もうすぐ新著を刊行する予定であり,折原などに対して反論を返すものと思われるので,本ブログでは今後の推移に対して,学問的な関心をもって注目したいとだけいっておく。
補注)羽入辰郎『学問とは何か-「マックス・ヴェーバーの犯罪」その後-』ミネルヴァ書房,2008年が,羽入がいっていた新著である。このへんの論点についてはさらに,後述において関連する論及を紹介する。
※-4 経営学界への含意-学問論争の意義と役割-
本ブログの筆者は,経営学界に生きる1人の学究として,まだ30歳代前半の若いころ〔昭和50年代前半,1970年代後半〕,この学界で権威的な学者であった山本安次郎〔戦後は彦根大学経済学部・京都大学経済学部・名古屋市立大学経済学部・南山大学経営学部の教授を経て,当時亜細亜大学経営学部教授〕との論争を体験したことがある。
最近の筆者は,明治大学経営学部で「経営哲学」を講じている筆者とほぼ同世代の教員が,2004年11月に公刊した著作,『経営哲学研究序説-経営学的経営哲学の構想-』(文眞堂,¥4000-)を,詳細に検討し,徹底的に批判をくわえた論稿を公表していた(2005年3月)。
さらには,明治学院大学名誉教授,現在(当時)愛知産業大学教授であった研究者が公刊していた著作,『経営財務本質論-もう1つの経営職能構造論-』(文眞堂,2007年3月)に対する「経営哲学」論的な批判論稿を執筆し,もちろん抜刷を差しあげてある。
なお,この最後の先生からの反応はなにももらえなかった。
明治大学経営学部所属だった前述の教員は,筆者などに対する「反批判を提示する論稿」を,専門的に関連する学会誌に公表していた。これに対して筆者は,同誌に「その論稿」に対しては再度「批判」した論文を,投稿していた。
羽入辰郎は,『マックス・ヴェーバーの犯罪』2002年の上梓を契機に,社会科学方法論の重要な領域である「マックス・ウェーバー研究」において論争がゆきかっていた様子は,ある意味で当然というべき学問世界における現象であった。
しかし,日本の経営学界において過去,学問上の論争だとみなせる交流がいかほど実現してきたかと回顧するに,それほど活発ではなかった。
昭和30〔1955〕年ころの「岩尾裕純 対 三戸 公」論争,昭和40年ころの「占部都美 対 雲嶋良雄」論争に比肩できるような経営学者同士による「批判の交流」「論争による学問の対決」は,それから半世紀以上が経過した21世紀のいま,ほとんどみうけられないものとなってしまった。
本ブログの筆者と山本安次郎との論争から早45年もの時間が経ったけれども,山本の弟子の世代に当たる経営学者がいないわけではないものの,その論争を超克しうる展開は,残念なことに途絶した。もっとも,そのように推移してきた時代の背景には,経営学本質論や方法論に対する伝統的な問題意識が希薄になった時代の風潮が控えていた。
※-5 学問論争の真価
とりわけ21世紀になってからの経営学界は,注目に値する学問上の「批判的な交流・創造的な論戦」,それも学問の本質や方法に関する議論がみられなくなった。日本の大学全般が「改革疲れ」のために教員たちが肉体的にも精神的にも疲弊した経緯も考慮しなければいけないにしても,この事情だけをその理由にしておいていい,という理由もなかった。
だからといって,世俗的な価値観=「○ 持ちケンカせず」というような,一見優雅な態度を,学問の世界において通用させるわけにはいかない。むしろ,当該学界が知的財産をより豊富に蓄積し,理論水準をより高度化させていくためにも,いい意味でのまともな学問論争が積極的になされねばならない。このことに反対できる同業者はいないはずである。
「批判や論争のないところに学問の発展はない」ということは,しばしば口にされるものである。ところが実際のところ,なかなか「そうは問屋が卸さない」のが実情である。とりわけ「権威的な学者先生」のいうことだからといって,初めから批判など棚上げしておき,それを鵜呑みにする学究の態度は「愚の骨頂」である。
学者同士が同じ課題をめぐってする研究であれば,当然ななりゆきとしてそれも生じることがありうる「見解の相違」の発生は,けっしてまれな事態だとはいえない。
にもかかわらず,相互間においてあえてなにも意見を交わさず,もとより,その批判点のありかさえ提示しないで済ますのであれば,真理を究めねばならない学問の本義からは退いた「後ろ向きの営為」である。
学問の発展という高邁な理念よりも,特定の学界内人間関係における友情維持のほうがより大切だというわけである。だが,こうした学的姿勢に人生訓としての一理はあっても,学問世界の作法でいえば普遍的な妥当性はいっさいありえない。
羽入辰郎と折原 浩〔など〕との論争を,専門外の人間として筆者は,はたでみている立場でしかなかったが,当事者間のやりとりとして「相当に熱がこもった応酬」が展開されていた。この展開は当然であった。
ましてや,当事者の学者的生命を賭した「批判-反批判」であるならば,必死になっての双方の攻防戦になるほかない。それでこそ,真実への接近も高まり,マックス・ウェーバー「社会科学論」の意義に関する評価も,その議論において精緻さをいっそう究めていくことができる。
もっとも,学者商売においておたがいに議論し,批判を交わして傷つくのが怖いのであれば,学問上の論争は止めて仲良し集団としての毛繕いに励めていればよいのである。しかし,それでは「学者が学者たるゆえん:資格」を剥奪されるほかなく,研究者失格の烙印を押されること必定である。
※-6 羽入辰郎の奇妙ないいぶん-ウィキペディアの解説から-
羽入辰郎は,自著『マックス・ウェーバーの犯罪-『倫理』論文における資料操作の詐術と「知的誠実性」の崩壊-』(ミネルヴァ書房,2002年)の公刊にきっかけに,問題が浮上した本書の論点に関連して,つぎのように論断していたが,こうした学問的な姿勢・応接の仕方は,不遜であるだけでなく,いわば開きなおりであった。
「論文における資料操作査の詐術」とかこれにまつわる「知的誠実性(の崩壊)」をウンヌンする当事者がつぎのように応えたら,これは完全にアウトであった。自説において肝要な核心の主張にもかかわって,この種の弁明を強説するようでは,ほぼご臨終。
要は,先行研究への渉猟が甘かっただけのことであり,つまりは,これにてお終いになっていたということになる。
『マックス・ヴェーバーの犯罪』の中心的論点は,ヴェーバーの引用する独訳聖書(「コリント人への第一の手紙」7章20節)における Beruf (宗教的召命と世俗的職業を同時に意味する)の訳語が,マルティン・ルター本人に由来するものではないというものであり,羽入はこれを(百年間誰も気づかなかった)「世界初の発見」(「エコノミスト」2002.12.10 P60,『学問とは何か』P228)としていた。
しかし,実際には沢崎堅造『キリスト教経済思想史研究』(1965年未来社,初出論文は1937年刊行)によって同様の指摘がすでにおこなわれていたことが判明し,「筆者は “Beruf” 概念に関する議論に関して,筆者が世界で最初の発見者であるという主張をここで取り消す」と述べた。ただし,「先達者がいた,ということが分かったとしても学問的にはなんら問題はないのである」(『学問とは何か』P194,196)としている。
自然科学の学問世界で羽入辰郎がこのように発言したら,初めからダメ押しされるしかない「学問以前の理屈だ」と断定され,そして排除もされ,あげくは相手にされなくなる。リクツは理屈でもほとんど屁理屈にしかなりえない抗弁であった。
「先達者がいた,ということが分かったとしても学問的にはなんら問題はないのである」
などと平気でいえるとしたら,これは暴論・盲説のたぐいであった。
「先達者がいた」ということは,学問の世界においては,はたしてどういう意味になるのか? 学問研究において先行して蓄積された成果・業績を,とくに自分の研究課題にかかわるそれを漏らしていたら,これは決定的にまずい学問展開上の手抜かりである。
羽入辰郎の口調でいわれていたように,その「研究者(先達者)がいた,ということが分かったとしても学問的にはなんら問題はないのである」と断定できるのであれば,学問も理論もなにもあったものではない。
羽入辰郎はその一言で自説の立場に関してボロを,みずから披露したことになる。ウカツにも,いってはいけない禁句を,学問の世界における作法を軽視するかのようにして口走った。
-----------------------
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
