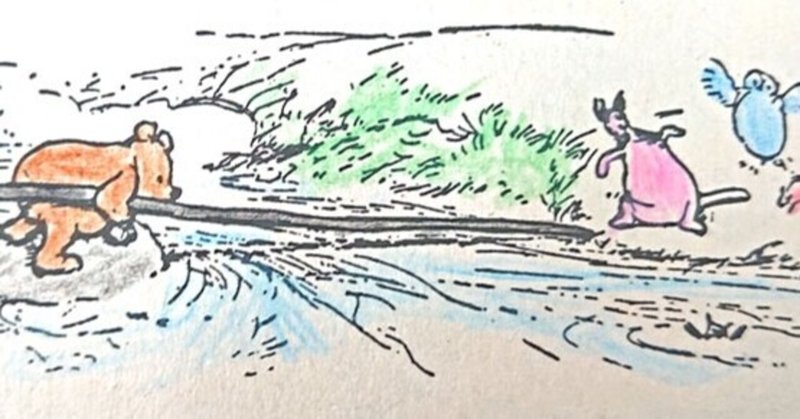
Yoga Recollections 1959-1984 (02)
遊び好きってそう見えますか? ええ、そう思われたのならそうなんでしょうね。新潟日報の記者の簔輪紀子さんに昔エッセイの連載を頼まれた。三〇年ほど前のこと。何しろタイトルが「遊び感覚」。大学に赴任してからの長き独身時代の遊びを毎週千二百字、一年半書いた。真に受けた保護者とか同僚から遊び過ぎだ!と言われたこともあったし、事務のオバサンから「休暇届出して下さい!皆、読んでますからね」と叱られたこともあったが、今はもう怒られることもないだろう。昔話だし。そんなわけで、幼少から大学院まで過ごした世田谷区用賀での遊びの色々を思い出しつつ書いていこうと思う。
冒険はしないとね
冒険は聞こえが良くていい。貸本屋で月刊誌「冒険王」をとっていたくらいだ。昭和39年頃は祖師谷にある貸本屋がオートバイで配達してくれた。漫画や童話が多かったが、母が寝る前に読んでくれた「クマのプーさん」がとくに好きだった。その中に北極探検の話がある。石井桃子さんの訳が奮っていて、探検 expedition をプーが言い間違えてexpotition と言ってしまう。それを「てんけん隊」と訳している。 これが妙に心に響き、僕も「てんけん隊」やるんだ、と思っていた。近くに関東中央病院の看護婦寮建設予定の空地があり、隅が草藪になっていた。ここが最初のてんけんの目標。近所のガキを引き連れて中央の灌木を制覇し、そこに基地をつくった。空き缶に駄菓子屋で買った非常食の麩菓子、読み終わった「少年サンデー」に宝物の鉄腕アトムのシール。口外しないことを誓約したのに、その日にタツちゃんが親にもらし一日天下に終わった。小3の時は成城学園前の現在は成城石井が店舗を構える場所に地下基地を設営した。前の建物を解体した跡地で、地下室の上に板をかぶせて作る。こちらは成城学園初等科の駄菓子屋も知らないお坊ちゃんたちと。基地の近くに住む濃緑色の革パンを履いてるマツダ君が婆やの料理をもってきて、さすがにそれはないだろ、てんけんじゃなくなってしまうと違和感をもったものだ。
冒険のお目当てはまだまだいっぱいある。現桜ヶ丘三丁目から用賀駅に抜ける道路沿いに公務員住宅が並んでいて、その側面が勾配のきつい崖で、延々百メートルくらい続いていた。そこを滑り落ちることなく横断するって誰が言い出したんだ?必ず無謀なことを言い出す奴がいる。そして大抵はいざとなるとやって来ない。途中で滑ったら交差点からやり直し。木の根っこが飛び出していて、小石も混じりなかなか危険ではあったが、中途から制覇するよりも滑ることの方がずっと楽しいことが分かり、むしろ滑走に専念するようになった。八百屋の子が段ボールの切れ端を持ってきたら、もう止まらない。ルールの突如変更は子どもの特権だね。母に破傷風になると怖いから、とやめさせられた。
病院の塀際はぐるっと木立になっていて、木登りに適した格好の樹木が沢山あった。背が足りない頃から習熟していて、長じて秋になれば近所の柿の木に登りカラスよりも早く盗み食いしたものだ。大抵は見つからなかったが、祖師谷大蔵の地主の家では、樹上で親爺と眼が合ってしまった。捕まって説教を喰らうかと思いきや「言ってくれれば分けたのに。落ちたりしたら洒落にならんぞ」と言われた。シャツがはち切れそうなくらい貰った。渋柿を。今でもスーパーの棚に置かれる柿を見ると「これは買うものではない」と思ってしまう。近くに枇杷の木があって、これは登らなくても獲れるけど、何かやってはいけない、とても悪いことだって直感が働いた。寂しげで寡黙な老婦人の一人住まいだったからか。その隣の塀にもたれかかる木苺は遠慮なく頂いたけれども。
廃屋に忍びこんだこともある。リーダーの名はコロッケ。二歳年上で今もって本名は知らない。夕食後懐中電灯をもって、コロッケが目星をつけた陋屋に忍び込む。なんでも家主が置き忘れた宝が必ずあるのだと。ある時天井近くに古びた箱を見つけた。みな色めき立つなか簡単に開けられた。指先ほどの黒い塊がはまっていて、それを外しコロッケが神妙な面持ちで言った。「これが世に言うデンジシャクだ、坊や大切に保管するんだ。親に言ったらダメだぞ」。帰ってすぐに父に見せたけど。よくやったと褒めてくれた。
牛乳の蓋を集めたきっかけは
家の前の砂利道を病院の方に三十歩ほど行ったところの大工の山本さん宅。ここの立派な作業台が会場だ。次男のターちゃん、三男シューちゃんを交えて、集まった面々ポケットから牛乳の蓋を取り出す。中2の時に給食が「超不味」の脱脂粉乳から瓶牛乳に変わった。更にテトラパックになるのは二年後。毎日蓋が手に入るようになった時にはこのゲームは廃れていたわけだ。さて各自蓋を一枚取り出し、それを銘々台の端から掌で叩いて台上を滑り飛ばす。向こうに落ちず一番遠くまで飛ばした者が残りの蓋を総取りできる。簡単なルールだけど裏面に蝋を塗ったり、空気抵抗を減らすために万力で潰してくるのもいた。小3だから東京オリンピックの頃だ。
低学年に流行っていたこの楽しみを冷ややかに一蹴したのが角地の広い家に住んでいるアッちゃんだ。「そんなザコ集めても意味ないよ」と言って、スクラップに貼り付けた全国の牛乳の蓋を見せてくれた。凄い!コレクションという言葉を初めて知った。お父さんが出張の度にご当地の牛乳を飲み、蓋を持ち帰ってくれていたらしい。兄貴ぶって「これをあげるよ」とくれた蓋は濃紺地に須藤善の三文字。こんな世界があるのかと感心し、すぐに実行するところが子供だね。もう自転車に乗れた小4の春に世田谷通りを西進。バス停で言うと🚏宇山を出発し、🚏砧ゴルフ場前(現・三本杉)、🚏砧町、🚏NHK技研前の路地を右折(左折すると厚生年金プールがあって夏はもっぱらそちら)。そこには全酪乳業の工場がある。自転車を隠し侵入し使用前の蓋を物色する。瓶に嵌め込むと辺縁が反ってしまうので未使用のものはレア扱いだったし、ザコ数枚と交換できる。自転車で遠出したので後で母から叱られた。同情した父は以後コレクションの手伝いをしてくれる。登山や温泉巡りが好きでよく一人旅するものだから、数か月でスクラップ6冊分になった。牛乳飲まないのにね、と母が不思議がっていたっけ。
父から更に裏技を伝授され、とうとうアッちゃんを抜くことができた…と言っても快挙を伝えに行ったら「フン、まだそんなことやってるんだ」と悔し紛れを言っていたけどね。裏技と言うのは父の考案で全国の牛乳工場長宛に「牛乳のふた集めてます。余ってるの送ってくれると嬉しいな」とハガキを書く。「いいか、子供みたいな字で書くんだぞ」と念を押していたけど、息子は小4ですからね。何をか言わんや!結果、稚拙な字が奏効してつぎつぎと蓋が送られてきたし、北海道からはアイヌ伝説の土産品と励ましの手紙入りの小包が届いた。「たくさん牛乳飲んで下さい」と結んであり、実は飲めないんです、とはとても言いづらかった。
メンコの全盛期
メンコはまず駄菓子屋で五~十円の新品を買う。あるいは誰かに恵んでもらう。表の絵柄は色々あり当時テレビで放映されていたアニメキャラ、8マン、月光仮面、鉄腕アトムとか覚えている。それぞれ参加者がメンコをかけて戦うゲーム。ルールは主に三種あった。絵柄を上にして一枚ずつ路面に置く。順に自分のメンコを手に取って強く叩きつける。その時の風と振動で一枚でも裏返しになれば自分のものにできるし、更に続けることができる。足で壁をつくり風を反射させる高度な技術も習得して、結構分捕ることができた。もう一つ名前の由来の分からない勝ち方がある。地面を滑らせて相手のメンコの下に挟まると「サバ」と言ってこれも勝ちとなる。勝ちは勝ちだがせこい勝ち方で爽快感がない。キヨシちゃんはこれが得意で、草野球でもバントヒットを狙ったり「せこキヨ」の本領を発揮していた。でも一歳上のキヨシちゃん、好きだったな。独特の間の取り方で人を笑わせるし、とにかく優しかった。近所の遊び友達は多くが一歳か二歳年上で中学に行くと遊ばなくなった。(私はいっそう遊ぶようになったけど)。詰襟の学生服姿をまるで出征兵士を見送るような気持で眺めたものだ。小6で遊び場の小さな大将になり、妹弟をまじえ専ら年少の子の面倒を見るようになる。
話を急ぎすぎた。近所の連中とは上記のルールでメンコをしたわけだが、ブルジョワ小学校のインフレルールは全く違うものだった。近くの区立用賀小学校に通わずに成城学園初等科に通ったのは、何も家がブルジョワだったからではない。父は自身が旧制成城高校の出身。その時の恩師の誘いで市立沼津高校から母校に転勤していた。同じキャンパス内の初等科に職員家族として入学すれば授業料が免除されたし、大学(流石にここからは半額負担)まで行けた。実際妹二人は大学まで進んだ。そんな事情を知らない四人兄弟姉妹は、有名人の子弟や後に芸能人となる子が多く通うブルジョワ小学校の日常に随分と面食らった。その話はまた別の機会に。
メンコを今で言う大人買いして、箱にいっぱいにしてもって来る奴がいる。ここでのルールは「山崩し」と言って二人で対決する。小メンを数十枚互いに同数出し合い裏面を上に向けて積み上げる。これを大メンで崩しつつ表に返す。一枚を残して他全部を表に返せば総取りとなる。もし一撃で全部が表に返ってしまえば、相手に番が移り大メンの打撃で一枚だけ裏に戻せば勝ちになる。ここまで書いてあの呪文のような言葉が甦ってきた。「いっちょいきなし、きゅうにっこなし」。実は当人たちも何を言っているのか分からなかったのではないか。ガキどもは呪文のようなジャーゴンをよく使ったものだ。想像するに…「いっちょいき」は「一丁行き」で「一気に勝つのはダメ」つまりいきなり勝つのはずるいからダメ。と言うことは、端から終形の一枚残しにしても勝ちにはならない。山崩しをじわじわと楽しもうということなのだろう。「きゅうにっこなし」は「急に言いっこなし」で、これは突如ルール変更を言い出すのもずるいということ。例えば、「一枚残し」じゃなく「全返し」にすると急に宣言してはならない、ということだと思われる。賭けのメンコ枚数のインフレは決して満足を齎さなかった。近所の公立の子たちとの日銭をコツコツ貯めるような遊びの方が数段好きだった。
パチンコについても同様のことが言える。子供にとってはお祭りが唯一の体験で、それ以外は親か年長者に連れていってもらう他なかった。メンコに熱中した頃のパチンコ台はまだ玉を一つひとつ穴から入れるタイプのもので、仕掛けもチューリップが一つ二つあるだけのシンプルなものだった。中学の頃には玉の自動送りのポケットが設けられ、天釘下部の中央部に命中すると、からくり仕掛けが動いてチューリップが満開になったりする。これが好きで儲けは度外視して渋谷か下北沢のパチンコ屋の常連になった。この時はもう高校生だった。メンコと同じでパチンコ機も出玉のインフレ化が進み、昭和50年頃にはほぼすべての台が電動になり果て、パチンコへの情熱を一切失ってしまった。電動ダイヤルを紙片で固定し見ているだけなんて、退屈きわまりない。バイトした方がずっと生産的だと思い、機種の進歩にしたがってパチンコ屋から足が遠のいた。それでも、今もときどき旅の途次、手打ちのレトロ台を見つければ、儲かるわけでも失うわけでもない、玉はじきと仕掛けだけの享楽を味わっている。富山の総曲輪と釧路にあったなあ、レトロ台。今はどうだか…。
閑話休題。メンコのもう一つのルールは「幽霊」や「風」と呼んでいた。小メンを裏返しに一枚ずつ地面に置いて、大メンを使わずに平手で風を起こして裏返しにすればそれを自分のものにできる。山崩しで大負けして没落すると、なけなしの数枚からこの「幽霊」でコツコツと稼いでいくしかない。それでも負けるとメンコ資産家から数枚借り受け、あとで利子をつけて返すか、帰りにランドセル持ちを引き受ける。でもこの屈辱は味わったことはないな。メンコの時代は小6まで。実はメンコと並行して将棋に熱中していて、もう道場通いして腹巻したおっさん達に交じってリーグ戦なんかに出ていた。
ごっこ遊び
忍者ごっこはロジェ・カイヨワの「遊びと人間」だと、ミミクリに相当するんだろうね。真似事なのだから。ごっこ遊びはおもに近所の子たちと。何と言っても横山光輝の「伊賀の影丸」の影響が大きかった。(白戸三平のサスケは少し上の年代だ)。ジャンケンで勝った者が影丸になれて、剣を背負うことと風呂敷を使った頭巾をかぶることができる。木の枝で作った剣とボール紙を切り抜いた手裏剣で攻撃し、切られたり当たったりすると百数えるまでは倒れて死んでいないといけない。影丸役は忍法「木の葉隠れの術」を使うことができ、集めておいた枯葉を懐から取り出し、呪文とともにまき散らす。この必殺技には全員が「うーっ!」と唸ってもだえて倒れるのがお決まり。眼鏡のオサム君はこの時「思い知ったか隠密めっ!」と大声で決め台詞を言う癖があった。影丸はれっきとした隠密なんだけどね、回りが気がつかないので黙っていた。
キヨシちゃんが空缶の蓋を切り取ってリアル手裏剣を作ってきたことがあったが、木の幹に突き刺さるのを見て怖くなったこともあり使用禁止にした。でも新兵器は欲しいねとみんな思っていたら、ある日父が「弩を試したらどうだ?」と、効果的で安全な中国古代の兵器の簡単な模型を作ってくれた。朧げな記憶から製作手順を復元しよう。当時お風呂は薪を燃やして沸かしていた。家の軒下に炭屋の若松屋さんが届け置いてくれた薪の一本を使い、テッペンのところに釘で輪ゴムを固定し、底部には洗濯ばさみを紐で結わいてとりつける。手裏剣代わりのボール紙の小片にゴムを引っかけて伸ばし、これを洗濯ばさみで止めれば発射準備完了となる。後で図録で調べたけれど、これは弩じゃないね。それでも他の子もそれぞれ自作し、われら忍者隊にも近代がやってきたということか。いや、古代だったか。
書き出したら他にもいろいろと思い出してきて、遊びの逸話は尽きないことが分かった。明治四〇年刊行の松浦政泰編『世界遊戯法大全』には何と八百四十七の遊びが掲載されているが、これにも触れられていない遊びも随分あった。またいつか、書いてみたい。
でもそれはまた別の話。2021.12.2
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
