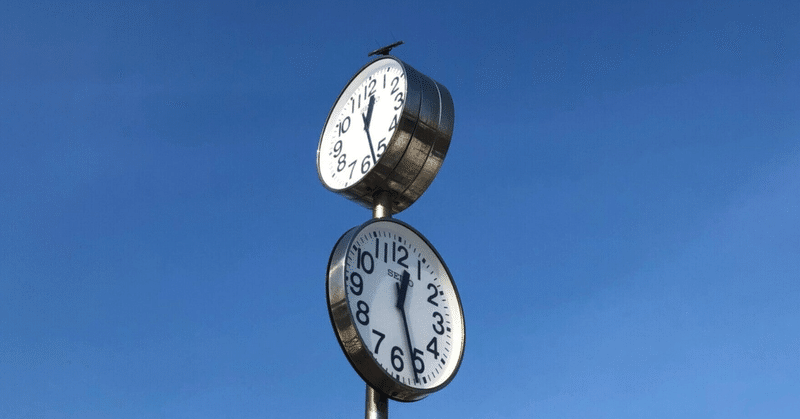
卒業発表会を視聴して…
昨日は通信制文芸コースの卒業発表会。
以前通学部の講評会を視聴した時のこと、
あらすじとか概略だけでは曇ったガラスを通してみるようで
つかみどころがない。会場の参加者は冊子のようなものをもっているので
それはどこかでみられるのかと思ったがそうではなかった。
オンラインで各作品は購入できる、といわれましても
よしあしのわからないものを買う気は起らない。
今回はもっとわかるようなものだろうか、と期待した。けれども。
まず、10名の発表のはずがトップバッターがいない。
何事もなかったかのように繰り上げて進行される。
ねらいとあらすじ、ないし抜粋は事前資料として配布されてはいるが
これだけではやはり要領を得ない。
本人が作品について述べた後、担当教員が評を述べたり質問したりする
(担当が参加しておらず代行されるケースあり)
資料に載っていないシーンについてのやりとりは
こちらにはなんだかわからない。
何人かの話を聞いているうちに資料化するのが物理的に無理があるのが
理由の一つではないかと思った。
一人あたり少なくとも3万2000字。多くの方がそれ以上書いているようで、これを資料化するのも、受け取って読むのも大変だ。
参加者の方もコメントを、と求められてもかなり難しい。
まさに『読んでいない本について堂々と語る方法』が必要だ。
私的には旅とワインの話やアステカの物語、書くことのカタルシスなどについては、口をはさみたい気もしたのだが、それは作品についての問いかけではなくなってしまいそうなのでやめておいた。
うらやましいのは約2年、人によってはそれ以上の時間をかけ担当講師と作品を作り上げたことだ。私が卒論に関わるときは時間もボリュームも圧倒的に少ないカリキュラムになる。口頭試問もないんだよ!
入学した価値が下がってるよ。
短い作品だって練り上げるのはたいへんなことですが
それにしてもねぇ。
あと、気になったのはWEB上にも10名の方の作品があがってますが
発表会名簿とは一致しない方も。
なかでも賞をとられた方3名が発表会にいらっしゃらなかったこと。
賞に値する作品くらいは全部読ませてくれてもいいんじゃない?
実際のところは京都まで出向いてみるしかない。
時間とお金をかけてまで今することなのか?
卒業近くなったら、3年のときとかでもいいよね。
だって、カリキュラム変わっちゃうんだし。
さてさて、いったい今期の卒業生は何名だったのでしょう?
プライバシーとか著作権とかいろいろハードルがある。
絵や彫刻、そのほか立体や一目で見られる作品を作っている学科とは
異なる難しさが文芸にはある。
そのあたりを踏まえたうえでも
これはなんだかな、ともやもやする発表だった。
ともあれ。ご卒業の皆様、おめでとうございます。
参加の方、おつかれさまでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
