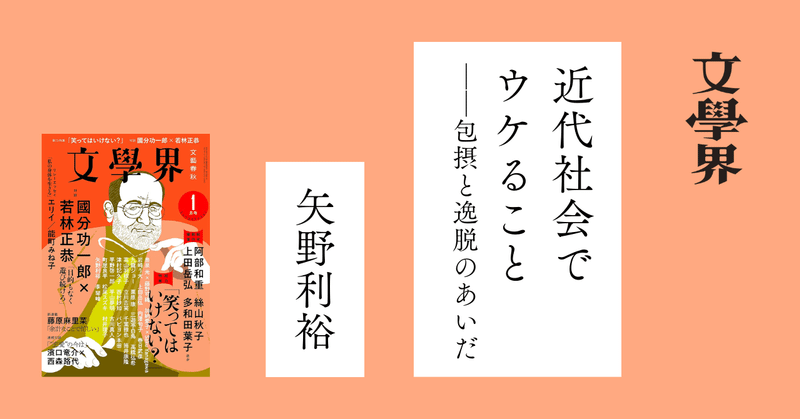
【批評】矢野利裕「近代社会でウケること――包摂と逸脱のあいだ」
現代のリベラル傾向
10年まえに笑えていたことがもう笑えなくなっている。いや、10年まえどころではない。ほんの数年まえに楽しんでいたはずのテレビやラジオの番組でさえ、久しぶりに観/聴きなおしたら、その不用意な発言や振る舞いに気持ちがざわついてしまう。ましてや、YouTubeで昭和のヴァラエティ番組なんか観たら、ジェンダーや人種といった問題に対してあまりに配慮のないことに驚いてしまう。ここ1〜2年、多くの人が少なからずそのような経験をしているだろう。
人権意識やハラスメント意識が高まったこの社会において、笑いに対する意識は確実に変化した。芸能の野蛮なありかたに郷愁をもつ者は、この変化に対して批判的になるだろうが、とはいえやはり、この意識の変化はもう前提である。セクシャル・マイノリティや有色人種に対して、その属性を笑いの対象にすることはできない。あるいは、発達障害を想起させるようなキャラクターに対して、彼/彼女のコミュニケーションそれ自体を笑いの対象にすることはできない。
作家の中島らもはかつて、「笑いとは「差別」だ」となかば挑発的に宣言し、「見世物」たるプロレスについて、「「異界人」の混沌の中から試合が組まれ、観客はその「異界性」を外側から眺め、楽しみ、笑う」と指摘していた(『何がおかしい』白夜書房)。しかし、さまざまな身体的条件を社会の内側に包摂する現在にあっては、「「異界性」を外側から眺め、楽しみ、笑う」という無責任な態度は許されないだろう。
先日おこなわれた『キングオブコント2021』は、そんな笑いをめぐる意識の変化を本格的に感じさせるものだった。『キングオブコント2021』において示されたのは、「感動コント」の傾向(堀井憲一郎)という以上に、もっと具体的に、なにを笑いの対象とするか、という問題だったはずだ。
例えば、優勝した空気階段の一本目のコント「火事」は、SMクラブに通う消防士(鈴木もぐら)と警察官(水川かたまり)が登場するものの、彼らの変態性を笑う構造にはなっていない。そのセクシャルな志向はむしろ、ダイバーシティ的な価値観のもと認められるべきものとなっている。そのうえで力点が置かれているのは、それぞれの職業倫理を果たそうとする必死な姿のほうである。
また、決勝で披露された「メガトンパンチマンカフェ」のコントも、自らが描いた架空のマンガをカフェにするという妄想癖的な危うさを抱える人物(鈴木もぐら)が登場するものの、彼の性格それ自体を笑う構造にはなっていない。ナイツの塙宣之が「いい奴なんだよ、あいつ」と感想を言うように(「キングオブコント2021・勝手に採点してみた!」『ナイツ塙の自由時間』)、力点はむしろ、彼のひたむきさに置かれている。
空気階段に限らず、『キングオブコント2021』において笑いが起こったのは、コントに登場する人物たちのひたむきさに対してだった。ここで細かく分析する余裕はないが、『キングオブコント2021』において、多くのコントは、登場人物の異質性を突き放して笑うような構造にはなっていなかった。彼らの異質性は、いち条件にすぎない。むしろ、その条件のもとでひたむきになにかをする、その「夢中」さのともなった「ボケ」(マキタスポーツ『決定版 一億総ツッコミ時代』)のほうが強調されていた。
さらに言えば、そのひたむきさはまるで、過酷な芸人の世界を生きる彼らのひたむきさを示しているようだった。芸人の身体は、キャラと人格を、ウソと本当を、貫通するように存在している。「ドーランの下に涙の喜劇人」(ポール牧)という昭和芸人の美学もいまは昔、優勝した瞬間の空気階段が体現していたように、キャラも人格も貫通した地点でおおいに涙を流すのが、令和の芸人のありかたである。
上記のような笑いに対する意識の変化は、もちろん社会的な意識の変化と対応している。とくに2010年代、ジェンダー論やポスト植民地主義といった学問的成果を背景に、ポリティカル・コレクトネスの意識が広まると、それは芸能界をはじめとするエンターテイメント業界にも適用された。結果、ヴァラエティ番組やお笑い番組は、差別的な振る舞いが厳しくチェックされることになる。
このことは、人種や階級といった従来的な社会的差別に限らない。むしろ、ここ数年でとりわけ一般化しつつあるのは、ルッキズムに代表される外見的特徴を笑うことへの批判意識だろう。ヴァラエティ番組においても、例えば「ブス」といった言葉で笑いを得ようとすることは、ここ数年で完全に時代遅れになった印象がある。ここでは、このような傾向を総じて《リベラル》と呼んでおこう。
このようなリベラル傾向については、近代社会を生きる者として基本的に好ましく思っている。わたしたちの社会は誰もが平等に生きられるべきであり、自分ではどうしようもできない条件について、他人からどうこう言われる筋合いなどない。お笑いの世界がリベラルでクリーンなものになっていくことは、近代社会の歩みとして否定されるものではない。その意味において、わたしたちの社会はまだまだ課題は多いものの、少しずつ良いものになっていると言うこともできる。
《大衆》性としてのリベラル
とはいえ、慎重にならなければいけないのは、この社会の歩みがそのまま笑いの世界にパラフレーズできるのか、ということだ。やはり、芸能の論理は、演芸の論理は、社会とは別の水準にあると考えるべきではないか。
社会的な水準で言えば、いまだに「ブス」とか言って笑いを取ろうとする芸人は、この社会を生きるリベラルな市民としての意識が低い、ということになる。それは例えば、よく話題にされるようなハラスメント気質の残る中年男性の意識の低さと同様だ。もちろん、芸能の論理が社会の論理と異なるからといって、そのような振る舞いを擁護する必要はない。言われたほうが嫌だと思うならば、先輩芸人だろうが会社の上司だろうが、粛々と批判をすればいい。芸のためならばなんでもアリなのだ、という「浪花恋しぐれ」(岡千秋、都はるみ)的な芸人のロマンを盾に取ったような開き直りに付き合う必要はない。
では、芸能の論理が社会とは別の水準にあるとはどういうことか。さきほどとは逆の方向から問うてみよう。つまり、現代的な芸人における、それ自体は好ましいと思える芸風は、本当に現代的なリベラル意識の高さから来ているのだろうか、と。演芸の論理を社会の論理とイコールで結んではいけない。そこでは、もうひとつメタの位置から考える必要がある。
例えば、寛容な態度で前向きに相手を認めていくような「ノリツッコまないボケ」(松本人志)によって「誰も傷つけない笑い」の筆頭となったぺこぱは、いかにも現代のリベラル的な価値観を見すえた芸風でブレイクした。しかし、ツッコミの松陰寺太勇がさまざまなキャラを変転していたことはよく知られているし、実際、松陰寺自身、ぺこぱのネタについて「漫才をフリにした漫才で、優しさ先行ではない」と言っている(テレビ朝日『太田伯山』2020・3・12放送)。
松陰寺の発言より少しまえ、ライターのハシノイチロウは自身のブログで、ぺこぱの漫才をジャンル内在的な視座から評価しつつ、「誰も傷つけない笑い」という言いかたには違和感を表明している。
普通の漫才であれば、ボケがおかしなことを言ったのに対して、ツッコミが訂正や叱責や暴力やときにはドン引きするといった否定的なリアクションをとることで笑いを生んでいくところ、ぺこぱはどんな素っ頓狂なボケに対してもすべて受け入れていくという、他にはないスタイルを打ち出した。
ようするに、差異化をしていたということである。ぺこぱは、それまでの漫才から差異化するように「ノリツッコまないボケ」というスタイルを作り出したのであって、本人としては寛容さを目的としたわけではない。その意味では、ハライチの発明した「ノリボケ」と同様、あくまでも漫才というジャンル内のイノヴェーションとして、「ノリツッコまないボケ」という方法が生み出されたに過ぎない。それはむしろ、自らの商品価値を高めることを目指す、すぐれて資本主義的な態度だ。いちアイデアとしての「ノリツッコまないボケ」が時代的な追い風を受けるかたちで、ぺこぱをブレイクさせたのだ。
『キングオブコント2021』も、同じ論理で捉える必要がある。例えば、ザ・マミィの一本目のネタ「この気もちはなんだろう」は、ぶつぶつと独りごとを言う変わったおじさん(酒井貴士)に対して青年(林田洋平)が道をたずね続けるネタだが、ここで最初の笑いどころとなっているのは、「お前、すごいねえ!」というおじさんの青年に対するツッコミであった。つまり、変わったおじさんが笑いの対象になると思いきやそうならない、むしろ、青年のほうが実はボケだった、という“ズラし”の瞬間に笑いが起きているのだ。
その後、おじさんは「偏見とかないの。普通あんまこういうタイプの人に話しかけないんだよ」と続けるが、このセリフは、変わったおじさんに対する差別的な「偏見」をむしろお笑い的な「普通」としつつ、その「普通」を裏切っていこうとする方向性を知らせている。従来的な展開からの“ズラし”こそが、「この気もちはなんだろう」というネタの鮮烈さを支えているのだ。
ここから見えてくるのは、笑いを求めることを第一義的に考える芸人の姿である。ぺこぱにしてもザ・マミィにしても、あるいは空気階段にしても、例えばダイバーシティ的な価値観を体現する目的でネタを作っているわけではない。お笑い芸人としての彼らは、当然のことながら、観客にウケることを目的としてネタを作っている。
芸人・ミュージシャン・俳優のマキタスポーツは、リベラルな価値観に反する芸風がもはや客にウケない、ということを指摘しながら、次のように述べる。
我々お笑い芸人っていうのは、そうは言ったってさ、実際にお客さんのまえに立って市場調査をやって、これのほうがウケるからとかっていうさ、それしか考えてない人たちなんだから。だから、別になにか思想があってやっているというよりも、ウケないからやらない。
芸人の美学を打ち出しつつも、クレバーな分析だと思う。この優先順位の付けかたと行動原理が、社会の論理と演芸の論理との最大の違いである。爆笑問題・太田光の言葉を借りれば、「とにかく俺らが思ってるのは、笑いがほしいっていうことだけだから。そこに倫理もなにもないんですね」ということだ(『Quick Japan vol.156』2021・6)。
芸人は第一義的に笑いを求めている。この点を見誤ってはいけない。だから、漫才にしてもコントにしても、ネタにあらわれた程度のリベラルさを根拠に、その芸人を称揚する態度は安易である。演芸の論理を見すえたうえで、彼/彼女らはウケるためにやっているのだ、という冷静なまなざしをもっていなければダメだ。
だとすれば、次のように言える。すなわち、現在の芸人のネタがリベラルな傾向にあるのは、芸人が笑いを求めた結果なのだ、と。ここには、《大衆》の動向とともにあろうとする演芸の論理がある。現代的な笑いにおけるリベラルさは、他ならぬ《大衆》性として発見されている。
外見をいじるのは、もはや“アウト”なのだろう。では、なぜ“アウト”なのか。社会的な良識に反しているから? 倫理的でないから? 半分正解だが半分間違いである。というのも、上記の答えは社会的な論理から導かれたものに過ぎない。演芸の論理から導くならば、次のようになる。すなわち、外見いじりは、客に「このネタで笑っていいのか?」と思わせてしまう、したがって、客からしたら笑えなくなっている、そのような《大衆》の動向を捉えそこなっている点においてこそ、“アウト”なのだ。
外見をいじったネタで笑っていいのかわからない、という客席の空気を敏感に察知するからこそ、芸人は「ブスいじり」をしなくなる。反対に、客席が「誰も傷つかない」ことに安心して笑うからこそ、「誰も傷つかない」ネタが選ばれていく。そこでは、道徳心や倫理以上に、舞台での現場判断が働いているのだ。というか、道徳や倫理すらも演芸のなかに包んでしまうのが、芸人の基本姿勢である。
ちなみに、お笑いを題材にした青春小説、大前粟生『おもろい以外いらんねん』(河出書房新社)には、このような社会的な論理と演芸の論理が重なる瞬間が描かれている。お笑い芸人の道に進まなかった咲太は、従来的な価値観を手放そうとしない滝場に対して、次のように話す。
「(前略)おもろい以外いらんねん。おまえらの笑いをさあ、外野によごされたくないんやったら変な意地を張るなや。傷つけるとか傷つけないとかおまえどうでもいいやろ。笑えるかどうかにしか興味ないやろ。せやったら『傷つけない笑い』とかを前提にしてもうたらいいやん。早くそれやって早くみんながそれを当たり前やと思うようになったらわざわざ言及されることもなくなるやん」
物語は咲太のほうを語り手としていることもあり、リベラルな価値観を称揚するものとして読まれうるし、作者もそのようなものとして書いているのかもしれない。この引用部も、咲太が自分の思いをやっとのことで滝場に伝えようとする、物語のハイライトである。
しかし、ここで注目すべきはむしろ、お笑い芸人の滝場が、最後までリベラルな価値観を獲得しているかどうかは不明だ、という点である(そして、この点において『おもろい以外いらんねん』は、芸人小説としてすぐれている)。咲太は滝場を理念的に説得するのではなく、あくまで「おもろい」という演芸の論理から、リベラルという「振る舞いモデル」(荻上チキ『社会的な身体』講談社現代新書)を要求しているに過ぎないのだ。
「アップデート」論の移ろいやすさ
だとすれば、昨今の芸人における人権意識やハラスメント意識の高まりをベタに賞賛する必要はない。突き放して言えば、そのような態度は社会的な約束事に過ぎないのであって、テレビを中心とするメディアで活躍しようという芸人であれば、放送コードと同じように守って当然のものなのだ。ふたたび、太田の言葉を借りれば、「そういう意味ではテレビのタレントっていうのは汚れてますよ。計算で喋ってるし、そんなのは当たり前に受け入れてるから」(『splash!! Vol.4』2012・7)ということである。
前節のマキタスポーツは「半歩さきを行ってるようなイメージが当たってるかもしれないけど、むしろお笑い芸人は、半歩うしろを歩いているから」と言っていたが、現在において、リベラルな意識は進歩的なものではなく、《大衆》の動向と知るべきである。別にリベラル派に対する嫌味を言っているわけではない。むしろ、リベラルな意識が《大衆》的なものとして到来している事態については、基本的に歓迎する立場だ。『おもろい以外いらんねん』の咲太が示すように、このような《大衆》の動向にともなうかたちで、社会の「当たり前」は形成されていくだろう。
言論の問題として気になったのはむしろ、そのような《大衆》への寄り添いに過ぎない芸人たちの行為を必要以上に称揚する類の言説のほうだ。とくにここ1〜2年、「アップデート」という言葉でリベラルな振る舞いを評価する言説が目立った。いわく、お笑い芸人には価値観のアップデートが必要だ、視聴者も価値観をアップデートしなければならない云々。そのような物言いは——どこまで意識的かわからないが——芸人のリベラルさを称揚することによって、それを指摘する者のリベラルな態度を表明する構造になっている。
本当ならばここで、「アップデート」を言い募る記事なり文章なりを提示しなければいけないだろう。しかし、論壇らしきものはすでにTwitterをはじめとするSNS空間に移りつつある。上記のたぐいの「アップデート」論は、ライターや評論家筋の断片的なつぶやきなどによって醸成されたものなので、個別に紹介するのが難しい。ともあれ、ライターの武田砂鉄が「「アップデート」と言うだけで七十点はもらえるような風潮」に対して批判的に言及する(能町みね子との対談「逃げ足オリンピックは終わらない」『文學界』2021・9)くらいには、一部の界隈では共有された物言いだと言える。
このような「アップデート」論の「風潮」に対しては、たいへん違和感を覚えた。というのも、過去の自分をあたかもないものとするような「アップデート」という表現こそ、いかにも《大衆》の移ろいを言いあらわしたものに他ならないではないか。にもかかわらず、「アップデート」論者は、それが進歩的なものであるかのように振る舞う。その点、違和感を覚えるとともに、少なからず問題だと思った。
フェミニズムにしてもジェンダー論にしても、あるいはポスト植民地主義にしても、運動の現場や学問的な場で、何十年も議論されてきたものだ。現在のリベラル意識の高まりは、その議論の成果である。「アップデート」という言葉は、そのような何十年もの議論の蓄積にフリーライドすることを意味する。
価値観が「アップデート」される以前から、差別や偏見と闘っていた人がいただろう。人知れず苦しんでいた人がいただろう。そのような人たちからすれば、それまで無配慮だったような人が、ある日なに食わぬ顔で「アップデート」している様子を見たらどう思うか。「アップデート」という言葉には、そうした調子のよさ、もっと言えば、信頼のできなさが含まれている。
過去の自分を振り返って、価値観が変わっていくこと自体は否定されるべきことではない。問題だと思うのは、その変化を「アップデート」と表現し、自称さえしてしまうことだ。どのような点で問題か。その問題性を細かく挙げるならば、次のとおりである。
まず、過去の自分との連続性を切断し、過去の振る舞いを不問にしてしまうこと。そうして、過去の自分との連続性を切断した地点から、いまだ「アップデート」していない者に対して攻撃をしてしまう論理が用意されること。さらに言えば、現在の価値観もまた「アップデート」の名のもとに消去される余地を残すこと。
現在、芸人のリベラルな意識を称揚する論者は、他ならぬ自分自身が、《大衆》の移ろいに巻き込まれるかたちでリベラルな価値観を称揚していることを知るべきである。その人のリベラルな発言は、芸人がウケを狙うのと同様、《大衆》に向かったポピュリズム的なウケ狙いとして機能してしまう。リベラル的な物言いこそが、ある面においては、読者を安心させる程度の芸になっている。
くり返すが、それ自体は別に悪いことだとは思わない。社会としてのまっとうな歩みである。良くないのは、自分にとっては切実で倫理的なことが、芸として機能してしまうことに無自覚なことである。ましてや、少なからず言論人であろうとする人が。そのような振る舞いは、欺瞞に映ってしまう可能性があるし、別種の攻撃性をもつ可能性がある。
だとすれば、現在の価値観を特権的なものとして捉えないほうがいいだろう。個人にとってどんなに大事なものに思えたとしても、その価値観は究極的には、ある条件下での約束事に過ぎない。時代によって場所によって、価値観は変わる。本当に守りたい価値観があればこそ、そうしたアイロニカルな態度を忘れてはいけない。普遍的であることを無批判に信じるのではなく、普遍的であろうと努めること。そういう社会を作ろうと努めること。そのような働きかけのほうが大事だ。
だから、現在のお笑いについて「どこまで笑えるか」という問いがあったとして、そのラインが明らかになったところで、それはあくまで暫定的な基準である。外見の特徴をいじるのはダメ、コミュニケーション下手を笑ってはいけない云々——そのお笑いをめぐるラインは、おおいなる《大衆》的移ろいやすさのなかにあり、時代が変わればいくらでも変わりうる。
現代的な価値観が大事だと思うなら、むしろそのような移ろいやすさを見すえながら、その価値観を粘り強く守り続けることだ。「アップデート」論ではもち得ない、時間をかけた粘り強さをもって。時代の変化を根拠に重要性を謳う「アップデート」論は、批判性に乏しい。「アップデート」論は、守るべき価値観を捨て去る余地もあれば誤った価値観をもち込む余地もある。いまわたしたちが守ろうとしている価値観は、はたして軽薄な「アップデート」に耐えうるのか。自らに向けた批判が必要である。
秋田實と「モダン万歳」
そもそも歴史を振り返ってみれば、演芸の世界は「アップデート」の連続だった。現在の価値観では容認できるものではない昭和のお笑いだって、それ以前の時代から比べたら、ずいぶんと「アップデート」された価値観でおこなわれている。お笑いをめぐる言説はいつの時代も、非—社会的なのが良くない/非—社会的だからこそ良い、という両極の意見のあいだで行ったり来たりしている。
昭和の演芸において批判が殺到した存在としては、例えば、ザ・ドリフターズが思い浮かぶ。放送作家の田村隆はドリフについて言及するなかで、「食べものを粗末にする。言葉づかいが汚い。下品だ。子供の教育上よくない——この頃、ワースト番組が取り沙汰されると、まず矢面に立たされるのが『8時だョ!全員集合』だった」(『昭和バラエティ番組の時代』河出書房新社)と振り返っている。『8時だョ!全員集合』に関しては、「日本PTA全国協議会」がスポンサー商品の不買運動を呼びかけるなど、現在のキャンセルカルチャーをも思わせる動きが起きている。一部の人にとっては、そのくらい社会性の欠如した番組に映っていた、ということだ。
しかし一方、ドリフがテレビを席巻しているのと同じ時期(1973年)、例えば、俳優の小沢昭一なんかは次のようなことを言っている。
昨今、芸能者は、カタギ社会の内側に安住の座を得ている。芸能民は安定を求めて、カタギ社会の枠組の中に埋没して散ってしまった。そして芸能の担い手は、逐次、ショウバイニンからカタギへ、クロウトからシロウトへと移行しつつある。そして、うらみもつらみもなくなってしまったから、かつてショウバイニンがやっていた、身を挺してお追従することも、体を張って毒をふりまくことも、止めてしまったのである。そうなった芸能のツマラナサ加減はご承知のとおり。
全国をフィールドワークし、各地の放浪芸を研究する小沢にとってみれば、「芸能民そのものが、はじめから、世の中の枠組の外におかれた」存在であって、テレビで活躍している時点でじゅうぶん「カタギ社会の枠組の中」にいることになる。当時『8時だョ!全員集合』を批判していた人は、ドリフが社会の良識に反していると思っていたのだろうが、芸能本来の歴史からすれば、ドリフはむしろ、社会的な存在の筆頭とも言えるのだ。
あるいは、昨今すっかりマッチョな価値観や弱者切り捨てとも取れるような発言が批判される松本人志だが、折口信夫的な芸能の神秘的な力にロマンを見出す中沢新一からはむしろ、「東京に出てきた松本人志は、テレビの解毒作用にやられて、いまでは息も絶え絶えだ」と、すっかり毒っけが抜かれ、去勢されたものとして扱われている(『大阪アースダイバー』講談社)。ちなみに中沢は、しばしばそのホモソーシャル性が指摘される『アメトーーク!』(テレビ朝日系)に対しては、「吉本興業の若手お笑い芸人は、雨上がりの森のなかのキノコのように繁茂しているけれど、毒を期待して食べてみても、調子がいいばかりで、しびれはいっこうにやってこない」と婉曲的に嫌味を言っている。
このように考えると、演芸の舞台もヴァラエティ番組も、そのときどきで非—社会性や反—良識を指摘されながらも、その批判自体を飲み込むように延命し続けている。芸能や演芸は、社会の姿を見すえてその動向に気を配ると同時に、社会から逸脱しようとする。《大衆》性と《前衛》性のあいだで、社会的な逸脱と包摂を両輪にしながら、芸能・演芸は駆動しているのだ。
このことは、近代漫才の祖とされる漫才作者、秋田實の時代からしてすでにそうだった。戦前期、一九三五年頃から吉本興業の文芸部に所属し、エンタツ・アチャコの座つき作家としてしゃべくり漫才を確立した秋田は、それまで下品で猥雑だった万歳を《大衆》に広めるべく改良することを目指した。それは、アンダーグラウンドの尖った芸としての「万歳」を「漫才」として社会的に包摂することを意味していた。
秋田が「無邪気な笑い」を求めたのは、当時の「万才」小屋が家族づれや女がひとりで入っていける雰囲気ではないからだった。そこは、ひと時の気晴らしに、ドギツイ笑いを求めるところだった。秋田は、母親といっしょにいっても、顔を赤らめることなく笑える漫才を理想とした。
こうした秋田の試みは「モダン」と称された。秋田自身、「服装もかわり、話の内容も無邪気になりモダンになった」と述べている(『私は漫才作者』文藝春秋)。実際、「漫才」という名称が定着する以前、秋田流の漫才は「モダン万歳」と呼ばれている。
思想史/文学史的に興味深いのは、そんな秋田がもともと東大新人会出身で、プロレタリア文芸誌『戦旗』にも参加したプロレタリア作家だった、ということだ。プロ文作家としての秋田のいくつかの作品は、現在では『日本プロレタリア文学集19 「戦旗」「ナップ」作家集(六)』(新日本出版社)などで読むことができる。「犬——或る工場の一記録——」などは、自身の経験を反映した工場労働者の立場から資本家との闘争を描いた作品である。
左翼運動と漫才作者としての活動とのつながりについて、秋田自身はあまり言及しないが、「労働者町で生活した」秋田の「漫才作者への道を、社会科学の運動と結びつけよう」とする「評論家」の意見などはあったらしい。この意見について、秋田は「私は、自分ではそうは思ってはいないが、あるいはそういう点があったのかもしれない」と書いている(『私は漫才作者』)。
いずれにせよ重要なことは、現在の漫才に直接的につながるしゃべくり漫才のスタイルが、講座派的な意味での近代化の文脈から出てきていることだ。秋田による「漫才」は、差別的で猥雑だった「万歳」から「毒」(小沢昭一/中沢新一)が抜かれるかたちで成立している。この「毒」抜き作業こそが、「モダン」化を意味している。秋田にとって、新しい時代の「モダン万歳」は、近代的な市民のためのものでなくてはならなかったのだ。そのためには、差別性や猥雑性は取り除かれなければならなかった。
このように考えると、秋田が確立した「モダン万歳」=「漫才」には、相反するふたつのベクトルがあることがわかる。ひとつは、「モダン」の時代にふさわしく差別的で猥雑なものを排すベクトル、もうひとつは、伝統的な「万歳」にふさわしく社会の秩序から逸脱しようとする「ドギツイ」ベクトルである。例えば、いかにも左翼出身らしく治安維持法を茶化し、「判ったら、ここらで潔く転向して甦生したらどうや」とオチがつく「恋愛禁止法」(もともとのタイトルは、治安維持法をもじった「思案医師法」)は、比較的「ドギツイ」方向性と言えるだろう。
漫才はこれら相反するベクトルを抱えることによって、ときに《大衆》性が指摘され、ときに非—社会性が指摘されることになる。演芸一般も同様だ。「モダン」の時代にある演芸は、近代社会にふさわしい価値観をコードとして求められ、それに対応しようとする。その態度は、「母親といっしょにいっても、顔を赤らめることなく笑える漫才を理想とした」秋田の態度になぞらえることができる。現代的な「誰も傷つけない笑い」も、基本的にはこの流れにある。
しかし、それだけではない。「モダン万歳」=「漫才」は一方で、伝統的な「万歳」の流れ、すなわち「毒」を含んだ「ドギツイ」態度もまた含む。現状の社会のありかたに疑問を呈すように「毒をふりまく」(小沢昭一)振る舞いが、演芸には期待されている。現在、演芸について考えるならば、「モダン」性と「ドギツイ」性の両方に目を向ける必要がある。
社会に対する「毒」を示しつつも、再帰的に自らの「毒」をチェックすること。その「毒」を解消しつつも、また新しい「毒」を示すこと。「モダン」と「万歳」を両輪で駆動するかのように、近代の演芸は漸進的に運動している。だとすれば、近代演芸が求めるのは、「この芸風はアウトでしょう」という批判それ自体である。そのような批判自体を反省的に飲み込みながら、演芸はしぶとく延命し続ける。その意味では、近代の再帰的ないとなみの一部として、演芸もまた存在している。
そして、そのような近代演芸の運動の中心に横たわるのが、「ウケる/ウケない」という現場判断に他ならない。この演芸の論理を踏まえずに、ただ演じられたものを通じて社会を見通すのみでは、近代演芸のダイナミズムは捉えきれないだろう。
近代社会でウケること
最後にあらためて、『キングオブコント2021』におけるザ・マミィの一本目のコント「この気もちはなんだろう」について考えたい。リベラルな視点のみで判断するなら、コントの終盤、林田洋平演じる青年がおじさん(酒井貴士)を試すような展開は、少し差別的に見えてしまう。したがって、リベラルな価値観を体現したことのみを評価しようとすれば、このコントに対する評価は微妙なものになる。そうではない。このコントに見るべきはやはり、おじさんが「お前、すごいねえ!」と叫んだところである。
コントにおいて「偏見」の対象とされる、酒井演じるおじさんは、自ら「少しは見た目で人を判断しろ!」と青年を叱責し、その後、「悲しいこと言わせんなよ」とつぶやく。つまり、おじさんのなかには「モダン」性と「ドギツイ」性の両方が抱えられている。そのうえで特筆すべきは、おじさんに対するこの「偏見」が、社会的な視線(「モダン」性)とも差別的な視線(「ドギツイ」性)とも言いうる、ということだ。このとき、おじさんの振る舞いは「モダン」性と「ドギツイ」性が高度に二重化されている。その点が重要だ。この二重性こそ、近代における演芸の二重性に他ならない。社会の価値観に沿いつつも、同時に、それを逸脱して見せる。このような二重性のなかで、客席の笑いは生まれていた。「この気もちはなんだろう」というコントの本領は、その点にこそある。
近代社会を生きる者として、芸能の領域ではなにをしても許されるのだ、という開き直りをするつもりはない。なにより、そのような芸能ロマンは、「ドギツイ」ものとして《大衆》に「ウケない」可能性がある。芸能もまた、片足を社会に突っ込んでいるのだ。
とはいえ、社会的な価値観を追認するだけのものは、演芸たりえないだろう。ましてや、舞台で演じられたものをベタに進歩的なものとして称揚する手つきは、演芸の核心を外している。そこでは、「ウケる/ウケない」という生々しい現場判断の感触が抜け落ちてしまっている。
たしかに、ここ10年ほどで笑いに対する意識は変化した。しかし、それはいつだってそうだったのだ。漫才に代表される近代演芸は、いつだって再帰的な自己チェックが入るのだ。なにより、ウケるために。だったら、近代社会と演芸の両方を信頼したうえで、こう言おう。——すなわち、ウケるということをもっともっと追求するべきだ。社会を追認しているだけでもウケないし、ドギツすぎてもまたウケない。近代演芸は、時代の変化に負けてしまうほどやわではない。いつの時代だって、その時代に対応したものとして新しい演芸は到来する。新しい毒をもって。その移ろいやすくもしぶといありかたこそ、わたしたちの生きる近代社会の似姿である。そのようなものとして演芸を捉えるべきである。
この態度は、進歩的なリベラルの立場ではない。とはいえ、無頼さを称揚するたぐいの芸能ロマンでもない。もっと根源的に、「ウケる」という《大衆》の反応に対する信頼である。この近代社会において、「ウケる」ということについてマジで考えよう。
(初出 「文學界」2022年1月号)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
