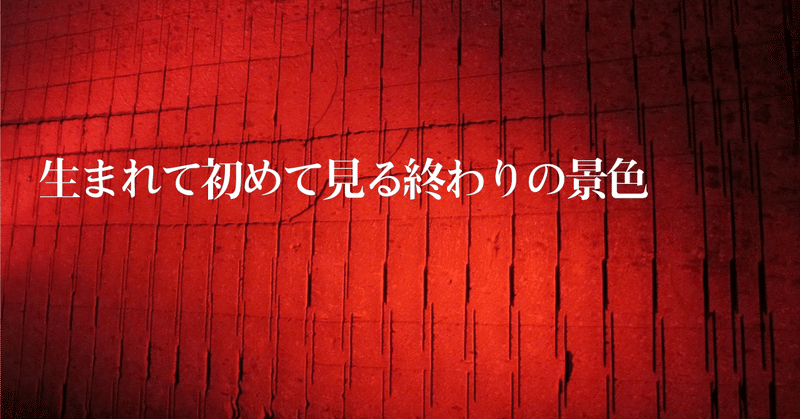
終の棲家デザイナ 太田健司の日常3
「あんただれよ」
「たしかに おれは かずおだけれど え かあさん だぁー」
「まじか だけど おれあんたのかおをおぼえてねぇっていうか しらないんだよ おれだって よくわかったねぇ」
「ははおやだから わかってあたりまえだぁ よくいうぜ おれをほっぽらかし どっかいっちまったくせによ どうせ またおれをおいていくんだろ もうちょっと ほんわかとやさしいひとを おもいえがいていたんだがな あんがい おへちゃだな」
「おまえのおやだからとうぜんだって か そりゃちがいねえ ごちゃごちゃいってないで ついてくればよいだと」
「わらっちゃうよ あした あのせんせにいわなくちゃな ほんとうにおふくろがおむかえにきたって よ」
「かあちゃん さいごぐらい てをひいてくれないか」
「あぁ おもってたとおり やわらかくってあったけぇ」
翌早朝、巡回の看護師が長谷川和雄が亡くなっているのを見つけた。
長谷川は両まなじりに涙の乾いたあとを残しながらも、幸せそうに微笑んでいたと、看護師は記録している。
*
人間が定住生活を始めてから長い間、生まれた家が終の棲家であるということが普通であった。それ以前は、倒れ伏した場所が終の棲家であるという身もふたもない現実だけがあったに違いない。
近現代になり、人が労働者として消費されるようになるにつれ、故郷を離れての移動や移住が珍しくなくなり、兵士となれば、主にしたがって遠く異国の地へ出向くことも多かった。生まれ故郷からは離れたが、というか、それにゆえに、終の棲家を求めるという願望はなかったと思われる。畳の上で死にたいとか、故郷で死にたいとか、舞台の上で死にたいという「空間」「場」に対する願いはあっただろうが、建物としての選択はなく、ましてや、購うものではなかったはずであり、それもいまは変わりない。
ところが、現代日本では、子どもに迷惑をかけたくないと、子どもたちを育てた家を捨て、あるいは建て替え、終の棲家とするのがブームのようになっている。ハウスメーカーも焚きつける。だが、その終の棲家とそれまでの棲家が何が違うのかと言われれば、よくわからない。
だが、わたしも「終の棲家ブーム」その恩恵を受けている建築デザイナの一人である。
*
「院長先生から、終の棲家のデザイナがいるって聞いてね。わるかったね、こんなに遠くまで」
数年前にリノベーションをしたホスピス美柑園の院長山岸から電話があったのは一昨日である。
「あんたに改装してもらった個室は好評だよ」
「ありがとうございます」
「ところが、気にいらないという人があらわれてねぇ」
「おやおや」
「そこまで気に入らないなら、ほかのホスピスを紹介するといったんだが、死にそうな人間を追い出すのかって、さぁ」
電話の向こうで人の好さそうな院長が眉をハの字に曲げて苦り切っているのが目にうかぶ。
「何がそこまでお気に召さないのでしょうか」
「うーん、できればこっちに来て本人から聞いてくれないだろうか。ほかに相談にのってもらいたいこともあるし」
ホスピス美柑園はその名称の通り周囲をミカン畑に囲まれたている。ローカル線の最寄駅から緩やかな斜面を登り歩いて30分ほどで着く。門前で振り返れば、なだらかに広がりくだる硬質な緑の森のはるか向こうに、きらめく海がみえる。
院長を困らせている人は長谷川和雄さんと言った。
窓に背を向けてベッドに座る長谷川さんを黒く切り取り、柔らかな陽ざしが部屋にぼわーんと静かに入ってくる。さきほどから、影になって表情のみえない長谷川さんに話聞いているのだが、なにがお気に召さないのかよくわからなかった。
このホスピスは、入院時に本人が部屋を選べる。洋間、和室はもちろん、配置するカーテンから、障子の柄、家具の形もかなり選べる。もちろん、頼めば、模様替えもしてくれる。
もう、なにも選ぶことができないと考えて、美柑園に着いた人にとっては、難題でもあり、部屋を掃除していて10円を見つけた程度だが、喜びでもある。
たいがいの人は「どこでも良い、どうせ」と言うが、担当することになる看護師に付き添われて、選べる部屋を見ながら、最後は、「あそこが」「ここが」と居を定めるのだ。
長谷川さんは「昭和のちゃぶ台があるような和室」がご希望ということで、いまの部屋に入っている。
「青い鳥と同じで、終の棲家なんて実在しないんですよ、長谷川さん」
「脳みそがかゆくなるような難しい話はやめてくれ、せんせ。具合が悪くなって寝込むぞ、はは」
「いや、人に与えられるものなんて少ないってことです。院長先生も、わたしも、長谷川さんに提供できるのはこの空間とおもちゃみたいなしかけだけ。なにがご不満なんでしょう。もし、飾りけのないのっぺりした病室がよいなら、空いている部屋に移りますか」
「不満とか不足じゃないんだよな。どうも、思い違いをしていたのかもしれないんだよ。ガキの頃に暮らしていた家ではなくて、夢に出てくるときには背中を向けている母親の顔が見たいだけなのかもしれない。母親に会える場所が終の棲家なのかもしれない」
「でも、写真も何も残っていなんでしたよね。記憶をお聞きしながらここを作ったわけで。ここにきてからもお母さんは夢に登場されるのですか」
「ああ。気のせいか前より増えたな」
「で、いつも背中」
「そうだ」
「顏を見せって、と頼んでみましたか。長谷川さんのことだから怒鳴ったりしているんじゃないの」
「むうう」
「ま、子どもだましみたいなおまじないですけど、やってみましょうか。長谷川さんは夢の中のお母さんに向かって絶対に怒鳴らないでくださいね。約束ですよ」
「うむむ。わかった」
わたしは長谷川さんの部屋に母親の世代が使ったであろう鏡台を置いた。「これならおかあさんが背中を向けていても顔が映ります」 *
「石川様、本日は、ようこそおいでくださいました。わたくし、鵠楽舎代表を勤めます、太田健司と申します。
お電話では、なんですか、終の棲家を考えておられるとか。今日は、具体的なお話を伺えればと思っております。
さ、どうぞこちらへ。
え? この画像ですか。これまで弊社で手掛けた終の棲家です。
もし興味を惹かれるものがありましたら、タッチしてください。24時間の景色がご覧いただけます」
*
「石川さんの終の棲家のイメージはどのようなものでしょうか」
石川さんは、長い間日本料理の板前として暮らしてきたと聞いている。自前の店を持ったり、名店やホテルの厨房に招かれたりしてきた。メディアには出ないものの、業界では知られた人間であると、事務の山本さんが教えてくれた。そんな人に「粗末なお茶をお出しするわけにはいかない」と、失礼なことを社長の私に言い放ち、昨日は銀座方面に茶葉を買いに出かけていた。
「お、これは、築地の澄野家さんですね」
石川さんが茶を一口含み、山本さんに声をかける。
「羊羹は新橋の華匠さんかな」
言い当てられた山本さんは身をよじって喜んでいるが、普段は、わたしが資料と称して本を買いすぎだとか、このコーヒーは高すぎると文句ばかり言っているのだ。
わたしは建築デザイナである。終の棲家が専門のように言われ、仲間内では棺桶屋の健ちゃんと陰口を言われている。大学の卒業生が棺桶で、賞までもらった報いである。
「太田さん、まさに私の願いは、この旨い茶と添えられる菓子です」
「と、おっしゃますと」
「どちらかだけでももちろん成立するが二つ合わさるとよりよいものになる。終の棲家は文字通りそうあって欲しいと願う場所ですが、死に場所ではなく、生きることができる場所としてあって欲しい」
「石川さんのおっしゃること、なんとなくですが理解できます。わたくしも設計の際は、施主様と一緒に生き、衰えることができる設えを心がけております。死ぬための家なんて存在しません。ホスピスでさえそうです。ホスピスは最後まで生き切るための空間です」
「ホスピスというところには行ったことはないのですが、そういう場所なのですか」
わたしは、石川さんに、ホスピス海の家や、美柑園の映像を見せ、それぞれの物語を聞かせた。
「愉快、といっては不謹慎ですね。みなさん羨ましい最期をお迎えだ。ホスピスも悪くないですね。味噌汁や出汁の香るホスピスなんてのはないですかな」
「いますぐには手配できませんが、お望みであれば、ご相談させていただきながらおつくりすることはできると思います。よろしければホスピスを見学されませんか。先程の美柑園の院長から頼まれごとをしておりまして、そのプレゼンテーションに行く予定なんです」
「それは、ぜひご一緒させてください。せっかくですから、ご無理でなければ、なにか、料理を作らせていただくことはできますでしょうか」
「院長に聞いておきます。口から召し上がることができない状態の方もいるとは思いますが、料理は耳で、目で、鼻で楽しむものですものね」
院長は「そんな料理の達人にみんなの最期の晩餐を頼めるなんて悪いなぁ」と、一方的に拡大解釈をして、翌日には、美柑園に生活している7人全員の希望メニューが届いた。ついでに院長の希望も書いてあった。
おそるおそる石川さんに連絡すると「全部をつくることはできません。ですが、お一人一つは必ず、ご希望に沿えるようにいたします。調理場とスタッフのかたがたの手をお借りできるようにお願いしておいてください」
「用意しておくものはなにかありますか」
「最低限必要な物は先方のスーパーに寄って買います」
「スーパー、ですか」
「ええ。それがなにか」
一週間後の最期の大晩餐会──といっても午餐だが──は、歓喜の声に満ちたものだった。院長もわたしもスタッフのみなさんも相伴にあずかった。
「いつも美味しいものをだしてくださるけれど、今日は特別美味しい」
石川さんたち厨房スタッフも、あちこちらのテーブルに分散して一緒に食べながら、リクエストした人の声にうなづいている。
「こんなにたくさんのメニューがよく早くできましたね」
「メニューに特別な品はなかったので、すべて美柑園のスタッフが作ったんですよ。わたしはちょっぴり魔法をかけたただけ」
たしかに、最後の晩餐というと何か凝ったものを考えがちだが、たいがいはありきたりのメニューだ。わたしの目の前には、ソース焼きそばと赤飯がある。
「いや、スタッフの人も美味しいと言っているんだからかなりの魔法ですね」
石川さんやわたしと同じテーブルで、リクエストしたおでんを香りと目で楽しんでいた垂木さんが声をあげた。
「一番のご馳走と言っては一流料理人を前に失礼だが、美柑園にこんなにお仲間がいたなんてね。いつもは食事もそれぞれの部屋でもぐもぐしていることが多いけれど、今日は皆さんに会えてうれしい。すぐにお別れだろうけれど、なぁーに、またすぐに会えるさ。そのときこそ、飲めや歌えの無礼講で行きましょう。料理人さん、そのときは出張頼みますよ!」
当事者だから言える冗句。みなニコニコしている。
「まいりましたね。確かに、太田さんに終の棲家をお願いしようと思っているんですが、まだ、覚悟ができていないんですよ。出張はご勘弁いただいて、クール宅配便でお願いいたします」
「約束ですよ。届け先は、必ず連絡するから」
垂木の軽口にを合図に食事会はお開きとなった。笑い声と笑顔をデザートにもらって部屋に帰っていく。
「死の話をあんなにおおっぴらに、それも、笑いごとにして、気分を悪くする人はいないんですか」
わたしは院長に尋ねた。
「内心、苦々しく思っている人もいるだろうさ。でも、事実だからね。孤独や孤立、なんで私だけがという苦しみはみんな抱えている。垂木さんも感じていたんじゃないのかな。そうではないとわかって安心したんだろうね。垂木さんに言われてどきっとしたけれど、たしかに、横のつながりが足りなかったなぁ。毎日毎食はそれはそれで難しいだろうけど、たまには集まって食事会もいいのかもなぁ」
「院長先生、今日の石川さんは特別ですからね。毎回期待しちゃだめですよ。期待するなら、きちんとそれなりのものを頂かないと。ねぇ、石川さん」
「そんなことわかっているさ。でも、メニューの相談ぐらい、良いですよねぇ」
「えぇ、まぁ」
「石川さん、だめです。甘い顔すると、きりがないですから。そんなことより、院長先生、先日の別館のお話ですけれど、こんなプランはいかがでしょうか」
わたしは、石川さん自身の希望、そして、今日の体験を通じて描いたものを院長だけでなく石川さんにも聞いてもらった。
「ホスピスは、一般のイメージは死者の家です。入ったら、生きて出てくることがない。だからこそなのか、それなのになのか、死を感じさせるものを極力排除しようとしているように見えます。死を突きつけろというのではなく、孤独や孤立を感じている、まさに、心が叫び苦しんでいるかたがたを、ここに来てよかったね、ここに来ることができた貴方は幸せなんだ、そして、私はあなたに会えたことをうれしいよ、ありがとう、と伝えられるような空間。今を生きていることを共有し、馥郁とした茶の香り、周囲を囲むミカンの香り、胃袋がならずにはいられない出汁の香りも共有する。日々個室で暮らしていても、一緒に今ここで生きている仲間を感じられる空間。逝った仲間を見送り窓越しにせよ声を掛けられる空間。そんな空間を作ってみたいと思います」
「ま、理想はわかったけれど。どういう形になるのかな。あんまり豪華でも懐が寂しいからね」
「院長の懐具合は小銭の端数までわかっていますよ。ご安心ください」
「いや、それじゃかえって不安になるな。掘っ立て小屋はごめんだよ」
「石川さんにもぜひご協力いただきたいのですが」
「え、わたしもですか」
怪訝な顔つきの石川さんを引き連れ東京に帰ったわたしは、翌日から線を引き出した。
*
完成までの三日間、石川さんは弁当を作って事務所に通ってきた。石川さんの弁当を食べるた事務の山本さんは「今日死んでもかまいません!」と毎日言っていたが、わたしには「まだ死にたくないので、できるだけ仕上がりを先延ばしにしてください」と矛盾したことをわたしに迫った。
「なるほどね、日本料理屋だったら、この部分が築地塀か板塀で雰囲気を予感させ、これがのれんで、その先が、玄関までの路地ですかね。その先には非日常がある。ところがうすうす感じていたものとはまるきり違うんだものなぁ。皆さん、がっかりするんでしょうかねぇ」
図面から起こした完成予想CGを見ながら石川さんは、いたずらを共有する悪童のように笑っている。
造作は特に凝ったものではない。ミカン畑の中の道を進むと少し見上げるような場所に展望室のような弧を描いた建物が目に入ってくる。まもなく道はトンネルに入り、次に外に出たときには、弧の内側に入る。
「で、ここが厨房ですね。カウンターの向こう側で料理人が一人一人に料理を作り、カウンター越しに出してくれるといったところでしょうか。少人数だからできることですね。美柑園もスタッフは腕も良いからうまくいくでしょう」
弧のセンターにエントランス、ナースステーション、事務所、厨房などのオフィス棟がある。とくに厨房は居室のほうを向いてあり、ガラス張りで、居室それぞれの前につくられた配膳口と直結している。
「今のスタッフは本館で手いっぱいなんで、新しい調理人を探すんです。石川さん、いかがですか? 現場が落ち着くまでの指導役でもけっこうですよ。給料は安いでしょうけど、住宅もあります。ミカン畑の中に古民家がありまして、なに、院長の実家なんですが、私が中を改装して、ゲストハウスにしてあります。海外からの見学者や、応援を頼んだ医師などの宿泊に使っています。それに美柑が食べ放題ですよ。もちろん無理にとは言いませんけど」
一流、名人と言われる石川さんが病院の厨房で給食をつくることを承諾するとは思わなかったが、言うのはただである。
とうぜんながら、返事はなかった。
それでも、石川さんは、その後も別館の施工現場に行くわたしに同行し、ゲストハウスに泊まり、厨房スタッフと設備の話をしたり、ときには本館厨房で一緒に働いた。
完成後、石川さんは、常勤ではないが、相談役に就任した。
給料は安いが、院長から「ゲストハウスを生涯自由に使ってよい。美柑も一生食べ放題。相談役は一年で良い」という破格というより、やけくその条件を提示されたらしく「そこまで言われたら、しかたないよね」と笑っていたが、まんざらでもないようすだった。
石川さんが相談役にいるというだけで、厨房スタッフはあっという間に集まった。
相談役として美味しい食事を提供すべく日々チャレンジをしていると聞いている。
「太田さん、病院の一般食と特別食の違ってご存じでしたか。わたしは幸いなことにこの歳まで入院生活を送ったことがないもので、知らなかったんですよ。そんな私が厨房に立っているんですから、自分の未熟さを呪う毎日です。食べていただきたいものを自分が創りたいように作ってだすのではなく、食べたいものを食べていただけるようにおだしする。簡単なようでむずかしいですねぇ」と言う声は、みかんのように明るい色がついているようだった。
やけくその条件でたなぼたのように一流料理人を手にした院長は「割烹型ホスピス、レストラン付属病院という、ありがたい評判もたってね。最近では、海外からの問い合わせもあるよ。病室がないと言ったら、近くに土地があれば自分で建てて寄付するとまでいうんだよ。太田さん、頼めるかねぇ」と、金臭い息を電話の向こうから流してくる。
「院長先生、建物を立てれば、維持が必要ですから、お金でもらったほうがいいですよ。その金持ちもいますぐ死ぬわけじゃないんだろうから、美味しい病院食研究財団でも設立して、食事の開発だけでなく、世界じゅうから調理人を呼んで養成もすればいいのではないですか」
「太田さんも商売っ気がないなぁ。これからは病院も客を意識した、オーダーメイドの経営だよ」
「どこのコンサルに焚きつけられたのかわかりませんが、先日まで、小銭の端数まで気にしていたくせに、何を言っているんですか。名声を得たのは石川さんのおかげなんですから、石川さんにも相談してくださいね」
わたしはじゃりじゃり砂まじりの言葉を投げつけて会話を切った。二度と院長からの依頼はないだろうと覚悟した。
完全に、散歩の途中で3億円を拾った人になっている院長だったが、石川さんには相談したらしい。
「病院経営のことはわかりません。が、わたしたちがつくる食事を召し上がっていただく方の顔が思い浮かばないような環境になるであれば、辞めさせていただくことになるかもしれませんねェ、とお答えしたところ、急にしぼんじゃいましてね」
東京へ買い出しついでに事務所に立ち寄った石川さんはその時のようすをおかしそうに話してくれた。石川さんは相談役の傍ら、院長から無償貸与された形のゲストハウスを和食のオーベルジュとして改造し、月の半分程度、限定一日二組の客を迎えている。またたくまに予約の取れないオーベルジュとなっている。
「そりゃそうでしょう、巨額の富豪マネーが消えてしまったんだもの。マネーだけじゃなくて、毎日の美味しい昼食も失ってしまうわけですから」
「最近では、三食です。検食だ、とおっしゃって」
「そりゃそりゃ」
「しぼみすぎちゃっても困るので、そのお金持ちの家の料理人を費用むこうもちで派遣してもらって、養成すればいいのではないでしょうか、と提案しました」
「院長、少しは元気になりましたか」
「銀行通帳の空想残高が増えたとは言えないようでしたが、可能性がゼロでなくなったので、先方に提案したようですよ」
「へぇー。でも、わたしは今後、院長から仕事はいただけそうもないな」
「大丈夫ですよ、きっと。派遣受け入れ費用に驚くような額を提示されたらしいです。事務長さんの話では、一人あたり億単位とか。それも、金持ちが死の床につくまでは、毎年、一人か二人を派遣するそうです。院長せんせ、最近、鼻歌交じり、スキップで院内を歩いてますよ」
ホスピスの経営が厳しいのはわたしも重々承知している。院長も私腹を肥やすために富豪マネーが欲しかったわけでないこともわかっている。たとえ数年でも、院長の心の重しが外せるようになったのは、喜ばしいことだ。
「太田さん、美柑園はわたしの終の棲家ではないのかもしれませんが、のれんをくぐり、その先の路地を歩いてわくわくしている過程のように感じます。万が一のときの終の棲家は、目の前に見えますし」
事務所に初めて来たときとはちがう迷いのない声に、石川さんの終の棲家のイメージに、白木のカウンターが浮かんだ。染み一つなく吹き上げられ、柔らかな照りをみせるカウンターにワクワクするような一皿を置く。皿を挟んで高まる緊張……。一度、石川さんの厨房姿を映像に残して置くこと、と心にメモをした。
事務の山本さんは、石川さんの弁当を思い出してため息を尽くし、オーベルジュの予約が取れなくてわたしに文句を言う。
「先生、責任取って、何とかしてください」
「なーんでわたしが。それじゃ、院長に頼んでホスピスの事務職に転職するかい」
この日から1週間ほど、わたしは、山本さんからお茶を出してもらえなかった。
石川さんが事務所に来て以来、茶葉が築地の澄野家のものになっており、内所使いものもグレードが少し下がるが美味しいお茶だった。それがなぜか自分で淹れても美味しくない。(つづく?) [ぶんろく 2020.01.25.]
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
