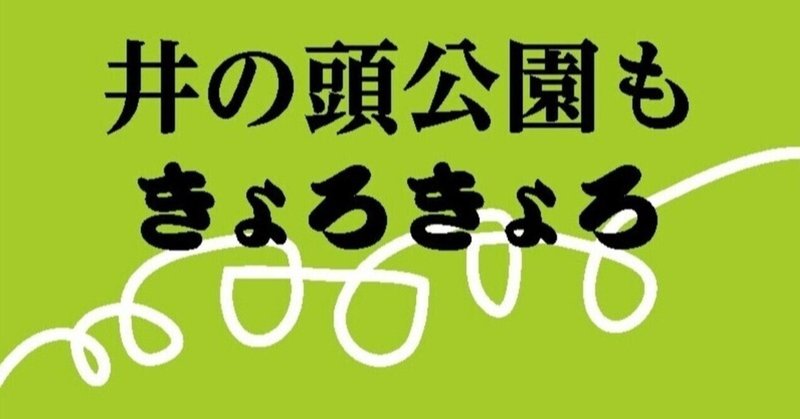
井の頭公園の散歩(6)水船組合の存在と矜持を示す石碑
茶店「井泉亭」がイタリア料理「ISENTEI」となり老舗の進化に驚いた。緋毛氈(ひもうせん)を敷いた縁台で、みたらし団子にお茶は、はるか遠くになりにけり。
さて、目の前の弁財天に向かってちょっと歩いた右手に、見ている人をほとんど見かけないというか、見落としてしまう石碑がある。石碑は、徳川家光が「井之頭」の名をコブシの木に彫ったという伝説を伝えており、寄進は深川水船組合となっている。
この組合は、神田上水が江戸・東京市中のあちらこちらに分配した残りの水をもらう権利を持っている組合で、その水を隅田川の対岸の深川や本所まで運んで売る商売をしていた。対岸には「水屋」とか「水売り」と呼ばれる人が、その水を桶に入れて天秤棒で町内を売り歩いたそうだ。いかに井の頭の湧水が貴重だったかが分かる。
石碑の建立が1893年(明治26年)となっているが、東京の近代水道の工事着工が1892年(明治25年)であることを考えれば、江戸時代から明治の近代水道開設まで、井の頭の湧水を無駄にせず運んだ水船組合の存在と矜持を伝える記念碑とも言えるだろう。
(引用:『井の頭公園*まるごとガイドブック』安田知代著/ぶんしん出版)
『ぶんしん出版+ことこと舎便りVol.6 2021/11/16』掲載
このコラムは、(株)文伸 が運営する自費出版専門工房「ことこと舎」が毎月発行しているメールマガジン「ぶんしん出版+ことこと舎便り」からの転載です。メールマガジンをご希望の方は、ことこと舎のお問い合わせフォームから、メルマガ希望とお知らせください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
