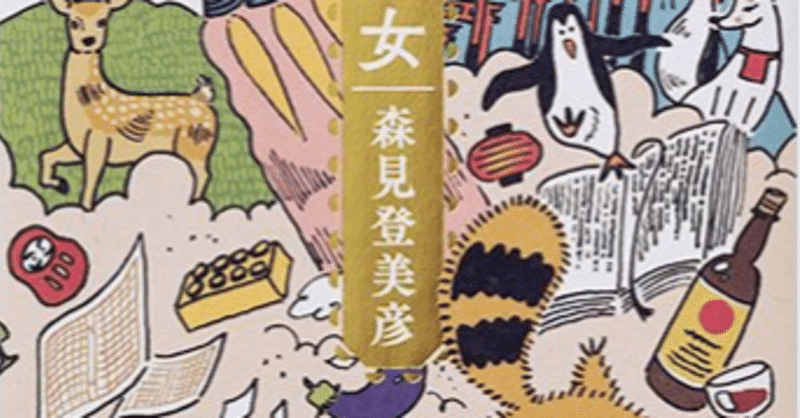
森見登美彦的な創作プロセス 2
前回(こちら)、作家の森見登美彦氏が、エッセイ集『太陽と乙女』の中で、自身と劇作家の上田誠氏の創作法について次のように語っている部分を紹介した。
・自分が作りたい作品の全体構想をあらかじめ粒度高くFIXするなんてことはできない
・とりあえず作りはじめてみて、作りながら新たな発見を繰り返す。そういう風に制作は進めていくのである。
そして、私自身の考察として、「森見氏が言及しているのは、自身と上田氏の作品づくりのおけるプロセスであるが、実はこれ、あらゆるものを作るときに言えるのではないか。アメリカの哲学者でありプラグマティズムの創始者でもあるC・S・パース(1839〜1914)の仮説に基づく厳密でない推論「アブダクション」のアプローチそのものではないだろうか。という話で結んだ。
▶︎パースのアブダクション

パースの「アブダクション」とは、論理学における推論の一つで、「仮説を形成」する方法である。米盛裕二氏は『アブダクション 仮説と発見の理論』の中で、パースのアブダクションについて、次のように記載されている。
パースはアブダクションによる仮説の形成は二つの段階を踏まえて行われると考えているのです。つまりアブダクションは最初に色々な仮説を思いつく示唆的(洞察的)段階とそれらの仮説について検討し、その中からもっとも正しいと思われる仮説を選ぶ(あるいは、それらの仮説のほかにもっと適切な仮説がないかどうかを考える)熟考的な推論の段階から成り立っています。
このアプローチは、森見氏が実践している創作プロセスに当てはまる。「これは面白くなるのではいか?」という着想を得る段階が洞察であり、それを表現するための文章や言葉の選択することが推論である。
つまり、森見氏は仮説のもとに文章を執筆して、絶えず「自己修復」を繰り返しているのだ。(自己修復についても本著の中で言及されている)
森見氏の創作プロセスは、とても科学的なアプローチなのである。
『アブダクション 仮説と発見の理論』には、他にも創作に関係しそうな示唆深いことも書かれている。良書なので興味がある方は、一読をお勧めしたい。パース自身の著作は読むのも理解するのもとても難しいが、これは割と分かりやすく、慶應義塾大学の井庭崇先生の研究室でも必読の本にしているらしい。(こちら参照)
▶︎あるべきかたち
創造プロセスについて、もう一つ言及したい。上述の慶應義塾大学の井庭崇先生は『クリエイティブ・ラーニング 創造社会の学びと教育』の中で、宮崎駿さん、村上春樹さん、谷川俊太郎さん、ミヒャエル・エンデ氏といったクリエイターの言葉を引き合いに出しながら、次のように言っている。
何かをつくり込むときには、つくられるものの「あるべきかたち」があるということを、ここでは強調したい。つくり手がつくりたいようにつくれるわけではないのである。(中略)物語において主人公がとるべき言動はそのキャラクターと文脈に応じて自然なものであるべきだろう。このように、つくり手の「こうしたい」という作為にもとづいてではなく、「こうあるべき」だということに従ってつくられるのである。
(中略)例えば、映画監督の宮崎駿は、その感覚について、次のように述べている。
映画を作るって言うと、なんかクリエイティブとか創造、そういう格好いい言葉並べますけど、実は、こういう映画を作るっていう素材を選ぶまでは、自分が決められる。......それは決められますが、一旦決めて映画を作りだすと、映画作ってるんじゃないですね。映画に作らされるようになるんです。
あらかじめ、頭の中に完璧なものがあって、それを現前させるだけで作品が完成する、なんていう創作は不可能に近い。
※不可能、ではなく不可能に近い、と表現したのは例外がいるからである。三島由紀夫は小説を書く時「頭の中で全ての文章を組み立てて、あとはそれを書くだけ」だといい、モーツァルトは作曲する時「音楽の全てが、一度に頭に降ってきて、あとは譜面に書き出すだけだった」という。信じがたい話である。
▶︎まとめ
前回、「太陽と乙女」から引用した文章を再掲したい。
何をおいてもまず仕事にとりかからなければならない。それが一番難しい。(中略)書きたいことを見つけると、次はある程度準備をする。どんなことをするのかというと、それがどのような小説になるのか、漠然と思い描いてみる。書きたいことを並べて、なんとか物語の流れを作ってみる。しかし、準備はあくまで準備にすぎない。事前の構想がどれぐらい実現するかというと、ほとんどしないのである。
だいたい小説の文章が一行も書かれていない状態で、その小説の行き着く先を想像するのは不可能である。
(中略)
私の場合、書いてみなければ何も分からない。
「この物語はおもしろくなるのではないか?」
そういう予感だけは持っている。そうでなければ始めようがない。しかしその予感が本物なのか、あるいは錯覚なのかは、実際に文章を積み重ねていかなければ確かめることができない。私はモーツァルトではないから、作品全体の曖昧な破片が頭の中に降ってくるだけなのである。だから、発掘された土器を復元するようにその破片を組み合わせ、小説の世界を再現してやらなければならない。
森見氏にしろ、上田氏にしろ、「なんかこれ面白そう」というものが浮かんだら、とりあえずエチュードしてみる。やってみないことにはそれが本当に面白いかどうかは分からない。そうやってパーツパーツを作り上げて、一つの作品に仕上げていくのである。
それは、最初に仮説を立ててとにもかくにも創作をスタートさせ、仮説の修正を繰り返しながら、作品の「あるべき姿」を次第に見出していく作業である。
これは、何も作家がフィクションを作るときだけに限らない。僕はこれがどんな仕事や研究についても言えるし、なんなら人生やキャリアについてすら言えるのではないかと思っている。とりあえずやってみて、それでできたものをみて、次にどうするか決める。何もかもガチガチに決めないと動けない人生なんて窮屈ではないだろうか。
森見登美彦も「自分が事前に計画できるようなものは大したものではない。とにかく仕事をしているうちにハッキリしてくるのが本当の仕事ではないだろうか」と言っている。
森見登美彦氏の『四畳半タイムマシンブルース』から思ったよりずっと話が広がってしまったが、最後はタイムマシン的に出発点に戻る。
今年は、夏のイベントは自粛が多いが、幸い近所でささやかだけれど、8月最後の週末に夏祭り的なイベントが開催される。その前夜祭で『サマータイムマシン・ブルース』の上映会をやるそうだ。素敵な企画だ。『四畳半タイムマシーンブルース』を読んでからみに行こう。
#森見登美彦 #四畳半タイムマシンブルース #太陽と乙女 #上田誠 #サマータイムマシン・ブルース #パース #アブダクション #井庭崇 #クリエイティブ・ラーニング
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
