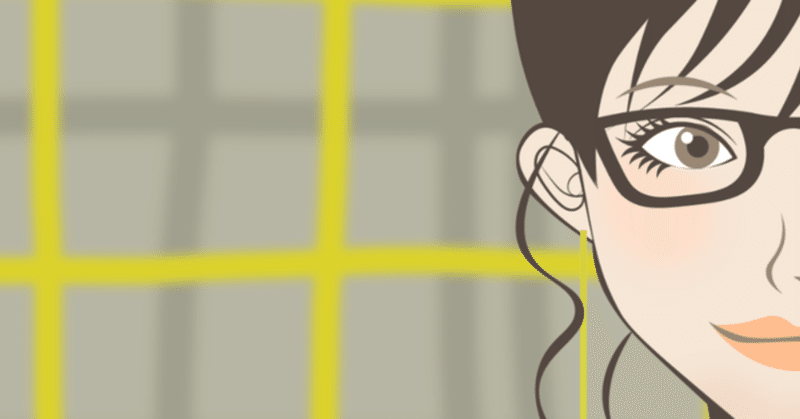
眼鏡を愛し、愛されて。【短編小説、再掲・加筆修正】約12,000字
雲ひとつ無い晴天の空。太陽の眩い光がビルの窓から射し込んでいる。窓の外にはオフィス街が広がり、眼下では多くの人々が往来している。私はその風景を、少し太めの黒縁眼鏡を通し見渡して、こう思う。
生きているって、素晴らしい。
東京に出て来たのは、眼鏡屋で働く為だった。東京は世界一多くの眼鏡が集まる都市だと、私が勝手にそう思っていたからだ。
生まれ育ったのは、東北は青森県の片田舎。林檎農家の一人娘として生まれた私は、初めての子どもで女の子だったから、しばらくの間はただただ手放しで可愛いがられていた。祖父母にとっても初孫で、いろいろな物を買ってくれたし、車に乗っていろいろな場所に連れて行ってもらった。祖父も父も林檎のことをたくさん教えてくれたけど、小さい私にはよくわからなくて、「早く食べたいなぁ」とばかり思っていたし、そう口に出すと「可愛いなぁ」と頭を撫でて笑ってくれた。だから大人になった私には林檎についての知識はほとんど記憶に残っていないし、(とても残念な事に)それほど林檎が好きなわけでもないから、実家からたくさん送ってもらっても、それはそれで扱いに困るだけなのである。
青森県が誇る名物であるねぶた祭りも、私はずっと苦手だった。あの巨大で厳つい灯籠が、怖すぎるのだ。怪獣や妖怪の類にしか思えないから、怖くて怖くて仕方がない。毎年家族で見物に行くのだが、私はその度に「嫌だ。行きたくない」と言って家族を困らせた。「大きくなったら良さがわかる」と言われ続けたが、嫌々連れて行かれて母の陰にコソコソ隠れていた思い出しかなくて、大人になった今でも好きにはなれないでいる。職場の仲間に「ねぶたって凄いんでしょ」と言われても「うん」という2文字でしか返事が返せない。青森県民としては何がどう凄いのかを具体的にプレゼンするべきなのだろうけど、自分が好きじゃないから言葉が出ないのだ。出された料理が美味しくなくても、ちゃんとコメント出来る芸能人リポーターには感心するばかりだ。林檎と同じく、少なからず罪悪感を伴う、扱いに困る祭りなのであった。
幼稚園に入る前には、弱視のせいで眼鏡を掛けることになってしまった。もう少し早く気がつけば治療も出来たらしいが、眼鏡家系だったせいで「遺伝だから仕方ないね」で済まされたそうだ。でも、幼い私はそれが嬉しかった。母も父も、そして祖父母も眼鏡を掛けていたから、眼鏡を掛けることで皆んなの、大人の仲間入り出来たような気がしたのだ。
初めての眼鏡屋は、地元の商店街にある老夫婦の営む小さなお店だった。品数も少なめで、その中で子供用となるとなおさら限られている。その時の選択肢はたったの2種類だけ。同じタイプの少し太めの楕円形フレームで、色は黒かピンク。要するに、男児用か女児用か。そこから選ぶ他なかったけれど、それでもやっぱり嬉しい気持ちは変わらなかった。そして私は、黒縁眼鏡を選んだ。理由は自分でもわからなかったけど、なんだか眼鏡に呼ばれたような気がして、もう、黒い方の眼鏡じゃないとどうしても嫌だった。母は「女の子はこっちなのよ」と言ってピンクを買おうとしたけれど、さんざ駄々をこねて、私は初めての、黒縁眼鏡を手に入れることが出来た。
それからは、私にとって眼鏡は体の一部だった。眼鏡が無いと生活出来ないから、相棒でもあったし、歳を重ねる毎に選べる眼鏡の種類が増えて、友人のような、大切な親友のようでもあった。眼鏡を外せば見たくない物は見ないで済むし、眼鏡を掛けることで見えない物が見える。眼鏡は私が生きる上で、無くてはならない物になった。
小学校は全校生徒合わせて100人に満たない学校で、同級生は12人しかいなかった。12人の内、眼鏡を掛けていたのは私だけ。だから私は特別なのだと思った。自分だけ違う、他の誰にも無い個性なのだと思っていた。でも、周りの見方はそうではなかった。3年生になった頃から、私は異物として扱われるようになったのだ。突然、眼鏡を掛けているというそれだけで、仲間外れにされた。そんなことをされる意味がわからなくて、傷ついて、始めは泣いた。悲しくて、悔しくて仕方がなかった。だけど、しばらく泣いて気がついた。私にとって眼鏡は無くてはならない物だから、眼鏡を馬鹿にする奴らと仲間になる必要なんてない。そんな奴らはこっちから願い下げだ。そう思い直して、その日から私は、学校では先生以外と一切話さなくなった。卒業までそれは続き、家族や先生にも心配されたけれど、最後まで意思を貫いた。
高学年になったくらいだっただろうか、祖父母の母に対する当たりが急にキツくなった。原因は林檎農家の後継者問題だ。私は女だし2人目が生まれなかったから、そのことで母が責められる姿を頻繁に見るようになった。父は「富士美が後継ぎ連れてくっから大丈夫だ」と言ったが、それがそんなに簡単じゃないことは祖父母の方がよくわかっていた。地方の林檎農家に婿入りしてくれる男を探すのは、ひょっとしたら宝くじに当選するよりも難しいかも知れない。ある日、「早く次の子産まないと、間に合わなくなるわ」と祖母に言われた母は泣いていた。父がいない時に限って、祖母は母を傷つけるようなことを言うのだ。小柄だけど活発で、元気だけが取り柄みたいな母だったのに、暗い表情を見せることが増えた。私は気づいていないふりをしていたけれど、心は一緒に傷ついていた。あぁ、生まれたのが私だから母が泣いているのだと、家族にバレないようにお風呂や布団の中で泣いていた。家族の誰も嫌いなわけじゃないのに、私が直接責められているわけじゃないのに、だんだんと居心地が悪くなって行った。
卒業後は地元から少しでも遠くに離れたかったから、中学校は自転車で40分以上掛かる場所に通った。同じ小学校から来た生徒も数名いたが、大半は初めて会う人ばかり。それでも私はほとんど目を合わせることもせず、必要な会話だけを交わすようにした。小学校の時の出来事で、人間は裏切る生物なのだと強く感じたから、進んで友だちを作ろうとは思えなかった。
その頃の私には、月三千円のお小遣いとお年玉を貯めて新しい眼鏡を買うこと、それが唯一の楽しみだった。中学校は地元よりは栄えた場所にあり、最寄りの駅にはショッピングモールが隣接していた。その中に有った眼鏡屋には、あの商店街の小さな眼鏡屋とは比較にならない種類の眼鏡が、とてもオシャレに陳列されていて、照明がレンズや色とりどりのフレームに反射して、お店全体が神々しく輝いて見えた。初めてお店に入った時には、興奮し過ぎて動悸を感じるほどだった。美術部の部活がある日は帰りが遅いし、通学はジャージだったから、帰り掛けに寄ることも出来ない。直ぐに学校にバレて、セット商品のように竹刀を持った体育教師から、オラオラと指導が入るからだ(あれって何故わざわざ連絡するのだろうか)。だから休みの日に、自分なりに着飾って眼鏡屋に行く。それは自分に合う眼鏡を探す上での決め事であり、眼鏡に対する礼儀でもあった。中学生の間に購入出来た眼鏡は3本。弱視矯正のレンズ代も掛かる為、当時まだ眼鏡は高級品であった。毎日1本1本に声を掛けながら手入れをし、愛情を注ぐ日々だった。
林檎農家の後継者問題は、祖父母の死去という形で幕が降りた。祖父が収穫中に足を骨折して、入院中に認知症を患った。退院後は家に戻ったものの症状は悪化の一途を辿り、夜中に徘徊を繰り返すようになり、自分の妻である祖母や息子である父の事も、何もかもすっかり忘れてしまった。そのように変わり果てて行く祖父を献身的に介護していた祖母の方が先に倒れ、間もなく息を引き取った。体力的な問題以上に、心労が祟ったのだろうということだった。そしてそれから半年も経たぬ内に祖父が後を追う形となった。ずっと一緒だった祖父の変わりゆく姿も、人の命ってこんなに簡単に失われてしまうんだという想いも、思春期の私の心にはあまりに重くて、ニ人の葬儀の時には涙が止まらなかった。
祖父母の死去によって、すぐに家族が良い方向に進んだわけではなかった。母が心に負った傷はそのまま癒えず、心療内科に通うようになった。具体的な話を聞くことは怖くて出来なかったが、何かしらの精神疾患だったのだろう。明るかった母の笑顔は鳴りを潜め、活発な母の姿を見ることは出来なくなった。唯一救いだったのは、父が気丈に振る舞ってくれたことだ。私のことを気遣いながら、母にも意識して明るく接し、黙々と農家の仕事を続けていた。母も元気は無いながらも、父の仕事の手伝いは続けた。近所に住んでいた伯父夫婦の支えもあって、なんとか我が家は家族の体裁を保つことが出来ていた。
高校生になって、アルバイトで貯めたお金で初めて1人で東京に来た。目的はひとつだけ。時間が許す限り眼鏡屋を回り、出来るだけたくさんの眼鏡を見ることだ。実家のある青森から夜行バスに乗り、新宿駅で降りた。初めて見る高層ビル群や人の多さに面食らったが、そんなことを気にしてはいられない。時間は限られていたから、事前に調べておいたエリアをひたすら走って見て回った。
衝撃的な1日だった。新宿という限られた場所だけでも無数に眼鏡屋があり、全く見切れなかったのだ。慣れない街の迷路のようなビルの中で、眼鏡屋に辿り着くだけでも一苦労だった。新宿だけでもそうなのだから、都内にある全ての眼鏡屋を回ろうと思ったら、いったい何年掛かるのだろうか。そう考えた時、私は決めたのだ。高校を卒業したら、東京に出る。その為に、東京の大学に進学するのだと、私は決意した。青森に帰るバスの中で、今後の具体的な計画を練り始めた。
その後も高校卒業までに何度か東京を訪れ、その度観光をするでもなく、とにかく眼鏡屋だけを見て回った。眼鏡の声がハッキリと聞こえるようになったのも、その頃だった。思い返せば初めて黒縁眼鏡を買ってもらったあの時から、ずっと聞こえていたんじゃないかと思う。けれど、無意識の内に空耳だと思うようにしていたのだ。いくら眼鏡が好きだからとは言え、眼鏡と話が出来るなんて、我ながら現実味が無さ過ぎる。ただでさえろくに人間の話し相手もいないのに、眼鏡と話せるなんて誰が信じるだろうか。それこそ頭がどうかしてしまったと言われかねない。だから受け止めるまでに時間が掛かり、高校生の時にようやく受け入れることが出来たのだ。
眼鏡業界もデフレ化が進み始め、安価な上に処方箋さえ有れば、その日の内に買って持ち帰れるお店が増えた。おかげで高校時代に集めた眼鏡の数は最終的に20本を超え、それをカラフルな眼鏡ケースと共に専用のアクリルケースに並べて飾って、ニヤニヤと鑑賞するのが嬉しかった。大好きなアジアンカンフージェネレーションのCDを買う以外は、ほとんど全てのお金を眼鏡に費やしていた。
学校は好きではないが、勉強は好きだった。学校に行ってもほとんどコミュニケーションを取らないから、勉強に集中することが出来た。成績はそれなりに良い方だったから、志望の大学にも難なく受かり、計画通りに東京に出ることに成功した。奨学金で学費を賄い、生活費は自分で稼ぐ約束だったから、実家にいる内から家賃の安い学生寮を探しておいて、入学して間もなくアルバイトを始めた。勿論、眼鏡屋だ。それ以外の選択肢は頭に無かった。学生寮の近くをネットで検索し、応募をしたら直ぐに採用してもらえた。引っ越しをした翌日には、都内だけでも数十軒ある大手のメガネチェーンで働けることになった。「採用しないと殺られるような気がした」とは当時の店長から頂いた、ありがたいお言葉。眼鏡への執着(愛情と言ってほしいものだ)が尋常じゃなくて、採用する以外に逃げ道が無いと感じたそうだ。私を何だと思っていたのだろうか。
初めてハッキリと聞こえた眼鏡からの言葉は「アナタにはアタシよね」だった。その眼鏡は赤くて太めのフレームで、確かに自分に合っている思った。それからは「アタシも試して行ってよ」とか「僕を選ぶ女の子もいるんだぜ」とか、いろいろな声が聞こえて来て、その子たちがキラキラと光って見えた。眼鏡には眼鏡のマナーが合って、合わないと思う相手に自分を売り込むことはしない。声を掛けるには眼鏡側に相応の根拠があるから、試すと私は大概気に入って買ってしまい、気がつけば20本以上になっていたのだ。クラスでのニックネーム(悪口かも知れない)はまんま「メガネ」になったけど、それも別段嫌な気はしなかった。私の名前なんて、存在なんて、有って無いようなものだったのだから。
東京で暮らすようになり、都内の眼鏡屋を見て回るようになってからは、さすがに慎重に選んで買うようにした。眼鏡側からのアプローチを受けても「また今度ね」と断って、その日のベストを厳選する。そうでないと生活が立ち行かない。それでも私の生活は眼鏡一色で、髪型も化粧もファッションも、全てを眼鏡ありきで合わせていた。面白い物で、眼鏡のバリエーションが豊富だと、それに合わせて化粧や洋服のバリエーションも広がる。オシャレになりたいと思っていたわけではないのに、結果として同級生からはオシャレ好きだと思われるようになっていた。相変わらず自分からコミュニケーションを取ることには消極的だったけど、過去の私を知っている人がいないから、周囲の私を見る目も全然違った。人間って本当に勝手だよねって、眼鏡に共感を求める私だった。大学の卒論も『眼鏡から見た日本の歴史』という内容で書いた。眼鏡と話せることを隠しながら、眼鏡目線で書くのはなかなかに難しかったが、我ながら納得のいく物が書けたし、ゼミの講師やお気に入りの眼鏡たちも褒めてくれた。
就職活動ではずいぶんと悩んだ。SNSもやっていたから、私の眼鏡好きは一部で知られるようになっていて、在学中に雑誌の眼鏡(アイウェアと言うらしい)特集でコメントを求められたこともあった。そんな経緯からジャーナリストを薦められたりもしたが、結局私は大手の眼鏡会社に就職することを選択した。採用後の研修の際には本社勤務も提案されたけど、しばらくは店舗勤務が出来るようにお願いした。とにかく私は、眼鏡のある場所で、生きた眼鏡たちと戯れていたかったのだ。
眼鏡にもそれぞれに個性がある。真面目そうな眼鏡の一人称は「ワタクシ」だし、子供用であれば「ボク」「アタシ」だ。奇抜なイロモノ感の強いフレームは子どもがふざけて掛けると「どや、おもろいやろ」などと言っているし、正統派なデザインなのになかなか手に取られないフレームは「私の存在意義って何なんでしょうか」とボヤく。眼鏡を生み出している私たち人間と同じなのだ。ポジティブだったりネガティブだったり、個性があり感情がある。本当にそんな風に話しているのか、私というフィルターを通しているからそう聞こえるのか、そればかりは、私にもわからないけれど。
そして眼鏡選びは、眼鏡側からのアプローチが正しく届けば概ね失敗はしないのだが、流行という悪魔には、さすがの眼鏡も敵わない。若い女の子が全く似合わない大きなサングラスを試していれば、「アナタには他のコの方が良いわよ」と律儀に伝えるのだが、悪魔に心を支配された者たちは、意気揚々と会計に向かうのだ。眼鏡たちも人間のそういう習性は理解しているから、決まってしまえば後は沈黙する。短期間しか使ってもらえないことも理解した上で、黙って受け入れる。「人間って、そうだよね」と。
そのように眼鏡との幸せな日々が続いていた。
入社して3年が経ち、25歳を迎えて間もない時だった。朝から少し調子が悪いなと思ってはいたが、なんとか仕事を終えて自宅に戻ると激しい悪寒に襲われた。熱を計ってみたら、液晶には生まれて初めての、40度を超える表示。身体の節々が激しく痛み、動くこともままならなくて、常備薬の解熱鎮痛剤だけを飲んで、倒れるように眠ってしまった。
翌朝になっても熱は下がり切らず、その日の仕事は休ませてもらった。熱以外にも違和感があったけれど深く考える余裕はなくて、なんとか服を着替え、這うようにして近くのクリニックに向かった。
リムレスメガネを掛けた、神経質そうな中年男性の医師の診断は「ただの風邪」だった。季節性の何かでも無ければ、何らかの感染症でも無かった。点滴を受け、帰宅して薬を飲んで寝ていると、夕方頃には熱が下がり始め、夜中には嘘のように平熱に戻っていた。明日は仕事に行けそうだと思い、そのまま朝まで眠った。
普段より早く起きて、シャワーを浴びた。身体はもう何ともなかった。身なりを整えて、買っておいたバターロールとバナナを食べ、牛乳を飲み、歯を磨いて家を出た。
職場に着いて直ぐ、昨日の違和感の正体がわかった。眼鏡の声が、聞こえなくなっていた。幼少期からずっと聞こえていたであろうその声が、全く聞こえなくなってしまったのだ。
まだちゃんと調子が戻ってないからかなぁ、なんて思いながら仕事をしていたけど、結局その日は何も聞こえないまま、一日が過ぎた。声が聞こえないことに気づけなかった罪悪感と、これがずっと続いたらどうしようという恐怖で、心は不安で仕方なかった。
一週間が過ぎても状況は変わらず、眼鏡が私に声を掛けて来ることはなくて、眼鏡の声が聞こえて来ることも、やはり無かった。眼鏡が喋っていないのか、私の方が聞こえていないだけなのかもわからない。職場の仲間たちは、私が眼鏡の声を聞くことが出来るなんて、露ほども知らないから、いつも通りに見えただろう。いつも通りに仕事をこなし、いつも通りに帰り、いつも通りにまた出勤しているように見えただろう。
でも、本当は全然違う。
私の心は喪失感に苛まれ、置かれた状況に打ちひがれていた。ぽっかりと、大きな大きな穴が空いてしまった。眼鏡と共にあった生活が、眼鏡と共にあった世界が、唐突に終わりを迎えたのだから。しっかりと立っているようで、背骨をすっぽり抜かれてしまったような気分だった。私の眼鏡の向こうにある世界は今、グニャリグニャリと歪んでいる。それはまるで、激しい乱視のように。
それでもなんとか周りに悟られないようにしながら、日々の仕事を続けていた。
「芦野さん、最近元気なくないですか」
声を掛けて来たのは、1年後輩の佐藤君だ。私は元々感情を表に出すことをほとんどしないから、特別に元気な姿というのも見せたことはないはずだ。それでもそう思ったということは、佐藤君なりに何かを感じたのだろう。
「ううん、全然普通。いつも通りだよ」
私は心を偽った。
「芦野さんて、甘い物好きですか」
返事に困った。質問が唐突だったこともあるが、私は食べることに執着が無いからだ。最低限栄養バランスを気にしたりはするが、生きるのに必要だから食べるだけ。目の前にある物を食べるだけ。甘党とか辛党とか、そんなことは考えたことも無かった。
「ぼちぼちかなぁ」
迷ったあげく搾り出したのは、最高に曖昧な言葉だった。
「僕、甘い物大好きなんです」
急に何を宣言しているのだろうか。
「すぐ側にシャインマスカットのパフェが有名なお店があるんです。僕、めちゃくちゃ行きたいんですけど、さすがに男1人じゃ入りづらくて。芦野さん嫌じゃなかったら一緒に行ってもらえませんか。お金は当然僕が払うので」
そういうことか。だとして何故私なんだろうかと少し疑問ではあったが、眼鏡との関係が崩れて以来、家に帰っても特別に何をするわけでも無かった。ご飯を食べて、お風呂に入って、本を読んで眠りにつく。後はアジアンカンフージェネレーションか、最近聴くようになったくるりや七尾旅人をサブスクで聴くぐらいだ。佐藤君は苦手なチャラチャラやオラオラはタイプじゃないし、断る理由も別段見当たらなかった。
「うん、いいよ」
仕事が終わった後、目的のお店の前で待ち合わせることになった。
勤務終了後、制服からの着替えを済ませてお店に向かうと、既に佐藤君が待っていた。
「良かったです、来てくれて」
本当に嬉しそうな笑顔だった。よっぽどシャインマスカットのパフェが食べたいのだろうなと、私は思った。
「値段、高くない?私、自分の分出すよ」
お店の前にメニューが飾ってあった。佐藤君の言っていたパフェの値段は1,800円もするのだ。外食でも500円以内で済ませたい私には、信じられない高級品。でも、私のが先輩だし、全部出させるなんて申し訳ない。
「何言ってるんですか。僕が来てもらいたくて誘ったんですから、僕に払わせて下さい」
しっかりと私の目を見て、佐藤君が言った。その表情を見て、佐藤君ってこんな顔だったっけと思った。よく考えたら、みんなの顔をちゃんと見たことないかも知れない。眼鏡というフィルターを通してしか、みんなを見ていなかったのかも知れない。
オーバル型の青縁眼鏡がトレードマークの佐藤君は、小柄で親しみやすく、愛嬌があるキャラクター。職場では先輩に、お客様では歳上のお姉さんの懐に入り込むのが得意な販売員だ。お姉さん達は佐藤君に上手く乗せられて、ニコニコしながらお似合いの眼鏡を買って帰る。販売員として、それはとても素晴らしいことだと思う。
店内はほとんど満席だったが、お目当てのパフェは注文して、それほど待つこともなく私たちのテーブルに届けられた。
「ヤバっ」
パフェを目の前にした佐藤君は、爛々と瞳を輝かせている。
「シャインマスカットの一粒一粒が輝いていて、純白の生クリームとのコントラストが絶妙で…」
テレビ番組のように食レポを始めた佐藤君の目の方が、私にはよほど輝いて見えた。
「美味しそうだね」
私も本当にそう思った。食べ物を見て美味しそうだなんて感じたのは、いつ以来だろうか。記憶を掘り起こそうとしてみても、結局辿り着くことは出来なかった。
ひと通り食レポを終えた佐藤君は、今度は黙々とシャインマスカットパフェを食べ始めた。ひと口食べる毎にうんうんと嬉しそうにうなづいている。それを見ていて、私はなんだかすごく幸せな気分になった。
「芦野さん、本当にありがとうございます」
半分ほど食べた辺りで、佐藤君が唐突に私の目を見てそう言った。お礼を言うのは私の方だし、言う相手がいるとしたらパフェを作って下さった店員さんと、シャインマスカットの生産者さんだと私は思った。
「芦野さんが一緒に来てくれなかったら、僕はこのパフェと一生出会えなかったかも知れない」
なるほど、そういう感謝の仕方もあるのか。誘われて、タダで美味しい物を食べて、幸せな気分にされて、最後にお礼まで言われる。こんなに心地良い時間は、生まれて初めてじゃないだろうか。
「また誘っても良いですか」と佐藤君に聞かれた私は「うん」と答え、「次は私にも払わせてね」と言った。佐藤君はしぶしぶという顔で「仕方ないですね」と言った。
その日以来、週に1回か2回は佐藤君から誘ってくれて、いろいろな場所で食事をした。イタリアンだったり、インドカレーだったり、ラーメンだったり、焼肉や甘味処にも行った。休みが合えば、少し遠出をして浅草で有名な天丼屋へ行ったり、築地で新鮮なお寿司を食べにも行った。佐藤君は美味しいお店をたくさん知っているなぁと、とても感心する。食事のついでに東京タワーに登ったり、浅草寺に参拝に行ったり、映画を観たりもするようになった。東京にはこんなに楽しい場所があったのだなぁと、初めて知ることだらけだった。
「本当は毎日でも良いんですけどね」と言う佐藤君に、私は「そうだね。シフトの問題とか、お金の問題もあるからなかなか難しいけど」と答えた。そうなのだ。毎日一緒のシフトにはならないし、眼鏡屋の給料はそれほど高くはないから、頻繁に外食をするのはなかなか経済的に厳しいのだ。佐藤君に出させてばかりはいられないしね。それさえ無ければ、本当に毎日でも良いのだけどと、私も心底思っていた。
そんな日が続く内に、私の心にぽっかり空いていた大きな穴は、少しずつ少しずつ埋まっていった。すっぽり抜けてしまったはずの背骨はすっかり再生し、グニャリと歪んでいた世界は以前よりもくっきりと鮮明に映り、彩りも豊かになっているように感じられた。
あぁ、生きているって、素晴らしいな。
そのことに気づいてしまったのは、ある日の仕事中だった。私は絶望した。幼少期からずっと一緒だった、一番大切な物。私の人生の全てだった物。今も私を囲んでいて、私を包み込んでくれている、眼鏡たち。それなのに、失ったショックを忘れて、それよりももっと大切な物を見つけてしまったのだ。取り返しのつかないことをしてしまった。そんな自分を、私は心から軽蔑した。
仕事中なのに、店内にはお客様もいるのに、自然と溢れ出る涙を、私は止めることが出来なかった。ボロボロと流れる大粒の涙を、止めることが出来なかった。その場に膝から崩れて、しゃがみ込んで、子供みたいに、眼鏡を初めて買ってもらった幼稚園児の時のように、わんわんと大泣きした。感情をどうすればいいのかわからなくなってしまった。
真っ先に私の異変を察知したのは佐藤君だった。しゃがみ込んだ私を包み込むように抱きしめながら、「芦野さん、大丈夫です」と言った。それでも泣き止まない私に、何度も「芦野さん、大丈夫です」と繰り返し言った。それはだんだんと叫びに変わり、「芦野さん、大丈夫です。僕がついているから、大丈夫です」と大きな声で言ってくれた。最後には「富士美さん、あなたには僕がいるから、大丈夫です」と全力で言ってくれた。
そうだ、私の名前は芦野富士美だった。
佐藤君がそうしてくれている間に、少しずつ、私は呼吸を取り戻していった。佐藤君の体温が私の心を温めてくれた。
「フジミ…」
どこからか、聞き覚えのある声が聞こえて来る。それは勿論、眼鏡の声だ。昔からずっと聞いてきた、あの声だ。あの声が、私を呼んでいる。
「アシノフジミ、アナタには、サトウクンがいる」
そう聞こえたと思った刹那、売場にある全ての眼鏡が輝き始めた。キラキラと、今まで見たことがないくらいに輝き始めたのだ。眩い輝きの中で、久しぶりの声を聞きながら、全身の力が抜けてしまった私は、気を失い、その場に倒れてしまった。
目を開けると、そこは職場のバックヤードだった。ソファの上に寝かされていたようだ。壁に掛けられた時計は午前11時を回ったところで、気を失ってから、それほど時間は経っていなかった。
「あっ、芦野さん、大丈夫ですか」
声を掛けてくれたのは、やはり佐藤君だった。
「うん、ごめんなさい」
仕事中に迷惑を掛けてしまったことを、私は詫びた。
「いえ、全然大丈夫です。店長と救急車呼ぼうかって相談してたんですけど、なんか芦野さん気持ち良さそうにいびきかいて寝てたから、少し様子見ようって一旦ここに」
寝ちゃってたのか、私。いびきなんかかいて。恥ずかしかったけど、大丈夫。体の方はなんともない。体だけじゃなく、心の方も。
体も心も、何かから解放されたみたいだった。脱皮した蝉のように、蛹から飛び立つ蝶々のように、まるで生まれ変わったみたいに軽くなっていた。
「帰りますか。お店は僕たちでなんとかしますから」と佐藤君に言われ、「ううん、大丈夫」と私は言った。帰る必要はないし、帰りたくなかった。それよりも、この場所に一緒にいたかった。
私には佐藤君がいる。それが私の、今、この世界の全てだ。
そして、あの日からもう、5年が経った。
私は本社に異動して、広報の仕事をしている。高層ビルが立ち並ぶオフィス街、その中の一室で、PCの画面と向き合う日々。広報の業務の傍ら、アイウェア・ジャーナリストとして書籍も出させてもらった。
名字は佐藤に変わり、2人で暮らすようになった。私は今新しい命を授かっているから、来年にはもう1人家族が増えることになりそうだ。
子育てが落ち着いたら、青森県に戻ろうと思っている。実家の林檎農家を継ぎたいと佐藤君が言ってくれたのだ(結婚後も、私は佐藤君と呼んでいる。私も佐藤になったのだが)。一度父の収穫の手伝いをした時に、父の林檎に対する想いを聞いて、そう思ったらしい。母の症状も改善されて、少しずつ笑顔が戻って来ていた。佐藤君が美味しそうに林檎を食べる姿を見た時には、とても嬉しそうにニコニコしていて、母の笑顔を見た私は目頭が熱くなった。そして佐藤君は初めて観るねぶた祭りにも、甚く感動していた。「ヤバっ」と感動して泣いている佐藤君を見て、私もほんの少しだけ、あの怪獣のような灯籠が好きになった。
あれから眼鏡の声は、一切聞こえて来ない。きっともう、聞こえることはないのだろう。
それでも私は眼鏡を愛しているし、眼鏡は私を見守ってくれている。眼鏡は私と共にあり、私は眼鏡と共にある。私には、それがわかる。私はわかっているのだ。
そうだ。
生きているって、素晴らしい。
おしまい
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
